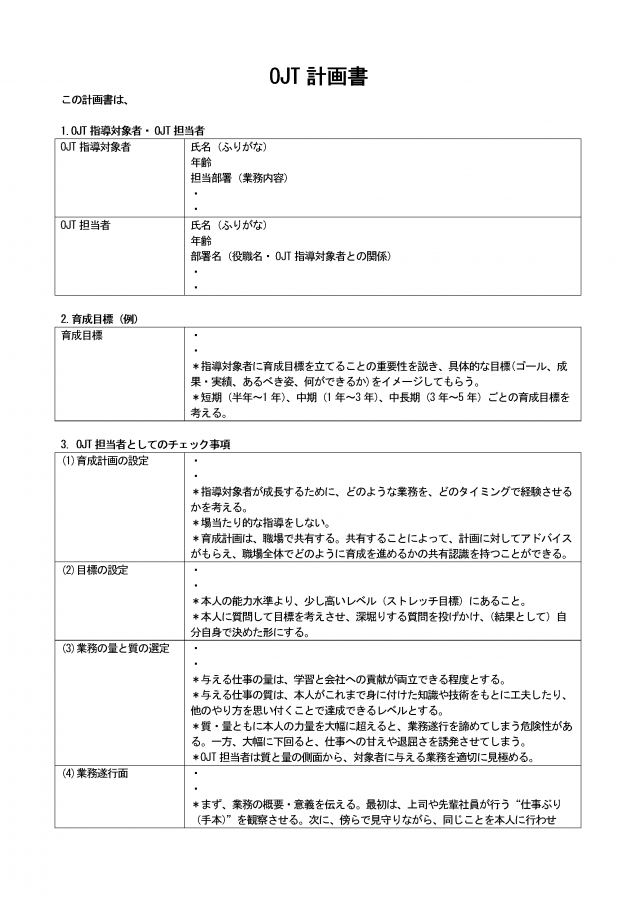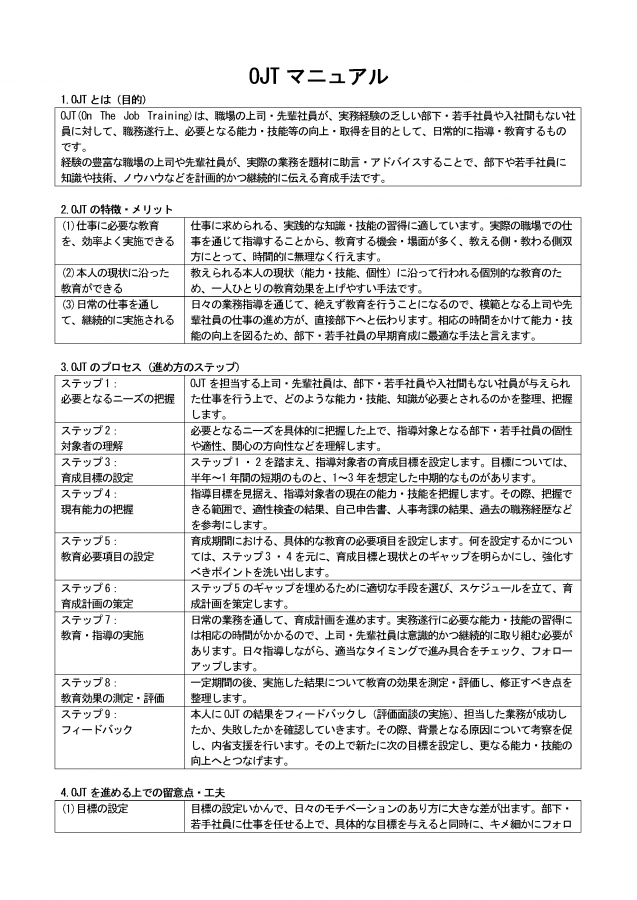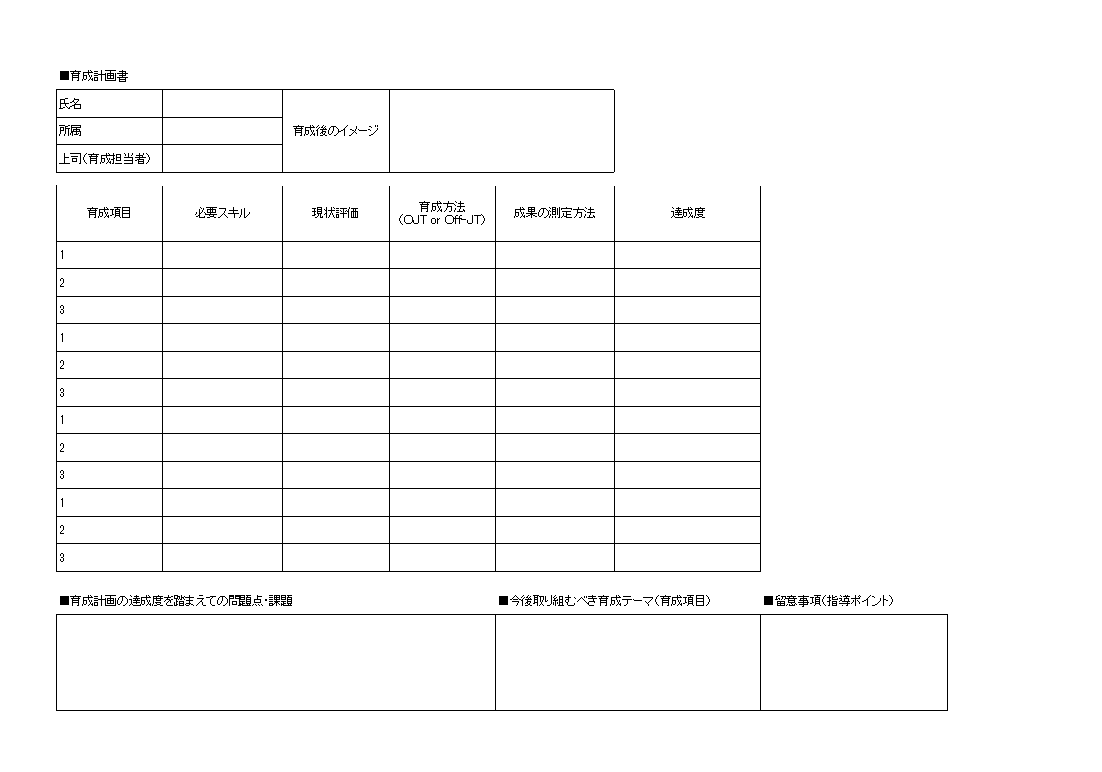知識の呪い
知識の呪いとは?
「知識の呪い」とは、知識のある人が、知識のない人の立場に立って考えられなくなる心理現象のことです。専門用語を多用したり、説明を省きすぎたりすることで、誤解や業務の行き違いを招きやすくなります。職場では、マニュアルが分かりづらい、引き継ぎがうまくいかない、顧客に伝わらない、といった問題として現れます。人事部門やマネジャーには、伝え方を工夫し、知識を共有しやすい環境を整えることが求められます。
なぜ職場で起きやすいのか
知識の呪いが与える影響と防ぐ工夫
知識の呪いは、心理学の研究でもよく知られた現象で、私たちの日常や職場で頻繁に起こります。たとえば、パソコン操作に慣れた社員が「フォルダーを開いて保存してください」と依頼しても、その相手が初心者であれば「どのフォルダーか分からない」と戸惑うことがあります。説明する側にとっては当たり前のことでも、相手にとっては未知の領域なのです。
この現象は職場にさまざまな悪影響をもたらします。新入社員への教育や業務の引き継ぎで「これくらい分かるだろう」と説明を省くと、相手は理解できずに時間を浪費してしまいます。社内資料やマニュアルに専門用語が並んでいると、読み手は混乱し、人に聞かなければ業務が進みません。顧客対応の際に業界用語を多用すると、相手に真意が伝わらず、信頼を損ねるリスクがあります。
では、どう防げばよいのでしょうか。ポイントは「相手の立場に立って確認する仕組みをつくる」ことです。たとえば研修や打ち合わせでは、説明を聞いた相手に「自分の言葉で言い換えて説明してもらう(teach-back)」方法が有効です。これにより、理解のずれをその場で修正できます。また、社内のマニュアルや資料は「読み手を想定して作る」ことが大切です。専門用語は必ず説明し、手順は一つひとつ段階を追って書く必要があります。
組織に「心理的安全性」があることも重要です。分からないことを遠慮せずに質問できる雰囲気があると、誤解や行き違いが早めに修正されます。人事部門や管理職には、定期的な1on1やフィードバックの場を設け、疑問を口にしやすい環境を整えることが求められます。さらに、知識を分かりやすく共有した社員を評価する仕組みをつくれば、「説明する力」も自然と育っていきます。
大切なのは、知識の呪いを「個人の怠慢」や「能力不足」として責めないことです。相手の立場を意識することで、知識はよりスムーズに共有され、無駄な摩擦を減らせます。
- 参考になった0
- 共感できる1
- 実践したい0
- 考えさせられる0
- 理解しやすい0

用語の基本的な意味、具体的な業務に関する解説や事例などが豊富に掲載されています。掲載用語数は1,500以上、毎月新しい用語を掲載。基礎知識の習得に、課題解決のヒントに、すべてのビジネスパーソンをサポートする人事辞典です。
会員登録をすると、
最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!
- 1
無料会員登録
記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。


 テーマで探す
テーマで探す サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 学び・実務
学び・実務





 イベント
イベント