【後編】制度だけでは人は育たない│人的資本に必要なモノとは?

本稿は、【前編】制度があるだけでは人は育たない │ 人的資本に必要なモノとは?の続編です。前編をご参照の上、御覧くださいませ。
物質タスク型と人間重視型の二輪
ある企業の工場で、最新鋭の生産システムが導入されました。
工程は見事に標準化され、作業マニュアルは分厚いファイルに整えられ、チェックリストも完璧に揃っています。
経営者は、胸を張りました。
「これで安心だ。効率も品質も確保できる」
しかし、半年後。
現場は、思わぬ問題に直面していました。
ルール通りにやっているはずなのに、不良率が下がらない。
残業は増え、社員の疲弊感は強まっている。
原因は――人の心が追いついていなかったことです。
社員たちは、「マニュアルに従うだけ」の毎日にやりがいを失い、改善提案も減っていました。
立派な骨格(仕組み)はできても、それを動かす血流(人の意欲や協力)が滞っていたのです。
片輪走行の危うさ
経営をメタファー(比喩)で表現するなら、自転車に例えるのが分かりやすいでしょう。
物質タスク型の経営は「右の車輪」。
効率化、標準化、ルール、ISO、PDCA。
人間重視型の経営は「左の車輪」。
対話、協力、士気、レジリエンス、信頼。
右の車輪だけで走ろうとすれば、くるくるとその場で回ってしまいます。
左の車輪だけでも、前に進めずフラフラと倒れてしまいます。
二輪がそろって初めて、企業は安定して前進できるのです。
物質タスク型に偏った組織の症状
・「マニュアルに従えばいい」と思考停止が広がる
・監査や審査は乗り切れるが、現場の士気は低下
・改善がトップダウンの押しつけになり、自発性がなくなる
・数字は一見安定しているが、裏では人材流出や不満が増える
これは、骨格は立派でも血液が流れていない「ミイラ化した組織」の姿です。
人間重視型に偏った組織の症状
一方で、人間関係や雰囲気ばかりを重視するとどうなるでしょうか?
・会議は和気あいあいとしているが、決定が曖昧で進まない
・「仲良しクラブ」になり、改善の厳しさが薄れる
・数字や仕組みの裏づけがなく、属人的な対応が増える
これは、血流は盛んでも骨格が弱い「軟体動物のような組織」です。
バランスこそが成長の鍵
大切なのは、物質タスク型と人間重視型のバランスです。
ISOやPDCAが示す仕組みは「骨格」であり、企業を支えるフレームワークです。
一方で、人に関わる力は「血液」であり、組織にエネルギーとしなやかさを与えます。
骨格と血液がそろうとき、企業は持続的に改善を続け、成長を加速させます。
二輪をそろえた企業
ある製造業では、ISO維持に必要な作業は最小限にとどめ、浮いたリソースを「自律型人財育成」に振り分けました。
研修では「問題検出力」「対話力」「レジリエンス」を重点的に鍛え、現場が自ら改善を楽しむ文化を醸成しました。
結果、10年以上にわたり増収増益を達成。
ISOは「看板」ではなく「土台」として機能し、人と仕組みの両輪がかみ合ったのです。
・あなたの会社は、どちらかに偏っていませんか?
・骨格ばかりでミイラ化していないか?
・血流ばかりで軟体化していないか?
もし「片輪走行」だと感じたら、それは危険信号です。
ここまでで、仕組み(骨格)と人の力(血液)の両輪が大切だと分かりました。
では、どうすれば人と組織の成長を同時に進められるのか?
次の章では、心理学・脳科学・成人発達理論・コーチング心理学の科学をもとに、人と組織が進化する姿を紐解いていきましょう。
科学が示す人と組織の成長
ある工場で、安全活動を形だけで続けていたときのことです。
現場に掲げられたスローガンは「ゼロ災害!」。
社員たちは、毎朝唱和していました。
ところが、その工場では小さなヒヤリ・ハットが絶えず、事故につながりかねない状況が繰り返されていました。
なぜでしょうか?
答えは単純です。
人の意識や行動が変わっていなかったからです。
スローガンは声にしても、脳は危険を「当たり前」と処理し、改善の行動に結びついていなかったのです。
この事例は、「仕組み」や「標語」だけでは、人も組織も成長しないことを教えてくれます。
成長のカギは、科学が明らかにしている“人の内側のメカニズム”にあります。
バイアスを乗り越える
心理学は、人が危険や課題を見落とす原因を教えてくれます。
正常性バイアス:危険があっても「自分には関係ない」と思い込む。
確証バイアス:自分に都合のいい情報ばかり集め、リスクを軽視する。
これらを前提にして仕組みを設計しないと、「見せ物小屋」のように外面だけ整った状態に陥ります。
逆に言えば、バイアスを意識させる問いやワークを組み込むことで、人は「自分ごと」として考えられるようになります。
行動を変えるホルモンの力
脳科学は、人がどのように行動を習慣化するかを解明しています。
ドーパミン:達成感や喜びを感じると分泌され、次の行動を促す。
オキシトシン:仲間との信頼や一体感を強め、協力行動を生む。
コルチゾール:過度なストレスで分泌されると、判断力が低下する。
つまり、改善や安全活動を「楽しい」「達成感がある」と感じさせれば、脳は自然とその行動を強化します。
逆に「やらされ感」や「恐怖」で進めると、脳は防衛的になり、行動が続きません。
自律から相互自律へ
成人発達理論では、人は発達段階を経て成長していきます。
1. 他律:上からの指示に従う段階
2. 自律:自分で考え、判断する段階
3. 相互自律:仲間と協働し、全体最適を意識する段階
多くの組織が「他律」レベルで止まっています。
安全も品質も「言われたからやる」という段階に留まっているのです。
しかし、本当に強い組織は「相互自律」に到達しています。
社員が自分で考え、仲間と共に改善を楽しみ、組織全体で成長する。
これは、ISOの文書には書かれていませんが、最も価値のある成果です。
問いと承認の力
コーチング心理学は、人を動かすのは「問い」と「承認」であることを示しています。
「なぜこれが危険だと思う?」と問うことで、自分の頭で考え始める。
「よく気づいたね」「ありがとう」と承認されることで、次の行動への意欲が高まる。
これは、単なるコミュニケーションではなく、科学的に証明された動機づけの方法です。
改善を文化にするには、社員が自ら考え、承認されるプロセスを日常に組み込むことが欠かせません。
個人の成長と組織の成長を結びつける
心理学・脳科学・成人発達理論・コーチング心理学を統合したアプローチが、「組織開発」です。
個人の成長:自律性を高め、改善の主体者になる
組織の成長:対話や協力を基盤に、全体最適を目指す
循環:個人が育つと組織が育ち、組織が育つとまた個人が育つ
この循環が回り始めたとき、ISOは単なる証書ではなく、「人と組織が進化する舞台」へと変わります。
組織は、一人ひとりが光る「灯り」の集合体です。
心理学は灯りの色を変え、脳科学は灯りを強くし、成人発達理論は灯りの広がりを示し、コーチング心理学は灯りをつなげます。
組織開発は、それらを集めて「街全体を明るく照らす仕組み」にするのです。
あなたの会社の灯りは、十分に輝いていますか?
まだ「他律」に留まっていませんか?
人が自ら考え、仲間と協働する仕組みはありますか?
問いと承認が日常に組み込まれていますか?
もし「まだ足りない」と感じたなら、それは伸びしろです。
続いては、ISOにリソースをかけることをやめ、人財育成に舵を切った企業の事例を紹介します。
人と組織が成長する姿を、現実の物語としてお伝えしましょう。
人的資本経営の落とし穴―畑を耕すだけでは実らない
近年、「人的資本経営」という言葉がビジネス誌を賑わせています。
人的資本の情報開示が義務化され、多くの企業が「教育研修制度」「キャリア開発支援」「人事評価制度の刷新」などを次々と打ち出しています。
表面だけを見ると、日本企業は大きな変革期にあるかのように見えます。
しかし、実際に現場で働く人々の声を聞くと、そこには深刻なギャップが存在します。
「制度はある、でも人が育たない」現実
ある会社では、人的資本経営の名のもとに、膨大な予算を投じて立派な教育制度を整備しました。
外部講師を呼び、最先端のプログラムを導入し、研修参加率も100%。
ところが、数年経っても次世代リーダーは育たず、むしろ若手の離職率が上がってしまったのです。
経営会議で挙がった言葉はこうでした。
「研修はやっているのに、なぜ人が育たないんだ?」
答えはシンプルです。
「仕組みを作ること」と「人を育てること」は”別物”だからです。
心理学と脳科学が示す“育たない理由”
1. 外発的動機の限界
「上司に言われたから」「昇進に必要だから」といった動機では、脳の学習定着は弱い。
本人が内発的に意味を感じないと、人は変わらない。
2. 承認不足
せっかく学んでも「どうせ評価されない」と思えば、自己効力感が下がり、行動は続かない。
心理学で言う「学習性無力感」がここで生まれる。
3. 孤立感
人は仲間とのつながりを感じたときに、オキシトシンが分泌され、やる気や安心感が高まる。
ところが、制度が個人単位に偏ると、孤独な学びになり、職場に戻った瞬間に萎んでしまう。
成人発達理論から見る「人的資本の空回り」
成人発達理論では、人は「他律→自律→相互自律」と成長します。
ところが、多くの人的資本経営は「他律」の枠組みに閉じ込めてしまいます。
「この研修を受けなさい」
「このキャリアパスを選びなさい」
こうした指示型の仕組みは、一見すると整っていても、本人の自律性を奪い、結局は相互自律(仲間と共に創造する段階)に到達できないのです。
畑を耕すだけでは作物は育たない
人的資本経営を「農業」に例えてみましょう。
制度や研修は「畑を耕すこと」
研修カリキュラムは「種をまくこと」
しかし、これだけでは作物は育ちません。
必要なのは「水」「太陽」「肥料」。
つまり――
水=承認(日々の声かけ、感謝、評価)
太陽=つながり(仲間意識、チームワーク)
肥料=問いと学び(考える力を引き出すコーチング)
これらが揃って初めて、人という“作物”は根を張り、花を咲かせ、実を結ぶのです。
「人が辞めてしまう」本当の理由
経営者の多くは、若手が辞めると「忍耐力が足りない」「Z世代だから」と片付けます。
しかし実際には、制度や研修を整えても「心が育たない」から去っていくのです。
彼らが本当に求めているのは、
自分の存在が認められること
成長の実感が得られること
仲間と共に未来をつくっていけること
人的資本経営が、これらを満たさない限り、人は辞め続けます。
あなたの会社の人的資本経営はどうでしょうか?
制度の充実だけを誇っていませんか?
研修をやって「やった感」に浸っていませんか?
本当に人は育ち、辞めずに定着していますか?
人的資本経営は、「開示資料のための制度」ではなく、「人が輝くための実践」でなければ意味がありません。
本当の人的資本経営とは
ISOも人的資本経営も、仕組みは大切です。
しかし、仕組みはスタートラインに過ぎないのです。
必要なのは、仕組みを「人が育つ場」へと進化させること。
対話、承認、レジリエンス、相互自律
これらが根づいたとき、人的資本経営は単なる制度ではなく、「人と組織が未来を共に創る営み」となります。
経営者の皆さん―― あなたの会社の人的資本経営は、「畑を耕すだけ」で終わっていませんか?
それとも、水と太陽と肥料を与え、人が本当に育つ環境をつくっていますか?
このコラムを書いたプロフェッショナル

坂田 和則
マネジメントコンサルティング2部 部長 改善ファシリテーター・マスタートレーナー
問題/課題解決を現場目線から見つめ、クライアントが気付いている原因はもちろん、その背景にある奥深い原因やメンタルモデルも意識させ、問題/課題改善モチベーションを高めます。
その先の未来には、改善レジリエンスの高い人材が活躍します。

坂田 和則
マネジメントコンサルティング2部 部長 改善ファシリテーター・マスタートレーナー
問題/課題解決を現場目線から見つめ、クライアントが気付いている原因はもちろん、その背景にある奥深い原因やメンタルモデルも意識させ、問題/課題改善モチベーションを高めます。
その先の未来には、改善レジリエンスの高い人材が活躍します。
問題/課題解決を現場目線から見つめ、クライアントが気付いている原因はもちろん、その背景にある奥深い原因やメンタルモデルも意識させ、問題/課題改善モチベーションを高めます。
その先の未来には、改善レジリエンスの高い人材が活躍します。
| 得意分野 | モチベーション・組織活性化、リーダーシップ、コーチング・ファシリテーション、コミュニケーション、ロジカルシンキング・課題解決 |
|---|---|
| 対応エリア | 全国 |
| 所在地 | 港区 |
このプロフェッショナルの関連情報
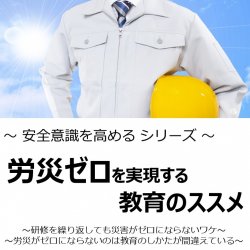
- 無料
- WEBセミナー(オンライン)
- モチベーション・組織活性化
- 安全衛生・メンタルヘルス
- コーチング・ファシリテーション
- コミュニケーション
- ロジカルシンキング・課題解決
【11/17開催】【無料セミナー】~ 安全意識を高める シリーズ ~
労災ゼロを実現する 教育のススメ
開催日:2025/11/17(月) 13:30 ~ 15:30
- 無料
- WEBセミナー(オンライン)
- モチベーション・組織活性化
- キャリア開発
- リーダーシップ
- コーチング・ファシリテーション
- ロジカルシンキング・課題解決
【11/18開催】「なぜを5回繰り返せ」が上手くいかない理由はこれだ!
なぜなぜ分析12カ条 体験セミナー
開催日:2025/11/18(火) 13:30 ~ 14:45
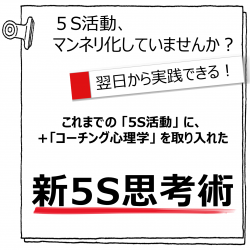
- 無料
- WEBセミナー(オンライン)
- モチベーション・組織活性化
- リーダーシップ
- コーチング・ファシリテーション
- チームビルディング
- コミュニケーション
【12/3開催】 5S活動 × その気にさせる心理学 =『 新5S思考術』体験セミナー
~継続できる5S活動とは~
開催日:2025/12/03(水) 13:30 ~ 15:00
- 参考になった0
- 共感できる0
- 実践したい0
- 考えさせられる0
- 理解しやすい0
無料会員登録
記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。


 テーマで探す
テーマで探す サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 学び・実務
学び・実務





 イベント
イベント








