【前編】真の緊急時対応訓練とは│人の行動の揺らぎに備える

あの日、酸性液体のシャワーが降った
30年近く前のことです。
私は、まだ製造現場で働いていました。
普段の仕事は淡々と進み、特に緊急事態を想定するような緊張感はありませんでした。
ところが、その日突然、忘れられない光景が、私の目の前で広がったのです。
ある工程の近くを歩いていたときのことでした。
突然、鋭い音とともに配管が破損し、そこから酸性液体が勢いよく噴き出しました。
高い位置に取り付けられていた塩ビ配管の損傷部分から、まるでシャワーのように液体が四方八方に飛び散り、雨のように降り注ぎました。
光が反射して飛沫がキラキラと散る様子は、今思い返しても妙に鮮烈で、恐怖と非現実感が入り混じる光景でした。
幸いにも、その落下地点に人はおらず、直接の被液は免れましたが、その危険性は言葉にできないほどのものでした。
その瞬間、周囲の人たちが見せた行動は、私の想像を大きく超えるものでした。
ある人は、飛散点をじっと見つめたまま動けなくなりました。
体が硬直し、ただその場に立ち尽くすだけ。
これが「フリーズ反応」だと後から知るのですが、そのときは「なぜ動かないんだ!?」と焦燥感に駆られました。
別の人は、何も言わずに走って逃げました。
自分の身を守るために、本能的に出口へと一直線に向かう姿は理解できるものの、周囲に声をかける余裕はなく、ただ自分を守ることに集中しているようでした。
そして、驚いたことに、ある人は果敢にも発生点に近づこうとしました。
「原因を止めて被害を最小化しよう」という使命感からでしょう。
しかし、強酸が飛び散る状況下に踏み込もうとする姿は、危険極まりないものでした。
勇敢さと無謀さは、紙一重です。
私は、その人を後ろから両脇で抱きかかえるようにして、引っ張り出しました。
今振り返れば、その瞬間に「二次被害を防ぐ」ための最も重要な介入をしていたのだと思います。
しかし最も衝撃的だったのは、その場にいた職場の責任者の行動でした。
いや、正確に言うなら「行動できなかった」というべきでしょう。
彼は、膝を床につき、頭を抱えて震えていました。
私は「大丈夫ですか!?」と声をかけ、肩を叩きましたが、返ってきたのはうなずきだけ。
目は虚ろで、指示を出すこともできませんでした。
普段は頼りがいのある管理職であっただけに、その姿は現場の人間にとって大きな動揺をもたらしました。
そんな中で、私は自分でも驚くほど大きな声を上げていました。
「安全確保!避難!避難!」
今まで生きてきた中で、一番大きな声だったと思います。
声を出すと同時に、自分自身も「やらなければ」というモードに切り替わっていきました。
その声を聞いて、避難を始める人もいれば、固まったまま動かない人もいました。
責任者は、依然として動けないままでした。
そこで私は思い切って、責任者に向かって叫びました。
「私がこの後の指揮をとります。いいですね!?」
彼は、ただただ頷くだけでした。
若い自分が、責任者を差し置いて指揮を執るなど、本来ならためらう場面です。
しかし、その瞬間は迷っている時間がないと悟りました。
避難を促し、全員を外へ誘導し、さらに「元バルブを閉めろ!」と指示しました。
誰が実際にバルブを閉めたのかは分かりませんが、その行動によって酸性液体の飛散はようやく収束に向かいました。
後続の中和処理や応急処置、製品への影響確認などは、各担当部署が集まり組織としての事故対応が始まりました。
しかし、私の中に強烈に残ったのは「人は危機の中で必ずしも合理的には動かない」という事実でした。
固まる人、逃げる人、突っ込む人、動けない責任者・・・・そして、若手の自分が代わりに指揮を執ったという事実。
あのときの光景は、30年経った今でも鮮明に脳裏に浮かびます。
この体験は、単なる「化学物質事故」ではなく、私にとって「人間の心理の実相」を突きつける事件でした。
嵐の中の船―人の行動は揺らぐ
緊急事態に直面したとき、人は必ずしも冷静に、合理的に動くわけではありません。
むしろ、想定外の行動が次々と現れる。
それは、私が酸性液体の事故で目の当たりにした現実でしたが、このことをより多くの人に理解していただくために、私はよく「嵐の中の船」という比喩を使います。
想像してみてください。
あなたは仲間と一緒に、大海原を航海している最中、突然大嵐に巻き込まれたとします。
激しい風が帆をはためかせ、船体は大きく揺さぶられ、甲板には雨と波が打ち付けます。
そのとき、船の乗組員たちはどのように動くでしょうか。
ある者は、帆を下ろさねばならないと分かっていながら、恐怖に体を固めてしまいます。
風に煽られる帆をただ見つめるばかりで、手も足も動かず、頭の中は真っ白です。
また、ある者は「このままでは沈む」と感じ、小さな救命ボートを降ろして自分だけでも逃げ出そうとします。
仲間のことを顧みる余裕はなく、本能の赴くままに「ここから離れたい」という一心で動いてしまうのです。
さらに、勇敢さを誇る者は、逆にマストを登り、嵐の中で帆を必死に操作しようとします。
自分が何とかしなければ、船は助からないと信じて疑わないからです。
しかし、荒れ狂う風の中でマストに登ることは、最も危険で、命を落としかねない行動です。
そして・・・・・本来なら冷静に指示を出すべき船長が、その場に膝をつき、頭を抱えて動けなくなることさえあります。
普段は頼れる存在であっても、極限状況では心が耐えきれず、思考も体も機能を停止してしまうのです。
この比喩は、私が経験した酸性液体事故での光景と重なります。
固まる人、逃げる人、突っ込む人、動けない責任者・・・・それぞれの姿がまるで「嵐の中の船」で揺さぶられる人々の姿と一致するのです。
ここで重要なのは、誰が「正しい」「間違っている」ではありません。
むしろ人間とは本来、こうした多様な反応を示す存在であるということです。
理屈やマニュアルよりも、情動や本能が優先されるのが緊急時の人間なのです。
しかし、この「揺らぎ」をどう扱うかが、組織の運命を大きく左右します。
・嵐の中で、固まった仲間に声をかけ、恐怖で動けない手を握って一緒に動かす者がいるかどうか。
・救命ボートに飛び乗ろうとする者を制止し、仲間を置き去りにしないよう導けるかどうか。
・無謀にマストに登ろうとする者を後ろから抱えて止め、安全を優先させられるかどうか。
・動けなくなった船長に「代わりに私が指揮を執ります」と宣言し、舵を取る覚悟を持てるかどうか。
この行動の違いが、生死を分けるのです。
緊急時の対応を「嵐の中の船」としてイメージすると、読者の皆さんも「自分はどの行動を取るだろう?」と自然に想像できるはずです。
固まるのか、逃げるのか、突っ込むのか、それとも声を出して仲間を動かすのか。
そして大切なのは、「どれが良い悪い」ではなく、「それが現実に起こる」ということを前提に備えることです。
人間の行動は揺らぎます。
感情は乱れます。
だからこそ、緊急時対応訓練では「人の動き・情動の動き」をリスクとして、見込まなければならないのです。
嵐の中で船を守るのは、マニュアル通りの冷静な操作だけではありません。
仲間の揺らぎを理解し、そこにどう介入するかという“人への眼差し”が求められるのです。
私がこの比喩を使うのは、あなたやセミナー受講者の頭の中に「嵐の船上の自分」という映像を思い描いてほしいからです。
そうすれば、訓練や準備の意味が、単なる儀式ではなく、「自分を、仲間を救うリアルな力」に変わるからです。
緊急時、人間は合理的には動かない
私たちは、緊急時の対応を考えるときに、つい「人は理性的に動く」と期待してしまいます。
マニュアルを読めば分かるし、訓練をすればその通りに動けるだろうと。
しかし、実際に事故や災害が起きると、目の前で繰り広げられるのは理屈では説明できない人間行動の数々です。
ここでは、心理学や行動科学の知見を使って、その「非合理な反応」を解き明かしてみたいと思います。
1.フリーズ反応―動けなくなる人
危険が迫ると、人は「逃げる」か「戦う」かの二択を取るとよく言われます。
しかし実際にはもうひとつ、「凍りつく(フリーズ)」という反応が存在します。
強烈な恐怖や驚きに直面したとき、体は硬直し、頭は真っ白になり、視線だけが危険源に釘付けになるのです。
これは動物行動学的には「捕食者に気づかれないための防御反応」と考えられています。
つまり、人間も進化の過程で身につけた、本能的な行動なのです。
現代の職場では、フリーズは命を危険にさらすリスクですが、本人に悪意があるわけではありません。
むしろ誰でも、同じ条件で起こり得る自然な反応なのです。
2.フライト反応―何も言わずに逃げる人
次に多いのが、「フライト(逃走)」です。
危険を感じた瞬間に、自分の身を守ることだけに意識が集中し、仲間への声掛けもなく出口へ走ってしまう。
これもまた、人間として極めて自然な行動です。
ここで重要なのは、逃げる人を責めるのではなく、「逃げ出す人は必ずいる」と前提にすることです。
だからこそ訓練では、逃げる人がいても、残りの人が混乱しないように設計する必要があるのです。
3.ヒーロー行動―危険に突っ込む人
緊急時に必ず現れるのが、「ヒーロー」的に振る舞う人です。
危険源に近づき、「自分が止めなければ」、「原因を突き止めなければ」と行動してしまう。
これは強い責任感や使命感から生まれる行動ですが、冷静に見れば無謀な行為であり、二次被害を招きかねません。
行動科学では、こうした行動は「プロソーシャル行動(他者や組織を助けたい気持ち)」の一形態と説明されます。
つまり善意から出る行動なのですが、安全文化の視点からは「勇敢さと無謀さの境界」をどう教育するかが課題になります。
4.リーダーの無力化―動けなくなる管理職
私が目撃した中で、最も衝撃的だった行動は、責任者が膝をつき、頭を抱えて動けなくなった場面でした。
普段は冷静で頼れる存在が、緊急時では、まるで別人のように無力化してしまう。
これは、心理学的な「急性ストレス反応」のひとつであり、「トンネルビジョン(視野狭窄)」や「解離反応」と呼ばれる現象に近いものです。
責任感が強い人ほど、「想定外の事態に直面したときの自己効力感の崩壊」が起こりやすいのです。
指揮系統のトップが動けなくなることは、組織全体の混乱を拡大させます。
だからこそ、緊急時対応訓練では「リーダーが動けない場合をどうするか」まで想定する必要があります。
5.エマージェント・リーダーシップ―その場に生まれる指揮
事故の際、私は若手でありながら責任者の前で「私が指揮をとります」と宣言しました。
これは、社会心理学でいう「エマージェント・リーダーシップ(状況的リーダーシップ)」の典型です。
リーダーシップは必ずしも役職や年齢で決まるものではなく、状況によって自然に立ち上がる人が現れる。
大声を出すことで周囲に、「この人の指示に従おう」と思わせ、行動を収束させることができるのです。
この「一声」は、緊急時において何よりも大きな意味を持ちます。
6.声掛けと身体介入の効果
心理学には、「外部刺激が認知を切り替える」という考え方があります。
固まった人も、「避難!」という強い声を受けて、初めて行動を起こすことがあります。
逆に、勇敢に突っ込もうとする人を後ろから抱えて引き止める・・・・これもまた「身体介入」による外部刺激で、危険な行動を止める効果を発揮します。
ここで大事なのは、声や身体を使った介入は決して「乱暴」でも「パワハラ」でもなく、命を守るための正しい行為であるということです。
緊急時には、「優しく諭す」よりも「短く強い声」「直接的な制止」が、必要になる場面があるのです
いかがですか?
私が体験したことを、心理学や行動科学などの“科学”の視点で、読み、考えると、人って様々なタイプがいることが解ります。
そして、緊急時の人間行動は予想外であり、必ずしも合理的ではありません。
これらはすべて「人間である以上起こり得る反応」なのです。
だからこそ、緊急時対応を考えるときに大切なのは「マニュアル通りに動ける」と過信しないことです。
人は合理的には動かない。
その前提に立って、訓練や準備の中に「人間の揺らぎ」を組み込むことが、真の安全文化を築く第一歩なのです。
続きは【後編】へ
このコラムを書いたプロフェッショナル

坂田 和則
マネジメントコンサルティング2部 部長 改善ファシリテーター・マスタートレーナー
問題/課題解決を現場目線から見つめ、クライアントが気付いている原因はもちろん、その背景にある奥深い原因やメンタルモデルも意識させ、問題/課題改善モチベーションを高めます。
その先の未来には、改善レジリエンスの高い人材が活躍します。

坂田 和則
マネジメントコンサルティング2部 部長 改善ファシリテーター・マスタートレーナー
問題/課題解決を現場目線から見つめ、クライアントが気付いている原因はもちろん、その背景にある奥深い原因やメンタルモデルも意識させ、問題/課題改善モチベーションを高めます。
その先の未来には、改善レジリエンスの高い人材が活躍します。
問題/課題解決を現場目線から見つめ、クライアントが気付いている原因はもちろん、その背景にある奥深い原因やメンタルモデルも意識させ、問題/課題改善モチベーションを高めます。
その先の未来には、改善レジリエンスの高い人材が活躍します。
| 得意分野 | モチベーション・組織活性化、リーダーシップ、コーチング・ファシリテーション、コミュニケーション、ロジカルシンキング・課題解決 |
|---|---|
| 対応エリア | 全国 |
| 所在地 | 港区 |
このプロフェッショナルの関連情報
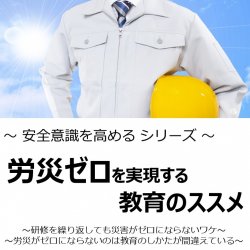
- 無料
- WEBセミナー(オンライン)
- モチベーション・組織活性化
- 安全衛生・メンタルヘルス
- コーチング・ファシリテーション
- コミュニケーション
- ロジカルシンキング・課題解決
【11/17開催】【無料セミナー】~ 安全意識を高める シリーズ ~
労災ゼロを実現する 教育のススメ
開催日:2025/11/17(月) 13:30 ~ 15:30
- 無料
- WEBセミナー(オンライン)
- モチベーション・組織活性化
- キャリア開発
- リーダーシップ
- コーチング・ファシリテーション
- ロジカルシンキング・課題解決
【11/18開催】「なぜを5回繰り返せ」が上手くいかない理由はこれだ!
なぜなぜ分析12カ条 体験セミナー
開催日:2025/11/18(火) 13:30 ~ 14:45
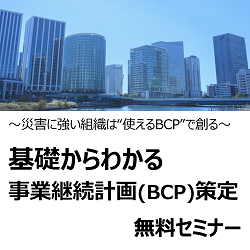
- 無料
- WEBセミナー(オンライン)
- 安全衛生・メンタルヘルス
- マネジメント
- リスクマネジメント・情報管理
- 法務・品質管理・ISO
- その他
【11/26開催・無料】 基礎からわかる事業継続計画(BCP)策定セミナー
~ 災害に強い組織は“使えるBCP”で創る ~
開催日:2025/11/26(水) 13:30 ~ 15:00
- 参考になった0
- 共感できる0
- 実践したい0
- 考えさせられる0
- 理解しやすい0
無料会員登録
記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。


 テーマで探す
テーマで探す サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 学び・実務
学び・実務





 イベント
イベント









