【後編】AI時代の羅針盤│原理原則思考が拓くキャリア

このコラムは、前編からの続きになります。
原理原則を科学的に裏付る
「原理原則思考は大事だ」と言われても、「それって経験則でしょ?」と思う方がいるかもしれません。
けれど実は、この思考法は心理学・脳科学・成人発達理論といった科学の視点からも、裏付けされています。
ここでは、原理原則思考の効果を、3つの科学的レンズで解き明かしていきます。
脳科学のレンズ―ワーキングメモリと学習効率
人間の脳には、「ワーキングメモリ」と呼ばれる作業台のような機能があります。
容量は、とても限られていて、同時に処理できる情報はおよそ7つ前後。
例えば、ある業務手順を丸暗記しようとすれば、変更がある度にすべての手順を意識的に覚え直さなければなりません。
しかし「この手順は“安全を守る”ため」「このチェックは“不良を防ぐため”」という原理原則を理解していれば、細部を覚えていなくても筋道をたどりやすくなります。
これは、脳の作業台に無駄な書類を並べずに、必要な引き出しだけを開けるイメージに近いでしょう。
結果として、思考のスピードが速くなり、余力をクリエイティブな発想や説明力に回せます。
心理学のレンズ―スキーマと認知の枠組み
心理学には、「スキーマ理論」という考え方があります。
人は新しい情報を受け取るとき、既に持っている「枠組み(スキーマ)」に当てはめて理解するのです。
例えば、エアコンの冷却原理を知らない人に、「室外機の前に物を置かないように」と伝えても、「なぜ?」と疑問が残ります。
一方で、「部屋の中で集めた熱を、室外機を経由して外に逃がしているから」と原理原則を知っていれば、行動の意味が腹落ちします。
つまり、原理原則を学ぶことは、スキーマを形成すること。
そうすることで、新しい知識や経験を効率よく整理し、理解を深められるのです。
成人発達理論のレンズ―成長の段階を押し上げる
成人発達理論によると、人は年齢とともに段階的に「ものの見方」を発達させます。
• 初期段階:他人の指示や規範に従う
• 次の段階:自分の枠組みを持ち、自律的に判断する
• さらに上の段階:自分の枠組みすら相対化し、柔軟に状況に応じて考える
20代から30代前半は、まさに「他者の枠組み」から「自分の枠組み」へ移行する重要な時期です。
このとき、原理原則思考を身につけることは、自分の判断軸を築き、発達のステージを一気に押し上げるきっかけになります。
不安が安心に変わった瞬間
ある若手社員が、製造現場の改善プロジェクトに参加しました。
「この作業を標準化してほしい」と指示を受け、必死にマニュアルを書き写していました。
しかし、なぜその順番なのか、なぜそのチェックが必要なのかが分からないため、自信を持てず、不安を抱えていたのです。
そこで私は、「なぜその作業があるのか?」を、一緒に確認しました。
実はその作業が、「安全に作業を終えるためのリスク回避」「不良を未然に防ぐチェックポイント」であると理解できた瞬間、彼の表情が変わりました。
「なるほど!これなら説明できます!」
彼は、原理原則を知ることで、不安が安心に変わり、自分の言葉で語れるようになったのです。
このエピソードが示すのは、原理原則思考が「安心感」「説明力」「自律性」を育むということです。
科学的効果を整理すると
脳科学的効果:ワーキングメモリの負荷を減らし、考えを効率的に進められる。
心理学的効果:スキーマが形成され、新しい情報を整理・理解しやすくなる。
成人発達理論的効果:若手が自律的判断へと成長し、リーダー候補として育つ。
人財育成計画
人事部の方々にとって、この科学的裏付けは「教育投資の正当性」を示す材料になります。
「原理原則思考は大切です」と感覚的に伝えるだけでは響きにくいですが、脳科学・心理学・発達理論で裏打ちされた説明をすれば、研修カリキュラムに組み込む意義が明確になります。
さらに、原理原則思考を持つ若手は、不安やストレスに強く、レジリエンスを発揮できる人材に育ちます。
これはVUCAの時代に求められる、まさに戦略的人財なのです。
教育訓練計画や人財開発には、組み込みたいコンテンツですね。
そして、この原理原則思考は、不安やストレスを軽減し、レジリエンスを高めることもできます。
さらに、掘り下げていきましょう。
原理原則思考がもたらす効果
仕事をしていると、誰もが必ず「不安」や「ストレス」に直面します。
納期が迫っている、初めてのプロジェクトに参加する、先輩から難しい仕事を任される……。
20代や30代前半のビジネスパーソンにとって、これらは日常の一部かもしれません。
私自身も若い頃(今でも?)は、夜眠れないほどの不安を抱えたことがありました。
「これでいいのか?」「自分にできるのか?」
――そんな思いで心がいっぱいになったことを、今でも覚えています。
しかし振り返ると、その不安を乗り越えられた背景には、いつも「原理原則」がありました。
原理原則を知っていたからこそ、状況を正しく捉え直すことができ、前に進む力を持てたのです。
不安を減らす―予測可能性がもたらす安心
脳科学によれば、人は「先が読めないこと」に強いストレスを感じます。
未来が不透明だと、脳の扁桃体が過剰に反応し、不安や恐怖が増幅されるのです。
原理原則を知っていると、この「不透明さ」が減ります。
例えば、エアコンの仕組みを知っていれば、「外が暑いのにどうして部屋は冷えるの?」という漠然とした疑問は消えます。
同じように、業務においても「この手順は品質を守るため」「この確認は安全を確保するため」と理解できれば、ただ漠然とした不安ではなく、筋の通った安心感が得られるのです。
ストレスを軽減する―コントロール感を取り戻す
心理学では、「コントロール感」がストレスを左右すると言われています。
「自分が状況をコントロールできている」と感じるとき、人はストレスに強くなります。
逆に「自分には何もできない」と思うと、ストレスは増大します。
原理原則を知っていると、たとえ困難な状況でも「どう考えればいいか」が見えます。
それは「行動の選択肢」を持つことにつながり、自分の力でコントロールしている感覚が得られます。
レジリエンスを高める―困難を糧にする力
レジリエンスとは、逆境や失敗から立ち直る力のこと。
原理原則思考は、このレジリエンスを育てる大きな要素になります。
たとえば、プロジェクトで失敗したとき、原理原則を知らない人は「自分が悪かった」「全部ダメだ」と自分を責めがちです。
一方、原理原則を持つ人は、「この部分の仕組みに問題があった」「プロセスをこう改善すればいい」と建設的に考えられます。
つまり失敗を「自分の価値」ではなく、「仕組みの問題」として捉え直せるため、早く立ち直ることができます。
新人時代のある出来事
あるとき、私は新人の指導をしていました。
彼は資料作成で大きなミスをし、会議で厳しく叱責されてしまいました。
落ち込んだ彼に、私はこう尋ねました。
「なぜこの資料が必要なのか、わかる?」
彼は首を横に振りました。
そこで、私は一緒に確認しました。
「この資料は上司のためではなく、製品の安全性を守るためにあるんだよ」と。
その瞬間、彼は、肩の力が抜け表情が変わりました。
「そうだったんですね。じゃあ次はこう直せばいいですね」
不安とストレスで押しつぶされそうだった彼は、原理原則を知ることで、前を向く力を取り戻したのです。
科学が示す3つの効果
整理すると、原理原則思考がもたらす効果は、科学的に次のように説明できます。
不安を減らす
脳科学的に、予測可能性が増すことで扁桃体の反応が和らぎ、安心感が生まれる。
ストレスを軽減する
心理学的に、コントロール感が回復し、「自分にもできる」と思える。
レジリエンスを高める
成人発達理論的に、困難を「自分の失敗」ではなく「仕組みの改善点」と捉えられ、成長につながる。
人を育てる側の視線
人材育成において、ストレスマネジメントやメンタルヘルスは、大きなテーマです。
しかし、「心を強くしましょう」とだけ伝えても、効果は限定的です。
そこに「原理原則思考」を組み込めば、若手は自分の頭で考え、不安を減らし、困難を前進の糧にできます。
これは、単なるストレス対処ではなく、レジリエントな人財を育てる教育戦略となります。
若手を育てる
これまでお話ししてきたように、原理原則思考は若手にとって「考える力の土台」であり、不安やストレスを減らし、レジリエンスを育てる強力な武器です。
ここからは、人事部や教育担当者の方に向けて、どのようにこの思考法を育成プログラムに組み込むべきかを考えていきましょう。
なぜ今、原理原則思考を育成に組み込むべきか
時代は大きく変わりました。
生成AIが普及し、知識や答えは誰もが瞬時に手に入れることができます。
つまり「知っていること」だけでは差別化できない時代になったのです。
必要なことは「知識をどう捉え、どう使うか」。
原理原則を理解し、考えの軸を持った人財こそが、これからの組織をリードします。
そして20〜30代前半は、まさにキャリア形成の黄金期。
この時期に原理原則思考を身につけさせることは、企業にとって「未来への投資」となります。
教育への組み込み方―3つのアプローチ
1.身近な例から始めるワーク
最初から難しい理論を教える必要はありません。
むしろ、日常生活にある身近な原理原則を題材にすることで、若手は「なるほど!」と腑に落ちやすくなります。
• エアコンの仕組み→「熱は移動する」という物理の原理
• 交通ルール→「安全を守るための最小限の約束」
• 料理のレシピ→「化学反応としての加熱や調味」
• あいさつ→「相手の立場や存在を認め、経緯を持って話す姿勢を示す。」
こうした事例から始めると、「原理原則は身近なところにある」と実感でき、職場での学びに結びつきやすくなります。
2.実務に直結するケーススタディ
若手が最も悩むのは、「現場でどう考えればいいかが分からない」ということです。
そこで、日々の仕事にある課題を「原理原則」に照らして考えるケーススタディを取り入れましょう。
• 品質管理なら「なぜ検査が必要なのか」を原理から考える
• 安全教育なら「なぜヘルメットをかぶるのか」を科学的に説明する
• コミュニケーションなら「なぜ確認が必要か」を心理学的に理解する
こうした実務との接続が、原理原則思考を「机上の理論」ではなく「使える武器」に変えます。
3.生成AI活用と組み合わせる
AIの答えを鵜呑みにせず、「なぜその答えになったのか?」と問い返すトレーニングを取り入れることも効果的です。
• 「ISO9001の改訂点を教えて」と聞くだけでなく、「文書管理の原理原則に照らすと、改訂点はどう説明できる?」とAIに問いかける。
• 出てきた答えを「本当に原理に合っているか?」と検証させる。
これにより、AI時代に必要な「使う側の人財」を育成できます。
学習環境をデザインする
人事部や教育担当者は、単に知識を提供するだけでなく、「考える環境」をデザインする役割を担っています。
具体的には、
• 「なぜ?」を問いかける文化をつくる
• 「なぜ?」と問いを抱くことが正しい行動と認める
• 原理原則に立ち返る習慣を促す
• 失敗を責めるのではなく「仕組みを見直そう」と導く
この環境があれば、若手は自然と原理原則思考を育み、安心して挑戦できるようになります。
人事部の投資が組織を変える
ある企業の人事部が、若手研修に「原理原則思考ワーク」を導入しました。
テーマは、「なぜ安全靴を履くのか」。
受講者は最初「決まりだから」と答えました。
しかし講師が、「衝撃吸収の原理」「足の骨の構造」「事故時のリスク低減効果」を解説すると、受講者の表情が一変しました。
「なるほど!だから大切なんだ」と。
その後、現場での安全意識が高まり、指示されなくても自主的に声を掛け合う文化が生まれたのです。
これは、人事部が原理原則を育成に取り入れた結果、組織の文化そのものが変わった例です。
育成戦略の核としての原理原則思考
若手育成の最初期から原理原則を教える
ただのルール遵守ではなく、背景にある「なぜ?」を理解させる。
現場での事例とセットで伝える
机上ではなく、実際の業務や安全に直結させることで浸透する。
AI時代を見据えて“問いを立てる力”を育む
AIを使いこなす人財を育てるために、原理原則思考をベースにした質問力を磨かせる。
人事部にとって、原理原則思考は「教育テーマの一つ」ではなく、すべての教育の基盤となるものです。
これを若手育成に組み込むことで、社員は知識に振り回されず、自ら考え、自ら行動できる人財へと成長します。
そして組織は、変化の激しい時代にも折れない強さ
――レジリエンスを備えた集団へと進化します。
未来を切り拓く思考法
ここまで読み進めてくださったあなたに、まずは感謝をお伝えしたいと思います。
忙しい日々の中で「自分の学び」に時間を割くことは、簡単なことではありません。
それでも、このコラムに目を通してくださったということは、きっとあなたの中に「もっと成長したい」「部下や若手を育てたい」という強い想いがあるのだと思います。
あなたの中にある「原理原則」
原理原則思考は、特別な才能ではありません。
誰もがすでに日常の中で、その片鱗を使っています。
例えば、
・ 電車が遅れたときに「原因はどこだろう?」と考えるとき。
・ チームでトラブルが起きたときに「根本は何か?」と探るとき。
これらはすべて、原理原則に近づこうとする自然な行為です。
つまり、あなたの中にもすでに「原理原則を求める力」が眠っているのです。
この力を少しずつ磨けば、不安を安心に変え、説明力を高め、困難をチャンスに変えることができます。
人事部・教育担当者へのメッセージ
もし、あなたが人事部や教育担当者であれば、考えてみてください。
若手社員が「なぜ?」と自ら問いを立て、原理原則を理解し、自信を持って説明できるようになったら――。
・ 会議で堂々と意見を述べる20代社員
・ 失敗を糧にし、すぐに立ち直って改善策を提案する若手リーダー
・ AIを巧みに使いこなし、戦略的な視点でチームを導く新しい世代
そんな姿が職場に増えていったら、組織の未来はどう変わるでしょうか?
きっと「人に頼られる会社」「挑戦できる会社」へと進化していくはずです。
成長を大きく加速させる
ある研修で、20代の若手社員が「自分は説明が下手で……」と悩んでいました。
彼に「なぜこの作業をするのか、原理から考えてみよう」と問いかけると、しばらく考えた後、こう答えました。
「製品の安全を守るためです。もし省略したら事故につながります」
その瞬間、彼の声は力強さを帯び、表情には自信が宿りました。
会場にいた人事担当者は、「たった一つの問いかけで、こんなに変わるんですね」と驚いていました。
原理原則思考は、人を変える力を持っています。
それは、難しい理論ではなく、「本質を見つめる習慣」を与えるだけ。
でも、その一歩が人の成長を大きく加速させるのです。
あなたへの問いかけ
• あなた自身は、どんな原理原則を軸に仕事をしていますか?
• あなたの周りの若手社員は、「なぜ?」を考えながら成長していますか?
• あなたの組織に、未来を切り拓くリーダー候補はどれだけ育っていますか?
もしここで少しでも「もっと伸ばしたい」「もっと変えていきたい」と感じたなら、それはすでに次の一歩を踏み出すサインです。
未来を切り拓くために
原理原則思考は、知識やスキルを超えた「考える力の基盤」です。
それを若手に伝えることは、単に教育をする以上の意味を持ちます。
それは、組織の未来を守り、挑戦を後押しし、レジリエンスを育てる「文化」をつくることだからです。
そして、その文化づくりの第一歩は、あなたの「関心」と「行動」から始まります。
最後に
もしこのコラムを読んで、
・ 「自分ももっと原理原則思考を学びたい」
・ 「若手育成に取り入れてみたい」
そんな気持ちが少しでも芽生えたのなら、ぜひその思いを大切にしてください。
原理原則思考は、一人で身につけるよりも、対話や体験を通じて育つものです。
あなたの組織やチームの現場に合わせて、一緒に考え、設計し、実践していくことができます。
どうか気軽に声をかけてください。
私は、あなたの挑戦に寄り添い、共に未来を切り拓くお手伝いをする準備ができています。
「原理原則を知る者が、AI時代の舵を取る」
その一歩を、あなたと一緒に踏み出せる日を楽しみにしています。
このコラムを書いたプロフェッショナル

坂田 和則
マネジメントコンサルティング2部 部長 改善ファシリテーター・マスタートレーナー
問題/課題解決を現場目線から見つめ、クライアントが気付いている原因はもちろん、その背景にある奥深い原因やメンタルモデルも意識させ、問題/課題改善モチベーションを高めます。
その先の未来には、改善レジリエンスの高い人材が活躍します。

坂田 和則
マネジメントコンサルティング2部 部長 改善ファシリテーター・マスタートレーナー
問題/課題解決を現場目線から見つめ、クライアントが気付いている原因はもちろん、その背景にある奥深い原因やメンタルモデルも意識させ、問題/課題改善モチベーションを高めます。
その先の未来には、改善レジリエンスの高い人材が活躍します。
問題/課題解決を現場目線から見つめ、クライアントが気付いている原因はもちろん、その背景にある奥深い原因やメンタルモデルも意識させ、問題/課題改善モチベーションを高めます。
その先の未来には、改善レジリエンスの高い人材が活躍します。
| 得意分野 | モチベーション・組織活性化、リーダーシップ、コーチング・ファシリテーション、コミュニケーション、ロジカルシンキング・課題解決 |
|---|---|
| 対応エリア | 全国 |
| 所在地 | 港区 |
このプロフェッショナルの関連情報
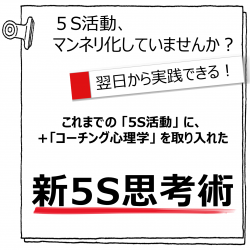
- 無料
- WEBセミナー(オンライン)
- モチベーション・組織活性化
- リーダーシップ
- コーチング・ファシリテーション
- チームビルディング
- コミュニケーション
【12/3開催】 5S活動 × その気にさせる心理学 =『 新5S思考術』体験セミナー
~継続できる5S活動とは~
開催日:2025/12/03(水) 13:30 ~ 15:00
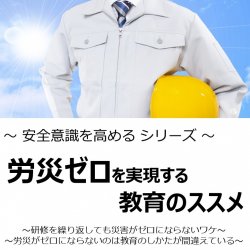
- 無料
- WEBセミナー(オンライン)
- モチベーション・組織活性化
- 安全衛生・メンタルヘルス
- リーダーシップ
- コーチング・ファシリテーション
- コミュニケーション
【1/9開催】【無料セミナー】~ 安全意識を高める シリーズ ~
労災ゼロを実現する 教育のススメ
開催日:2026/01/09(金) 13:30 ~ 15:30
- 参考になった0
- 共感できる0
- 実践したい0
- 考えさせられる0
- 理解しやすい0
無料会員登録
記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。


 テーマで探す
テーマで探す サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 学び・実務
学び・実務





 イベント
イベント









