【前編】AI時代の羅針盤 │ 原理原則思考が拓くキャリア

「このままで、自分は成長できるのだろうか?」
「若手社員にもっと主体的に動いてほしい…」
そんな思いを胸に、日々を過ごしてはいませんか。
答えをすぐに出してくれる生成AIが広まり、知識や情報は指先ひとつで手に入る時代になりました。
けれど――本当に求められているのは「知っていること」ではなく、「考える力」です。
誤った方向に進まず、効率的に物事を進め、人を納得させられる。
そして、不安やストレスに押しつぶされることなく、むしろ困難を糧にして成長できる。
そのための最強の武器こそ、原理原則思考。
若手にとっては、キャリアを飛躍させる加速装置になり、人事・教育担当者にとっては、「自走できる人財」を育てる戦略の核になります。
このコラムでは、私が30年以上の現場経験と心理学・脳科学の知見から確信した「原理原則思考の力」を、ストーリーと科学的根拠を交えてお届けします。
もしあなたが、
・「もっと成長したい」と願う20代~30代のビジネスパーソンなら。
・「次世代リーダーを育てたい」と考える人事責任者なら。
きっとこの先に書かれていることが、あなたにとっての羅針盤になるはずです。
AI時代に必要な「考える力」
あなたは最近、生成AIを使ったことがありますか?
もしかすると、会議の議事録をまとめてもらったり、企画のアイデアを出してもらったり、あるいは転職活動で自己PR文を考えるのに利用した、という方がいるかもしれません。
今や、インターネットで調べるよりも早く、膨大な知識をAIから引き出せる時代です。
ほんの数十秒で、専門的な内容を解説してくれたり、資料のたたき台をつくってくれます。
まさに「知識はいつでも取り出せる道具」となりました。
しかし、ここで立ち止まって考えてほしいのです。
もし「答えがすぐに出てくること」に慣れすぎてしまったら、私たち自身の「考える力」はどうなるでしょうか?
生成AIを便利に使う人と、ただ答えを受け取って流される人。
両者の間には、これからのキャリアにおいて、大きな差が生まれるでしょう。
「使う側」と「使われる側」
私はよく、「生成AIを使うか、使われるか」と表現します。
AIを上手に“使う側”は、自分の考えを整理し、問いを深めるためのパートナーとしてAIを活用できます。
一方で、“使われる側”は、AIから出てきた答えをそのまま信じ、ただ従うだけになってしまいます。
違いを生むのは、実は「技術の知識」ではありません。
必要なのは、「原理原則をおさえて考える力」――つまり原理原則思考なのです。
若い頃の私と「原理原則」
私は30年前、ISO9001推進室で品質管理に携わっていました。
若い頃、文書管理の仕組みづくりに悩んでいた時期があります。
会社の規定通りに文書を扱ってはいたものの、「これでは本当に品質を保証できない」と感じていました。
そのとき私を導いてくれたのが、「文書管理の原理原則」をまとめたJIS規格でした。
・文書はなぜ必要なのか?
・どのように保管、配付、管理、廃棄されるのか?
その「なぜ」「どのように」を知ることで、手順をなぞるだけでなく、仕組みそのものを改善できるようになったのです。
振り返ると、若かった私はとにかく必死でした。
知識を得ることに夢中で、原理原則を理解するたびに、目の前の霧が晴れるような感覚を味わいました。
そして、この経験が、原理原則さえおさえれば、誤った方向に進まないという確信につながったのです。
身近なものに潜む原理原則
例えば、エアコン。
冷たい風が出て、外では熱い風が吹き出す。
仕組みを知らなければ「そういうものだ」と思うだけですが、原理を理解すると見方が変わります。
「冷媒が気化するときに熱を奪い、外で凝縮するときに熱を放出する」
――これが冷房の原理です。
この知識を持つだけで、
・ なぜ室外機の周りは風通しを良くすべきなのか
・ どんな工夫をすれば省エネになるのか
・ 冷媒ガスが地球温暖化にどのように影響するのか
これらのことを、科学的に考えることができるのです。
つまり原理原則を知ることは、単に知識を増やすだけではなく、考える視点を広げ、行動を変える力になるのです。
20〜30代こそ、原理原則を学ぶ黄金期
今この文章を読んでいる、20代から30代前半のあなたへ。
キャリアの初期は、どうしても「目の前の仕事を覚えること」に追われます。
しかし、そこで原理原則思考を身につけておくと、後の成長が何倍にも加速します。
なぜなら、原理原則は「知識のハブ(知識や情報の中心的拠点)」だからです。
一つの原理を理解しておけば、そこから派生する知識を整理しやすくなり、新しい知識もスッと結びついていきます。
その結果、学習効率は高まり、人に説明するときも「分かりやすい」と評価される。
若いうちにこの力を育てることは、将来のリーダーシップ向上につながります。
人事部・教育担当者の視点
人事部や教育担当者の方にとっても、若手に原理原則思考を種を植えることは、重要な戦略です。
「資格の取得」「スキルの習得」ももちろん大切ですが、それだけでは変化の激しい時代に対応できません。
むしろ、どんな技術が現れても、揺るがずに「考える力」を持つ人材こそが、組織の未来を支えます。
原理原則思考を研修に取り入れることで、若手は「単なる作業者」から「課題を自分で捉え、解決に動ける人財」へと成長していきます。
それは結果として、組織のレジリエンス(しなやかに立ち直る力)を高め、持続的な成長へとつながるのです。
原理原則は未来を拓くカギ
生成AIが広がるこれからの時代、知識を得ること自体の大きな価値は、なくなりつつあります。
価値を生むのは、「その知識をどう捉え、どう使うか」という思考の力です。
原理原則思考は、あなたを誤った方向から修正し、効率的に考えを深め、人にわかりやすく伝える力を与えてくれます。
そして、それは不安やストレスを減らし、レジリエンスを高め、AIを戦略的に活用する基盤にもなるのです。
原理原則を知る者が、AI時代の舵を取る。
この言葉を胸に、あなた自身の成長のため、そして組織の未来のために、「原理原則思考」をこれからの学びの軸にしていただきたいと思います。
原理原則思考とは何か
「原理原則思考って、結局どういうことなんですか?」
研修で私がこの「原理原則」という言葉を口にすると、必ずと言っていいほど、若手から質問されます。
難しく考える必要はありません。
原理原則思考とは、ものごとの本質的な仕組みや法則を理解し、それを基盤に考えることです。
言い換えれば、「答えを丸暗記する」のではなく、「なぜそうなるのか」を掘り下げ、そのルールや仕組みを軸に判断する思考法です。
ただの知識と「原理原則」の違い
少しイメージしてみましょう。
あなたが新しいレシピで、料理を作るとします。
レシピ通りに材料を切り、調味料を加えれば、それなりに美味しい料理はできます。
しかし「なぜここで塩を入れるのか?」「なぜ火加減を弱めるのか?」という原理を理解していればどうでしょうか。
たとえレシピ通りの材料がなくても、別の食材で代用できますし、分量を調整する応用力も身につきます。
これが「知識」と「原理原則」の違いです。
・ 知識は「レシピ」そのもの
・ 原理原則は「料理の化学」や「味の法則」
だからこそ、原理原則を理解することで、状況が変わっても自分の頭で判断できる力が身につきます。
若き日の経験から
私はかつて、ISO9001推進室に所属していた頃、文書管理に頭を悩ませていました。
規定通りにやっていても、現場では混乱が起こり、必要な文書が探せないことが多発していたのです。
そんなとき、私はJISの「文書管理」に関する規格を読みました。
そこには、「文書はライフサイクルで管理する」という原則が書かれていました。
作成、承認、配布、改訂、廃止。
なるほど、文書とは単なる紙やデータの集まりではなく、「生まれてから役目を終えるまでの命の流れ」を持っているのだ――この理解が、私の中で大きな転機になりました。
そこからは、手順を追うだけでなく、文書の仕組み全体をデータベースで管理する発想へと至り、効率化と信頼性を両立できたのです。
若さゆえに知識を必死に吸収していたあの頃。
でも実際に役立ったのは、知識そのものよりも「原理原則を学んだこと」でした。
身近な例え―エアコンの仕組み
エアコンの話を思い出してください。
・ 冷たい風が出るのはなぜか?
・ 室外機から熱風が出るのはなぜか?
答えは、冷媒の「気化熱」と「凝縮熱」の原理にあります。
この基本を知っているだけで、省エネの工夫や環境問題への理解がぐっと深まります。
逆に、原理を知らなければ「冷えるボタンを押せば冷える」という表面的な理解にとどまり、それ以上考えることはできません。
この違いこそが「原理原則思考」と「表層的な知識」の差なのです。
科学的な裏付け
心理学・脳科学でも、原理原則思考の有効性は裏付けられています。
• スキーマ理論(認知心理学)
人は新しい情報を既存の「枠組み」に当てはめて理解します。
原理原則を持っていれば、情報は整理されやすく、忘れにくくなります。
• ワーキングメモリの負荷軽減(脳科学)
原理原則を押さえていれば「細かいことを全部覚える必要」がなくなり、脳がスムーズに働きます。
• 成人発達理論
若手のうちは「与えられた枠組み」に従いがちですが、原理原則を学ぶことで「自分の考えを持ち、状況に応じて判断する力」へと成長が加速します。
説明力・納得感を高める
原理原則を知っている人の説明は、わかりやすく、説得力があります。
なぜなら「なぜそうなるのか」を筋道立てて語れるからです。
例えば、「なぜ残業を減らさなければならないのか」を説明するとき、「会社の方針だから」と言ってしまうとそこで思考は止まってしまいます。
しかし、「脳科学的に疲労は判断力を下げ、ミスや事故につながるから」と語ると、相手の納得感が全く違います。
原理原則を持つことは、単に考える効率を上げるだけでなく、人を動かす力にもつながるのです。
変化に強いチームをつくる
人材育成に携わる方へお伝えしたいのは、原理原則思考は「スキルの上位概念」だということです。
資格や技術は変化する時代に合わせて学び直す必要がありますが、原理原則思考は普遍的な土台となり、どんなスキルも受け止めて強化する基盤になります。
若手社員に原理原則を教えることは、彼らに「一生ものの思考法」を授けることです。
それは組織の知的財産を増やし、変化に強いチームをつくる投資になるのです。
原理原則思考とは――
• 本質をとらえる「羅針盤」であり、
• 知識をつなげる「ハブ」であり、
• 人を納得させる「力強い言葉の源泉」でもある。
これを身につけることで、若手ビジネスパーソンは知識の洪水に流されず、自らの成長を加速させることができます。
そして人事部にとっては、次世代リーダーを育てるための強力な教育テーマとなるのです。
それでは、この原理原則思考が、なぜ若手にとって特に重要なのかをさらに掘り下げていきましょう。
なぜ若手に必要なのか
20代から30代前半――。
この時期は、社会人としての基盤を築く大切な時間です。
目の前の仕事に追われ、先輩や上司の指示をこなすことで精一杯になりがちですが、同時に「考え方の土台」を身につけるには、これ以上ないタイミングでもあります。
私が「原理原則思考は若手のうちにこそ学んでほしい」と強く思うのは、若き日に自分自身がそれを体験したからです。
「とりあえずやってみる」だけでは伸びない
社会人になりたての頃は、何もかもが新しく、覚えることばかりです。
先輩に教わった手順を丸暗記し、上司の指示に従って動く――それ自体は間違いではありません。
むしろ最初は必要なステップです。
しかし、この時期に「なぜそうするのか?」を自分に問いかける習慣を持つ人と持たない人では、数年後に大きな差がつきます。
ただ言われた通りに仕事をする人は、状況が変わったときに立ち止まってしまいます。
一方で、原理原則を理解している人は、自分で応用し、新しい解決策を生み出せるのです。
地図を持たずに旅をする人
想像してみてください。
Aさんは、旅行先で現地の人から「この道をまっすぐ行けば目的地に着くよ」と教わり、その通りに歩きます。
確かに着きました。
Bさんは、その土地の地図を最初に手に入れていました。
「この道を行けば着くのか」と理解すると同時に、「別のルートでも行けるな」「寄り道すれば観光もできるな」と発想が広がります。
どちらが充実した旅をするでしょうか?
原理原則を知らずにただ手順をなぞるのは、地図を持たずに旅をするようなもの。
原理原則を持つことは、人生やキャリアの地図を持つことに他なりません。
若手時代の私の気づき
私自身、20代の頃は知識を必死に覚えるだけで精一杯でした。
ところが、ISO9001推進室で文書管理に携わったとき、「なぜ文書管理が必要なのか?」を深掘りすることで、単なる事務作業が「品質保証の根幹」だと理解できたのです。
そこからは、同僚と話すときも説明が変わりました。
「規定だからやる」ではなく、「正しい情報を正しい人に届ける仕組みを守ることが、会社の信頼につながる」――そう語れるようになったのです。
この経験は、後のキャリアにおいても大きな自信になりました。
そして今思うのは、もしこの気づきが10年遅れていたら、私はここまで「改善や問題解決に強い人財育成」に情熱を持てなかっただろう、ということです。
科学的な観点からの裏付け
1.脳の可塑性
20代から30代前半は、脳が柔軟で学習能力が最も高い時期です。
この時期に「原理原則を基盤に考える癖」を身につければ、その後のキャリア全体にわたり、大きな思考資産になります。
2.成人発達理論
成人発達理論では、若手の段階は「他者の枠組みに従う」時期とされます。
ここで「自分の考えの軸=原理原則」を持ち始めることで、より高い発達段階へと進み、自律的に判断できる人材へ成長します。
3.心理的安全性との関係
原理原則を持つことで、「どう考えればいいか」が明確になり、不安や迷いが減ります。
これは心理的安全性を高め、挑戦への一歩を踏み出しやすくする効果もあります。
生産性とレジリエンスを高める人財育成
人事部・教育担当者にとって、若手育成のカリキュラムに「原理原則思考」を取り入れることは、戦略的な投資です。
スキルや資格は時代によって陳腐化しますが、原理原則思考は不変の土台です。
これを早い段階で身につけた社員は、自ら課題を発見し、上司に頼らずに改善に動ける人財へと成長します。
つまり「指示待ち社員」から「自走できる社員」へのシフトを加速できるのです。
これは人事部にとって、組織全体の生産性とレジリエンスを高める最大の武器となります。
若手にとって原理原則思考は、次のような効果を持たらします。
• 誤った方向に進まない「羅針盤」
• 学びを効率化する「加速装置」
• 説明力とリーダーシップを育む「源泉」
20代から30代前半のこの時期にこそ、原理原則思考を身につけることは、キャリアを大きく左右します。
そして人事部にとっては、次世代リーダーを育成するための最重要テーマになるのです。
【後編に続く】
このコラムを書いたプロフェッショナル

坂田 和則
マネジメントコンサルティング2部 部長 改善ファシリテーター・マスタートレーナー
問題/課題解決を現場目線から見つめ、クライアントが気付いている原因はもちろん、その背景にある奥深い原因やメンタルモデルも意識させ、問題/課題改善モチベーションを高めます。
その先の未来には、改善レジリエンスの高い人材が活躍します。

坂田 和則
マネジメントコンサルティング2部 部長 改善ファシリテーター・マスタートレーナー
問題/課題解決を現場目線から見つめ、クライアントが気付いている原因はもちろん、その背景にある奥深い原因やメンタルモデルも意識させ、問題/課題改善モチベーションを高めます。
その先の未来には、改善レジリエンスの高い人材が活躍します。
問題/課題解決を現場目線から見つめ、クライアントが気付いている原因はもちろん、その背景にある奥深い原因やメンタルモデルも意識させ、問題/課題改善モチベーションを高めます。
その先の未来には、改善レジリエンスの高い人材が活躍します。
| 得意分野 | モチベーション・組織活性化、リーダーシップ、コーチング・ファシリテーション、コミュニケーション、ロジカルシンキング・課題解決 |
|---|---|
| 対応エリア | 全国 |
| 所在地 | 港区 |
このプロフェッショナルの関連情報
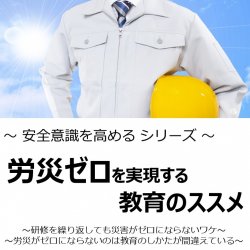
- 無料
- WEBセミナー(オンライン)
- モチベーション・組織活性化
- 安全衛生・メンタルヘルス
- コーチング・ファシリテーション
- コミュニケーション
- ロジカルシンキング・課題解決
【11/17開催】【無料セミナー】~ 安全意識を高める シリーズ ~
労災ゼロを実現する 教育のススメ
開催日:2025/11/17(月) 13:30 ~ 15:30
- 無料
- WEBセミナー(オンライン)
- モチベーション・組織活性化
- キャリア開発
- リーダーシップ
- コーチング・ファシリテーション
- ロジカルシンキング・課題解決
【11/18開催】「なぜを5回繰り返せ」が上手くいかない理由はこれだ!
なぜなぜ分析12カ条 体験セミナー
開催日:2025/11/18(火) 13:30 ~ 14:45
- 参考になった0
- 共感できる0
- 実践したい0
- 考えさせられる0
- 理解しやすい0
無料会員登録
記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。


 テーマで探す
テーマで探す サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 学び・実務
学び・実務





 イベント
イベント









