一分で伝えるやさしさ │ 話が伝わらないのは地図がないから

「一分で話せ!」という指示に、五分かける上司の不思議
「いいか、お前は一分で話せ!ダラダラ話すな!」
そう言った上司が、なぜかその説明に五分かけて語っている。
私が実際に現場で見かけた、ちょっとした“あるある”場面です。
講師として多くの研修やセミナーに立ち会う中で、この手の矛盾に苦笑いした経験、みなさんにもあるのではないでしょうか。
「一分で話せ」と言いながら、まるで“話しながら思い出しているかのように”展開されていく上司の話。
結局、「何を伝えたかったのか」。
部下は分からないまま、その場は終わる。
でも、私は思うんです。
これは、決して“悪意”ではないんですよね。
むしろ、そこには“伝えたいという善意”がある。
それが暴走してしまっているだけなんです。
「なぜ伝わらないのか?」というズレ
この現象、心理学では「意図と行動の不一致」と呼ばれたりします。
本人は「的確に伝えたつもり」でも、実際にはその行動(話し方や長さ)が、意図と食い違っている。
実際、上司自身も「あれ、ちゃんと伝えたよな?」と、首をかしげていることもあるんです。
ここにあるのは、メタ認知のズレです。
「自分の話が相手にどう聞こえているか」に気づいていない。
つまり、自分の言葉を“外側から”見る力が弱い状態です。
私の研修では、そんな上司の背中を見て育ってきた部下たちが、 「うちの上司も、話しながら自分で整理してるタイプなんで…」 と苦笑いする場面もよくあります。
自己説明効果:話しながら整理している人の心理
実は、上司が長く話してしまうのには、心理学的な理由があるんです。
それが「自己説明効果(Self-Explanation Effect)」と呼ばれるもの。
人は話すことによって、自分の思考を整理しやすくなるという現象です。
つまり、「話す=考える」になってしまっている。
頭の中で構造化せずに、その場で“リアルタイム編集”しているんですね。
この状態になると、当然ながら話は長くなります。
構成が決まっていないので、話しているうちに「あ、そういえば…」と話題が広がり、「えーっとね」と間が入り、「うーん」と悩みながら着地地点を探す。
でも、それって話し手の“脳の整理”であって、 聞いている部下にとっては「処理する情報が多すぎてついていけない」状態なんです。
認知の限界:聞き手の脳は飽和している
人間の脳には、一度に処理できる情報の量に限界があります。
これは、「ワーキングメモリ」と呼ばれる短期的な記憶装置のようなものです。
研究によれば、人が一度に保持できる情報は「7±2チャンク(単位)」程度。
つまり、8個以上の情報を立て続けに話されると、ほとんどの人は理解できなくなるんですね。
ですから、5分間の説明であれこれ言われても、 部下の脳内には「最初の話、なんだっけ?」というモヤモヤが残るばかり。
ここで必要なのが、“構造化”されたメッセージです。
要点を整理し、「何を言いたいのか」「なぜそれが大事なのか」を明確に伝える力。
まさに、それが「一分で話す力」なんですね。
「一分で話せ」はスキルではなく、思いやりである
実は、「一分で話せ」という言葉自体、 相手への“配慮”と“思いやり”の形でもあるのです。
部下の時間は有限です。
集中力もそうです。
そして、若手ほど「結論から知りたい」傾向が強くなっています。
LABプロファイルで言うなら、 上司は、詳細説明を好む「プロセス型」で背景や経緯を語りたいタイプ。
でも部下は「直感型」で、どうすればいいの?を直感的に、先に知りたいタイプ。
このギャップを放置すると、コミュニケーションはどんどんすれ違ってしまいます。
だからこそ、「一分で話す」ことは、ただの時短テクニックではなく、 相手の思考の枠組みに合わせるという“リーダーの工夫”なんです。
笑い話にしながらも、本質を見つめてみませんか?
「一分で話せ!」と叱りながら、五分以上語る上司。
そこには“想い”も“混乱”もある。
部下も、そんな姿を「なんだかなぁ」と思いながらも、 「でも、ちゃんと伝えようとしてくれてるんだな」と感じていることもある。
だから私は思うのです。
この現象を責めるのではなく、笑い話にして共有しながら、そこに潜む“本質”を見ていくことが大事だと。
「一分で話せ」という言葉に、 “部下を育てるための思いやり”と“自分の訓練”の両方が込められていたとしたら。
リーダーのあり方も、部下の受け止め方も、ちょっと変わってくる気がしませんか?
「話す」と「伝える」は違うという当たり前の真実
——乾杯が始まらない夜に、私たちは何を学ぶのか——
あるプロジェクトの打ち上げでのことです。
その上司は、開口一番こう言いました。
「本日は皆さん、本当にお疲れ様でした。えー、私がこのプロジェクトに初めて関わったのは、そうですね……○年前のことでした」
乾杯が始まるはずのその瞬間、私はグラスを持ちながら軽く笑っていました。
でも、それがまさか、人生回顧スピーチの始まりだったとは……。
その上司は、プロジェクトを軸に自分の半生を丁寧に語り続け、 気づけば時計の針は40分を超えていました。
隣の席の若手社員は、乾杯の泡が完全に消えたビールを見つめながら、 「これ、開発工程と同じくらい長いスパンですね……」と、ボソッとつぶやいていました。
“伝説の乾杯”に込められたもの
あの夜、私は笑いながらも、心のどこかで感じていました。
この人、本当にみんなに“伝えたいこと”があるんだろうな」と。
ただ、その方法が“語ること”に偏ってしまっていた。
そう、ここにあるのはまさに、「話すこと」と「伝えること」の違いなのです。
情報処理の限界 「もう入らない」脳の叫び
心理学的に言えば、私たちの脳が一度に処理できる情報の量には、限界があります。
これは、先ほど登場した「ワーキングメモリ」と呼ばれる、7±2チャンクの情報しか同時に保持できないのです。
つまり、話し手がどれだけ熱量を持って語っても、 構造化されていなければ、聞き手の脳は“飽和状態”になってしまうんですね。
話が長くなると、「どこが結論なのか」「今どの段階の話なのか」わからなくなる。
まるで、地図を持たずに旅をしているような感覚に陥ります。
ですから、「話す」と「伝える」には、明確な違いがあります。
「話す」は、自分の思考をそのまま外に出すこと。
「伝える」は、相手の思考の枠組みにあわせて、“届ける形”に加工することなのです。
伝わるには“構造”がいる
伝えるには、“話す順番”がとても大切です。
例えば、PREP法(Point→Reason→Example→Point)やSDS法(Summary→Detail→Summary)など、 構造的に整理された話法を使えば、聞き手は内容をぐっと理解しやすくなります。
実際に私の研修では、こうしたフレームを体験型で練習します。
すると、受講者は口をそろえてこう言います。
「構造を意識しただけで、相手の反応がまるで違うんですね」
そう、これは話し方の技術というより、相手への思いやりの行動なんです。
LABプロファイルから見る“ズレ”の正体
ここで、私が研修やコーチングでよく使う、LABプロファイルの視点をご紹介します。
「話すことが好きな人」は、“プロセス型”の傾向が強いことが多いです。
つまり、「経緯」「流れ」「背景」を丁寧に語るタイプです。
一方で、“直感型”の人は、「で、結論は?」「どうすればいいの?」と先に答えを求める傾向があります。
打ち上げの乾杯の例も、まさにこれ。
上司は、プロセス型で人生をたどりたい。
部下たちは、直感型で早く乾杯したい。
このギャップが、話が“伝わらない”理由のひとつなんですね。
ドーパミンと報酬の仕組み
脳科学的にも、ここには面白いメカニズムがあります。
人の脳は、「予測した報酬が得られた瞬間」にドーパミンが放出されます。
たとえば、「乾杯するぞ!」と期待してグラスを持った瞬間、 その報酬(乾杯→飲む)を脳が予測します。
でも、40分経っても乾杯できないと、予測と結果のズレがストレスとなり、 脳内の報酬系がダメージを受けるんです。
つまり、「話しすぎ」は“報酬の先送り”でもある。
それが続けば、聞き手の集中力も感情も切れてしまうというわけです。
構造化とは「地図を描く」こと
私はよくこう伝えます。
「一分で話すとは、“情報の地図”を描くことだ」と。
なぜ地図が必要か?
それは、聞き手が「今、自分はこの話のどこにいるのか?」を迷わないようにするためです。
たとえば、こんな違いがあります:
話し方A(非構造) 話し方B(構造)
A:「えーっとね…最初に○○があって、それから…」
B:「今日は3点あります。まず…次に…最後に…」
後者のほうが、聞き手の頭の中に“地図”が描かれます。
そして、ゴールが見えているからこそ、集中力も保ちやすいのです。
若手世代にとって、構造は“救い”になる
最近の若手社員と話していて、こう言われたことがあります。
「情報が多すぎて、何を大事にすればいいのか分かりません」
これは非常にリアルな悩みです。
現代の若手は、日常的にSNS、動画、チャットなどから膨大な量の情報を浴びています。
脳は、常に切り替えを強いられ、深く“保持”する時間が少なくなっているのです。
これを裏づけるのが、最近の脳科学での知見です。
【最新脳科学】ワーキングメモリは「4±2」までが限界?
従来は「7±2」が有名でしたが、 最近の研究では、「4±1」「4±2」が現実的だと言われています。
「短期的に意識の中で操作できる情報は、せいぜい4チャンク程度である」と指摘もあります。
つまり、若い世代は「情報は多く見えても、処理と保持の容量は狭い」。
だからこそ、「一分で要点を伝えてくれる人」に対して、 “わかりやすい・信頼できる”という印象を持ちやすいのです。
一分で伝えるとは、「相手の脳にやさしい話し方」
あなたが伝えたい内容が、たとえ壮大で、熱い想いに満ちていたとしても、 それを“聞き手の脳にやさしい形”で届けるのが、伝える力なのです。
研修でもよくあるのですが、 「話すことに一生懸命な人ほど、聞き手の容量を忘れてしまう」ことが多い。
一分で話すとは、決して自分の言葉を削ることではありません。
相手の脳に優しく、“飲み込みやすい粒”に加工することなのです。
坂田式・一分話法の裏技3選
ここで私が実践している“伝わる一分話法”のコツを3つご紹介します。
1. まず結論から言う(ドーパミンの報酬を早く!)
→ 例:「このプロジェクト、成功させるポイントは3つです」
2. 数でまとめる(認知フレームに入れる)
→ 「3つあります」「2つだけです」などで脳が安心します
3. 比喩やストーリーを短く添える
→ 「これは、まるで信号機のようなものでして…」など
これらを組み合わせるだけでも、驚くほど“伝わる感覚”が変わります。
伝える準備は、思いやりの準備
「一分で話せ」とは、決して時短のテクニックではありません。
それは、聞き手への思いやりの構造化であり、自分の考えを磨く時間です。
準備を惜しまず、言葉に想いを込める。
それは、リーダーとしての品格であり、部下の信頼を育てる土台にもなります。
次にあなたが何かを伝えるとき、 「よし、これは一分で話してみようか」と自分に問いかけてみてください。
あなたの言葉は、必ず誰かの心に届きます。
そして、それがチームや組織を動かす“一分の魔法”になるかもしれません。
一分の言葉で、人が動く
──伝えるとは、信頼を注ぐこと──
「坂田さんの話、もうちょっと聞いてもいいですか?」
あるセミナーの終了後、一人の若手社員が小さな声で私にそう言いました。
彼は、人前で話すことに自信がなく、ずっともじもじしていた方です。
でも、たった“一分”のロールプレイを体験しただけで、何かが動いた。
「自分の話でも、人に届くんですね」
そう呟いた彼の瞳は、ほんの少しだけ、前を向いていました。
私たちは日々、「伝える」という行為を当たり前のように繰り返しています。
でもその一言が、人の心を震わせることがある。
その一分が、人の未来を変えるきっかけになることがある。
私はその瞬間に立ち会いたくて、今日も現場に立っています。
言葉には「命」がある
私が大切にしているのは、“一分の中に、その人の人生が映る”ということです。
言葉は単なる記号ではなく、そこに宿る「温度」「間」「感情」「信頼」が、 聞き手の脳と心を揺さぶるのです。
だから私は、一分で話す練習を、ただの時短トレーニングにはしません。
「その一分が、誰かにとっては、今日の灯になるかもしれない」 そう信じて伝える練習を、一緒に重ねていきます。
なぜ、あなたの言葉が必要なのか?
「自分なんかが話しても……」
「伝えるって苦手で……」
そんな声を、私は何百回と聴いてきました。
でも、それは違います。
あなたの経験、あなたの視点、あなたの選んだ言葉にしか、 届かない人がいるんです。
そして、あなたの一分が誰かを支える瞬間が、必ず訪れます。
私は“あなたの一分”を育てる伴走者でいたい
坂田和則(ポッポ3)という人間は、 一見、ちょっとお喋りで、話が長くて、ギャグを飛ばしてばかりいるかもしれません(笑)。
でも、私の中にはいつも、「誰かの中に灯をともしたい」という願いがあります。
だから私は、怒らず、押しつけず、 その人の言葉の奥にある“伝えたい気持ち”を一緒に掘り起こしていく。
あなたが話す一分に、 “自分の声で人を動かせた”という体感を持てるまで、私は伴走します。
伝え方が変わると、組織が変わる
私はこれまで、製造業、金融、福祉、自治体、教育現場…… あらゆる組織で「伝え方を変えたリーダーたち」が、 チームの空気を変えていく姿を見てきました。
朝の一分の挨拶で、事故ゼロが続いた現場
たった一言の声かけで、辞めようとしていた部下が踏みとどまった組織
苦手だったプレゼンを“ストーリーフレーム”で乗り切り、評価が逆転した若手社員
その変化は、小さくて、でも確かに“温度”がありました。
だから私は、伝える力を「リーダーシップの入り口」だと考えています。
もし、今この文章を読んでくださっているあなたが、
「もっと短く、もっと届く言葉を話したい」
「部下や仲間との関係を、もう一歩前に進めたい」
「坂田って人に、ちょっと会ってみたいかも」
そう思ってくださったなら
どうか、気軽に声をかけてください。
ラジオでも、セミナーでも、職場でも。
私はいつでも、“あなたの一分”を育てるために駆けつけます。
最後に、あなたに贈る一分の言葉
「伝えるとは、整理された想いを、信頼という器に注ぐこと。
伝える力が育つと、あなたのチームにも、未来にも、あたたかい風が吹き始めます。」
あなたの言葉は、あなたが思っているより、ずっと力があります。
そして、あなたの話を、聴きたいと思っている人が、きっとどこかにいます。
その人に届くように。
その人の背中を、そっと押すように。
私は、あなたの一分を、全力で応援します。
坂田へのご相談・ご依頼・お問い合わせは・・・・・にお気軽に!
研修・講演・ラジオ・記事・共創プロジェクトなど、どんなご縁も大歓迎です。
どうぞ、あなたの「話を聴きたい」という気持ちのままに、お声がけください。
今回は、一分で話すというテーマでしたが、このコラムを読むのにすごい時間がかかってしまいましたね。
最後まで、ありがとうございます。
このコラムを書いたプロフェッショナル

坂田 和則
マネジメントコンサルティング2部 部長 改善ファシリテーター・マスタートレーナー
問題/課題解決を現場目線から見つめ、クライアントが気付いている原因はもちろん、その背景にある奥深い原因やメンタルモデルも意識させ、問題/課題改善モチベーションを高めます。
その先の未来には、改善レジリエンスの高い人材が活躍します。

坂田 和則
マネジメントコンサルティング2部 部長 改善ファシリテーター・マスタートレーナー
問題/課題解決を現場目線から見つめ、クライアントが気付いている原因はもちろん、その背景にある奥深い原因やメンタルモデルも意識させ、問題/課題改善モチベーションを高めます。
その先の未来には、改善レジリエンスの高い人材が活躍します。
問題/課題解決を現場目線から見つめ、クライアントが気付いている原因はもちろん、その背景にある奥深い原因やメンタルモデルも意識させ、問題/課題改善モチベーションを高めます。
その先の未来には、改善レジリエンスの高い人材が活躍します。
| 得意分野 | モチベーション・組織活性化、リーダーシップ、コーチング・ファシリテーション、コミュニケーション、ロジカルシンキング・課題解決 |
|---|---|
| 対応エリア | 全国 |
| 所在地 | 港区 |
このプロフェッショナルの関連情報
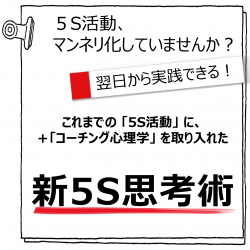
- 無料
- WEBセミナー(オンライン)
- モチベーション・組織活性化
- リーダーシップ
- コーチング・ファシリテーション
- ロジカルシンキング・課題解決
【9/8開催】 5S活動 × その気にさせる心理学 =『 新5S思考術』体験セミナー
~継続できる5S活動とは~
開催日:2025/09/08(月) 13:30 ~ 15:00
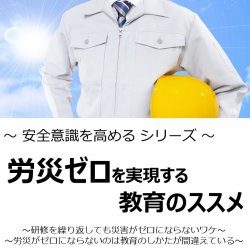
- 無料
- WEBセミナー(オンライン)
- モチベーション・組織活性化
- 安全衛生・メンタルヘルス
- コーチング・ファシリテーション
- ロジカルシンキング・課題解決
- リスクマネジメント・情報管理
【9/9開催】【無料セミナー】~ 安全意識を高める シリーズ ~
労災ゼロを実現する 教育のススメ
開催日:2025/09/09(火) 13:30 ~ 15:30
- 参考になった0
- 共感できる0
- 実践したい0
- 考えさせられる0
- 理解しやすい0
無料会員登録
記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。


 テーマで探す
テーマで探す サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 学び・実務
学び・実務





 イベント
イベント









