「育成方針が間違っていた」 ある先輩が気づいたこと
「自分の成功体験」が育成のベースになっていませんか?
部下や後輩を育成する際、多くの人が無意識のうちに「自分が成長してきた方法」をベースにしてしまいます。
「自分で考えて動く力をつけてほしい」 「主体性を持って仕事に取り組んでほしい」
これらは決して間違った方針ではありません。しかし、すべての人に同じアプローチが有効とは限らないのです。
本稿では、ある企業の営業所で実施したストレングスファインダー®(クリフトンストレングス®)を活用したチームビルディング研修での事例を通じて、一人ひとりに合わせた関わり方の重要性について考えます。
事例:すれ違いが生まれていた先輩と後輩
研修の概要
今回の研修は、営業所のメンバー全員を対象に実施しました。まず全員に事前診断を受けていただき、各自の上位資質を詳細にプロファイリング。その後、資質を可視化したレポートをもとに、グループワーク形式での相互理解セッションを行いました。
印象的だった対話
あるグループでの、先輩社員と後輩社員のやりとりが印象的でした。
先輩社員が、静かに、しかし確信を持ってこう言ったのです。
「これまでの育成方針が、間違っていた気がする」
そして続けてこう語りました。
「今までは、"自分で考えて、自分で動いてほしい"と思っていたけれど、あなたには、ある程度の方針を示した方がやりやすいんだね」
資質プロファイルから見えた違い
先輩社員の資質特性
この先輩社員は、上位資質に「分析思考」「戦略性」「目標志向」「達成欲」といった、いわゆる「思考力×実行力」領域の資質が集中していました。
このタイプの特徴として、情報を収集・分析し、自ら答えを導き出すことができます。複数の選択肢を比較し、最適解を見つけることを得意とし、主体的に行動を起こし、成果を追求します。明確な指示がなくても、自律的に動ける傾向があります。
つまり、「自分で考えて動く」ことが、本人にとって自然で心地よい働き方だったのです。
後輩社員の資質特性
一方、後輩社員の上位資質は「調和性」「共感性」「適応性」といった、「人間関係構築力」領域が中心でした。
このタイプは、相手の期待や求めていることを敏感に察知し、求められたことに誠実に応えようとする力が強い特徴があります。受け止める力、寄り添う力に優れる一方で、方針や指針がない状態では迷いが生じやすい傾向があります。
つまり、「方向性を示されることで、その中で最大限の力を発揮できる」タイプだったのです。
すれ違いのメカニズム
先輩の意図
先輩は「自律的に動ける人材に育てたい」という善意から、あえて細かい指示を出さず、後輩に考える余地を与えていました。これは先輩自身が成長してきたプロセスであり、自分の成功体験に基づいた育成方針でした。
後輩の受け止め方
しかし後輩は、方針が示されないことで「何を期待されているのかわからない」「間違った方向に進んでいないか不安」と感じていました。決して考える力がないわけではなく、「枠組みがあることで安心して力を発揮できる」タイプだったのです。
可視化がもたらした気づき
資質プロファイルという客観的なデータを前に、お互いの違いが言語化されたことで、先輩は「育成方針の見直し」という大きな気づきを得ました。
問題は「後輩の能力不足」でも「先輩の指導力不足」でもなく、「アプローチのミスマッチ」だったのです。
ストレングスファインダー®が示す育成の本質
「苦手の克服」ではなく「強みの活用」
ストレングスファインダー®のアプローチは、弱みを放置することではありません。一定レベルの補完は必要です。
ただし、それは「得意な人と同じレベルを目指す」ための努力ではなく、「自分なりに対処できる状態にする」ための努力であるべきという考え方です。
それぞれに合った関わり方を見つける
大切なのは、画一的なマネジメントではなく、個々の資質に応じて関わり方を調整することです。
明日から実践できること
1. 相手の「やりやすさ」を観察する
「この人は、どんな時に力を発揮しているか?」 「どんな状況で迷いが生じているか?」
日々の業務の中で、相手の反応を丁寧に観察してみてください。
2. 自分の「当たり前」を疑ってみる
「自分にとっての当たり前」が、相手にとっても当たり前とは限りません。
「なぜこの人は動けないんだろう?」と感じた時こそ、自分の成功体験を押し付けていないか振り返るチャンスです。
3. 対話の場をつくる
資質の違いをオープンに語れる場があるだけで、チームの相互理解は大きく深まります。
1on1やチームミーティングの中で、「それぞれの得意なこと、苦手なこと」を共有する時間を設けてみてください。
まとめ:「理解」がチームを変える
今回の事例で改めて感じたのは、「人を変える」のではなく「関わり方を変える」ことの重要性です。
相手の資質を理解し、どう関われば力を引き出せるのかを考える。そんな"理解の場"があることで、チームの中に信頼と安心感が生まれます。
この先輩と後輩のような対話が、日常的に交わされる職場。それこそが、成果とやりがいの両方を実現する「強いチーム」の姿ではないでしょうか。
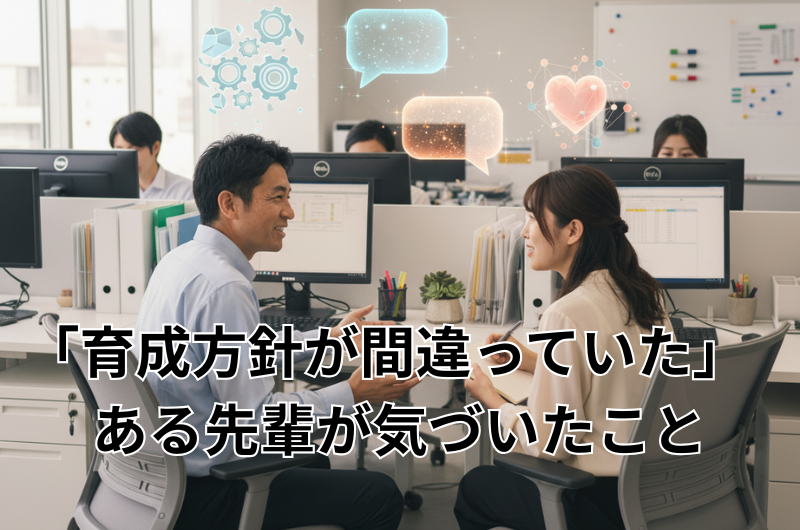
このコラムを書いたプロフェッショナル

知識茂雄
ガイアモーレ株式会社提携講師(株式会社ハート・ラボ・ジャパン)
前職では半導体製造技術者として勤務しながらコーチングやアサーション研修の社内講師も務める。独立後、ストレングスファインダーを活用したチームビルディングやリーダーシップ研修を中心に提供。ストレングスファインダーのプロファイリングに定評がある。

知識茂雄
ガイアモーレ株式会社提携講師(株式会社ハート・ラボ・ジャパン)
前職では半導体製造技術者として勤務しながらコーチングやアサーション研修の社内講師も務める。独立後、ストレングスファインダーを活用したチームビルディングやリーダーシップ研修を中心に提供。ストレングスファインダーのプロファイリングに定評がある。
前職では半導体製造技術者として勤務しながらコーチングやアサーション研修の社内講師も務める。独立後、ストレングスファインダーを活用したチームビルディングやリーダーシップ研修を中心に提供。ストレングスファインダーのプロファイリングに定評がある。
| 得意分野 | キャリア開発、リーダーシップ、コーチング・ファシリテーション、チームビルディング、コミュニケーション |
|---|---|
| 対応エリア | 全国 |
| 所在地 | 熊本市 |
- 参考になった0
- 共感できる0
- 実践したい0
- 考えさせられる0
- 理解しやすい0
無料会員登録
記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。


 テーマで探す
テーマで探す サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 学び・実務
学び・実務





 イベント
イベント








