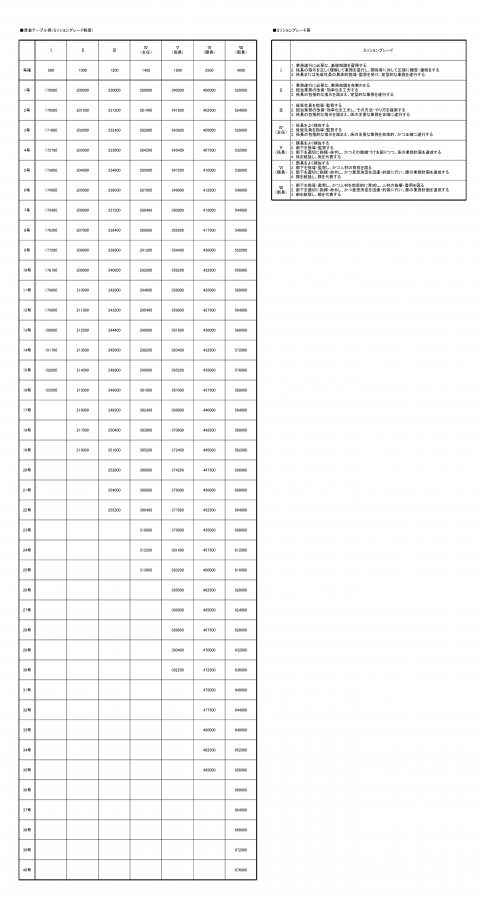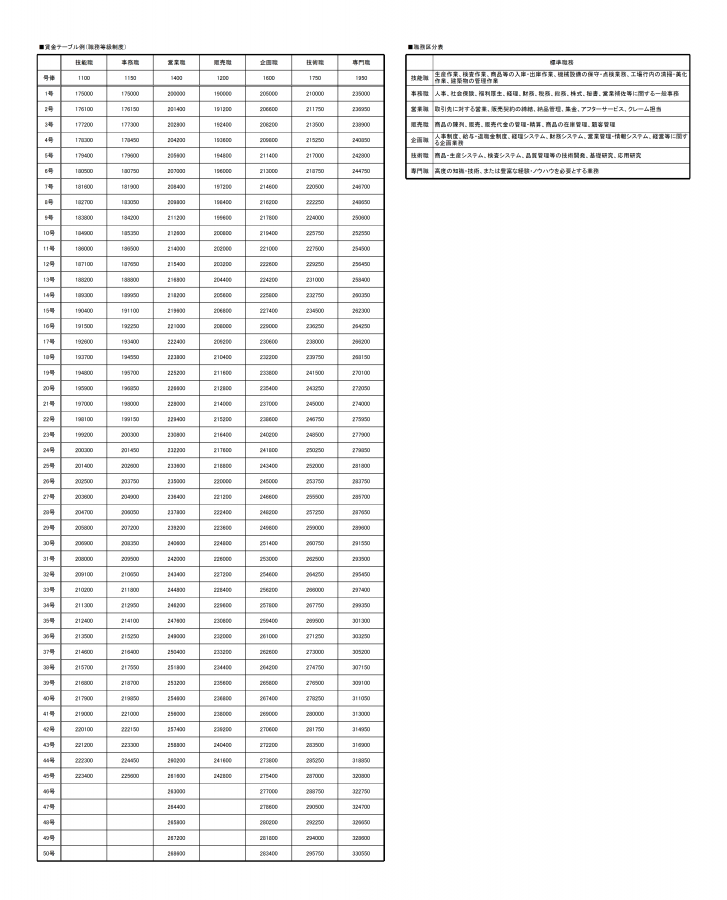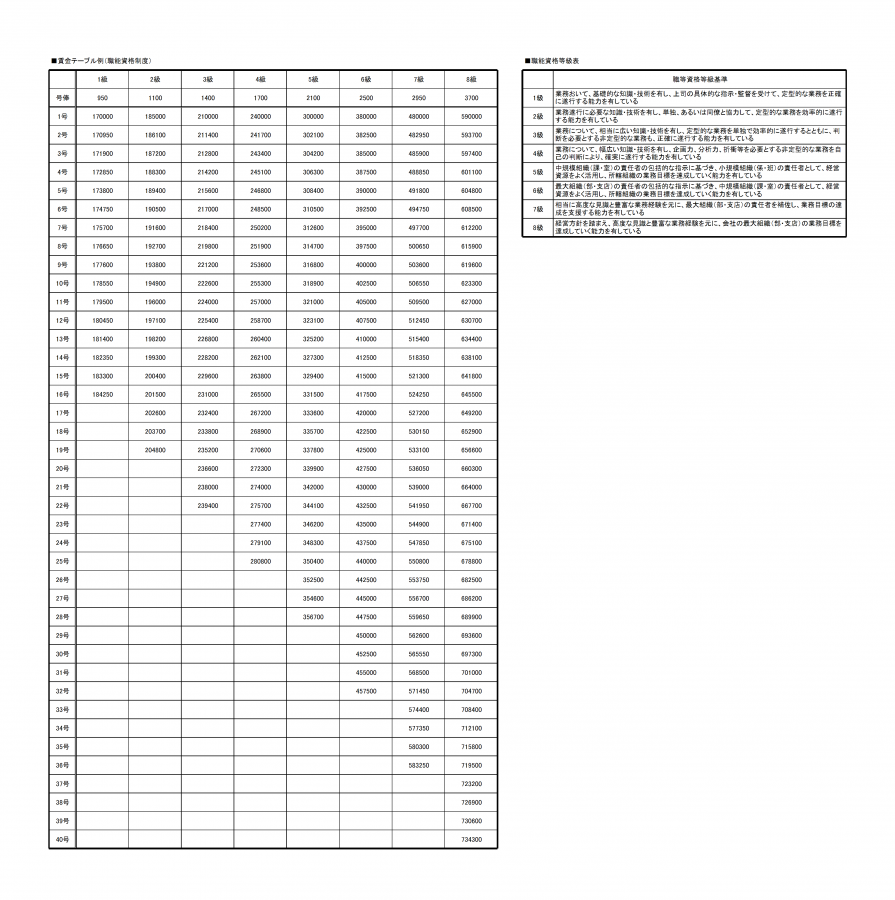発明対価
発明対価とは?
会社員が職務として新技術を発明して得た特許権を会社に譲る場合、特許法35条よって会社から「相当の対価」の支払いを受けられます。近年、対価が低すぎると発明者が会社を訴えるケースが続発、巨額の支払い命令なども出て、注目されています。
発明者の対価をめぐり訴訟続発
2005年4月から特許法が改正
発明対価が一般の関心を呼ぶようになったのは、ノーベル化学賞を受賞した島津製作所・田中耕一さんの発明対価が1万余円(受賞後、特別報奨金1000万円支払い)だったと報じられたころからでしょうか。当時、日亜化学工業を相手に米大学教授・中村修二氏が在職中の青色発光ダイオードの特許に対して裁判を起こしており、その後、一審判決が200億円の支払いを命じたため、企業側もにわかに関心を持ち始めました。
発明対価をめぐる訴訟では、これまでにオリンパスの光ディスク技術に対して約230万円の支払いが確定したほか、日立製作所のCD読み取り技術では約1億6300万円の判決があり、現在最高裁で継続中。最近では味の素と元同社社員との間で、人工甘味料の発明に対して1億5000万円を支払うことで和解が成立しました。
裁判所は味の素が得た利益を約80億円と認定しており、元社員が手にしたのはその2%弱。仮にもう一人の共同発明者にも同額と計算すれば、社員の取り分は利益の4%弱になりますが、現状では大手企業の発明対価は利益の0.1%〜1%が普通と言われます。
このため特許法35条の改正で、対価について合理的な基準を求める一項が付け加えられ、2005年4月から実施されます。それでも妥当な金額は定かでなく、会社と発明者のせめぎ合いが続きそうです。田中さんは「特許より仕事の面白さが大切」と言っていましたが、発明に縁のない社員にも、落ちつき先が気になるところです。
- 参考になった0
- 共感できる0
- 実践したい0
- 考えさせられる0
- 理解しやすい0

用語の基本的な意味、具体的な業務に関する解説や事例などが豊富に掲載されています。掲載用語数は1,500以上、毎月新しい用語を掲載。基礎知識の習得に、課題解決のヒントに、すべてのビジネスパーソンをサポートする人事辞典です。
会員登録をすると、
最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!
無料会員登録
記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。


 テーマで探す
テーマで探す サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 学び・実務
学び・実務





 イベント
イベント