第40回:「外部プロ人材(IC)」を有効活用する方法(前編:解説)
~「雇われない、雇わない」働き方=「IC」への期待とその効果
解説:福田敦之(HRMプランナー/株式会社アール・ティー・エフ代表取締役)
リーマンショック以降、厳しい経営環境が続く中にあって、人材をいかに有効活用していくかが、企業経営の大きなカギを握るようになってきた。事実、雇用形態の多様化を進め、外部の専門性の高いプロ人材を活用するケースが増えてきている。そして近年、その一形態である「IC(Independent Contractor)」に注目が集まってきた。ICとは、個人として自分の価値基軸で意思決定を行い、組織から独立(Independent)して活動し、会社の垣根を超えて働くというワークスタイル。個人が「雇用契約」ではなく、企業と「業務委託契約」を結ぶことに大きな特徴がある。この「雇用されない働き方」という点に企業が注目し、「外部プロ人材」としての期待が高まってきているのだ。今回は、「社員」という枠組みを超えた、ICという「労働力」のポテンシャルについて紹介していく。
「外部プロ人材」が求められる時代
■企業経営を圧迫する「雇用コスト」が増加
企業経営を取り巻く環境に、厳しい状況が続いている。特に雇用におけるコスト面。例えば、定年延長や年金改革などの負担がこの先、大きく企業にのしかかってくる。このような「雇用コスト」の負担増加の影響は極めて大きく、人材難だからといって、正社員を雇い続けていたら、コスト競争に勝ち残っていくことは難しい。人件費の変動費化という意味でも、正社員以外の人材をうまく活用していくことが、これからの不可欠な人材戦略となってきている。
とはいえ、アルバイトやパートに関しては、一定時間以上働くと社会保険や年次有給休暇の適用者となる。コスト対策として考えると、必ずしも効果的ではない場合が生じる。別の意味で、法改正が予定されている派遣スタッフもそう。だからこそ、雇用関係のない「労働力」に大きな注目が集まっているのだ。特に、スペシャリティを持った「外部プロ人材」に対して。
■「特定の個人」が持つスペシャリティに期待
既にアウトソーシングが一般化し、多くの企業では外部のスペシャリティを活用する図式が出来上がっている。問題は、「誰に頼むか」という点にある。考えてみれば、組織に頼んでも最終的には個人が仕事をすることに変わりはない。それならば、最初から成果の期待できる「特定の個人」と仕事をしたほうがいいのではないか。
結局のところ、専門能力がなければ、社内でも社外でも成果を期待することはできないだろう。誰が担当するか分からない「組織」よりも、紹介などを通してスペシャリティを持った「特定の個人」に頼んだほうがいい。ズバリ、あの人にお願いしたいという動きが顕著になってきているのも、もっともな話である。
競争の激しい現在にあって、企業に求められているのは、新しいサービスや高い付加価値を持つ製品をスピーディーに市場に投入していくこと。これが、今後の生き残りの重要な条件となってくる。しかし、企業内の人材だけでは、どうしても発想に限界がある。そこで、「外部プロ人材」であるICに期待がかかった。これも、ICの持つ「専門能力」や「外部からの視点」が、企業内の人材だけでは持ちえないものだからだ。
実際、個人への業務委託は増えてきており、この仕事を担っているのがまさにICである。専門性の高い技術を持ち、複数の企業でそのスキルを生かして働く個人事業主。彼らは個人として企業と対等に契約を結び、専門能力を生かして仕事をしているのである。
「IC」とは何者なのか?
■ICの「定義」
ICとは、Independent Contractorの略で、直訳すると「独立契約者」となる。人材の流動化が進んできたここ10年あまりの間、ICもある程度の市民権を得てきたように思う。新しい労働力として注目を集め、雑誌などでも特集が組まれ、実際に活用している企業も出てきている。また、ICと企業をマッチングするビジネスも興ってきていて、徐々にではあるが、ICは労働市場におけるポジションを確保しつつある。ここでもう一度、ICとはどのような働き方をしている人たちなのかを確認しておこう。
ICをサポートしている特定非営利活動法人インディペンデント・コントラクター協会(IC協会)では、ICについて、下記のように呼んでいる。
期限付きで専門性の高い仕事を請け負い、雇用契約ではなく業務単位の請負契約を複数の企業と結んで活動する独立・自立した個人のこと
雇う企業からみると、専門性の高い領域をコミットし業務を遂行するICを、「必要な時な時に必要なだけ」活用する事により、確実にプロジェクトを成功に導くことができるし、コスト面でもメリットが高い。米国では既に900万人近いICが活躍しており、今後日本でも企業の本業回帰の流れと、外部にある知恵を有効に活用していきたいという意向から、ICという働き方が拡大すると言われている。サラリーマンでも、事業家でもなくフリーエージェントである働き方。「雇われない、雇わない」。これが、ICの生き方と同協会では定義している。
■ICの「特徴」
現在、ICが活躍している領域はさまざまで、行っている業務も多岐に渡っている。ゆえに、企業から見ると、仕事の繁閑に応じてICに委託すれば、正社員を雇うより低コストで済む。また、派遣スタッフが比較的単純な事務の受託なのに対して、ICは高度専門職の外部委託の受け皿として役割を持つことになる。このようなICの特徴を整理すると、以下の5つにまとめることができるだろう。
(1)「雇われない、雇わない」
IC協会が定義するように、「雇われない」というのは、正規・非正規に関係なく、企業と雇用関係を結んでいないという意味である。一方、「雇わない」というのは、起業家ではないということを示している。もっともICの中には個人事業主だけでなく、法人化して代表取締役となっている人たちも大勢いる。しかし、それは契約上、法人であることが求められることが多いためで(あるいは節税上の問題など)、そもそも彼らには従業員を雇って自分の会社を大きくするという志向・メンタリティは弱い。肩書きは経営者であってもスペシャリストとしての自負を持っており、明らかに起業家とは異なるタイプである。
(2)幅広い「専門性」を持つ
ある分野において高い専門スキルや知識を持ち、それを使ってクライアントに価値を提供している専門家。ただし、その専門性は狭義のものではなく、かなり広いものである。特定の分野におけるスキルだけで勝負をしているのではなく、その周辺や、関連する知識、さらには一見全く関係のない知識をも知恵に変えて仕事をしているICが多い。
事実、活躍しているICを見ると、その時々の業務を通じて知識やスキルを高めている。学んでから新しい案件に取り組むというより、学びながらその案件で高い成果を出していくという行動特性を持っている。変化のスピードが早い時代、短期間で成果を出すことを求められているICにとって、学んでから仕事に取り掛かるのでは遅過ぎるのだ。
(3)柔軟な「対応性」を持つ
ICにとって、「商品」はまさに自分自身である。だからこそクライアントのニーズに応じて、どのようにでもカスタマイズすることが可能となる。このような柔軟な対応性が、ICの持つ大きな強みであり、競争力となっている。また、コストや体制面でも小回りがきき、融通もきく。この点は、いわゆるアウトソーサーなどの外注企業と異なる点であり、クライアントにとって大きなインセンティブとなるだろう。
(4)全てにおいて「自立」している
「雇われない」とは別の、精神的な意味での自立である。誰かの指示を待つのではなく、自ら主体的に動くのがICである。プレイヤーであると同時に、場合によってはマネージャーともなる。業務の始めから終わりまでコミットし、必要に応じてクライアントへ積極的に働きかけていく。さらに、クライアントをモチベートすることもある。自分自身が「商品」であり、その商品価値を高めるための仕掛けも自分自身で行う。誰かに育ててもらうのを期待するのではなく、自分の成長を主体的に考えている。このように、全てにおいて自発的であり、何より自立しているのがICの大きな特徴である。
(5)「複数の企業」で仕事をする
1社専属ではなく、同時に複数のクライアントの業務を行うケースが多い。諸般の事情から1社の仕事しか行っていないという時期もあるが、それは結果的にそうなっているだけで、ある特定の1社としか業務契約を結ばないというICは少ないようだ。複数のクライアントと仕事をし、さまざまな組織を見ることで視野が広がっていき、より多くの視点を持つことができる。それがクライアントに対するサービスの価値を高めていくことにつながっていく。
・社員に替わる「ホワイトカラー型」のIC
これまで、価値創造の役割を担う労働力を「非雇用」で活用するという発想はあまりされてきませんでした。つまり、図の左上のエリアはほとんど存在しなかったのです。一部、弁護士や税理士、会計士といった有資格者がある専門分野に特化して業務を行っていましたが、それは「広義のIC」の中の「士業型」に分類されます。また、デザインやプランニングなどのクリエイティブ職おいても、フリーランスといった名称でICが活用されていました。それは「クリエイター型」のICに入ります。その意味では、呼び名はともかくICはこれまでも存在していたわけです。
それに対して、現在注目されているのは「ホワイトカラー型」とも呼ぶべきものです。これらの人たちは、「資格の有無にこだわらない」「組織内の企画立案や戦略立案業務を行う」「企画や戦略の遂行業務を行う」といった特徴を持っています。このようなことは、今まで「社員」が行っていた部分であり、それを外部化しているのが「狭義のIC」と言うことができます。
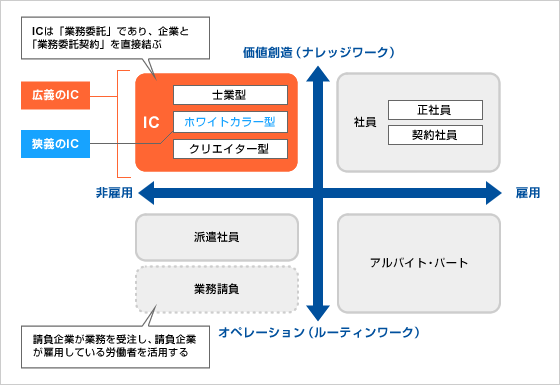
なお、ICと混同されやすいのが業務請負。これは、請負企業が業務を受注し、請負企業が雇用している労働者を活用するものである。
■IC活用で実現できること
組織において、ICのような高い専門性を持った能力の高い人材、しかも雇用関係を伴わない人材というのは非常に重宝される。ではICを活用することで、何を実現することができるのかというと、大きく4つにまとめることができる。
(1)社員採用の負担・リスクの軽減
まず、社員を採用することによって生じる負担やリスクを軽減できるという点を挙げたい。これには2つの側面がある。1つは採用や育成にかかるコストを単純に減らすことができるという点。「必要な時に、必要な要件の労働力を、必要なだけ調達する」ことが可能となる。
強調したいのは、もう1つの点だ。長期的に影響を及ぼす採用ミスのリスクを減らすことができる点である。ICの場合、業務委託契約時に期間を定めることになるので、期待通りの成果が出ない場合、失敗はその期間のみに抑えることができる。しかし、正社員を採用した場合、解雇要件の問題もあり、その失敗の影響は長期化する恐れがある。その意味でも、短期決戦できる労働力の持つ価値は大きいと言える。
(2)組織風土・社員に対する影響
ICという労働力を他の労働力と組み合せて使うことで、組織風土の改革を促すことも可能となる。ICは組織の中に入って業務を行いながらも、その組織に所属しているわけではない。しがらみや前例にとらわれることなく、改革を進めることができる。表立って指揮・命令することはなくても、実質的にプロジェクトをマネジメントする“影のプロジェクトリーダー”になることも少なくないのだ。また、社員にとっても、外部労働力との協働によるいい意味での影響が見逃せない。ここでは、中途採用で優秀な社員を採用した時に得られる効果と、同じ類のものが期待できる。
(3)発注コストの削減
ICを活用することによって、発注コストを削減することも可能である。一般的に企業へ発注するコストよりも、個人へ発注するコストの方が低くなる。これはICが、ある一定規模以上の企業のような「間接費」を必要としないからである。
(4)業務の効率化
副次的な効果と言えるが、ICを導入することにより、組織内の業務の見直し、棚卸しが進んでいくことが多い。その結果、社員は本業やコア業務に専念することができるようになり、短期目標・重点課題へと集中的に取り組むことになっていく。
このようにICを活用することによって、人件費を中心とした固定費の変動費化、そして価値を創造できる人材の調達という、両立の難しい“果実”を得ることが可能となる。
■ICのベースとなる「安心感」
以上見てきて思うのは、ICとは「古くて新しい労働力」だということ。ワークスタイルとしては、「士業型」や「クリエイター型」のICが既に存在していたし、行う業務は組織の中にあるものだからだ。では、このようなICのベースとなるものは何なのか。それは、ある種の専門的に高い知識や経験、能力を持っていて、この人に任せれば大丈夫だという「安心感」と言うことができるだろう。そして、この安心感には2つの側面がある。1つ目は、一緒に働いてみて「この人、できるな」ということを感じさせる「顕在化されたスキル」があること。2つ目は、これまでにやってきた仕事の成果による「評判」だ。現実的に外部の人材を活用する場合には、後者の部分が特に大きいように思う。
いずれにしても、外部人材の活用は昔からあったことを忘れてはならない。ただ、ICというネーミングをされなかっただけのこと。それが、人材の流動化、さらには雇用形態の多様化という部分からICの存在が顕在化し、スポットライトを浴びてきたのである。
■「採用」から「調達」へ
今後、労働力は「正社員という形で定期的に採用すべきもの」という発想から、「必要に応じて、必要な分を調達するもの」へと変わっていくと考えられる。このことは、単なるコストの問題だけでなく、労働力の確保を広い視野で考える必要性を意味している。「社員募集」では動かない層をどう発掘するか、「正社員」という位置付けではマネジメントできない層をどうつなぎとめるか、等々。その答えの一部が、ICを活用することで見つかるのではないだろうか。
バブル崩壊以降、多くの企業では「日本的雇用」に取って代わるものを模索してきた。その回答は企業によって異なるし、時代によっても変わることだろう。ただそれが、ICを活用することによって、正社員を含めた労働力全体をマネジメントする際のヒントが見えてくるようにも思う。外とのつながりを持ち、異質かつ有能な存在であるICと接点を持ち、コラボレーションを行うことは、閉鎖的で同質化・均質化へのドライブがかかりやすい人の問題に対して、いい意味で刺激を与えると考えるからである。
* *
以上、「前編」はIC活用が求められている背景と、活用の意味について紹介してきた。「後編」では、ICを社内に取り入れている企業の事例を交えながら、具体的な話をしていきたい。
この記事を読んだ人におすすめ
- 参考になった0
- 共感できる0
- 実践したい1
- 考えさせられる0
- 理解しやすい0
- 1
無料会員登録
記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。


 テーマで探す
テーマで探す サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 学び・実務
学び・実務





 イベント
イベント











