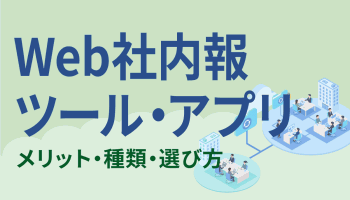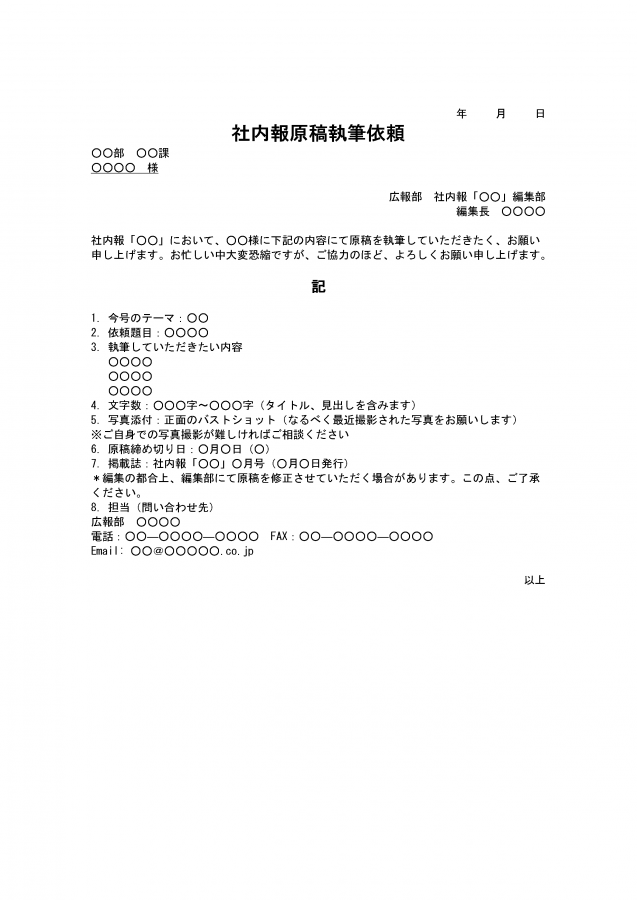リーン・スタートアップ
リーン・スタートアップとは?
「リーン・スタートアップ」(lean startup)とは、アメリカの起業家エリック・リース氏が2008年に提唱した、起業や新規事業などの立ち上げ(スタートアップ)のためのマネジメント手法のことです。リーンとは日本語で「ムダがなく効率的」という意味で、「かんばん方式」で知られるトヨタ生産方式を他分野に応用できるよう再体系化・一般化した「リーン生産方式」に由来します。リーン・スタートアップは、事業家の思い込みで顧客にとって無価値な製品やサービスを開発してしまうことに伴う、時間、労力、資源、情熱のムダをなくすための方法論。最低限のコストと短いサイクルで仮説の構築と検証を繰り返しながら、市場やユーザーのニーズを探り当てていくのが特徴です。
ムダなく効率的に成功するマネジメント
小さく始め、素早く何度も改善を重ねる
事業環境がめまぐるしく変化し、無数のベンチャーが生まれては消えていくアメリカ・シリコンバレー。その混沌の中でいかにスタートアップの成功率を高めるかという古くて新しい難題に取り組んだ前出のリース氏は、自ら紆余曲折の末にインターネットのコミュニケーションサイトの運営ベンチャーを起業した経験から「リーン・スタートアップ」の理論を同名の著書にまとめ、大きな反響を呼びました。
起業したベンチャーの、わずか0.3%しか生き残れないというシリコンバレーでは、顧客のニーズ予測に長い年月を費やし、満を持して投入したはずの商品やサービスでも、まるで需要がなかった……ということがめずらしくありません。本来なら、その失敗を次の商品開発に活かしてマネジメントを継続すべきですが、たいていの場合、起業やプロジェクトは頓挫してしまいます。最初のトライに万全を期すあまり、資金も時間も労力も注ぎこみ過ぎて、もはやその時点では方向転換する余力を失っているからです。
自らもこうした失敗体験を持つリース氏は、「失敗によって学んだ経験を次に活かせるようなマネジメントこそが事業の成功率を向上させる」と述べ、何が顧客にとっての価値なのかが見極められるまで、“仮設の構築→計測→学習”というサイクルを、できるだけ素早く小回りに、市場の反応を確認しながら何度も回し続けることを推奨しています。
具体的には、まずアイデアを思いついたら(仮説の構築)、完璧でなくてもいいから形にし、MVP (Minimum Viable Product)と呼ばれる必要最小限の製品を開発して顧客に試します。それが受け入れられるかどうか、フィードバックを得て(計測)、その結果をもとに改善や軌道修正を細かく繰り返していくのです(学習)。どんなに改善を重ねても事業として芽が出ない場合は、構築した仮説そのものが誤りだと判断し、早期に仮説の再構築を決断します。余力を失い、事業そのものが継続できなくなる事態を避けるために、ダメージが少ないうちに撤退して進路を変更するわけです。こうした事業継続のための方向転換を、リース氏は「ピボット」(バスケットボールで片足を軸にして方向転換を繰り返す動作のこと)と呼びます。
すでにシリコンバレーで大きな支持を獲得しているリーン・スタートアップの手法は、リース氏によれば、起業家にかぎらず、企業内で新しい事業を立ち上げる担当者にも応用できるといいます。実際、アメリカではいわゆる「企業内起業家」に広く浸透しつつあります。変化の激しいビジネスに関わるすべての人にとって新たな指針となりうる考え方といえるでしょう。
- 参考になった0
- 共感できる0
- 実践したい0
- 考えさせられる0
- 理解しやすい0

用語の基本的な意味、具体的な業務に関する解説や事例などが豊富に掲載されています。掲載用語数は1,400以上、毎月新しい用語を掲載。基礎知識の習得に、課題解決のヒントに、すべてのビジネスパーソンをサポートする人事辞典です。
会員登録をすると、
最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!
無料会員登録
記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。


 サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 調査
調査 人事辞典
人事辞典 イベント
イベント