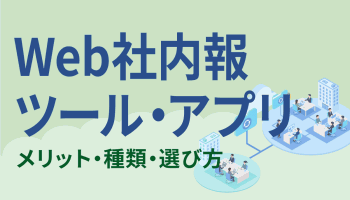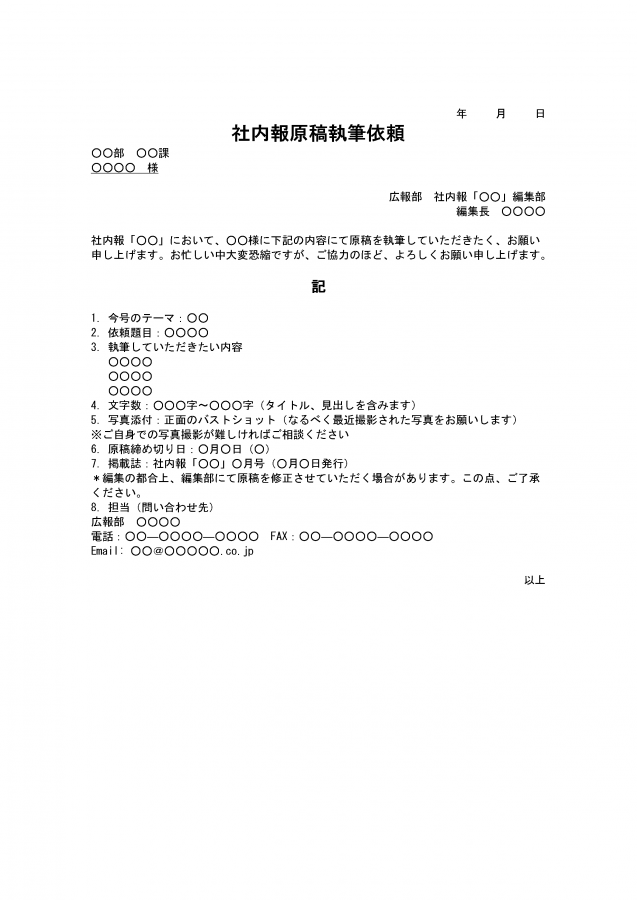創発
創発とは?
「創発」とは、部分の性質の単純な総和にとどまらない特性が、全体として現れること。物理学や生物学などで使われる用語「emergence」(発現)が語源で、自律的な要素が集積し組織化することにより、個々のふるまいを凌駕する高度で複雑な秩序やシステムが生じる現象あるいは状態をいいます。所与の条件に基づく予測や計画、意図を超えたイノベーションが誘発されるところから「創発」と呼ばれ、組織論やナレッジマネジメントの分野では、個々人の能力や発想を組み合わせて創造的な成果に結びつける取り組みとして注目を集めています。
個々の知恵を引き出して組み合わせる
1+1が3にも4にもなる創造的な組織へ
「全体が部分の総和を超える」という「創発」現象は、もともと自然科学の複雑系理論のコンセプトであり、たとえば人間の脳の働きにその典型例をみることができるでしょう。脳という器官を構成する神経細胞一つひとつをみると、比較的単純なふるまいをしていることがわかっていますが、脳の全体はそれらの相互作用によって驚くべき知能に目覚め、極めて高度かつ複雑な能力を発現しています。
経済・産業面でいえば、世界のIT産業を牽引する米・シリコンバレーでも、あるいは日本のものづくりを支えている東京・大田区や東大阪市などの中小企業群でも、数多くの企業が密集ししのぎを削り合う中で、高度な技術や先進的なイノベーションが繰り返し生み出され、結果、個々の能力の総和を超えるような業界全体の躍進をもたらしました。そして全体の発展がまた企業間の触発を生み、それぞれの技術開発力をさらに磨きあげていったのです。これも、ビジネスにおける創発の事例といえるでしょう。
全体を構成する個別要素の相互作用によって思いもよらない全体的な特性が現れる――最近ではこうした創発現象を、自社の組織内において意図的・戦略的に起こすための環境整備や仕掛けづくりに取り組む企業も少なくありません。社員一人ひとりの知恵や発想を最大限に引き出しながら、活発なコミュニケーションを通じてそれらを組み合わせ、創造的な成果へと結びつける。脳の神経細胞がつながって知能が芽生えるように、1+1=2ではなく、1+1を3にも4にもしようとする試みです。
具体的な策としては、クロスファンクショナルチームやナレッジマネジメントシステムの導入、組織のフラット化、社内ベンチャー制度の設置、ソーシャルネットワークの活用など。部署や上下関係にとらわれず、多くの人材が自由かつ活発に交流できる場や機会を拡充し、組織の活性化を図ることで創発の可能性を高めています。
もちろん体制だけを整えても、肝心のメンバーが受け身に回っていては、創発は促されません。一人ひとりが自発的に知識や情報を収集し、それを組織へと還元して成果につなげていく意識を高める必要があります。創発という現象は、仕事中や会議、研修の時間にのみ起こるわけではなく、休憩中や仕事を離れたたわいもない雑談の中にもその可能性の“芽”が潜んでいるのです。
- 参考になった0
- 共感できる0
- 実践したい0
- 考えさせられる0
- 理解しやすい0

用語の基本的な意味、具体的な業務に関する解説や事例などが豊富に掲載されています。掲載用語数は1,400以上、毎月新しい用語を掲載。基礎知識の習得に、課題解決のヒントに、すべてのビジネスパーソンをサポートする人事辞典です。
会員登録をすると、
最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!
無料会員登録
記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。


 サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 調査
調査 人事辞典
人事辞典 イベント
イベント