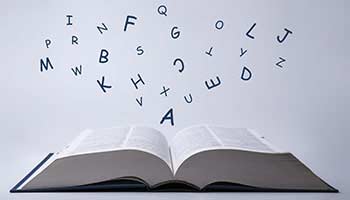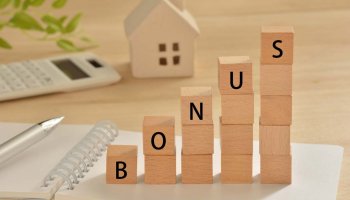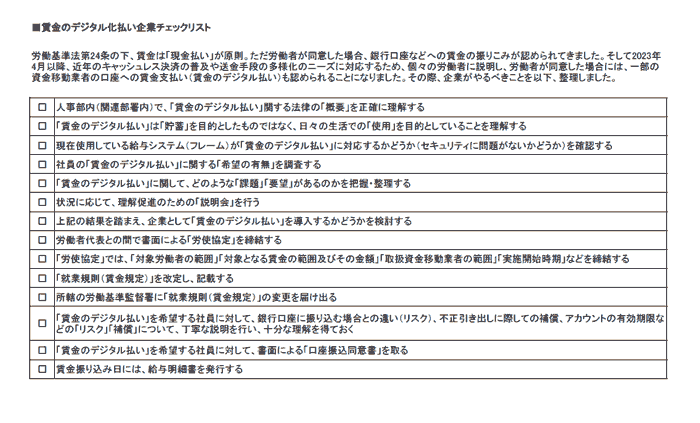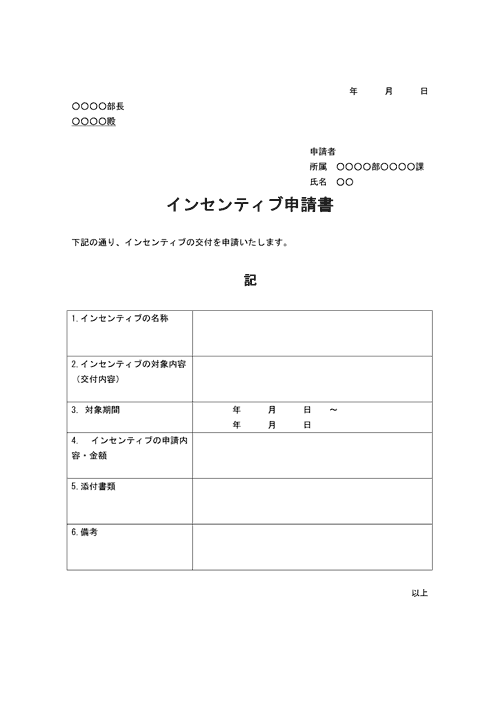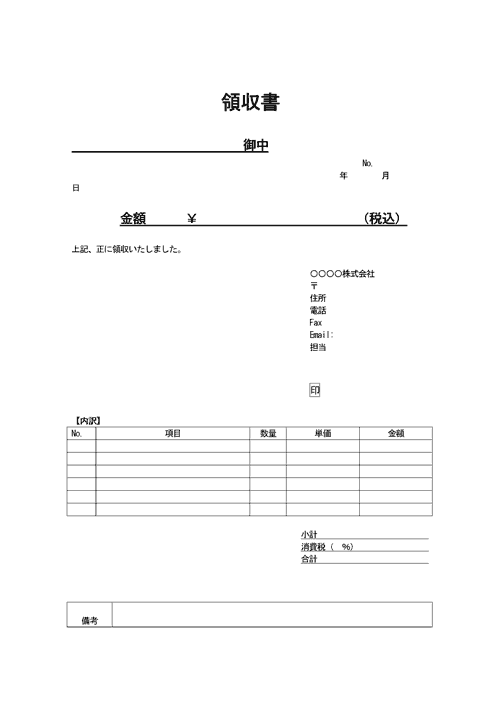格差社会
格差社会とは?
ある基準をもって社会を階層化した際の国民の間の格差(特に経済、所得、消費、資産など)が顕在化した社会のこと。
「同一労働、同一賃金」の原則の確立が課題
今後、格差の世襲や教育格差が起きる懸念も
1990年代以降の日本では、不景気が長引く一方、IT、金融など社会の需要をつかんだ一部の人たちの中には、若くして裕福になる人(いわゆる勝ち組)が出現しました。また終身雇用制度に護られた年配層なども、その既得権益により一定の利益を得ることができました。
こういった状況の中、既得権益を持たず就職難にあえぐ若年層の中から登場した、安定した職に就けないフリーターや、職自体に就こうとしないニートといった存在が社会的に注目されるようになりました。一方で、ジニ係数拡大の統計発表、セレブブームに見られる裕福層の生活が大きく報じられるようになったことなど、種々の要因により格差社会が成立しつつあるのではという認識がされるようになっています。OECDの2000年の統計では、日本の相対的貧困率(全体の中央値以下の所得を得ている者の割合)は、加盟国中アメリカに次ぐ2位となっており、格差は確実に存在しているというのが一般的な認識となりつつあります。
ただし、格差社会は以前から存在していたもので、特に最近になって成立したものではないという主張もあり、格差は一代限りのもので、その固定化を意味するものではないという意見や、そもそも何をもって格差とするのかなど認識はさまざまで、識者間でも認識の一致をみないこともあります。
かつて正規雇用と終身雇用が当たり前のように思われていた時代に整備された日本の社会保障制度は、正社員(正規雇用者)を中心に設計されており、健康保険や年金といった分野で、アルバイトやパートタイマー、派遣、契約社員などの非正規雇用者との待遇に大きな格差ができています。内閣府が実施した「家族とライフスタイルに関する研究会報告(平成13年)」では、女性の出産に伴う就業パターン変化による生涯賃金の推計を行っていますが、正社員として継続就業している場合と、退職後パートタイマーとして再就職した場合で、賃金だけで2億円近い差が生まれるとしています。これに加え、表面的な賃金には含まれない年金や健康保険等でも差が生じることになります。
また、日本では新卒採用が一般的に行われているため、卒業後にいったんフリーターになると、その後、正社員に転ずることは困難な場合が多く、そのため雇用形態による賃金差の固定化が問題視されてきています。パート、アルバイトでも正社員と同等の働きをさせている職場も多く、「同一労働、同一賃金」の原則の確立が課題となっています。さらにこれらの要因から、収入の高い家庭ほど進学率が高いという調査結果もあります。依然として学歴により就職が優遇されるという傾向は残っており、進学率が後の職業選択に直結し、その就学機会の格差が収入の格差へとつながり、さらに子弟の進学率に影響するという形で、事実上の格差の世襲、特に教育格差が起きる危険性も指摘されています。
- 参考になった0
- 共感できる0
- 実践したい0
- 考えさせられる0
- 理解しやすい0

用語の基本的な意味、具体的な業務に関する解説や事例などが豊富に掲載されています。掲載用語数は1,400以上、毎月新しい用語を掲載。基礎知識の習得に、課題解決のヒントに、すべてのビジネスパーソンをサポートする人事辞典です。
会員登録をすると、
最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!
無料会員登録
記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。


 サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 調査
調査 人事辞典
人事辞典 イベント
イベント