少人数組織では、組織サーベイを実施しなくても良い!
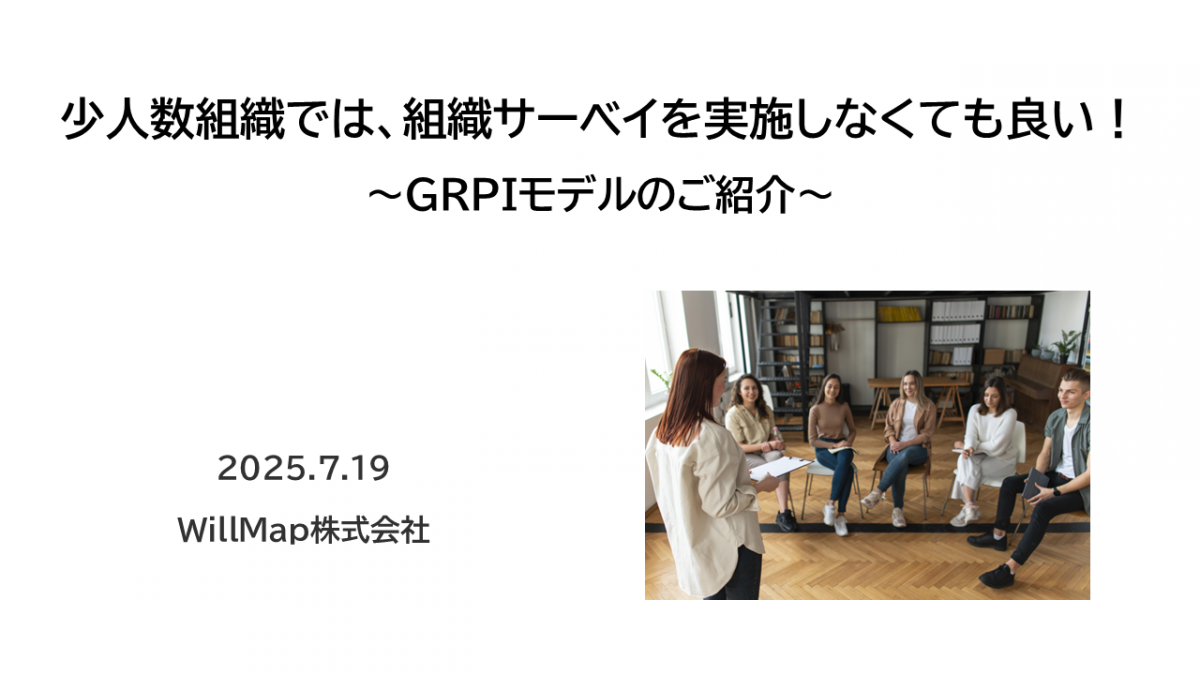
「うちの組織は10人なんですけど、組織サーベイをやれますか?」
エンゲージメントサーベイのセミナーを人事担当者向けに実施した際によくいただく質問です。10人程度の組織の場合、サーベイの中で階層や年齢などの属性を聞いてしまうと、誰の回答か分かってしまうこともあります。そうなると当然、本音が出にくくなり、正確な現状把握ができなくなることから、少人数の組織においては、組織サーベイの実施はお勧めしません。
その代わりに、チームの現状を把握し、課題を話し合うツールとして、「GRPI(グリッピー)モデル」の活用を推奨しております。
GRPIモデルとは?
GRPIモデルは、チームのパフォーマンスを向上させるために必要とされる4つの要素から成り立っています。
-
G(Goals): チーム目標
-
R(Roles): それぞれの役割
-
P(Procedures): 仕事の進め方
-
I(Interactions/Relationships): 他者との関わり、関係性
この4つの頭文字をとって「GRPI」という名前が付いています。
一般的な組織開発では、まず関係性に注目して、話し合いをスタートするケースが多いですが、GRPIモデルでは、その前に「関係性」に影響を与えている、「目標」「役割」「手順」の課題を整理しながら話し合いを進めることが大切という考えです
- G(Goals): チーム目標
- R(Roles): それぞれの役割
- P(Procedures): 仕事の進め方
- I(Interactions/Relationships): 他者との関わり、関係性
この4つの頭文字が「GRPI」を形成しており、チームのパフォーマンスを向上させるために必要な要素を整理します。
一般的な組織開発では、まず関係性に注目するケースが多いですが、GRPIモデルでは、その前に「関係性」に影響を与えている、「目標」「役割」「手順」の課題を整理することで、効果的に組織開発を進められます。

GRPIモデルの詳細解説
1. 目標(Goals)
まず、チーム活動の根幹となるのが「目標」です。目標が明確に設定され、その背景がメンバーにしっかり伝わり、全員が納得していることが大切です。また、目標が明確であっても、メンバー一人ひとりがそれを異なる解釈をしている場合、ベクトルがバラバラとなり、チームとしての力が結集されません。
2. 役割(Roles)
組織目標を達成するために、メンバー一人ひとりに与えられた役割を明確にし、誰が何をするのかをチーム内で共有することが求められます。また、そもそもの役割分担が適切であることも大切で、たとえば、一定のメンバーに過度に負担が集中している状態が続くと、関係性に悪影響を及ぼしてしまいます。
3. 手順(Procedures)
目標と役割が明確になった後は、実際に仕事をどのように進めていくかが観点となります。具体的には、業務の進捗管理や会議の進め方などがテーマとなり、全体で仕事の状況をタイムリーに共有し、メンバー間で協力し合いながら進めていくことが求められます。遅れが生じた場合には、迅速にフォローアップできる体制を作ることもポイントです。
4. 関わり方や関係性(Interactions/Relationships)
最後に、チーム内の関係性に注目します。チームメンバーが互いにどの程度お互いの強みや特徴を理解しているか、また、協力して成果を上げるために、どれだけオープンにコミュニケーションを取れているかが重要な要素となります。そして、衝突があったときに、遺恨を残さず解決し前進する風土が根付いているかどうかも、チームの成功と鍵となるでしょう。
具体的な進行方法
1. 目的と進め方の共有
最初に、チーム全員に今回の話し合いの目的と進め方を共有します。「今回の目的は、チームを良くするための話し合いであり、個人批判ではない」ということを明確に伝え、メンバーが意見を出しやすい雰囲気を作ります。
2. 1on1での事前ヒアリング
全体での話し合いに入る前に、マネジャー(またはファシリテーター)が、メンバー一人ひとりと30分程度の時間を使って、GRPIのカテゴリー毎に、チームの上手くいっているところや課題についてヒアリングします。ヒアリング内容は匿名の意見として扱い、個人を特定しないようにします。
3. ヒアリング内容の分析
ヒアリングした内容についても、GRPI毎に整理し、チームの強みと課題を明確にします。ごく少人数の場合は、意見を要約した文章としてまとめますが、人数が多ければ、KJ法などを使って発言内容を整理し、タイトル化して簡略化する方法も有効です。
4. フィードバックミーティングの実施(前半)~40分程度~
いよいよ全員を集め、フィードバックミーティングを行います。最初に目的や進め方を再確認し、ヒアリングで得られた情報を共有します。意見交換の時間を設けて、改めて、チームの強みや課題を話し合います。
5. フィードバックミーティングの実施(後半)~40分程度~
テーマを将来に切り替えます。それぞれのメンバーが思うチームの最高のシナリオ(ハイドリーム)や最悪のシナリオ(ロードリーム)を共有し、今後の将来像について話し合います。その後、4番での議論の内容も踏まえながら、取り組むべきキーテーマ(※)を抽出し、チーム全体で合意します。 ※)キーテーマ:今後取り組むべき課題を端的に表した標語。例:「メンバー一人ひとりがストレッチし、挑戦風土を創り出す」
6. アクションプランの計画
フィードバックミーティングで出てきたキーテーマをもとに、マネジャーが具体的なアクションプランを立案し、後日メンバーと共有して合意を取り、実際に進めていきます。
GRPIモデルでの話し合いのポイント
- 関係性に影響を与える他の要素に注目 いきなり関係性の課題に入らず、まずはGRPIモデルを基に、目標、役割、仕事の進め方に注目し、関係性への影響を整理することが重要です。
- メンバーが意見を言いやすい環境作り 組織を良くするための話し合いであることを強調し、個人批判を避け、すべての意見を尊重しながら発言しやすい環境を作りましょう。
- アクションプランの前にキーテーマを出す 課題からすぐにアクションプランを決めるのではなく、まずはキーテーマを設定し、合意を取った上で、アクションプランに繋げていくプロセスと取ると良いです。
GRPIモデルの効果
組織の現状を知るには、まず組織サーベイをやらなくては、と考える方も多いように思いますが、必ずしもそうではありません。特に少人数組織においては、シンプルに対話の機会を作っていくことが大切です。そのために、GRPIモデルの考え方は大変有効です。GRPIモデルは、チームの根幹となる目標、役割、手順、そして関係性という4つの要素を網羅的に点検できる点が最大の特徴です。これらの要素を通じて対話を深め、表面的な問題だけでなく、その奥に潜む本当の課題に気づくことにも繋がります。また、組織課題について対話しても、話が拡散し、整理できないという悩みに対しても、GRPIモデルは大きな助けになります。
【参考文献】
中村和彦.(2021).『マネジャーによる職場づくり 理論と実践』.日本能率協会マネジメントセンター.
このコラムを書いたプロフェッショナル

柿沼 昌吾
WillMap株式会社 代表取締役
人事と経営の両視点から29年。組織サーベイ等のHRデータ分析を通じて、持続可能な組織づくりと成果創出を支援しています。

柿沼 昌吾
WillMap株式会社 代表取締役
人事と経営の両視点から29年。組織サーベイ等のHRデータ分析を通じて、持続可能な組織づくりと成果創出を支援しています。
人事と経営の両視点から29年。組織サーベイ等のHRデータ分析を通じて、持続可能な組織づくりと成果創出を支援しています。
| 得意分野 | モチベーション・組織活性化、コーチング・ファシリテーション、チームビルディング、リスクマネジメント・情報管理 |
|---|---|
| 対応エリア | 全国 |
| 所在地 | 大田区 |
- 参考になった0
- 共感できる0
- 実践したい0
- 考えさせられる0
- 理解しやすい0
無料会員登録
記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。


 テーマで探す
テーマで探す サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 学び・実務
学び・実務





 イベント
イベント









