生成AIをどう活かす?人事業務にもたらす効果と活用例(後編)
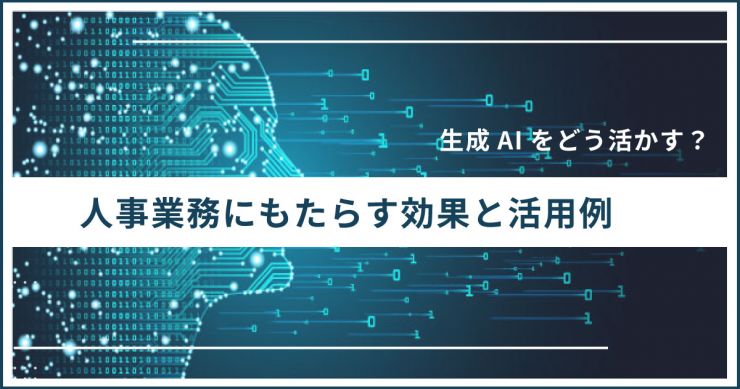
近年、AIに関する新技術や活用事例が頻繁に報道され、そのニュースを見ない日はほとんどありません。
企業の経営陣や人事業務を担当する方の中には、これらの情報を受けて、自社での応用の可能性を模索している方もいらっしゃるでしょう。
一方で、ChatGPT等の生成AIツールに対しては、登場から間もないこともあり、現時点では人事業務での活用アイデアが浮かばない、またはその導入効果を具体的に想像しにくいこともあるのではないでしょうか。
前編では、生成AIが持つ創造的な能力と、それが人事業務の多様な場面でいかに活用できるか、そして組織にもたらす大きな効果についてご紹介しました。
後編となる本コラムでは、実際の導入手順や、セキュリティ・プライバシーといったリスクへの対策について掘り下げていきます。
前編目次
生成AIとは
人事業務での生成AI活用例
生成AI活用が人事業務にもらたす効果
後編目次
人事業務での生成AI活用ステップ
人事業務における生成AI活用の注意点
人事業務での生成AI活用ステップ
実際の業務で生成AIを使った運用をはじめるまでのステップを、人事業務における例を交えながら紹介します。
ステップ1 業務の洗い出し
日々の業務や作業の中で、複雑度の低い単発業務や定期業務を挙げてみましょう。
たとえば、定期的に行う人事研修やセミナーの購買稟議の作成や、従業員から人事部への日々の問い合わせ対応等、人間が主体となり、生成AIがサポートするような業務は多くの企業が最初に取り組みやすい領域です。
ステップ2 業務フローの確認
作業を行う際の手順を、簡単なステップに分けて書き出してみましょう。たとえば、チャットボットによる問い合わせ対応を考える場合、以下のような手順が考えられます。
1.問い合わせを受領する
2.回答を調べる
3.回答内容を作成する
4.回答する
5.ステータスを完了済みにする
ユーザーストーリーマッピング*の手法を用いて、利用者の行動をもとにしたステップを設定します。それぞれのステップでAIが活用できるか、また活用する場合には、草案をAIに考えてもらい、最終判断は人間が行う等、AIを活用する部分と人間が行う部分を判断しながら業務フローを細分化することが重要です。
ステップ3 必要なデータのリストアップ
ステップ2で挙げた業務フローの中で、必要な情報やデータをリストアップしてみましょう。これは、生成AIへ指示をする際に必要な情報を考える手がかりとなります。
たとえば、セミナーの購買稟議の作成であれば過去のセミナー開催による予算や規模、人事部への問い合わせ対応であれば就業規則やFAQ等が該当します。
また、プライバシーリスクを考慮して、はじめのうちは個人情報に該当するデータは扱わないようにすることも検討しましょう。
ステップ4 業務手順の具体化
人事部へ新しく配属された従業員にその業務を教えると仮定した場合、どのような説明をするかを考えてみましょう。
生成AIも新しく配属された従業員と同じように、具体的な指示が必要なため、この工程は重要です。
ステップ5 検証
最後に、ステップ3と4で考えた内容を生成AIのプロンプトに入力して、費用対効果を検証してみましょう。
ハルシネーションリスクを考慮して、生成された内容のチェックを行い、生成AIの精度をもとに、どの業務で今後も継続的に生成AIを活用できそうか検討することも必要です。
成功事例・失敗事例を人事部内で共有することにより、新しい活用手法が見つかる場合もあります。
まずは業務自体が複雑ではないものからはじめ、一定の費用対効果が見込まれた後に、実現難易度が比較的高い業務で大きな効果を出すことによって、社内での生成AIの活用や業務への無理のない浸透が期待できるでしょう。

人事業務における生成AI活用の注意点
生成AIを活用するうえで注意するポイントと解決策の一例を紹介します。
セキュリティリスク
生成AIサービスに入力した情報が、意図しない形で学習等に使用されたり、サービス事業者が攻撃を受けたりする可能性があるため、情報漏洩のリスクがあることを認識しましょう。
特に人事業務では、従業員の個人情報を大量に扱うため、不正アクセスや情報漏洩が起きてしまうことで、個人情報が流出してしまう可能性があります。
セキュリティ対策として、信頼性の高い生成AIサービスを選び、従業員情報の暗号化やアクセス管理を徹底し、定期的なセキュリティチェックを行うことで、情報漏洩のリスクを低減できます。
プライバシーリスク
プライバシーリスクとは、特定の誰かのプライバシーや個人情報が不適切に扱われるリスクです。
個人情報保護法において、「個人情報」と「個人データ」は明確に区別されています。一般的に、「個人情報」は個人を特定できる情報を指し、「個人データ」はデータベース化され、検索可能な状態になっている情報を指します。
また、個人データには個人情報よりも厳格な取り扱いの規制が適用されています。第三者に個人データを提供する場合は、本人の同意が必要であり、生成AIを使用する際にも同様に慎重な取り扱いが必要です。
プライバシーを守るには従業員の同意を得たうえで情報を厳密に管理し、生成AIによるデータ処理がプライバシー保護の法律に適合していることを確認する必要があります。
特に従業員の個人データは、人事業務の利用のために同意しているケースは多いですが、その他のデータ活用について同意を得ていないケースが多々あります。生成AIで個人データを使用することについて本人同意を取る必要があるため注意が必要です。
信頼性リスク(ハルシネーションリスク)
信頼性リスクとは、生成AIが生み出した生成物によって、現実には存在しない、つまり「幻覚」に相当するような情報やデータを生成してしまうリスクを指します。
生成AIが実際にはない情報を「事実」として提示してしまうことで、誤解を招いたり、不正確な情報を広めたりすることが懸念されます。
生成AIは基本的に、膨大な学習データから関連性のある単語を予測し、その過程を繰り返して答えを生成します。そのため、誤った回答が発生するのは避けられません。生成AIで作成された回答を鵜呑みにしてしまうと、誤情報を従業員に伝えてしまうことにも繋がります。
信頼できる情報を得るためには、生成AIが提供する情報を盲信せず、人間が最終チェックを行い、誤情報を防ぐための社内ルールを設けることが重要です。
生成AIの活用をはじめよう
生成AIを活用し、社内の生産性と効率性を高めるためには、生成AIを取り入れた活用例を集め、そのプロセスを通じて恩恵を得られるという経験が重要です。
活用例を社内で共有し、組織全体に利点や意義を広めることで、ビジネスイノベーションが生まれるきっかけとなります。また、新しいテクノロジーを導入することで、特に最新技術への興味が強い従業員のモチベーションにも繋がるでしょう。
本コラムで解説の通り、人事業務は生成AI活用による効果が期待される活用例が比較的多く考えられます。
まずは現在の業務を見直し、人事業務から率先して生成AI活用をはじめてみてはいかがでしょうか。
このコラムを書いたプロフェッショナル

袋瀬 淳
株式会社Works Human Intelligence / WHI総研
大手不動産会社にて企業の寮や社宅の運用支援を通じた業務改革に従事後、Works Human Intelligence入社。保守コンサルタントを経て、多くの企業を見てきた経験を活かし、人事全体の事例・トピックスの研究・発信活動を行っている。

袋瀬 淳
株式会社Works Human Intelligence / WHI総研
大手不動産会社にて企業の寮や社宅の運用支援を通じた業務改革に従事後、Works Human Intelligence入社。保守コンサルタントを経て、多くの企業を見てきた経験を活かし、人事全体の事例・トピックスの研究・発信活動を行っている。
大手不動産会社にて企業の寮や社宅の運用支援を通じた業務改革に従事後、Works Human Intelligence入社。保守コンサルタントを経て、多くの企業を見てきた経験を活かし、人事全体の事例・トピックスの研究・発信活動を行っている。
| 得意分野 | 経営戦略・経営管理、モチベーション・組織活性化、人事考課・目標管理、キャリア開発、情報システム・IT関連 |
|---|---|
| 対応エリア | 全国 |
| 所在地 | 港区 |
- 参考になった0
- 共感できる0
- 実践したい0
- 考えさせられる0
- 理解しやすい0
無料会員登録
記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。


 テーマで探す
テーマで探す サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 学び・実務
学び・実務





 イベント
イベント









