生成AIをどう活かす?人事業務にもたらす効果と活用例(前編)
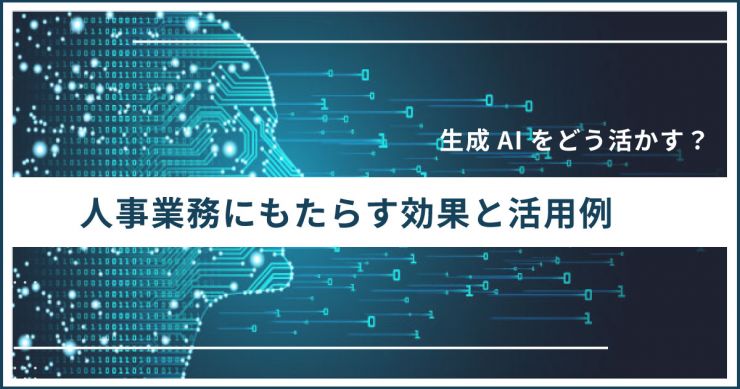
近年、AIに関する新技術や活用事例が頻繁に報道され、そのニュースを見ない日はほとんどありません。
企業の経営陣や人事業務を担当する方の中には、これらの情報を受けて、自社での応用の可能性を模索している方もいらっしゃるでしょう。
一方で、ChatGPT等の生成AIツールに対しては、登場から間もないこともあり、現時点では人事業務での活用アイデアが浮かばない、またはその導入効果を具体的に想像しにくいこともあるのではないでしょうか。
本コラムでは前編・後編を通じ、生成AIの特徴を改めて見直し、生成AIの活用例やもたらす効果、また人事業務において生成AIを活用する際の注意点を解説します。
前編目次
生成AIとは
人事業務での生成AI活用例
生成AI活用が人事業務にもらたす効果
後編目次
人事業務での生成AI活用ステップ
人事業務における生成AI活用の注意点
生成AIとは
生成AIとは、文章、画像、動画等の様々なデジタル作品を生み出すことが可能な人工知能(ジェネレーティブAI)を指します。
従来のAIが業務の自動化を目的としていることに対し、生成AIはデータのパターンや相互の関係を学習し、新たなコンテンツを生成することが主な目的です。
従来のAIとの違い
従来のAIは、主に整理されたデータを使って物事を分類したり、未来を予測したりすることに使われています。はっきりとした形式に従って整理された情報、つまり「構造化データ」を扱うことが得意です。
しかし、生成AIは違います。生成AIは、整理されていない情報、つまり「構造化されていないデータ」から学び、それをもとに新しい文章や画像等のコンテンツを創り出すことができます。
たとえば、ChatGPTをはじめとする生成AIのアプリケーションは、ある条件にもとづいて文章を生成するだけでなく、新しいデータを学習してその知識を蓄積し、生成する文章の品質を向上させることができます。
これにより、生成AIは柔軟に学習し、様々なコンテンツを生み出す能力を有することができます。
生成AIの種類
データのパターンや関係を学習し、新しいコンテンツを生み出す生成AIですが、大きく下記4種類に分類されます。
●文章生成
プロンプトと呼ばれる文章(指示文)をもとに、自動的に文章を生成するAIです。
代表的なサービスはChatGPTやGemini等があり、長文の要約やキャッチコピーのアイデア生成、プログラミングコードの生成等、幅広い用途で利用されています。
●画像生成
テキストで指示を与えるだけで、指示にもとづいた画像を瞬時に生成します。
「Stable Diffusion」や「Midjourney」等がその例であり、アートやデザインのクリエイティブな表現が必要な場面で利用されています。
●動画生成
テキストにもとづいてイメージに近い動画を生成します。
2024年2月にOpenAI社が公開した動画生成AIモデル「sora」は、文章で指示すると、最長1分の高い品質の動画が生成可能で、将来的には長尺の動画生成も期待されます。マーケティングコンテンツの作成や研修で利用する動画の作成等に応用されています。
●音声生成
音声やテキスト入力によって新たな音声を生成します。
個人の声質を学習させ、その人の声で様々な文章を話すことができます。ナレーションやアバターへの音声付加等に活用が期待されています。

人事業務での生成AI活用例
これまで、生成AIの概要についてご紹介しましたが、多岐にわたる人事業務にも生成AIが活用されはじめています。
採用業務において、応募者の履歴書や職務経歴書から最適な候補者をピックアップする製品や、従業員のスキルや興味に合わせてカスタマイズされた研修コンテンツを生成する製品等、様々な製品が発表されています。
本章では、人事業務における代表的な生成AI活用例をご紹介します。
●採用業務における文章生成
従業員や内定者等、対象者に合わせて雇用契約書、採用通知書、社内通知等の標準文書を自動で生成します。
また、応募者を惹きつける求人票の生成にもAIを活用することが可能です。
具体的には、過去の採用傾向を分析して、求めるスキルや経験を正確に反映した求人票を作成したり、潜在的な候補者へパーソナライズされたメッセージを送る等ができ、採用関連業務での効率化が期待できます。
●人材育成の研修コンテンツの発案
働き方や働き方に対する価値観の多様化により、企業は従業員の志向やニーズに沿った人材育成に取り組む必要性が高まっています。
そのため、一人ひとりの従業員に最適化された研修資料やシナリオの作成にAIを活用し、合理的な学習機会の提供に役立てることもできるでしょう。
●キャリアパスの提案
終身雇用が当たり前だった時代から、キャリアアップや自身が望む働き方の実現のために転職することが一般的となった今、従業員のキャリアが多様化していることで将来のキャリア像が描きにくくなっています。
そのため、従業員が将来の目標に向けて意欲的に仕事に取り組むことができるよう、企業はキャリアアップのために必要となる社内基準や条件を明確化したキャリアパスを提示することが求められています。
キャリアパスの構築においては、生成AIによるデータ分析を活用することで、従業員の過去の業績やスキルをもとに、将来の成長や昇進の機会を示唆するキャリアパスを効率的に提案することが可能になります。
●ダイバーシティ&インクルージョンのための分析
多様性の推進は、アイデアやイノベーション創出を促す一方、偏見やコミュニケーションの障壁になる可能性もあります。
多様な従業員の相互理解を促進し、企業の成長に繋げるためには、従業員一人ひとりの声を正確に理解して反映することが重要です。
生成AIは、様々な背景を持つ従業員からのフィードバックやアンケート結果、人事データを収集し、従業員のエンゲージメントや帰属意識等の分析を通じて、より開かれた職場文化の構築に貢献します。
●FAQの作成
給与や勤怠等、人事部は従業員からの問い合わせ対応業務をすることがありますが、業務に関する質問をまとめてデータベース化したFAQの作成に生成AIを活用することが可能です。
弊社でも、Azure OpenAI Serviceを利用し、自社で開発した生成AIが勤怠に関するFAQを作成することができるか、実証実験を行いました。
有用なFAQの作成においては課題があるものの、資料の読解、QA箇所の検討、文面の作成スピードの面で効果を実感できました。
生成AI活用が人事業務にもらたす効果
では、実際に人事部門で生成AIを活用した場合、どのような効果があるのでしょうか。本章では3つの期待効果について紹介します。
組織活性化
組織活性化を図ることも人事の重要な役割の一つです。
生成AIを通じて社内の情報共有が促進され、部門間の壁を低くすることで組織全体のイノベーションが加速され、新しいアイデアの創出を促します。
組織の活性化に繋がり、結果として組織全体のパフォーマンス向上に寄与することが期待できるでしょう。
データドリブンな戦略設計
生成AIを活用して従業員や組織に関するデータを一元的に収集・整理し、分析することで、データドリブンな意思決定に繋がります。勘や経験に頼る状況を減らし、事実にもとづいた戦略を立てられるでしょう。
たとえば、採用面接時のメモや評価データ等の情報を集約し、採用傾向の分析に生成AIを活用することで、次年度以降の人事戦略の設計や採用プロセスを見直す際の情報の一つとなると考えられます。
AIに代替できない業務への注力
チャットボットの生成AIツールによる問い合わせ対応や日常の文書作成等の業務を自動化することで、人事担当者は単純な対応業務から解放されます。
一方で、人事戦略の立案や他部門との折衝といった業務は生成AIで代替するのは難しいと考えられます。単純作業から解放されることにより、人事担当者はこれらの業務に注力できるでしょう。
また、日々の問い合わせを通じて生成AIによって収集されたデータは、従業員の関心事やニーズをより深く理解することに繋がり、改善点の特定に役立ちます。
前編では、生成AIが持つ創造的な能力と、それが人事業務の多様な場面でいかに活用できるか、そして組織にもたらす大きな効果についてご紹介しました。
後編では、実際の導入手順や、セキュリティ・プライバシーといったリスクへの対策について掘り下げていきます。
このコラムを書いたプロフェッショナル

袋瀬 淳
株式会社Works Human Intelligence / WHI総研
大手不動産会社にて企業の寮や社宅の運用支援を通じた業務改革に従事後、Works Human Intelligence入社。保守コンサルタントを経て、多くの企業を見てきた経験を活かし、人事全体の事例・トピックスの研究・発信活動を行っている。

袋瀬 淳
株式会社Works Human Intelligence / WHI総研
大手不動産会社にて企業の寮や社宅の運用支援を通じた業務改革に従事後、Works Human Intelligence入社。保守コンサルタントを経て、多くの企業を見てきた経験を活かし、人事全体の事例・トピックスの研究・発信活動を行っている。
大手不動産会社にて企業の寮や社宅の運用支援を通じた業務改革に従事後、Works Human Intelligence入社。保守コンサルタントを経て、多くの企業を見てきた経験を活かし、人事全体の事例・トピックスの研究・発信活動を行っている。
| 得意分野 | 経営戦略・経営管理、モチベーション・組織活性化、人事考課・目標管理、キャリア開発、情報システム・IT関連 |
|---|---|
| 対応エリア | 全国 |
| 所在地 | 港区 |
- 参考になった0
- 共感できる0
- 実践したい0
- 考えさせられる0
- 理解しやすい0
無料会員登録
記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。


 テーマで探す
テーマで探す サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 学び・実務
学び・実務





 イベント
イベント









