育成対象に応じた設計アプローチとは?
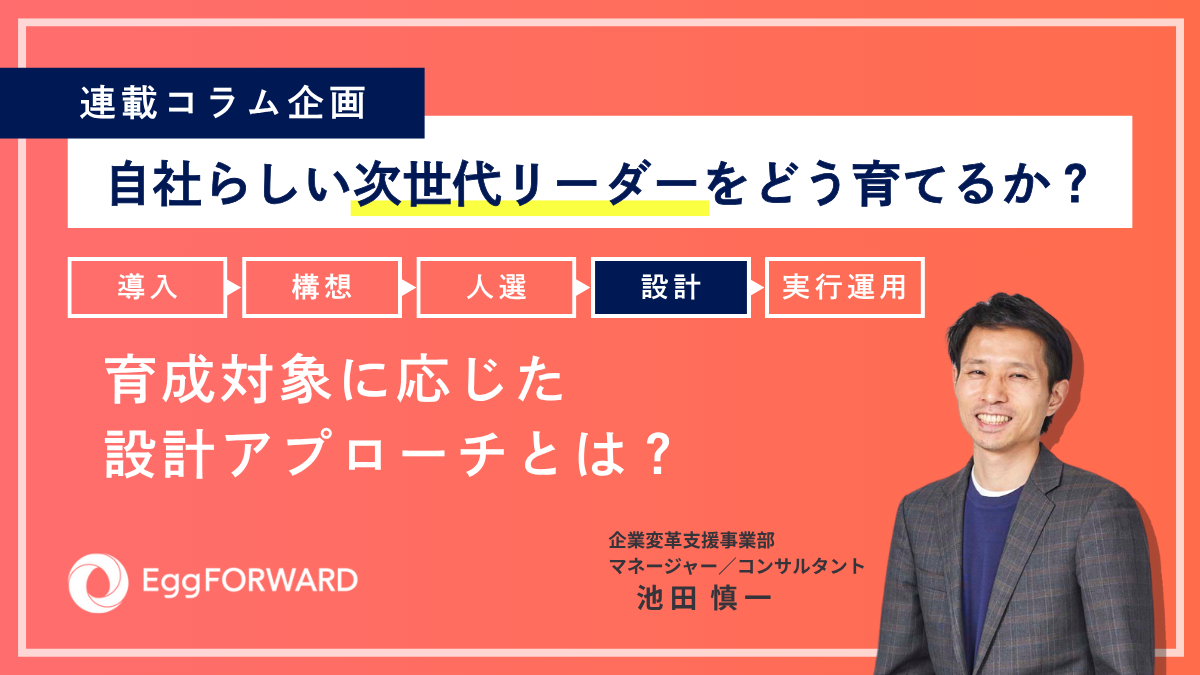
自社らしい次世代リーダーをどう育てるか?
【育成プラン編】育成対象に応じた設計アプローチとは?
本シリーズでは、「自社らしさ」を軸にした次世代リーダー育成の在り方を、紐解いていきます。エッグフォワードによる多様な企業との取り組み事例をもとに、育成の構想・設計・運用における実践的な観点を紹介します。
前回までの記事では、「自社ならではの目指す姿」や取り組みコンセプトに基づいて人選基準を定め、候補者を選出するプロセスについて実践的な観点から整理しました。
では、明確な方針のもとに候補者を選出したあと、いかにして「最適な育成プラン」を設計していくのか?今回は、短期・中長期それぞれの育成対象に応じた設計アプローチや、実践機会・支援体制・共通施策のつくり方など、育成プランを形にしていくための具体的な視点と工夫をお届けします。
「最適な育成プラン設計」の前提
自社ならではの「目指したい姿」や「取り組みコンセプト」を言語化し、将来のリーダー候補を想定した人選を行えたら、次は育成プランの設計に進む。
(後継者計画の文脈であれば、採用計画も並行する場合がほとんどだが、本稿では、特に次世代リーダー候補としての育成対象に焦点を当てて、育成プランを考えていきたい。)
改めて問うと、「最適な育成プラン」とは、何をもって判断できるものなのだろうか?
まずヒントとなるのは、これまで見てきた運用方針の判断と同様、自社が描く「理想状態・求める人材像」との連動であり、そこに近づくスピードを高められるかどうかという観点である。
加えて、現状理解=「理想と現実のギャップ把握」も重要となる。
たとえ理想を描いていたとしても、対象者の状況によって、必要とされる関わり方は大きく異なる。
把握したい情報を見極めた上で、各社ごとに「既に活用できる情報」と「新たに取得すべき情報」を整理しながら、適切なアセスメント(360度評価、業績評価、外部ツール活用など)を取り入れる。
「理想状態」と「現状理解」に基づく育成プラン設計
このように、「最適な育成プラン」を言い換えるなら、
「理想と現状のギャップを埋める、効果的な育成促進施策」と位置付けることができる。
では、具体的にはどのような育成促進施策が考えられるだろうか?
ここで重要なのは、「育成施策」が必ずしも集合研修やプログラムに限定されないこと。実務経験や日々の業務の中での学び、経営層(経営者含む)からの支援など、幅広い観点で考えることが求められる。
ここでは、多くの企業様から実際に相談いただくテーマ・課題感を踏まえ、対象層のレイヤーを、「A.短期:1~3年以内の上位ポスト任用を見据えた人材層」と、「B.中長期:5~10年以上先の次世代経営人材を見据えた若手層」の2つに分けて、それぞれの育成プラン検討において考慮されることの多い観点を紹介していきたい。
A.短期:1~3年以内の上位ポスト任用を見据えた人材層の育成プラン
上位のポストであり、短期的な任用を見据えた候補者であるほど、個別性のある育成計画が必要となる。「Aさんという個人が、求められる人物像に近づくために、実際にどのような機会やサポートを提供できるだろうか?」という観点である。
個別育成計画のポイント
多くの企業では「人材育成会議(人材開発会議)」を活用し、対象者1人1人の機会提供やフォロー方針を議論する。
(ここでも、以前のコラムで触れたように、経営層をはじめ、人材開発部門、事業部の育成担当、HRBP等、様々な視点を持つ関係者が連携し、多面的な視座を統合して育成プランを練ることが重要となる)
人材育成会議で議論する具体的な育成プランの内訳としては、例えば以下のようなアプローチを組み合わせるケースが多い。
-
タフアサインメント(海外事業、新規事業リード、子会社経営など、困難を伴う経験)
-
社長・役員直下プロジェクトへの抜擢(戦略上のキードライバー推進、部門横断の組織変革などのリードを通じて、経営視点を養う経験)
-
役員によるコーチング・フィードバック・メンタリング(困難な状況を打開するための経営視座での問いかけ・視野の拡大や、キャリア観点での覚悟醸成などをフォローする仕掛け)
トップによるコミットメント
上記のような育成プラン内容はいずれも貴重な機会であり、対象者への「適切さ」だけでなく、「社内リソース配分」の観点で全体最適を考える必要がある。
だからこそ、経営トップのコミットメントが極めて重要となる。
実際、社長自身が人材育成会議の議長を務めるケースも少なくない。
人事部門・外部パートナーのサポートを受けつつも、最終的な候補者人材の見極め・機会提供の意思決定においては、トップが主体としてコミットするメリットが非常に大きい。
なお、経営トップが多忙で人材育成委員会の時間を捻出できないと感じられるケースも多い。
そのような場合には、会社として、「未来を担う人材を見極め、機会提供を行うことの意義」を改めて問い直し、認識を揃える必要がある。
GEのジャック・ウェルチ氏がかつて、人材マネジメントプロセスに年間30日を費やし、仕事の時間の50%を人材の問題に費やしていた※という話は極端な例かもしれないが、他の仕事を敢えて他者に任せるなど、「経営トップが、いかに会社の未来を担う人材の議論や意思決定に関われる環境・構造をつくれるか」に問いを向けることで、視界が開けることもある。
<脚注> ※エド・マイケルズ、ヘレン・ハンドフィールド=ジョーンズ、ベス・アクセルロッド(2002)『ウォー・フォー・タレント』翔泳社、69・240ページより。ジャック・ウェルチはGE在任時、マネジメント人材評価プロセス「セッションC」に年間30日を費やし、退任まで仕事時間の50%を人材の問題に費やしていたとされる。
B.中長期:5~10年以上先の次世代経営人材を見据えた若手層の育成プラン
若手層においても、短期的な上位ポスト任用を見据えた人材層と同様、個別の実務環境を踏まえた育成計画は重要である。
ただし、対象人数が多く、現場上長がより詳しく実態をよく把握していることが多いため、育成責任を上長が担うケースが一般的である。
人材育成会議を運営する場合も、直属の上長が中心となって現場での機会提供や成長状況の報告を行い、経営層や人事などからは、育成に関する問いかけ・アドバイスを行うようなアプローチが取られやすい。
ここではさらに、上記のような上長中心で行われる日常的な現場個別フォロー以外に、「敢えて実務経験と異なる刺激・機会を設ける」という観点から、「複数の次世代候補者たち全体に向けた共通施策」の在り方について、紹介しておきたい。
共通施策設計のポイント
共通施策を講じる場合にも、原則としてはまず、
-
「候補者たちに期待する理想状態とは何か?に立ち返ること」
-
「候補者たちの現場実態を把握・分析すること」
が重要となる。
個別の実態把握やアセスメントなどを通じて得られるインプットも参考にしつつ、あくまで自社が優先すべき、「共通の育成方針」を見極め、設定できると望ましい。
参考として、自社ならではの「共通の育成方針」を言語化するために効果的な問いかけを2つ紹介しておく。
-
1つ目は「過去・現在を振り返り、特に現場で育ちにくい・より引き上げたい要素とは何か?」という問いである。主にこれまでの社内人材の強みや弱みなど、現状把握を基に、自社ならではの強化すべきポイントをギャップとして捉えるアプローチだ。
-
2つ目は「自社の未来を描いた際、これまで以上に優先して強化しておくべき要素とは何か?」という問いである。この観点を持つと、現状の延長線上に囚われず、自社なりの「ありたき姿」と紐づけたポイントを見出しやすい。
特に、時間軸が長く、未来を担うことが期待されている若手層向けには、後者の、自社の未来像と紐づけた問いに答えることが、より重要になると言えるだろう。
共通施策の具体イメージ
一般的に、未来の経営人材候補という性質を伴う場合、学習形式としては「座学」よりも「実務実践」に軸を置きながら、構成要素としても「覚悟」や「実践」・「内省」を伴うアクションラーニング型のプログラムを構築するケースが多い。
例えば、ある企業では、社長直下で若手選抜プログラムを組み、半年間「所属組織の課題を自ら特定・推進する」実践課題に取り組んだ。
実務現場での実践に加え、
-
MBA型ワークショップ
-
経営層の実体験に基づくケーススタディ
-
同世代の候補者同士のディスカッション
-
外部コーチや上長を交えた面談
などを組み合わせることにより、実践のヒントを得たり、覚悟や内省を促したりし続ける、複合的な取り組みであった。
初めは不安も見られた対象者が、会社からの期待や、同世代からの刺激・上長からの支援などに支えられながら、実際に所属組織が陥っていた悩ましい壁・実態に踏み込み、多くの関係者に働きかける中で、確かな手ごたえや、至らなさ・今後に向けた希望と覚悟を力強く宣言する様子が見られた。
この会社では、プロジェクト期間終了後も、各分野で多くの卒業生が活躍を続けている。
探究活動としての育成プラン設計
ここまで紹介してきた対象層やアプローチ観点はあくまで参考例だが、いずれの場合においても、具体的な育成プログラム設計を行う上では、
-
どのような実践機会を中心に据えるのか?
-
どの関係者まで巻き込んで支援を行うのか?
-
どのようなヒントや武器に触れてもらい、どのようなフォローや問いかけを行うのか?
といった一つ一つにおいて、都度、自社の目指したい姿や、理想の人物像、大切にしたい思想や価値観・カルチャーなどと照らし合わせながら、意思決定を行い続けることがポイントとなる。
また、育成プランは一度設計して終わりではなく、日々の実践と検証を通じて、絶えず見直し・調整し続けることで徐々に洗練されていくものだ。
こうした探究活動を繰り返すことにより、自社にとっての「最適な育成プラン」が、少しずつ形を帯びていくのである。
次回は、自社にとって最適な育成プランを練った後の【実行・運用編】として、最終的な育成の成否を大きく左右する、実行プランの遂行と磨きこみのヒントをお伝えしていきます。
このコラムを書いたプロフェッショナル

池田 慎一
エッグフォワード株式会社 企業変革事業部 マネージャー
リーダーや若手の育成、マネジメント強化、理念・カルチャー浸透など、企業の優先課題に応じて幅広く支援を行っています。
お客様固有の歴史や想い、組織文化に根ざした「ありたき姿」の言語化と、その実現に向けた構想・実行の伴走を得意としています。

池田 慎一
エッグフォワード株式会社 企業変革事業部 マネージャー
リーダーや若手の育成、マネジメント強化、理念・カルチャー浸透など、企業の優先課題に応じて幅広く支援を行っています。
お客様固有の歴史や想い、組織文化に根ざした「ありたき姿」の言語化と、その実現に向けた構想・実行の伴走を得意としています。
リーダーや若手の育成、マネジメント強化、理念・カルチャー浸透など、企業の優先課題に応じて幅広く支援を行っています。
お客様固有の歴史や想い、組織文化に根ざした「ありたき姿」の言語化と、その実現に向けた構想・実行の伴走を得意としています。
| 得意分野 | リーダーシップ、マネジメント、コーチング・ファシリテーション、チームビルディング、ロジカルシンキング・課題解決 |
|---|---|
| 対応エリア | 全国 |
| 所在地 | 渋谷区 |
- 参考になった0
- 共感できる0
- 実践したい0
- 考えさせられる0
- 理解しやすい0
無料会員登録
記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。


 テーマで探す
テーマで探す サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 学び・実務
学び・実務




 イベント
イベント









