研究テーマの仮説をたててみる「リサーチクエッション」
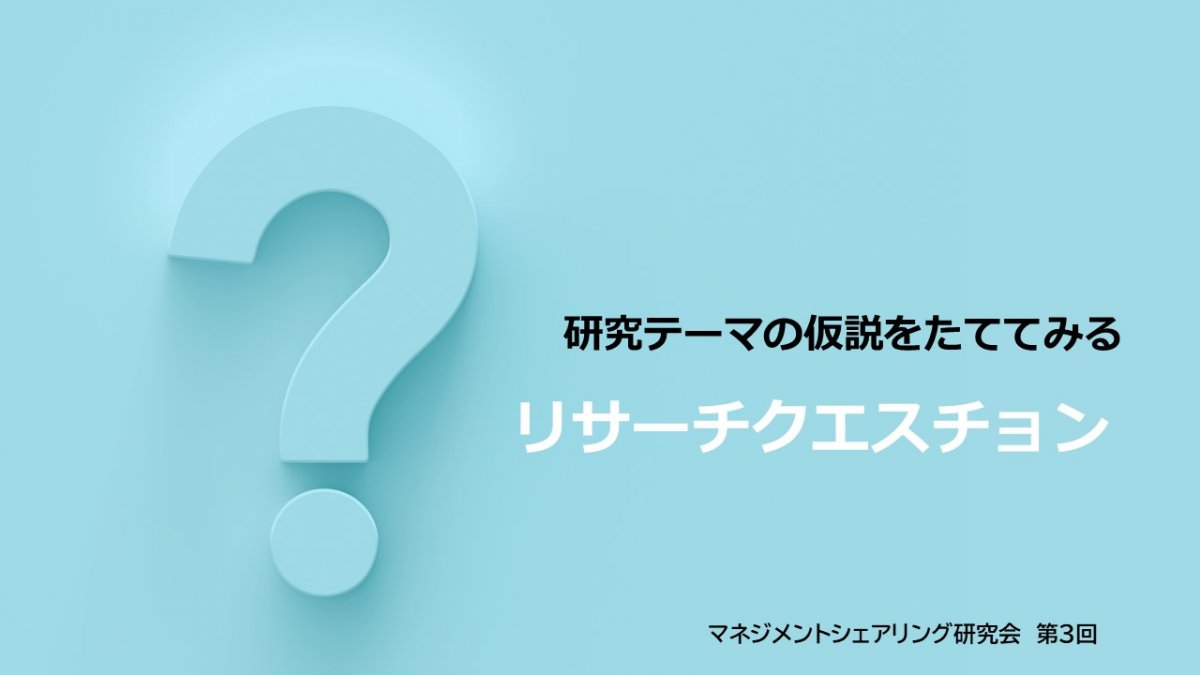
第3回「マネジメントシェアリング研究会」
―研究テーマの仮説をたててみるー
こんにちは。株式会社ジェイフィールの重光です。
先日、第3回「マネジメントシェアリング研究会」が行われました。
第2回では、各人が研究したいテーマを持ちより、近しい人同士、3つのチームに分かれてもらい「リサーチクエスチョン」(=研究のテーマ、問い)の仮置きを行ってもらいました。
今回はその「リサーチクエスチョン」に対する答えである「仮説」を立ててもらい、「仮説の背景や土台にある思い」「根拠となる(参考にした)情報や事例」そして、「仮説を検証する方法(今後、取り組みたいこと)」について話し合ってもらいました。
今回のコラムでは、皆さんの「仮説」を紹介する前に、「リサーチクエスチョン」から「仮説立案」までのプロセスを解説していきます。今後、何かを研究する際、特にチームで行う時の「思考の道しるべ」として活用してもらえたら幸いです。
なぜ、「仮説の背景や土台にある思い」を共有するのか
研究や調査に取り組むとき、その時点で明らかにしたい事柄は心の中では決まっていることが多いものです。「生成AIとの付き合い方について研究しよう」と言い出しても、実は「生成AIが凄いことはわかるけど、人間が支配されることはない。ないと信じたい」と強く願っているような例です。もちろん、研究ですから事実をねじ曲げることはできませんが、どういう領域や条件の下では願いが叶うのか、可能性を模索・調査していくわけです。その結果、私たちが今こんな行動をとることで未来を変えていける、といったことが見えてくる。この一連のプロセスが研究であり、研究成果になっていきます。
チームで行う研究においては、テーマは一致しても、背景にある思いはそれぞれ異なっていることがよくあります。出発点となる個人の思いを確認しないまま進めると、調査対象や方法で意見がまとまらなかったり、逆に妥協が生まれて結論が総花的になったりという危険性をはらんでしまいます。互いに思いを理解していると、相手の発言の真意が理解しやすくなり、自分も発言がしやすくなる、という効果もあるので、「仮説の背景や土台にある思い」を共有するのは欠かせないポイントです。
「根拠となる(参考にした)情報や事例」を共有する意味
その際、抽象的な思いを語るだけでなく、自分がそう思う背景にこんな事実がある、こんな情報を見たということまで共有すると、相互理解が進みます。実際、チームCの共有の場面でも、「実は、私の職場はこんな人員構成で、こんな課題に直面しているので…」という話が出てきました。聴いているメンバーは、なるほどと大きくうなずき、その点をクリアにしたいね、と理解を越えて共感が生まれてきました。
共感が生まれると、当初の自分の関心事ではない情報に接しても、「あれっ、この情報は彼(彼女)にとって面白いかも」と自然にアンテナが立つようになり、情報共有が進みます。こうしてプラスアルファのコミュニケーションが生まれると、感謝の気持ちが芽生え、健全な意味での「お返し」の情報共有が豊かになっていきます。
良い感情の連鎖が、情報共有や思考の質を上げていき、最終的な研究成果にポジティブにつながっていきます。
各自が仮説を検証する行動を宣言して活動を広げていく
仮説が立てられると、研究で目指すゴール(仮説の立証)も見えてきます。そして、調査活動に入ります。一つのゴールに向かうけれども、それぞれが取り組むのは少しずつ視点が異なっています。先ほど述べたように、自分の思いをもとに具体的な検証を行っていくわけです。すなわち、各人がそれぞれ、どのような調査活動でゴールに近づくのか、「仮説を検証する方法(今後、取り組むこと)」を設定します。
個人ではなく、チーム研究だからこそ、多角的なアプローチをとることが可能になるわけです。時間的制約はあっても、異なる環境と多様な視点でユニークな仮説検証が期待されます。
このコラムを書いたプロフェッショナル

重光直之
株式会社ジェイフィール 取締役 / 経営チームメンバー
ジェイフィールでは3名の取締役でマネジメントシェアリングを実施中。ミンツバーグ教授との出会いからリフレクションラウンドテーブル(R)を日本に導入。 第1回HR Award 受賞。主な著書「ミンツバーグ教授のマネジャーの学校」他

重光直之
株式会社ジェイフィール 取締役 / 経営チームメンバー
ジェイフィールでは3名の取締役でマネジメントシェアリングを実施中。ミンツバーグ教授との出会いからリフレクションラウンドテーブル(R)を日本に導入。 第1回HR Award 受賞。主な著書「ミンツバーグ教授のマネジャーの学校」他
ジェイフィールでは3名の取締役でマネジメントシェアリングを実施中。ミンツバーグ教授との出会いからリフレクションラウンドテーブル(R)を日本に導入。 第1回HR Award 受賞。主な著書「ミンツバーグ教授のマネジャーの学校」他
| 得意分野 | モチベーション・組織活性化、マネジメント、コーチング・ファシリテーション、チームビルディング、コミュニケーション |
|---|---|
| 対応エリア | 全国 |
| 所在地 | 渋谷区 |
- 参考になった0
- 共感できる0
- 実践したい0
- 考えさせられる0
- 理解しやすい0
無料会員登録
記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。


 テーマで探す
テーマで探す サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 学び・実務
学び・実務





 イベント
イベント









