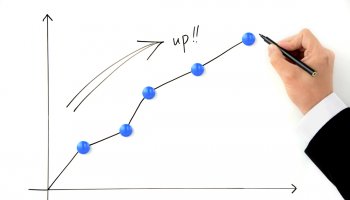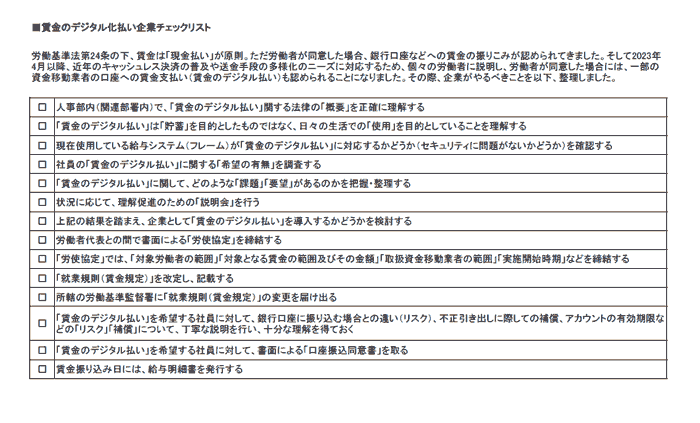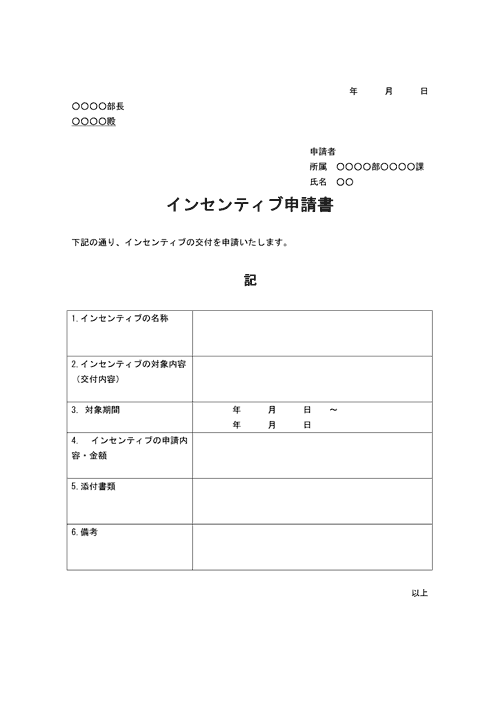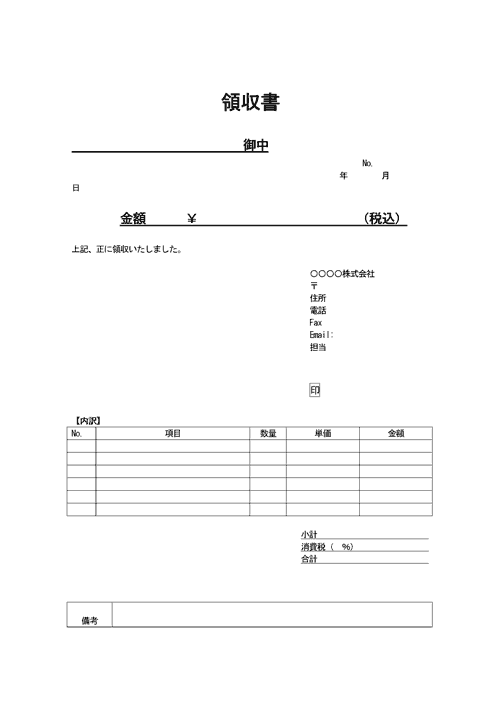賃上げ
賃上げとは?
賃上げとは、基本給のベースアップや定期昇給などにより、企業が労働者に支給する賃金の増額を行うことをいいます。日本ではバブル崩壊以降、物価が下がり、デフレによって賃金が上昇しない状況が長く続きましたが、2022年からの物価上昇・インフレを受け、春闘において「5%程度」の高い賃上げ要求が続いており、24年春闘では5.33%もの歴史的な賃上げを実現。2025年も、最低賃金全都道府県1,000円以上や、引き続き5%に迫る賃上げが予測されます。
賃上げの定義
賃上げは、「ベースアップ」と「定期昇給」の二つからなります。
ベースアップとは、基本給の底上げを指し、略して「ベア」と呼ばれます。能力や勤続年数などに関係なく、基本給の水準が一律で上昇するものです。たとえば「ベースアップ3%」の場合、全従業員の基本給の水準が一律で3%アップします。
定期昇給(定昇)とは、企業が決めた基準に沿って、毎年定期的に行われる昇給のことです。勤続年数に伴う昇給や、年齢に伴う昇給などが該当します。定期昇給のタイミングは、企業によってさまざまです。
連合春闘方針における「ベア」と「定昇」
2024年の春闘では、連合から「賃上げ分3%以上、定昇相当分(賃金カーブ維持相当分)を含め5%以上の賃上げを目安とする」という方針が打ち出されました。これは、ベースアップ相当分として3%以上、定期昇給分を含めて5%以上の賃上げを要求するという意味です。
「ベースアップ相当分3%以上」が実現した場合、基本給が3%(または3%以上)底上げされます。
「定昇相当分」とは、賃金カーブの維持・賃金水準の維持と同じ概念で、年齢・勤続年数に合わせて右肩上がりに上昇していく賃金カーブを維持するため、必要な昇給分を確保するための要求です。
たとえば、35歳、30歳、25歳の従業員を雇用している場合、賃金カーブに沿って定期昇給が行われれば、1年後は36歳、31歳、26歳と年齢(勤続年数)に応じた賃金を支払うことになります。従業員の勤続年数が上がるにつれて人件費が増額となるので、企業は賃金カーブに応じた定期昇給を行うための財源を確保しなければなりません。
賃金制度が整備されている大手企業では、定期昇給などで賃金カーブを維持することがほぼ制度化されています。しかし、中小企業には賃金表がない組織も少なくありません。毎年の賃上げ交渉で、賃金カーブ維持に必要な昇給分を確保することは、従業員の生活水準を維持するために重要です。
インフレが続くと物価が上昇するため、賃金カーブ維持の定期昇給だけでは生活水準の維持が難しくなります。そのため、ベースアップが賃上げの大きな論点になる傾向があります。
賃上げの動向
春闘などの動向を踏まえると、2025年はどのような状況が予想されるのでしょうか。
春闘の動向
春闘とは、「春季生活闘争」の略称です。多くの日本企業では会計年度に合わせて2月〜3月頃に翌年度の賃上げや労働条件を交渉する慣習がありますが、日本の労働組合にとって、1年で最も大きなできごとといえます。60年以上の歴史があり、景気や日本の社会環境に合わせて春闘で行われる賃上げ要求も変化してきました。
春闘で高い賃上げ要求が行われたのは、バブル景気により経済が好調だった、1980年代後半から1990年代前半です。定期昇給込みで5%~9%と、高い賃上げ要求がなされました。1990年代後半にバブルが崩壊すると、デフレが長期化する中で具体的な賃上げ要求の数値を掲示しない時期が続きます。この時期には、労働者の雇用安定が重視されていました。
再び具体的な数値が掲げられたのは、2014年になってからです。長引くデフレ脱却に向けて4%以上、4%程度といった賃上げ要求がなされました。2023年になってからは、物価上昇が続いたことを受け、賃上げ要求方針は5%程度に上昇。2024年の春闘では、賃上げの平均妥結額は1万7,415円、賃上げ率は5.33%を実現。実に1991年以来33年ぶりとなる、賃上げ率5%を達成しました。
2025年も引き続き、高い伸びとなる見通しです。2025年の春闘では、連合はベースアップ相当分として3%以上、定期昇給分を合わせて5%以上の賃上げ要求を決定。中小企業の労働組合はさらに1%以上を上乗せし、6%以上の賃上げを要求する方針です。
各シンクタンクによる2025年の賃上げ見通し
| シンクタンク | 賃上げ予想 | 備考 |
|---|---|---|
| 第一生命経済研究所 | 4.80% | 25年も5%に迫る賃上げが実現する見込み |
| みずほリサーチ&テクノロジーズ(※) | 4.30% | サービス業を筆頭とする構造的な人手不足から、25年の賃上げ率は高水準となる予測 |
| 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(※) | 4.0% | 高い伸び率が続くが、物価上昇率が鈍化しつつある上、高い賃上げに追随できない企業も増えつつあり、前年実績を下回る |
(※)労政時報4089号「2025年賃上げ見通しと経済・経営環境」より引用
2025年の春闘でも、各種シンクタンクは賃上げが実現する見通しを立てています。第一生命経済研究所は、人手不足、物価高への配慮、底堅い企業業績が賃上げ率の押上の要因となるとし、2024年に続く高い賃上げ率を予測しています。みずほリサーチ&テクノロジーズも、構造的な人手不足を原因に挙げ、2025年の賃上げ率を高く見積もっています。一方、三菱UFJリサーチ&コンサルティングでは、高い伸び率が続くものの、高い賃上げに追随できない企業も増えてくることから、前年度を下回ると予測しています。
政労使も賃上げに意欲的
政労使は昨年に引き続き、賃上げに意欲的です。政府は、24年11月に開かれた政労使会議にて、「今年(24年)の勢いで大幅な賃上げの協力を」と経済界、労働団体のトップらに要請。連合は25年春闘について、ベアと定昇を合わせて5%以上の賃上げを目指す構想を掲げており、「5%以上」を最低ラインとして取り組むことで賃上げの流れの定着を目指しています。
企業側も、賃上げに対して昨年よりも意欲的であることが伺えます。経済同友会の景気定点観測アンケートによれば(24年9月時点)、25年に賃上げを実施予定とする企業は68.3%と、前年同期と比較して14ポイント上昇。賃上げ率は「3~4%未満」としているところが33.3%と最も多く、賃上げ率は全体平均では3.58%となっています。
- 【参考】
- 2024年9月(第150回)景気定点観測アンケート調査結果|経済同友会(PDF)
- 春闘賃上げ率は+4.8%、ベア3%と高い伸びを予想。キーワードは「定着」|第一生命経済研究所
- 2025年賃上げ見通しと経済・経営環境|WEB労政時報
- 賃上げの流れを受け、人事はどう対応すればいいのか? 川口大司さんに聞く | 『日本の人事部』
賃上げを下支えする「賃上げ促進税制」
2024年は、賃上げ促進税制が強化された年であり、実際の賃金を底上げするための企業の取り組みが加速した年でもありました。

賃上げ促進税制とは|『日本の人事部』
- 参考になった0
- 共感できる0
- 実践したい0
- 考えさせられる0
- 理解しやすい0

用語の基本的な意味、具体的な業務に関する解説や事例などが豊富に掲載されています。掲載用語数は1,500以上、毎月新しい用語を掲載。基礎知識の習得に、課題解決のヒントに、すべてのビジネスパーソンをサポートする人事辞典です。
会員登録をすると、
最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!
無料会員登録
記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。


 テーマで探す
テーマで探す サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 学び・実務
学び・実務





 イベント
イベント