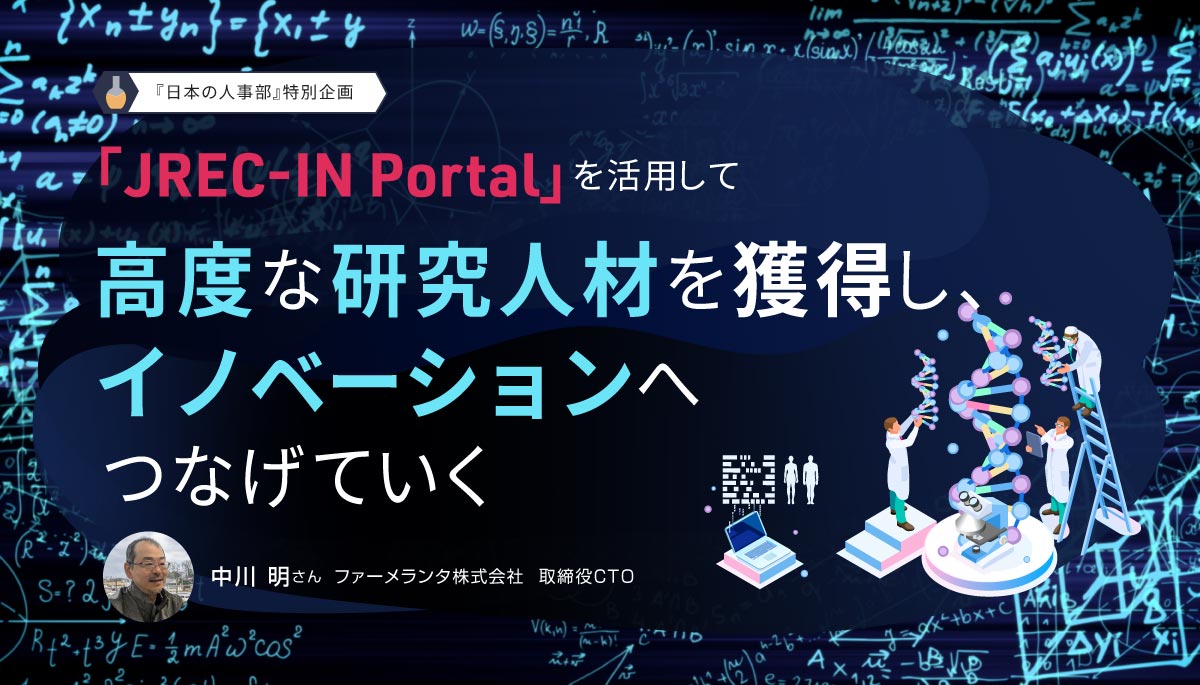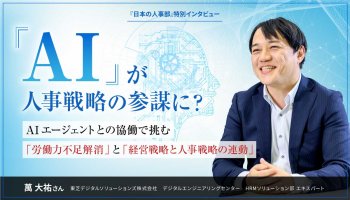複雑で変化が早く、多様化する現代においては多くの企業にとってイノベーションが欠かせないものとなっています。そこで注目されるのが博士などの「研究人材」の登用です。自社の取り組みや方針とマッチした高度な人材を採用することにより、事業拡大やイノベーションにつながることが期待できるからです。研究人材の採用は、大学の研究室とのつながりや民間のエージェントによる紹介などがありますが、いま注目を集めているのが「JREC-IN Portal」(以下JREC)。無償の公的サービスで、近年は民間企業の採用活動でも利用が活発化しています。JRECを活用して優秀な人材を獲得しているファーメランタ株式会社の中川明さんにお話しを伺うとともに、JRECの特徴を紹介します。

- 中川 明さん
- ファーメランタ株式会社 取締役CTO
協和発酵キリン株式会社博士研究員、石川県立大学博士研究員、同講師、同准教授を経て、2020年、産業構造を変革するようなスーパー大腸菌を開発することを志向し、植物有効成分を大腸菌で生産、販売するファーメランタ株式会社を起業
先進的な技術を実用化レベルで確立するため、専門分野を超え「優秀な研究者」を求めている
まずファーメランタの中川さんに、研究人材採用の事例についてうかがいました。
ファーメランタの事業概要と経営戦略について教えてください。
ファーメランタは石川県にあるバイオテックのスタートアップで、簡単にいうと「植物の有効成分を大腸菌で大量に作って販売する」会社です。現在の医薬品の多くは化学合成ができない、またはコストが高い、植物由来の成分が使われています。非常に広い土地を使い、手間暇かけて大量の植物を育て、ほんの少しだけ得られる有効成分を用いる方法です。それに代わる有効成分を大腸菌で作るというのが、当社の技術の根幹です。創薬ベンチャーとは違って技術が未熟であり、実用化レベルまで確立することが経営戦略として一番重要です。また、顧客にリーチするのが難しい分野なので、お客さまが求める品質、量、価格を探るのも課題となっています。
貴社における研究人材の状況や仕事内容、期待している能力についてお聞かせください。
現在、正社員の研究員が採用予定も含めて13名います。学士が1名、修士が2名、博士が10名という割合です。他にアルバイトが16名ほどいます。会社として事業拡大の時期にあり、今後は研究員を50人程度まで増やしていく予定です。
研究員の仕事の約90%は菌株開発で、残りの10%くらいはできた化合物を精製したり、分析したりという作業をしています。必要となる能力は、世界的にオープンになっている既存の方法を調べて、自分の実験に組み込めること。その上で、当社の独自技術を組み込むことです。それでも対応できないときは、自身が育んできた研究能力を発揮し、新しい系や細胞を作るという三段構えです。応用微生物学という分野ですが、この分野を研究してきたかどうかよりも、研究能力が高い人材を採用することを人材戦略としています。
研究人材の採用は、イノベーションや経営にどのくらい寄与しているのでしょうか。
植物の二次代謝産物を大腸菌で作るという論文はたくさんありますが、実用化した例は一つもありません。つまり、当社では大変なブレークスルーを目指しているのです。そのためには、純粋にイノベーションを起こすしかありません。「具体的にどうすればイノベーションを起こせるのか」は正直、誰にも分からないことです。一つひとつ研究するしかなく、そのために優秀な人材、研究能力が高い人材を採用することが当社の根幹と言えます。
募集要項に力を入れることで、価値観の近い応募者が集まった
どのようにして研究人材を採用しているのでしょうか。
研究員が審査し、皆で話し合って決めてきました。今年からは人事部門の人材を採用して、カジュアル面談などを行ってもらう予定です。
採用ツールのメインはJRECです。半分以上の人を、JRECを経由して採用しています。そのほかには、エージェントも利用しています。
採用プロセスで最も重視しているのは、レポートの提出です。当社の技術に関連した論文を読んでもらった上で、「あなたが実用化を目指すとしたら、どうしますか」といったテーマで書いてもらいます。レポートを読めば、その人が培ってきた研究能力がかなりの程度分かります。優秀なレポートを提出した人は面接に進んでもらい、最後はCEOが人物を評価して、合否を決めるという流れです。
採用後の研修など、教育体制についてお聞かせください。
即戦力の人材を採用しており、「これを調べてください」と言えば、自分でどんどん進めてくれるようなレベルの人ばかりなので、あらためて教育する必要はありません。
意識しているのは、研究のための環境です。年齢層が幅広く、上は58歳から下は24歳までいるので、若手でも発言しやすい雰囲気をつくるようにしています。たとえば、会議ではなくラボレベルでディスカッションをすることは、意識的に行っています。
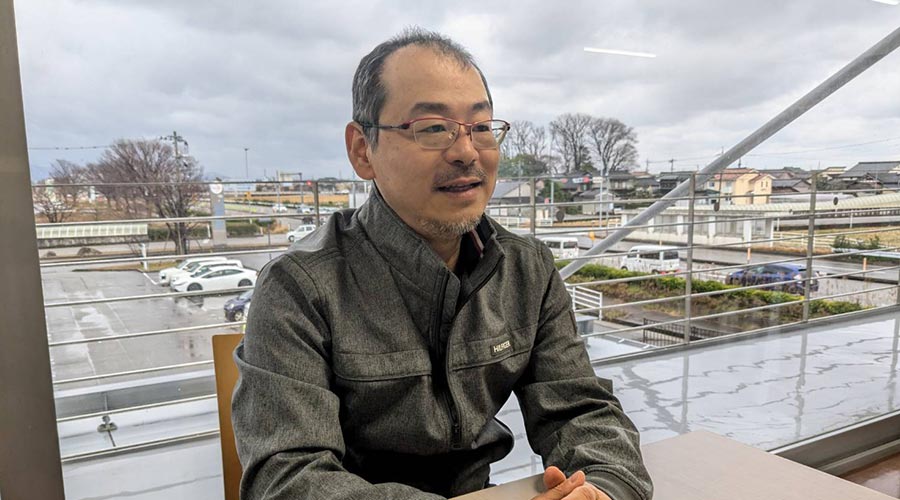
採用において、どのようにJRECを活用していますか。
JRECに掲載する募集要項を適宜更新し、応募を待つという使い方をしています。「応用微生物学」と書くだけでは、他分野の人がページを見てくれないので、分子生物学や神経科学など、考えられる生物系の分野を全てキーワードとして入れ、どのワードでも引っかかるようにしています。
募集要項には、「本気で研究をやりたい人、来てください」という趣旨を書いているのですが、結構インパクトがあるようです。応募してくれた人の多くが「募集要項の言葉が刺さりました」と言ってくれます。JREC経由で応募してくる人は、誰かに言われて受けるのではなく、自分で調べて応募しているので、やる気が高いと感じています。
エージェントの場合、研究分野が近い人が紹介される傾向にありますが、当社では分野を問わず、純粋に研究能力が高い人材を採用することにしているので、そういう点でもJRECの方がマッチしやすいように感じます。
より多くの研究者が「自分にあった職場」に出会うための手段に、JRECを
今後、JRECに期待することをお聞かせください。
今まで通り、研究人材の支えになってほしいですね。無料であること、そして公的に行われていることは意義が大きいと思います。民間では偏りが出ることもあるため、国益のためにもJRECの存在は重要です。
「論文のための研究」ではなく、「しっかりと研究できる場所」を求める人が、力を発揮できる場所を見つけられる。あるいは、ワークライフバランスを大切にする研究者にとってもマッチする場所があるなど、自分に合うところを見つけられるようになるといいですね。
研究人材の中では、JRECの存在自体は浸透していますが、「とりあえず見てみよう」という人がまだ多いと感じています。JRECが日本の科学技術を支えていることをもっと知ってもらい、インフラ的に浸透してほしいと思います。
企業の採用担当者に向けて、JRECを活用する際のアドバイスなどがあればお聞かせください。
どのレベルの人、どういった人にリーチするのかをはっきりさせることが重要だと思います。当社は「優秀であればいい」ということに特化して選考していますが、それが具体的に見えていたことが、成功のカギになっていると思います。
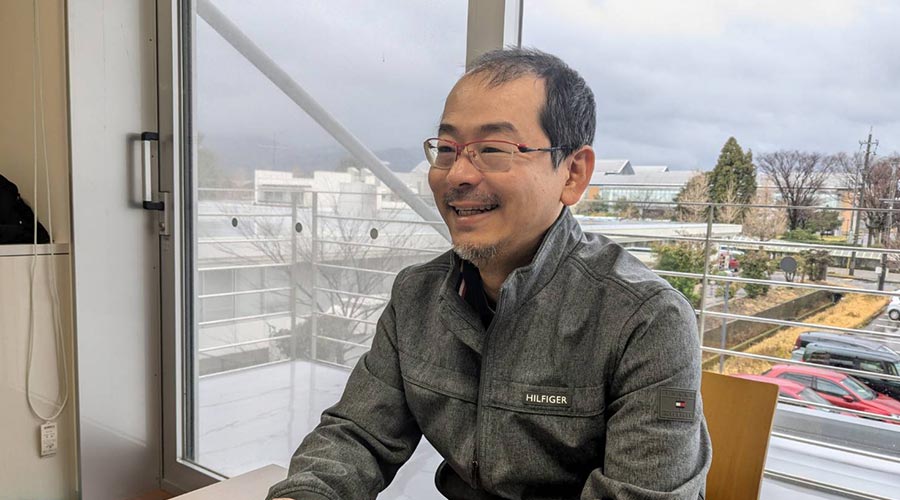
JRECは公的な無料のポータルサイト。近年、民間企業の登録数も増えている
続いて、JRECの特徴を紹介します。
JRECの概要
JRECは文部科学省所管の国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)が運営する、研究人材のキャリア活性化のためのポータルサイトです。初期の頃はアカデミアでのキャリア公募が中心でしたが、産業界のイノベーションのため、研究人材に活躍の場を広げてもらうことが重要であるという政府の方針から、近年は民間企業による研究人材への求人公募を増やすべく、積極的に活動しています。
現在は、研究職・専門職を希望する博士をはじめとした研究人材と、民間企業やアカデミア、研究機関などの求人公募を橋渡しするサイトとして運営しています。2023年にはUIの改善やスマホ・タブレット表示への対応、セキュリティの強化などを行い、より多くの方に使っていただきやすいようにリニューアルしました。
民間企業にとって便利な機能とJRECを活用するメリット
JRECには、専門の審査チームがあり、求人の掲載を非常にスピーディーに行うことができます。掲載した後で、WEB上で応募を受け付け、応募者とやりとりを進める機能もあります。
また、匿名にはなりますが求職者のキャリアやプロフィールの検索・閲覧、スカウトメールの送信ができます。そこからコンタクトをとって、ダイレクトリクルーティングにつなげることも可能です。求人をする機関は、希望する条件を登録することで、その条件に合致した新しい求職者の登録があった際はメールで通知を受け取ることもできます。
研究人材の登録者数は約14万人で、毎年1万5000人を超える新規人材にご登録いただいています。これは、研究人材としては国内最大級の規模です。サイトの年間アクセス数は、約5800万PVとなっています。
公的機関が運営していることによる高い信頼性と、中立性が強みです。また、求人の公募掲載から求職者の検索、スカウトメールの発出など、すべての機能を無料で使用することができ、内定や採用に至った場合も費用は発生しません。利用者満足度調査では、95%の方から「役に立っている」という評価をいただいています。
文系理系問わず、博士の高い能力はマネジメントで活きる。哲学の専門知識を企業の「ミッション」づくりに活かすケースも
登録している研究人材について
登録者の約6割は理系、約4割は文系で、理系の人材はアカデミア、文系の人材は民間のポジションを志向する傾向があります。求人公募のメール配信希望者の7割強が「民間企業にも興味あり」と回答しています。
これまで民間企業の博士人材の活用といえば、主に理系の研究所での限定された活動が多かったのですが、文系・理系を問わず、「研究して内容をまとめ、一つの成果を出す」という汎用性の高い能力を見込んで、企業のいろいろな分野で活動してもらう動きが出てきています。
文系の専門領域でも、行動経済学など、マーケティングで役立つ研究分野がありますし、企業が「ミッション」を定め、社会にコミュニケートする場面で哲学系の人材の力が求められる例もあります。
民間企業の利用状況
民間企業による求人公募は、研究分野として複数分野を設定可能ですが、ライフサイエンス系が多く約6割、次いで情報通信系が2割超となっています。
求める人材を戦略的に探し出し、ダイレクトリクルーティングにつなげている会社も
JRECを効果的に活用している企業の例
ある学術研究用ソフトウェアの開発を手掛けるベンチャー企業では、求職者情報の検索・閲覧とスカウトメールの送信を使って、多くのダイレクトリクルーティングに成功しました。情報システム系の会社ですが、情報の専門家だけで情報システムを作るわけではないので、物理の流体解析や経済・金融 のゲーム理論などといった他分野の専門家を情報システムのプロとして雇うため、JRECをかなり戦略的に使われています。ダイレクトリクルーティングでは求職者のプロフィールを見て直接アプローチできるので、その人の良いところを活かすことができるそうです。
また、官公庁、企業庁が技術系の専門職員のスカウトにJRECを使っている例もあります。傾向としては、人文・社会、ライフサイエンス分野の求職者へのスカウトメールが多いです。
企業によって目指すところや求める人材はさまざまなので、我々から「このように使うと良い」とは言いにくいのですが、先ほど中川さんのお話をうかがい、各企業の考えを、求職者がすぐに分かるように整理して表現することが、一番のコミュニケーションではないかと思いました。
研究人材の採用やJRECの活用を検討している人事部門の方々に向けて
企業をとりまく経営環境はどんどん複雑になり、変化のスピードも驚くほど速くなっています。そのような状況下、多くの民間企業にとってイノベーションを起こしていくことがますます重要になっており、そのための研究人材の確保と活用は、最も重要な経営課題の一つと言えます。
政府でも民間企業による研究人材の活用促進を方針としていますので、公的機関であるJSTが運営するJRECは、その一環として民間企業における研究人材の活躍に貢献したいと考えています。具体的な目標として、民間企業による求人公募掲載の拡大を掲げています。人事部門の皆さま、より利用しやすいサイトを目指し運営していきますので、ぜひJRECをご活用ください。
国の科学技術・イノベーション政策推進の中核的な役割を担う国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)が運営する研究人材のためのキャリア支援ポータルサイト「JREC-IN Portal(ジェイレックインポータル)」は、研究に関する職を希望する求職者の情報と、産学官の研究・教育に関する求人公募情報を掲載しています。求職者、求人機関双方がそれぞれのニーズに応じた内容を検索・閲覧することが可能であり、両者のマッチングを支援しています。自然科学や人文・社会学などの分野における研究人材の求職者と、大学・公的機関のみならず広く民間企業との架け橋として機能し、研究人材のキャリア形成に貢献していきます。

HRのトレンドと共に、HRソリューション企業が展開するさまざまサービスをご紹介。自社に最適なソリューションを見つけてください。
会員登録をすると、
最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!


 テーマで探す
テーマで探す サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 学び・実務
学び・実務





 イベント
イベント