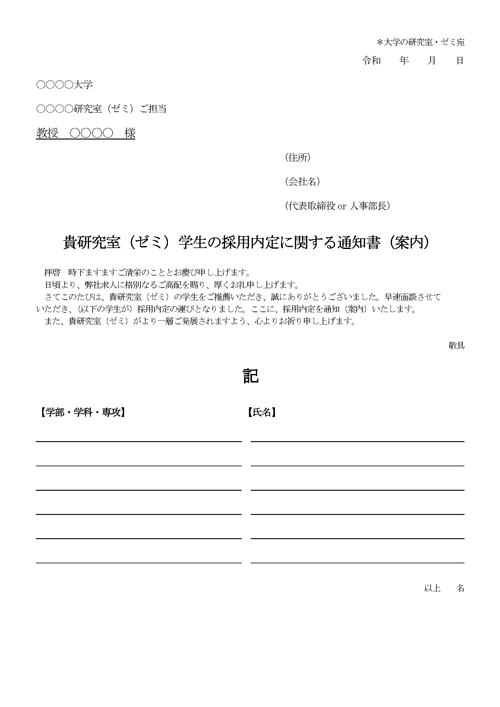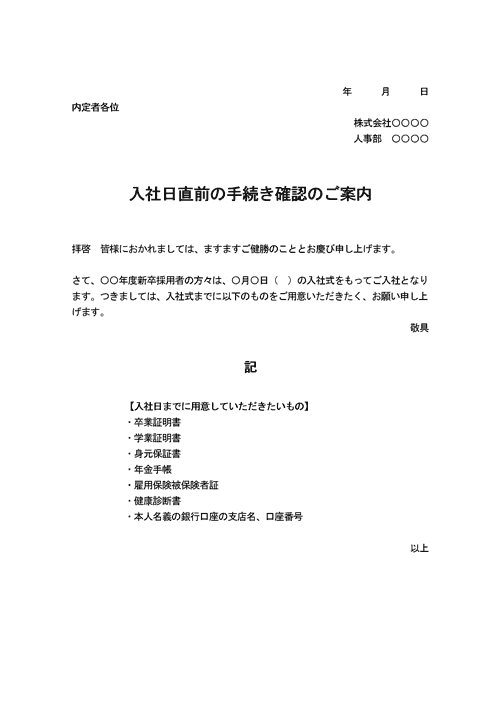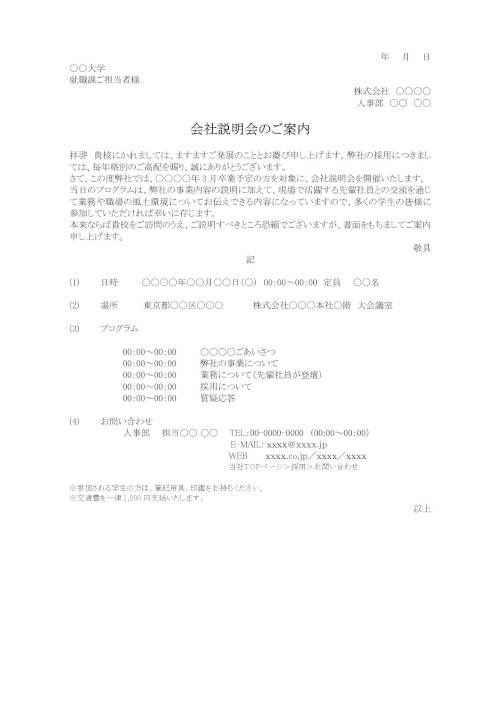プロパー社員
プロパー社員とは?
プロパー社員とは、「正しい、本来の」などの意味をもつ英語“proper”から転じた和製英語まじりの言いまわしで、いわゆる「生え抜き」の社員や正社員のことを指す、日本の企業社会特有の表現です。「プロパー」と略して使われることが多く、その意味するところは文脈や職場によって異なります。
1. プロパー社員とは

「プロパー社員」の意味と使われるケース
「プロパー社員」は、主に3種類の意味で用いられます。第1は、中途入社や出向社員ではない、新卒で採用された「生え抜きの社員」という意味です。第2は、契約社員や派遣社員、パート社員などの非正規雇用に対する「正社員」という意味。そして第3は、協力会社や下請け会社の社員などが常駐している職場において、そうした外部スタッフと区別するために自社の社員を「プロパー」と呼ぶケースです。
「プロパー社員」という言葉が使われる例をいくつか見てみましょう。
・「今は派遣社員として働いているけれど、いずれはプロパー社員になりたいと思っている」……「正社員」の意味で使用されるケース
・「この職場はプロパー社員が少なくて、常駐の外部スタッフがたくさんいる」……「自社の社員」の意味で使用されるケース
プロパー社員という言葉は主に職場内、あるいは業界内部の用語として使用されることが多いため、多くの人が社会人になって初めて耳にすることになります。コピーライター/エッセイストの糸井重里氏が主宰するウェブサイト『ほぼ日刊イトイ新聞』の連載『オトナ語の謎。』においても、ビジネストークに頻出する意味不明の独特な言葉「オトナ語」の例として紹介されています。
また、このオトナ語に関してライフネット生命がビジネスパーソンを対象に行った調査によれば、職場で使用する「カタカナ語・外来語が由来のオトナ語」で、「プロパー(社員)」は第2位でした。
参照:オトナの基本用語:その4~オトナ語の謎。|ほぼ日刊イトイ新聞
「正社員」など紛らわしい言葉との関係
「プロパー社員」に法的な定義などはありません。従って、職場や業界によって「正社員」や「生え抜きの社員」「自社の社員」など、複数の意味で用いられます。ただし、「プロパー社員」が使われる際のニュアンスは、それが指し示す「生え抜きの社員」「正社員」あるいは「自社の社員」の言葉のニュアンスとは異なる場合があります。
「プロパー社員」のニュアンスが、必ずしも良いとはいえないことを示すアンケート結果があり、総合人材サービスのマンパワーグループ株式会社によって実施された調査によると、「入社後、プロパー社員に対してどのようなギャップを感じますか?」と質問しました。それに対する回答は、「何かと融通がきかない」(21.8%)、「保守的でチャレンジをしたがらない」(14.3%)、「伝統・文化の変化を嫌う」(11.8%)など、ネガティブなものが上位を占めました。
引用:転職後、「プロパー社員」に対して感じたギャップとは?マンパワーグループ、転職経験者に対する「転職後の実態」調査結果発表|マンパワーグループ株式会社
プロパー社員という言葉の発祥
「プロパー社員」という言葉が生まれた経緯について、三省堂編修所は、「プロパー」が使われるようになった経緯を「各業界や職場で、それぞれ独自に用いるようになった表現のようです」と記しています。
戦時中には排除された外来語は、戦後になって多く用いられるようになります。漢字による多くの在来表現が、外来語に置き換えられていきましたが、「プロパー(社員)」も、そのような外来語への置き換えの一環として生まれたのではないでしょうか。
2. 「プロパー社員」を使用する上での注意点
定義を定めるか、社内制度の用語として使わないようにする

「プロパー社員」は職場や業界によって、また文脈などによって、さまざまな意味で使われます。そのため曖昧になりやすく、場合によっては誤解が生じる危険があります。人事制度の中に記載する場合には、「正社員」「生え抜きの社員」「自社の社員」などと明確に定義する必要があります。
ただし上で見た通り、「プロパー社員」はあまりニュアンスの良くない言葉として使われることもあります。社員が日常会話において使うには大きな問題はありませんが、社内制度の用語として使用する場合には、注意が必要です。
- 参考になった0
- 共感できる0
- 実践したい0
- 考えさせられる0
- 理解しやすい0

用語の基本的な意味、具体的な業務に関する解説や事例などが豊富に掲載されています。掲載用語数は1,400以上、毎月新しい用語を掲載。基礎知識の習得に、課題解決のヒントに、すべてのビジネスパーソンをサポートする人事辞典です。
会員登録をすると、
最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!
無料会員登録
記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。


 テーマで探す
テーマで探す サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 学び・実務
学び・実務




 イベント
イベント