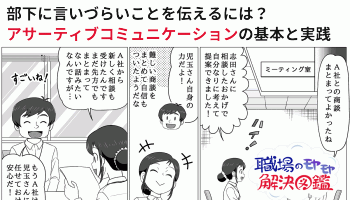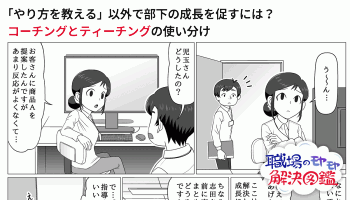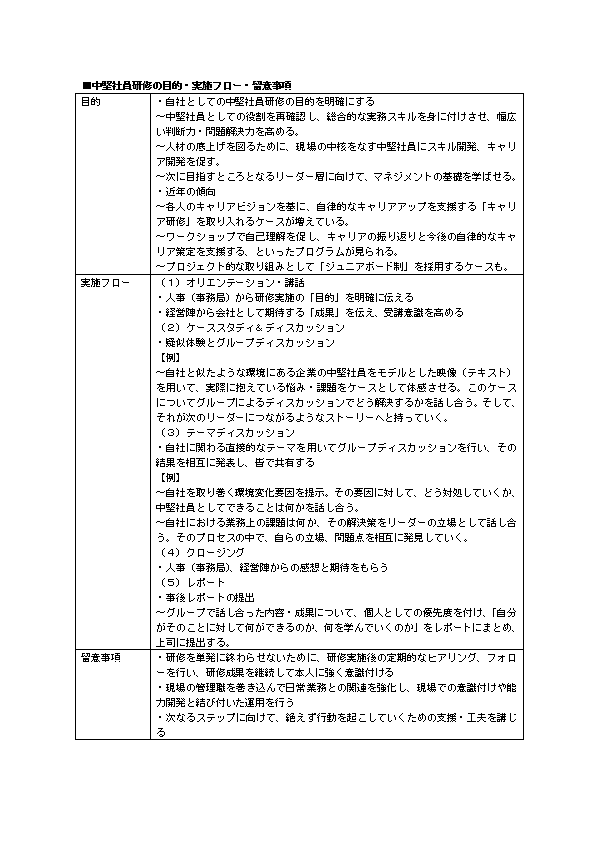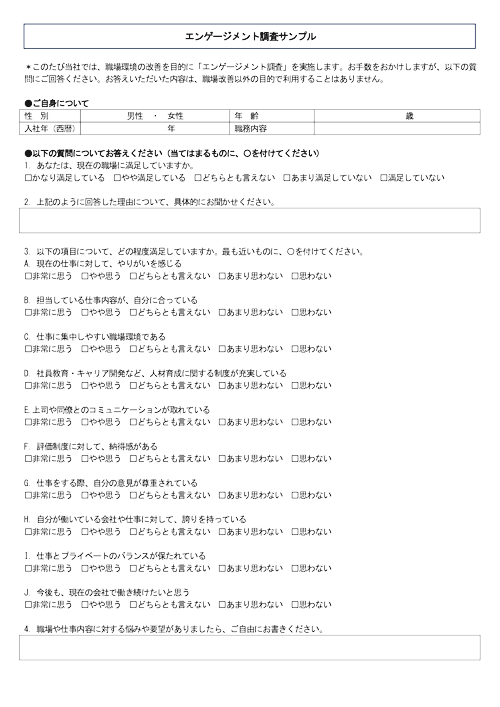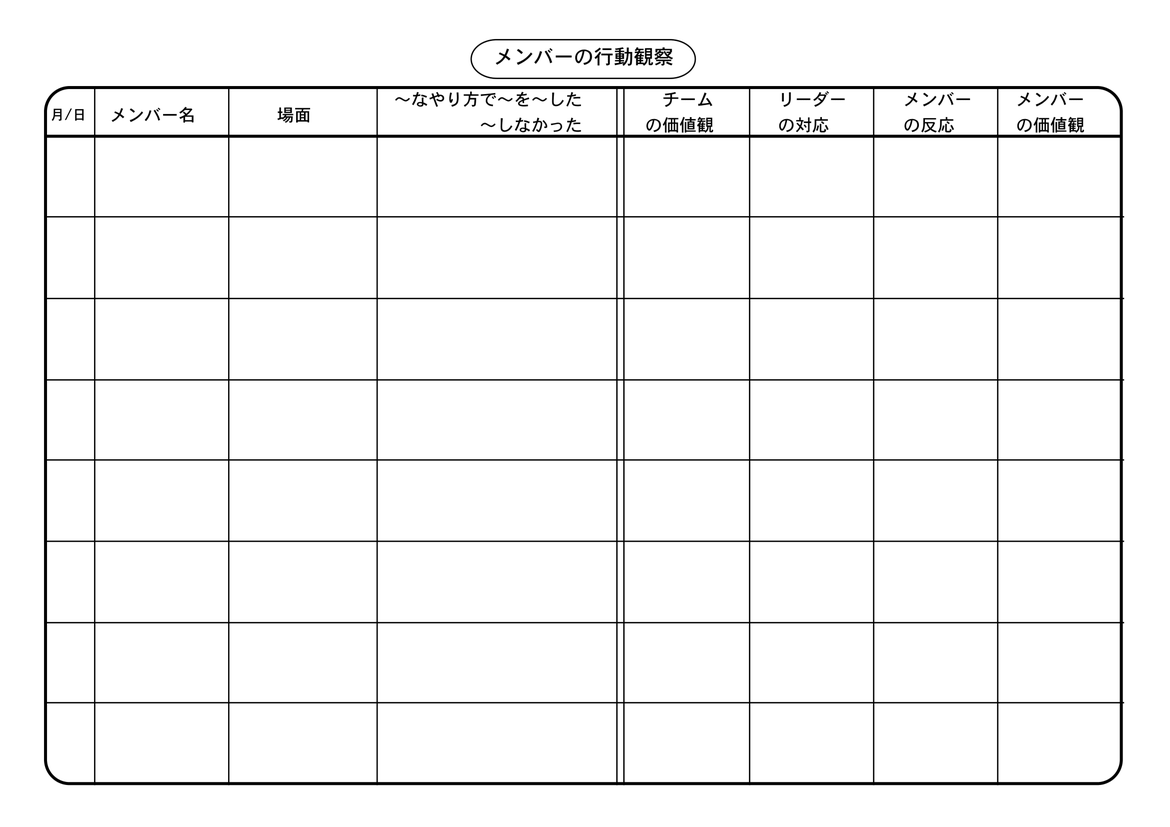限界認知
限界認知とは?
「限界認知」とは、それまでの仕事のやり方に限界を感じること。「過去と同じように仕事を続けていても、成果や影響力の発揮にはつながらない」と認知し、切迫感を持つことで、アンラーニングが促進されます。限界認知経験につながりやすい具体的な業務には、「業務上の修羅場」「越境的業務」「新規企画・新規提案業務」などがあります。アンラーニングやリスキリングが注目される今、人材マネジメントと組み合わせるなどして、戦略的に活用することが求められます。
それなりに評価されている人こそ注意!
今、アンラーニングが必要な理由
昨今、アンラーニング(Unlearning)が注目されています。アンラーニングとは、既存の知識、習慣、行動パターンなどを意識的に見直し、変容させるプロセスのこと。学びの重要性が高まっているにもかかわらず、なぜこれまで学んだことを手放したほうが良いのでしょうか。
それは、新しい学びを吸収しやすくするため。変化の激しい現代において、過去に得た知識や成功体験がもはや戦力にならないこともあります。例えば、ワープロが得意な人がいつまでもそのスキルにしがみついていれば、自動文字起こしサービスの台頭による社会の変化に太刀打ちできません。路頭に迷うことを避け、新たなスキルを得ようとするなら、その手前にワープロのスキルを手放す決意が必要なのです。
個人のキャリアだけでなく、イノベーション創出にもアンラーニングは重要です。固定観念や過去の学びの枠組みから外れることで、新しい情報に対するアンテナの感度が上がり、斬新なアイデアが生まれることもあります。
では、アンラーニングを進めるにはどうすればよいのでしょうか。パーソル総合研究所の「リスキリングとアンラーニングについての定量調査」によると、「今のままでは成果を出せない」など、高いハードルを感じる経験が、アンラーニングやリスキリングのきっかけになるとのこと。「限界認知経験」がアンラーニングを促進するのです。具体的には、顧客とのトラブルなどの「業務上の修羅場」、副業・兼業や他社との交流などの「越境的業務」、新規事業立ち上げなどの「新規企画・新規提案業務」などが限界認知につながるとしています。
一方で、限界認知を阻害する要素もあります。それは、人事評価が“それなりに”良いこと。5段階中「4」という、やや良い評価を得ている人が最もアンラーニングする傾向が低いことが分かりました。トップレベルではなくても、現状のままで問題がない程度の成績は、限界認知をする必要性を薄め、アンラーニングを抑制してしまうようです。また、業務に変化を加えることによる「コスト意識」も、新たな学びの障害になることが分かりました。
アンラーニングは、個人や組織が新たなアイデアや価値観を体得するために重要なステップの一つ。良い評価を得ている人材にこそ「限界認知経験」をつませ、戦略的に学びを促進させることが大切です。
- 参考になった0
- 共感できる0
- 実践したい0
- 考えさせられる0
- 理解しやすい0

用語の基本的な意味、具体的な業務に関する解説や事例などが豊富に掲載されています。掲載用語数は1,500以上、毎月新しい用語を掲載。基礎知識の習得に、課題解決のヒントに、すべてのビジネスパーソンをサポートする人事辞典です。
会員登録をすると、
最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!
無料会員登録
記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。


 テーマで探す
テーマで探す サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 学び・実務
学び・実務





 イベント
イベント