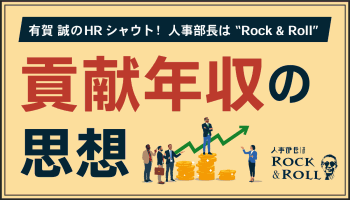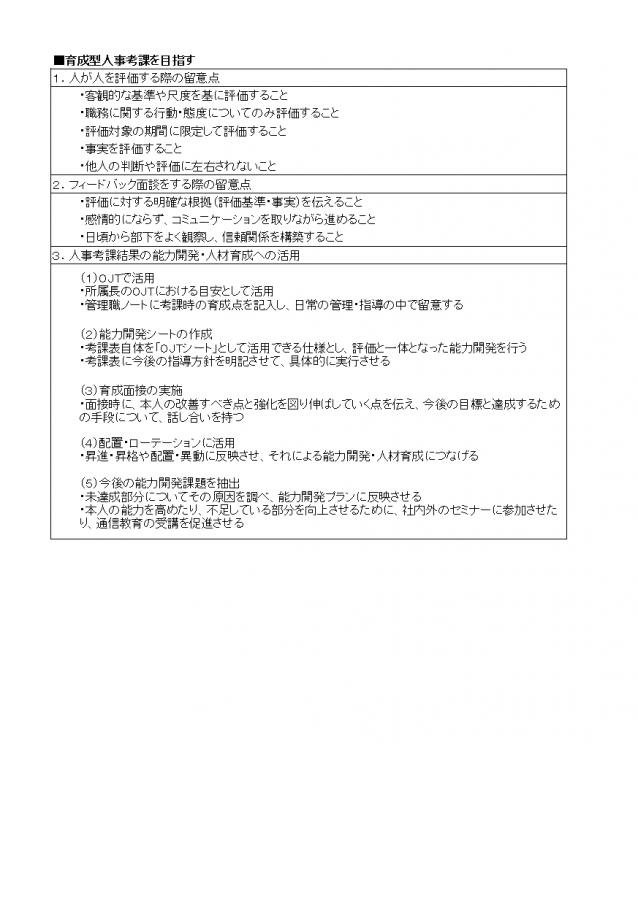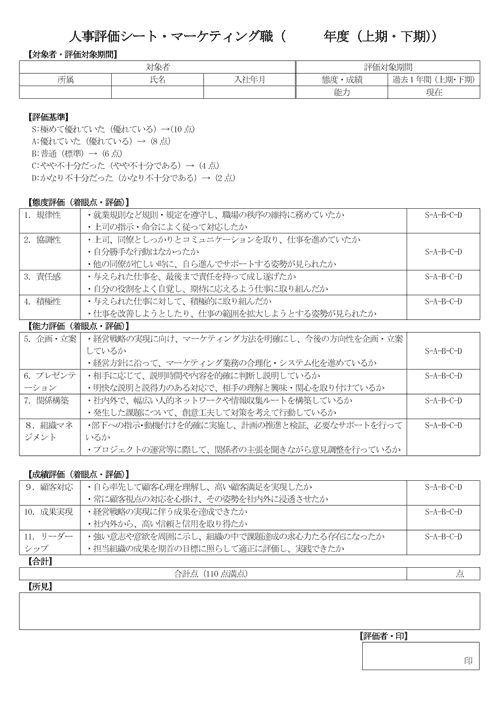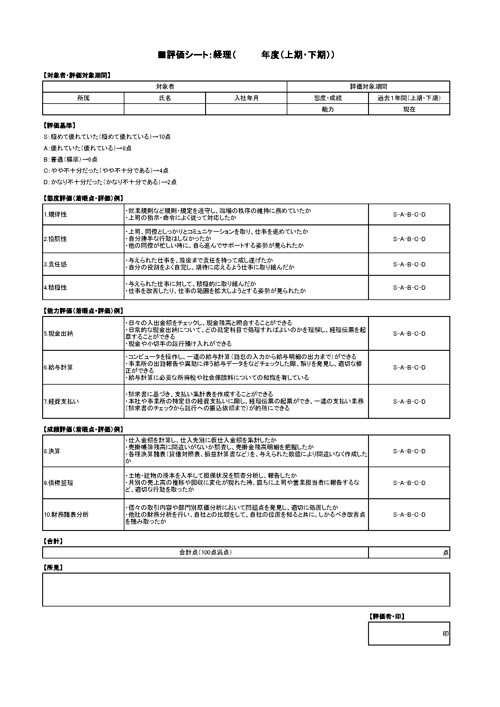MBO
MBOとは?
「目標管理制度」とも言われます。従業員自らが設定した目標を適切に管理し、マネジメントする手法です。英語表記は『Management By Objectives and Self Control』であり、目標と自己統制によるマネジメントを意味します。オーストリア出身の経営学者であるP.F.ドラッカーが、自身の著書である『現代の経営』のなかで提唱した概念です。
1.MBOとは
従業員自ら設定した目標を管理するマネジメント手法
MBOとは、従業員自らが設定した目標を適切に管理し、マネジメントする手法です。英語表記は『Management By Objectives and Self Control』であり、目標と自己統制によるマネジメントを意味します。オーストリア出身の経営学者であるP.F.ドラッカーが、自身の著書である『現代の経営』のなかで提唱した概念です。
MBOの特徴は、従業員自らが「自分は何を達成すべきか」と考えたうえで、目標を設定することです。会社や上司の一方的な指示とは異なるため、やらされ感が少なくなります。また自身の目標を達成すると、組織の目標達成にも寄与するため、モチベーションを高くもって業務に取り組めるメリットがあります。
現代においてMBOの考え方は、発祥地のアメリカはもとより、日本を含む世界各国の企業に広く浸透しています。またMBOとほかのマネジメント手法を組み合わせるケースも見受けられます。
日本で導入が急速に広まった時期と背景
近年はMBOの導入率が高くなっています。労務行政研究所が行っている「人事労務諸制度実施状況調査」によれば、2022年は78.4%の企業が導入しており、『日本の人事部 人事白書2018』では、77.3%の企業が導入しているという結果が出ています。
導入率の推移をみると、1987年は28.6%、1989年は36.3%、1991年は34.1%、1993年は46.5%、1995年は54.3%、1997年は54.7%、2001年は64.2%となっており、1990年代から急増していることがわかります。
産業能率大学が2000年に行ったMBOに関する調査をみると、MBOを導入している企業のうち、1991年以降に導入した企業は61.4%となっています。これら二つの調査から、MBOの導入が急速に広まったのは1990年代以降であるといえます。
この時期に導入が加速したのはなぜでしょうか。産業能率大学による同調査で導入目的を聞いたところ、「成果主義・業績主義の徹底」と回答した企業が最も多く、61.9%となっています。1990年代は日本で成果主義が広まりはじめた時期であり、MBOの導入と成果主義の徹底は、深く結びついているといえるでしょう。
- 【参照】
- 人事労務諸制度実施状況調査|労務行政研究所(1987年~2001、2022年)
- 『目標による管理』の現状と今後の課題--実態調査報告書|産業能率大学目標によるマネジメント研究会(旬刊労働実務掲載 1321号掲載)
2.MBOとOKRの違い
MBOは、しばしばOKRと比較されます。両者には誰の目標達成を目指すか、人事評価に反映されるのか、どの程度の達成を求めるのかなど、多数の相違点があります。
【MBOとOKRの違い】| MBO | OKR | |
| 概要 | 個人目標を自ら設定し、個人目標の達成を目指す | 組織目標の達成に貢献するような個人目標をたてる |
| 人事評価制度への反映 | あり | 評価と連動させづらい |
| 目標に取り組む期間 | 半年~1年 | 1週間~1ヵ月 |
| メリット |
|
|
| デメリット |
|
|
| 目標の共有範囲 | 本人と上司 | 組織全体 |
| 目指す達成度合い | 100% | 60~70% |
- 【関連記事】
- OKRとは|『日本の人事部』
3.MBOのメリット
人材育成
MBOが人事評価と連動していれば、従業員の目標達成に向けた行動を促しやすくなります。上司が部下の目標達成をサポートし、スキルの習得などについてアドバイスすれば、さらに効果的でしょう。自主的な取り組みと第三者からの的確なアドバイスによって、効率的な人材育成を実現できます。
主体性向上、モチベーションアップ
MBOの目標設定やプロセス管理は、従業員が主体となって決めます。「自ら目標を設定し、進行している」という意識があるため、やらされ感が少なくなることが特徴です。上司の指揮命令系統ではなく、自分で決めて進めるという意識を持つことで、主体性の向上やモチベーションアップが期待できます。
自己管理能力の習得
MBOでは、目標と目標達成に向けたプロセスを定めたうえで、自分自身で進捗管理をしながら業務を進めます。上司からのサポートは常にあるわけではなく、基本的に自分で行動します。責任をもって業務に取り組むことから、自己管理能力の習得につながるといえます。
4.MBO導入時の注意点
難度の低い目標が設定されてしまう
MBOの目標設定は従業員が率先して行なうため、目標レベルに差が生じがちです。高い目標を掲げる人もいれば、確実に達成できる内容を選ぶ人もいるでしょう。MBOは目標の達成度で評価するため、低い目標を設定した方が評価は高くなる傾向にあります。そのため、高い目標を掲げた挑戦者が低評価で、低い目標を掲げて努力しなかった人が高評価といった不公平な事態になりかねません。
不公平な状況は、従業員のモチベーションを下げるとともに、組織への不信感につながります。このような状況を防ぐためには、定められた目標に応じて、同じ達成度でも評価を変えることや、達成度が50%くらいと予想される目標を設定するなどの対策が必要です。
目標達成以外の行動が軽視される
目標達成にとらわれすぎて、目標とは直接関係ない内容を軽視する従業員が出てくる可能性があります。個人の目標達成のために、他の従業員を助けないのであれば、人間関係の悪化につながり、組織全体のモチベーションの低下につながってしまいます。
市場変化に即座に対応できない
MBOの目標設定期間は、半年から1年が一般的です。その間に市場が変化すれば、設定した目標やプロセスが最新の市場状況に合わなくなり、目標を達成してもあまり意味がない、ということになるかもしれません。競合他社との市場競争に出遅れる可能性もあります。
5.MBO導入の5ステップ
MBOを効果的に運用するには、前述で紹介した「MBO導入時の注意点」を踏まえ、成功するためのアプローチが必要です。
(1)個人が目標を設定する
上司は部下に「組織目標も考慮すると、どのように動くのがベストか?」や「自身の成長につながる目標とは?」といった問いかけを通し、従業員と一緒に適切な目標を定めます。今の部下の実力よりも、少し上の目標を定めるのがよいでしょう。ほかの従業員とレベルに差が生じないように、簡単すぎる目標や難しすぎる目標は避けます。
目標の内容は、達成することが目標にならないように、従業員のキャリアアップにつながり、「進んで行動したい」と思えるものを選びます。自発的な行動につながる目標は、ノルマ主義の考えを抑制し、周囲と協力する姿勢につながります。
(2)上司とのすり合わせを行ない、達成までの行動を具体化する
部下自身が達成までの行動を具体化することで、ゴールの方向性が明確になります。また上司とすり合わせを行なうと、組織目標とのズレを最小限にすることができ、上司から第三者目線でアドバイスすることも可能です。部下に課題が生じている場合は、本人との話し合いを通じながら適宜サポートします。同時に上司は適切なマネジメントができるよう、日頃からマネジメントスキルを鍛える必要があります。
(3)PDCAのサイクルを回す
MBOの運用では短期間で達成できるような目標はあまり設定されないため、中長期的な姿勢が欠かせません。PDCAサイクルを継続し各プロセスを管理することで、目標達成に近づきます。継続的な改善の推進は、組織マネジメントの基本といえます。
【MBOにおけるPDCAサイクル】| Plan(計画) | 目標達成から逆算し、部下と上司で達成に向けたプロセスを計画 |
| Do(実行) | 上司のアドバイスを受けながら、計画を実行 |
| Check(点検・確認) | 目標とその達成率を測定し、達成できなかった場合は課題を抽出 |
| Action(行動) | Checkで出た改善案を基に、次のPDCAを実行 |
(4)定期的な面談を行ない、進捗状況を確認する
MBOを効果的に運用するには、定期的な面談を行ない、進捗状況を確認することが大切です。定期的に面談を行なっていれば、問題があったときに迅速に対応できるため、問題レベルが小さいうちに解決できます。容易に軌道修正ができることは、従業員と上司の双方にとってメリットといえます。
進捗状況の確認では、定期面談と並行して、従業員から日報や週報を提出してもらうのも一つの方法です。定期面談では拾いきれなかった問題の発見にもつながります。ただし、日報や週報の提出が負担になる可能性もあるため、状況を見ながら判断する必要があります。
(5)達成度を評価・フィードバックし、次の目標を設定する
達成度の評価・フィードバックは、部下が自己評価を行ない、上司が総合的に判断する流れがよいでしょう。自己評価・上司からのフィードバックを繰り返すことで、業務の評価で共通認識を持つことができるようになります。
目標が達成できなかった場合は、定量的な部分だけでなく、定性的なプロセスも評価します。目標達成の可否のみで評価すると、達成できなかった人が意欲を失う可能性があります。未達成の理由や課題を考え、新たな目標を設定します。
6.MBOの運用における注意点
目標は高すぎず、低すぎず
目標が高すぎる場合は、「頑張っても仕方ない」と最初から諦めてしまう可能性があります。一方で目標が低すぎると容易に達成できるため、意欲や創造性の向上につながりにくく、努力しなくてもよい状況に手を抜く人が出てくるかもしれません。そのため、適切な目標は、「もう少し頑張れば達成できる」内容だといえます。
上司と部下との信頼関係を構築するためのコミュニケーション
信頼関係がなければ、本音が交わされず、上司からのアドバイスも効果がありません。信頼関係の構築には、コミュニケーションが不可欠です。
コミュニケーションの中でも特に重要なのが、目標達成度を評価する場面です。ここで双方が納得しあえば、信頼関係につながり、モチベーションアップも期待できます。評価結果が導き出された背景を説明し、ほめるべき部分をほめ、悪い点があれば次にどうやって改善するかを話し合います。引き続きの努力を促すために、労いの言葉をかけることも大切です。
評価者のマネジメントスキルの向上
マネジメントスキルの向上には、本人の努力はもとより、企業サイドが「マネジメントスキルを高める仕組み」を用意することも大切です。具体的な施策として「マネジメントに関する研修」や「マネジメント担当者専用の教育プログラム」が挙げられます。また「エンゲージメントサーベイ」「360度評価」「1on1」などの実施により、マネジメントに対する気づきを得られる可能性もあるでしょう。
- 参考になった0
- 共感できる0
- 実践したい0
- 考えさせられる0
- 理解しやすい0

用語の基本的な意味、具体的な業務に関する解説や事例などが豊富に掲載されています。掲載用語数は1,400以上、毎月新しい用語を掲載。基礎知識の習得に、課題解決のヒントに、すべてのビジネスパーソンをサポートする人事辞典です。
会員登録をすると、
最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!
無料会員登録
記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。


 サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 調査
調査 人事辞典
人事辞典 イベント
イベント