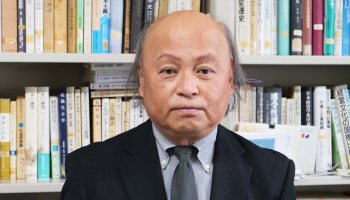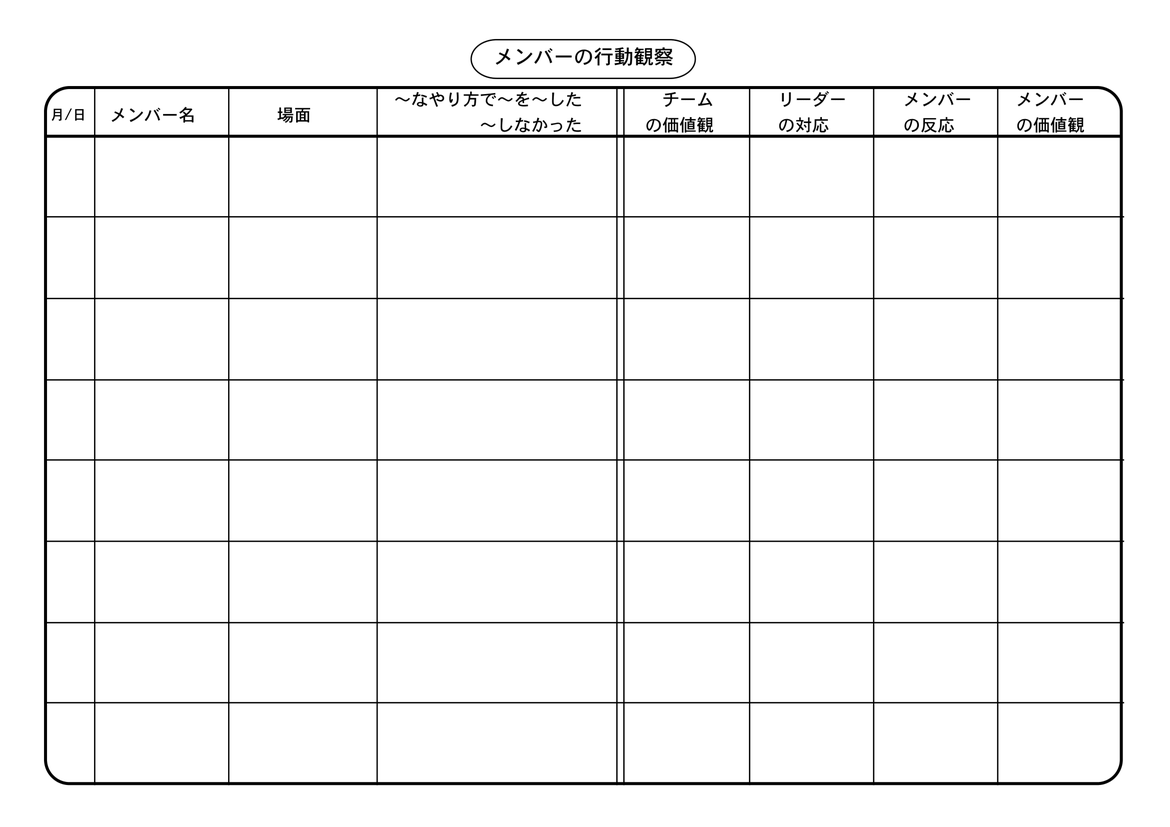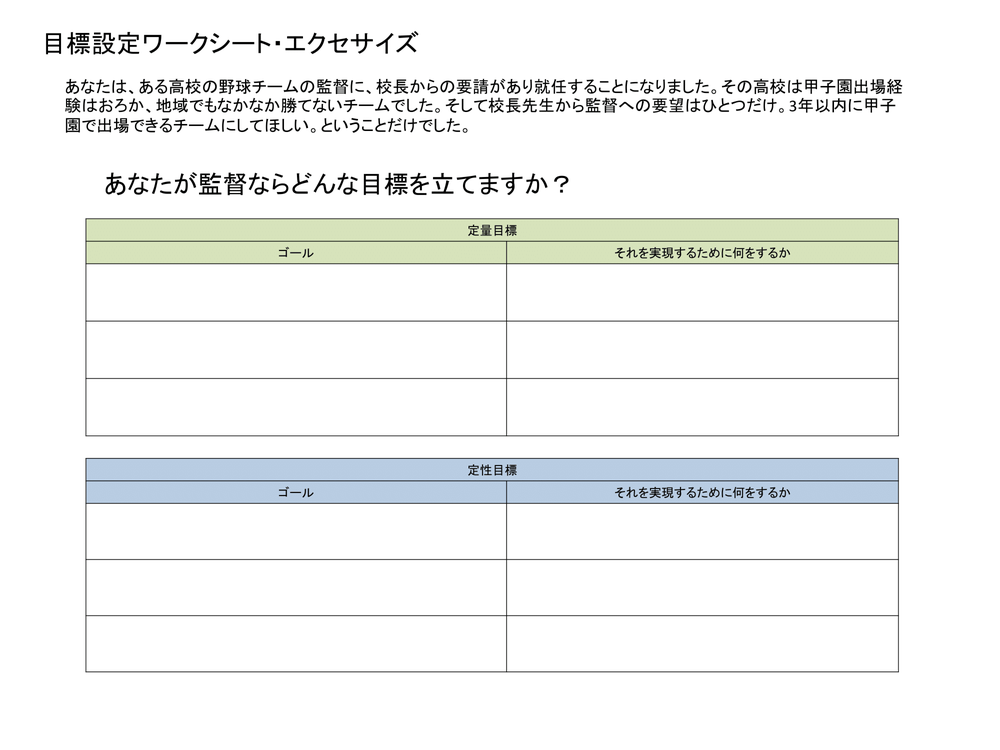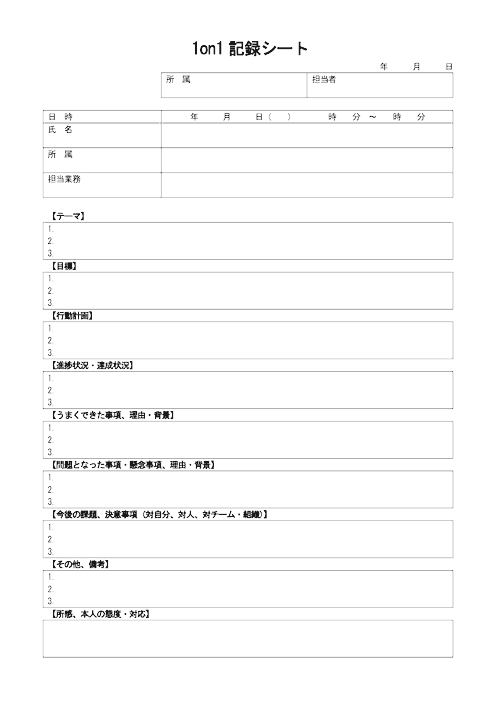チェンジマネジメント
チェンジマネジメントとは?
「チェンジマネジメント」とは、業務や組織にかかわるさまざまな変革を推進・加速し、成功に導くためのマネジメント手法のことです。組織には急激な変化を好まず、慣れ親しんだ環境ややり方に固執する社員も少なくないため、変革を進めようとすると必ず抵抗や軋轢が生じます。チェンジマネジメントでは、社員を変化にうまく適応させられるよう、経営トップが率先して変革のねらいや必要性を組織に浸透させ、社員の意識改革に努める必要があります。
最大の抵抗勢力は変化を怖れる人の心
日本特有の“チェンジモンスター”とは
経営環境のめまぐるしい変化に対応するためには、そのスピードを上回るほどの果断な意思決定をもって、改革を推進していく必要があります。しかし組織の誰もがその変化に速やかに適応できるわけではなく、多くの社員が変化を怖れ、慣れ親しんだ仕事の進め方や伝統的な慣習を捨てようとしません。改革に踏み切っても、社内の“抵抗勢力”に妨げられ、期待していたほどの効果が出ないといったことがよく起こります。
そこで重要になるのが、変革(チェンジ)をいかに適切に効率よくマネジメントするかという「チェンジマネジメント」の取り組みです。チェンジマネジメントは1990年代の米国で、BPR(Business Process Re-engineering:業務プロセス改革)を成功に導くためのツールとして開発、実践され、成果を上げてきました。一躍ブームとなったBPRですが、必ずしも導入に成功する企業ばかりではなく、多くは社内の抵抗を抑えきれずに頓挫しました。
BPRの考え方を提唱した元マサチューセッツ工科大学教授のマイケル・ハマー氏は「BPRの失敗の確率は50%~70%だが、その数字はBPR自体がもつ成功・失敗の確率ではない。その多くの原因は人に起因するものである」と指摘しています。実際、改革と名のつくプロジェクトが想定したとおりに進まないのは、戦略やプランそのものの欠陥、進め方の問題が原因というよりも、むしろそれに関わる人々の意識や感情といった“心理的側面”の影響が大きいと考えられるのです。
ボストンコンサルタンティンググループのコンサルタントであるジーニー・ダック氏は、改革を妨害したり、かき回したりする人間的・心理的な阻害要因のことを、総じて「チェンジモンスター」と呼んでいます。これには、人間関係のもつれや変わることへの怖れ・反発、喜怒哀楽・嫉妬・興奮など、改革にともなう諸々の感情が含まれます。ダック氏の指摘で特に興味深いのは、日本の企業組織に潜むという特有の“怪物”――「タコツボドン」(自分の担当を超えた視野を持つことを拒否し、よそ者の関与を否定する)や「ウチムキング」(社内で何が評価されるかを重視し、顧客などの外部ではなく社内にすべての行動の焦点をあわせ、社内外のズレに目を閉ざす)、「ノラクラ」(さまざまな言い訳を使いあの手この手で変革を避けようとする)、「カイケツゼロ」(課題の指摘やできない理由の説明は巧みだが、解決策の提言は出せない)などの存在です(『チェンジモンスター― なぜ改革は挫折してしまうのか?』ジーニー・ダック著、BCG東京事務所訳、2001 より)。
いくら改革に大義があり、プロジェクトが合理的でも、こうした心理にとらわれているモンスター社員を放置したままでは、うまくいくものもいきません。自社のチェンジモンスターの“正体”を探り、危機感の薄い社員に現状を打破する必要性を意識させることが、改革を成功に導くチェンジマネジメントの要諦といえるでしょう。
- 参考になった0
- 共感できる0
- 実践したい0
- 考えさせられる0
- 理解しやすい0

用語の基本的な意味、具体的な業務に関する解説や事例などが豊富に掲載されています。掲載用語数は1,500以上、毎月新しい用語を掲載。基礎知識の習得に、課題解決のヒントに、すべてのビジネスパーソンをサポートする人事辞典です。
会員登録をすると、
最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!
無料会員登録
記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。


 テーマで探す
テーマで探す サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 学び・実務
学び・実務





 イベント
イベント