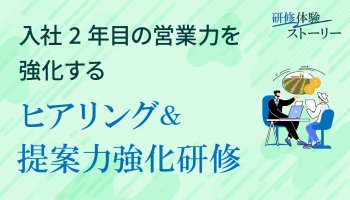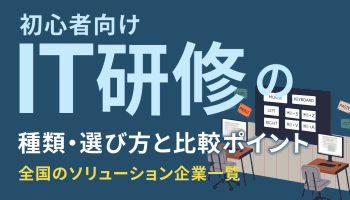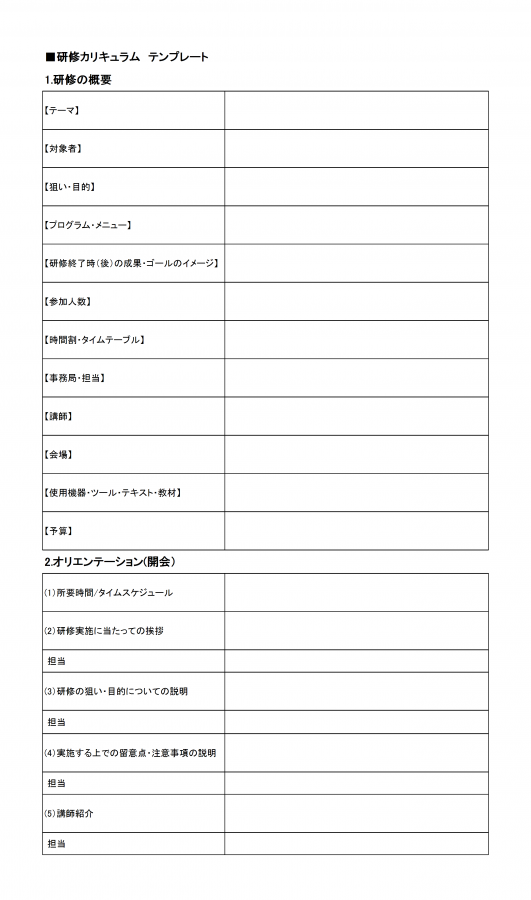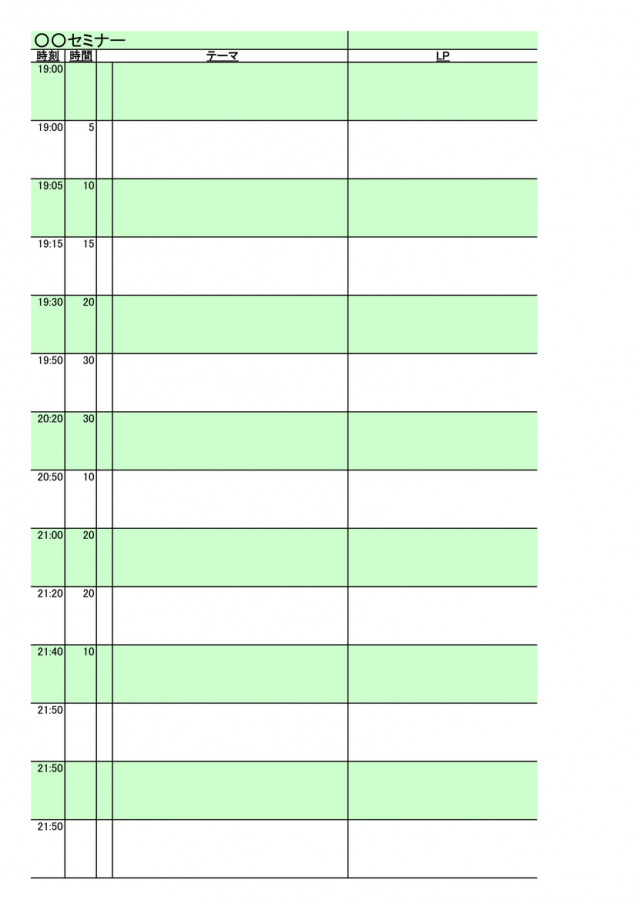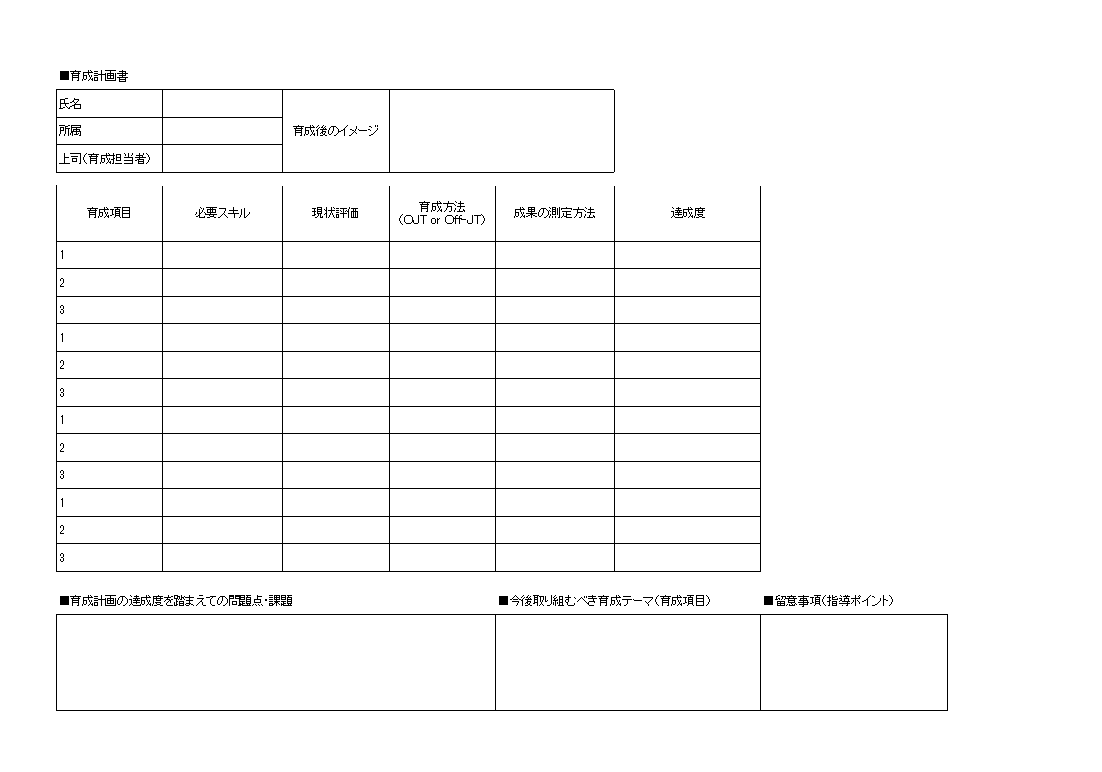カークパトリックの4段階評価法
カークパトリックの4段階評価法とは?
米国の経済学者、ドナルド・カークパトリックが1975年に提唱した教育や研修の効果測定法をまとめたモデルのこと。「4段階評価法」とも呼ばれます。このモデルでは、4段階に分けて教育研修の効果を測ります。レベル1は「反応」、レベル2は「学習」、レベル3は「行動」、レベル4は「結果」と、徐々に評価の難易度が上がっていきます。業務のIT化が進んだ2000年代に研修効果を可視化しやすくなり、このモデルが注目されました。現在、米国では約7割の企業が採用しており、日本でも広く浸透している方法論です。
研修後、満足度を聞いて終わっていませんか?
四つの指標から研修を精査する
研修の効果をどのように測定すべきか、多くの育成担当者が悩んでいます。研修実施後にアンケートを実施しても、参加者の満足度の収集にとどまっている企業は多いのではないでしょうか。効果測定は重要性が高い一方で、人の成長にはさまざまな要因が絡み合うため、研修単体の効果を正確に測ることは難しいものです。そのため参加者の満足度を指標にしてしまいがちですが、本来、研修は従業員を満足させるためのものではなく、組織に利益をもたらすことが目的であるはずです。
どうすれば、研修が組織へどう貢献したかを知ることができるのでしょうか。カークパトリックの4段階評価法を使えば、参加者の体感だけでなく、さまざまな軸から研修を評価できるようになります。
(1)反応
従来から行われてきた満足度調査は、参加者の「反応」として第1段階の評価指標に使うことができます。研修後にアンケートやヒアリングを行い、満足度や感想を収集します。
(2)学習
参加者が研修で何を学んだかを評価する指標です。研修後にテストを実施したりレポートを書いてもらったりすることで、何をどのくらい習得できたかを可視化。到達度に応じて、研修の効果を測定します。eラーニングやLMS(ラーニングマネジメントシステム)の浸透により、学習到達度を調査しやすくなりました。
(3)行動
学習した後に、行動が変容したかどうかが第3段階の評価指標です。1ヵ月や1年など、研修から一定期間がたった後に参加者やその上司にインタビューして、行動変容がみられたかどうかを調査します。育成担当者だけでなく、参加者が属する部署の協力も必要です。
(4)結果
第4段階では、行動変容が組織の成果に結びついたかどうかを評価します。営業成績やコンバージョン率など、数値化できる成果は評価しやすいでしょう。しかし成果には研修以外の要素も影響するため、高度な評価スキルが必要です。ROI(Return On Investment:投資利益率)を指標にする企業が多いようです。
EdTechやDXが推進され、教育・研修のオンライン化が進めば、データの収集や研修効果の可視化が行いやすくなります。正しく効果を測定することは、自社や従業員に本当に必要な研修とは何なのかを見極めることにつながるでしょう。
参考:ROIとは│日本の人事部
- 参考になった0
- 共感できる0
- 実践したい0
- 考えさせられる0
- 理解しやすい0

用語の基本的な意味、具体的な業務に関する解説や事例などが豊富に掲載されています。掲載用語数は1,500以上、毎月新しい用語を掲載。基礎知識の習得に、課題解決のヒントに、すべてのビジネスパーソンをサポートする人事辞典です。
会員登録をすると、
最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!
無料会員登録
記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。


 テーマで探す
テーマで探す サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 学び・実務
学び・実務





 イベント
イベント