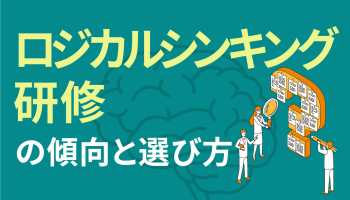国際成人力調査
国際成人力調査とは?
「国際成人力調査」とは、経済協力開発機構(OECD)が実施する国際調査の一つで、OECD加盟国など先進24ヵ国・地域の16歳から65歳を対象に、社会生活において成人に求められる能力を測定するものです。英語名のProgramme for the International Assessment of Adult Competenciesの頭文字を取り、PIAAC(ピアック)と略されます。2011年から12年にかけて初めての調査が行われ、13年10月に結果が発表されました。「読解力」と「数的思考力」の二つの分野で日本が1位になったことから、日本人全般のスキルの高さを示すデータとして注目されています。
「読解力」「数的思考力」で日本がトップ
全体的なレベルの高さに企業内教育も寄与
経済のグローバル化や知識基盤社会への移行といった変化に伴い、先進諸国においては、雇用を確保して経済成長を促すために、国民の社会適応能力を向上させる必要があるとの認識が広まっています。そうしたなか、先進国における成人層のスキルの現状を把握し、学校教育や職業訓練など今後の人材育成政策に資する知見を得るために、OECDが2011~12年に初めて実施したのが「国際成人力調査」です。
この調査は、OECD加盟国を中心とした世界24ヵ国・地域の16~65歳の成人、約15万7000人を対象に実施。社会生活に適応する上で成人に求められる能力のうち、(1)社会に氾濫する言語情報を理解し利用する「読解力」(2)数学的な情報を分析し利用する「数的思考力」(3)パソコンなど「ITを活用した問題解決能力」の3分野のスキルの習熟度を測定するとともに、スキルと年齢、学歴、職業、所得などとの関連性についても調べました。単に知識の有無を問うのではなく、日常生活や仕事のさまざまな場面で与えられた情報を解釈し、利用する基本的な活用力を重視。数学の公式など特別な知識がないと解けないような問題は出題されていません。
その結果、今回の調査では、日本は「読解力」の平均点が500点満点中296点で、OECD平均273点を大きく上回り、トップの成績だったことが分かりました。「数的思考力」でも、OECD平均269点に対し日本は288点、2位フィンランドに6点の差をつけて1位でした。特徴的なのは、日本の場合、各国に比べ成績下位者の割合が最も少なく、逆に上位者の割合は最も多かったこと。日本人全体が高いレベルの“成人力”を身につけていることを意味しています。さらに職業別の成績分布を見ると、他の国々では生産現場の作業員などいわゆるブルーカラーの平均点が、ホワイトカラーに比べ明らかに低かったのに対し、日本のブルーカラーのレベルは、各国のホワイトカラーと同程度か、それ以上でした。日本の優れた“現場力”の裏付けともいえるでしょう。
文部科学省では、こうした全体的なレベルの高さを義務教育の成果ととらえていますが、もちろん要因はそれだけではありません。専門家は「学力を維持する力」の高さにも注目。学力は使わないと下がるのが普通で、これを「学力の剥離」と呼びますが、国立教育政策研究所の斉藤泰雄総括研究官(比較教育学)は「日本では新聞や雑誌を読む成人が多く、学校で身につけた学力が落ちにくい。(中略)企業でも研修が多く、常に向上が求められる社内環境も学力維持の支えになっているのではないか」と、企業内教育の果たす役割に注目しています(毎日新聞2013年10月9日付)
- 参考になった0
- 共感できる0
- 実践したい0
- 考えさせられる0
- 理解しやすい0

用語の基本的な意味、具体的な業務に関する解説や事例などが豊富に掲載されています。掲載用語数は1,400以上、毎月新しい用語を掲載。基礎知識の習得に、課題解決のヒントに、すべてのビジネスパーソンをサポートする人事辞典です。
会員登録をすると、
最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!
無料会員登録
記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。


 サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 調査
調査 人事辞典
人事辞典 イベント
イベント