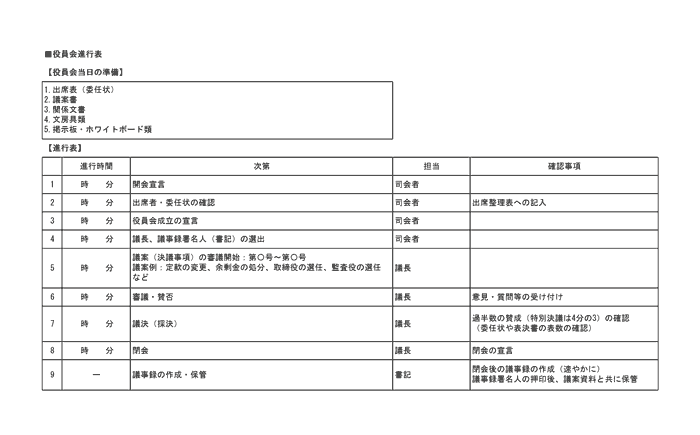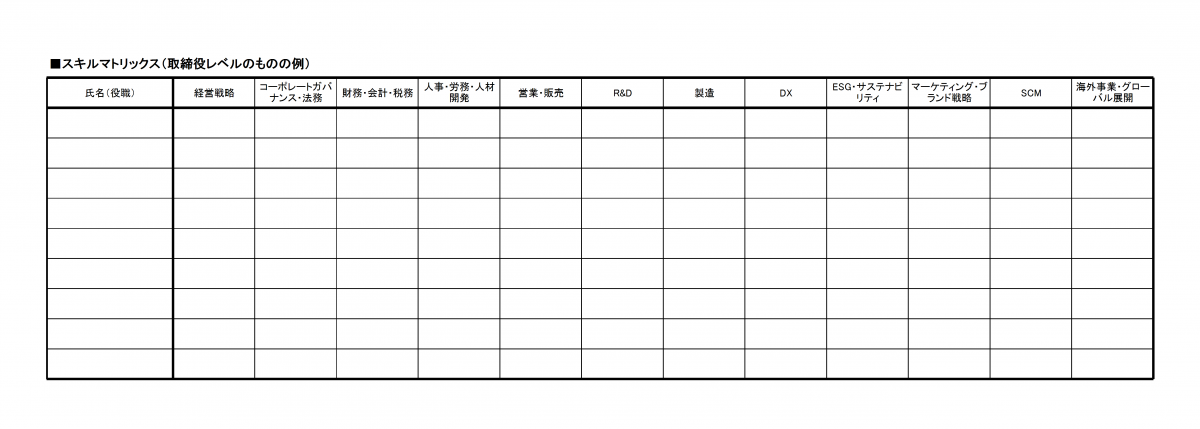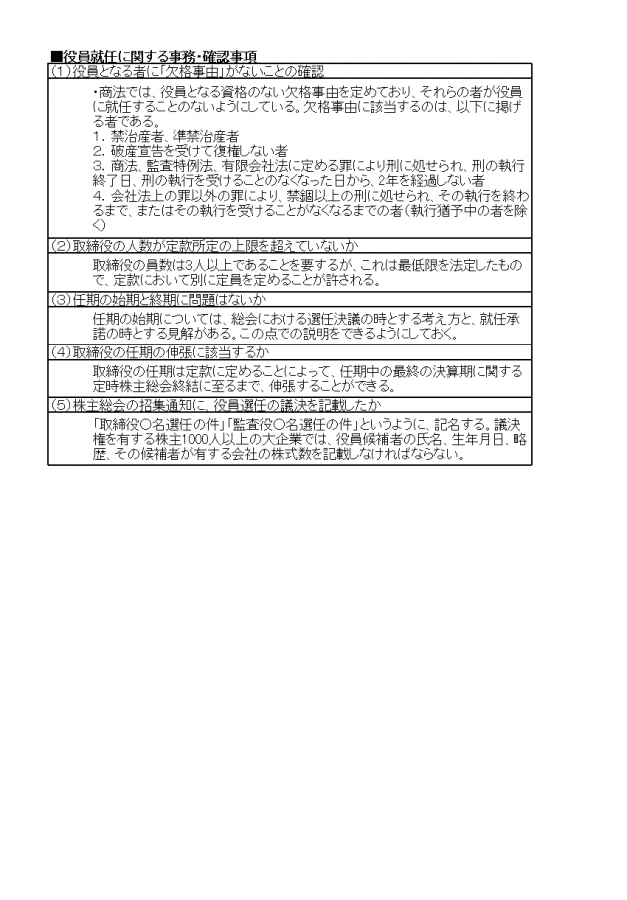デザイン経営
デザイン経営とは?
「デザイン経営」とは、デザインの力をブランドの構築やイノベーションの創出に活用する経営手法のこと。製品やサービスのデザイン性を向上させることにとどまらず、ユーザー体験やブランドの一貫性を企業活動の中心に据えることで、価値創造と競争優位を同時に高めます。2018年には経済産業省と特許庁が「デザイン経営宣言」を公表し、デザインを「コスト」ではなく「投資」と捉える流れが加速しました。モノがあふれた成熟市場では、使いやすさや物語性といった情緒的価値が差別化ポイントになります。デザインを経営資源として活用できるかどうかが、企業の成長を左右するのです。
なぜ今、デザイン経営が必要なのか
企業の実例とデザイン経営のポイント
デザイン経営が脚光を浴びる背景には、技術さえ優れていれば売れる時代が終わりつつあることがあります。たとえば、スマートフォンのアプリで家電を遠隔操作できる新機能は、今の時代ではすぐにコピーされてしまうため、技術や価格による差別化は難しい。そこで「共働きの子育て世帯に寄り添った製品」とPRすることで差別化を図ります。日々仕事に追われながら家事や育児をこなしている人たちから「私のことを深く理解しているブランド」と認知されるようになれば、信頼が生まれるでしょう。すると、製品が選ばれるようになります。
こうした環境下で各社が取り組んでいるのが、体験の再設計を通した顧客との長期的な関係を築く試み。パナソニックホールディングスは、生活者のインサイトを掘り起こす共創プロジェクトを展開し、リアルな暮らしを製品開発に反映。デザイナーが企画段階から入り、発掘されたニーズに基づいた家電を短期間でプロトタイプ化するなど、家電の枠を超えた新規事業アイデアが生まれています。
スタートアップのFABRIC TOKYOも、デザイン経営の好事例です。同社はオーダースーツの採寸から購入、カスタマイズまでをアプリ上で完結させることで、オーダースーツのハードルを下げつつ、最適な一着にたどり着ける導線を設計しました。顧客のニーズに沿った体験を設計することで、LTV(顧客生涯価値)を高めています。
これらの企業に共通するのは、デザインを経営の意思決定へ引き上げている点です。デザイナーをChief Design Officer(CDO)としてボードメンバーに迎えたり、企画職と営業職とのジョブローテーションを行ったりすることで、ユーザー中心で考える文化が醸成されます。また、デザイン思考を社員研修に組み込み、職種を問わず顧客視点で課題を捉えるスキルを底上げして、部門横断の協働を加速させる動きもあります。
デザイン経営は、単に見た目を磨くだけの取り組みではありません。企業の目的、提供価値、業務プロセスをユーザー起点で再設計し、ブランド構築とイノベーション創出を同時に推し進める経営改革です。人事や経営者にとって、デザインを組織戦略の核と捉え、推進できる体制を整えることは今後ますます重要になるでしょう。
- 参考になった0
- 共感できる0
- 実践したい0
- 考えさせられる0
- 理解しやすい0

用語の基本的な意味、具体的な業務に関する解説や事例などが豊富に掲載されています。掲載用語数は1,400以上、毎月新しい用語を掲載。基礎知識の習得に、課題解決のヒントに、すべてのビジネスパーソンをサポートする人事辞典です。
会員登録をすると、
最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!
無料会員登録
記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。


 サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 調査
調査 人事辞典
人事辞典 イベント
イベント