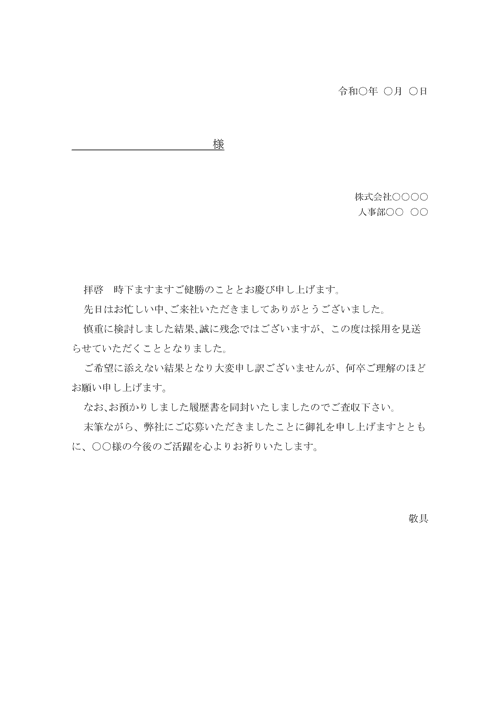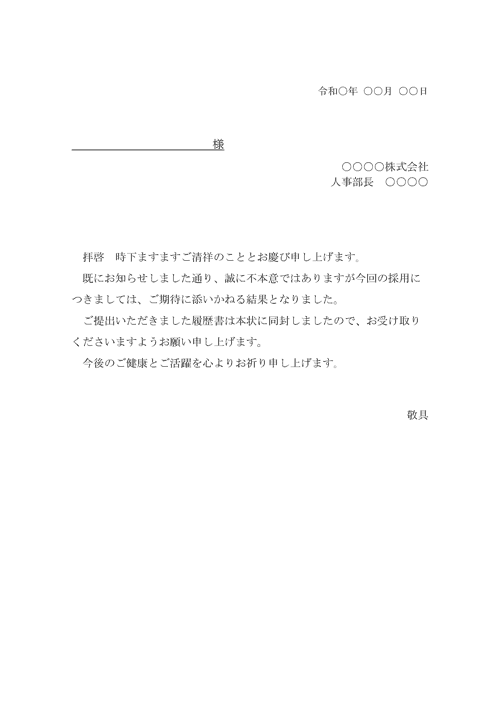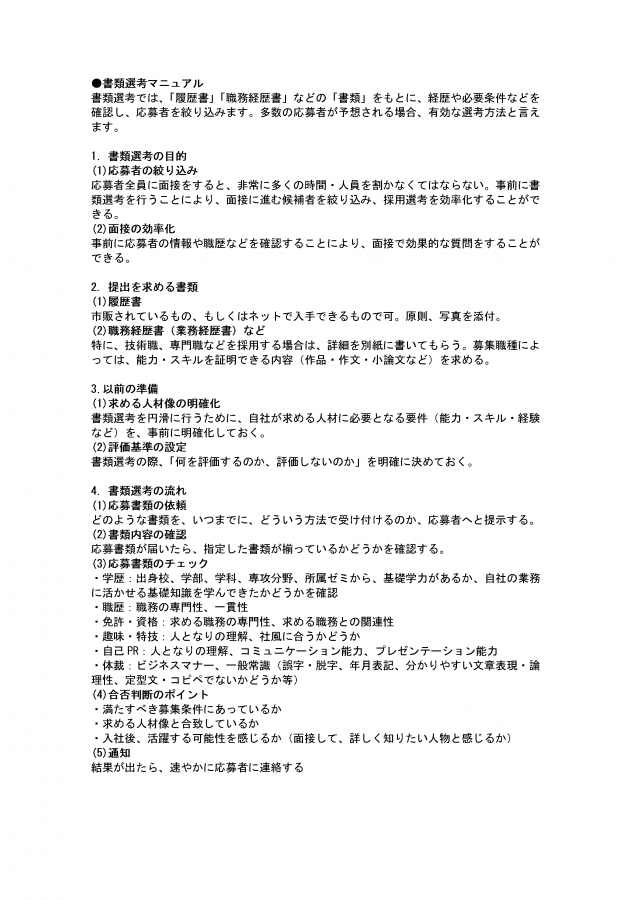構造化面接
構造化面接とは?
「構造化面接」とは、事前に質問項目や評価基準を設定した上で実施する面接手法。候補者全員に同じ質問をし、明確な基準に沿って評価します。一方、面接担当者が自由に質問を行い、面接担当者の主観によって評価が左右される面接手法は非構造化面接といいます。従来は、面接担当者の経験と勘による非構造化面接が主流でしたが、構造化面接は客観的な指標で評価するため、見極めの精度が高くなると言われています。採用プロセスの透明性や公平性が確保できるという点からも、昨今注目されています。
従来の面接はほとんど意味がない!?
面接官の「経験と勘」に頼らない面接方法とは
1998年、米国の心理学者フランク・L・シュミット氏とジョン・E・ハンター氏が研究論文を発表し、さまざまな面接手法がそれぞれどれだけ入社後の評価を説明できるかを数値化しました。例えば、「ワークサンプルテスト」は29%、「認知能力テスト」は26%。また「構造化面接」は26%だったのに対し、「非構造化面接」は14%でした。
かつて面接業務は、マネジメント業務に近い難しさがあり、「やっていく中で覚える」ものでした。面接を担当することになっても、教育やトレーニングなどで体系的に学ぶ機会を得られないまま本番を迎えることも珍しくありません。面接担当者の主観で評価するため、担当者によって評価のばらつきが起こりやすく、それによって優秀な人材を逃したり、反対にパフォーマンスを発揮しない人材を採用したりすることもありました。
一方、構造化面接では、決められた質問を順番通りに聞いていきます。「どのような組織で、あなたはどのような役割だったのですか」「どのような目標に対し、どのような課題がありましたか」「その課題をどう解決したのですか」など、過去の行動を掘り下げる質問を重ねます。効果的に相づちや質問をしながら話を引き出す必要はありますが、型が決まっていることで、面接担当者のレベルで面接の質が左右されるリスクが低くなります。
前述の研究の通り、評価の妥当性が高く、採用のミスマッチが抑えられる点も構造化面接のメリットです。客観的な指標で評価することでデータ分析をしやすくなり、入社後のパフォーマンスとひも付けて面接のPDCAを回しやすくなるのも特筆すべき点でしょう。
一方で、構造化面接にはデメリットもあります。まず、事前に質問内容や評価基準を準備するのに労力がかかる点。候補者全員に同じ質問をするからこそ、その質問は練られたものでなければいけません。
用意された質問への回答以上の情報は得られないため、候補者の魅力が質問範囲外にあった場合に魅力の発見が難しいというデメリットもあります。そのため最近は、構造化面接の決められた質問の後に面接担当者が自由に質問する「半構造化面接」という方法をとる企業もあります。
組織の規模や職種によって、適した面接方法は変わります。採用人数も応募人数も多い大企業であれば、採用の効率化を進めるために構造化面接が適しているでしょう。しかし、機動力や柔軟性が求められるスタートアップでの採用や、主観的な要素も重要であるクリエイティブ職の採用では、構造化面接が適さない可能性もあります。企業の採用ニーズや文化に合わせて、構造化面接を実施するかどうかを判断することが重要です。
- 参考になった0
- 共感できる0
- 実践したい0
- 考えさせられる0
- 理解しやすい0

用語の基本的な意味、具体的な業務に関する解説や事例などが豊富に掲載されています。掲載用語数は1,500以上、毎月新しい用語を掲載。基礎知識の習得に、課題解決のヒントに、すべてのビジネスパーソンをサポートする人事辞典です。
会員登録をすると、
最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!
無料会員登録
記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。


 テーマで探す
テーマで探す サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 学び・実務
学び・実務





 イベント
イベント