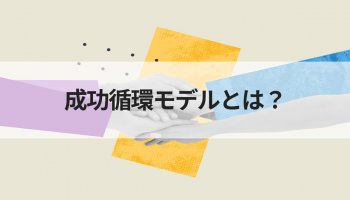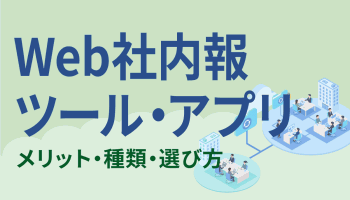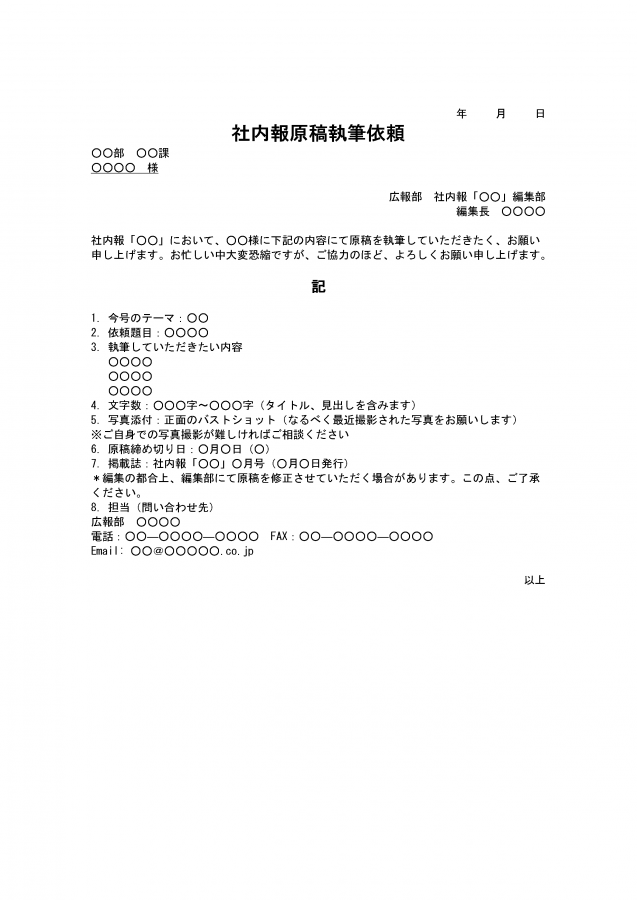7S
7Sとは?
「7S(Seven S Model)」とは、マッキンゼー・アンド・カンパニー社が提唱した組織変革のためのフレームワークです。組織の全体像といくつかの要素の相互関係を表しており、組織の現状を包括的に捉え、適切な対策をとっていくのに有効だとされています。
ハードとソフトの両輪で
組織改革を加速させるための7S
「7S」における組織の要素は、それぞれ頭文字をとった七つのSで表します。「ハードのS」と呼ばれるものが「戦略(Strategy)」「組織(Structure)」「システム(System)」の三つ。一方、「ソフトのS」と呼ばれるのが、「価値観(Shared Value)」「スキル(Skill)」「人材(Staff)」「スタイル(Style)」の四つです。ハードのSの変更は比較的容易ですが、ソフトのSは価値観に関わる要素であるため、変更には時間がかかるといわれています。
組織改革を行うとき、手を付けやすいという理由で、ハードの変更から着手する組織が多いのではないでしょうか。マーケティング戦略を変更したり、部署を統合するなど組織を改編したり、人事評価制度や報酬にまつわる規定を変更したりするのがハードに当たります。
ハードの変更は可視化されるため、「やっている感」が出てしまうのですが、ソフトの改革も忘れてはいけません。ハードとソフト、どちらがより重要ということはありませんが、両者が融合し、整合性があることが大切なのです。
例えば、ハードのSの対応として、事業戦略を変更したとします。しかし、それを実行する従業員にモチベーションを持っていないと生産性は下がり、スキルを持っていないと戦略を実行することはできません。最先端の営業管理システムを導入したとしても、従業員が情報管理に無頓着ではシステムの有効活用はで期待できません。
そこでソフトのSである価値観やスタイルの変更が必要になるのです。反対に、能力も志もある従業員がいたとしても、それを支えるシステムや組織構造が磨かれていなければ宝の持ち腐れになってしまい、組織のパフォーマンスを上げることはできません。
組織改革を行うならば、全方位的に取り組む必要がありますが、可視化されていないものへの網羅性を確信することは難しい。そこで「7S」のフレームワークが役立ちます。七つの要素を言語化することで、成長の阻害要因となっているものを洗い出すこと。それぞれの要素は相互に作用し合っているため、一つの要素をブラッシュアップすることで他の要素にも良い影響を与え、加速度的に組織改革が進むのです。
- 参考になった0
- 共感できる0
- 実践したい0
- 考えさせられる0
- 理解しやすい0

用語の基本的な意味、具体的な業務に関する解説や事例などが豊富に掲載されています。掲載用語数は1,500以上、毎月新しい用語を掲載。基礎知識の習得に、課題解決のヒントに、すべてのビジネスパーソンをサポートする人事辞典です。
会員登録をすると、
最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!
無料会員登録
記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。


 テーマで探す
テーマで探す サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 学び・実務
学び・実務





 イベント
イベント