ISOは器であり道具、どう使うか│品質マネジメントの本質は

ISO9001という“家”の話
あなたの会社に、家を一軒、建てることになったとしましょう。
建てる目的は、社員が安心して働ける「拠点」であり、顧客を招ける「信頼の象徴」としての場であり、長く快適に使える「資産」を築くことです。
つまり、その家は単なる建物ではなく、未来への基盤なのです。
ところが、いざ建て始めると、どうでしょうか。
工務店(コンサルタント)は、家の構造図を持ってきます。
「この図面通りにすれば審査が通ります。役所にも認可されますよ」と。
あなた(経営者)は、なるほどと思い、指示を出します。
品質保証部長も「この設計なら安全でしょう」と納得し、品質管理部長も「これで検査には合格できますね」と頷きます。
でも、実際に家を建てていくと、社員(住人)は違和感を覚えます。
「この扉、やたらと重くないか?」「なんで窓が開かないの?」「無駄に廊下が長くて移動が大変…」
やがてこうなります。
「とにかく、この図面通りに作れって言われてるから、仕方ないよ…」
こうして完成した家は・・・・
・見た目は立派だけど、誰もくつろげない
・手入れに手間がかかり、維持コストが高い
・現場の使い勝手を無視していて、日々の作業効率が落ちる
それでも外から見れば立派なので、周囲には「立派な家が建ったね!」と褒められます。
でも、住んでいる人は、日々小さなストレスを抱えて暮らしている…そんな家。
これ、まさに、いま多くの企業が築いている「ISO9001のマネジメントシステム」ではないでしょうか?
品質マネジメントの本質とは?
本来、ISO9001が目指す家とは、
・社員が安心して働ける仕組み
・顧客の期待に応えられる柔軟さ
・日々メンテナンスしやすく、使い勝手の良い運用
・時間と共に成長し、価値を増す仕組み
つまり「見栄え」ではなく「中身」こそが大切だったはずです。
人は、安心することで意識の領域を変化させる動物です。
例えば、時間に追われて焦っている様では、品質意識は高まりません。
また、ストレス環境におかれた状態では、目的意識も顧客志向も低下します。
ところが、現場では
「審査が通ればいい」
「文書を揃えればいい」
「認証を取ることがゴール」
という風潮が広まり、結果として“住みにくい家”を増やしてしまっている。
私が支援の中で疑問を抱いたのは、まさにこの点でした。
“仕組みのはずが、仕事を増やすものになっている。”
“改善のための道具が、負担とルールを押し付ける枠組みに変わっている。”
それは果たして、品質マネジメントと言えるのでしょうか?
ムダを省き、質を高める
品質マネジメントとは、「最も効果的で効率的な仕組みを構築すること」。
そのためには、まずムダを省くこと。
そして、仕事を増やさず、質を維持・向上させることが求められます。
仕組みをつくる目的は、現場を楽にすること、判断の精度を高めること、社員が納得感を持って取り組める土壌をつくることです。
つまり、品質マネジメントの中心にあるべきものは、文書でも規格でもなく、「人」と「思考」です。
必要なのは、問題解決力と改善力を高めていく文化。
小さな不便や違和感を放置せず、現場の声を拾い上げ、全体最適を図る視点。
ISOは、その“仕組みの土台”になるべきものだったのです。
──では、どうすればその本質を取り戻せるのか?
変革のストーリー “家を住みこなす”という視点
ある製造業の中堅企業で、私が支援を始めたときのことです。
ISO9001を取得して数年。
文書は揃っている。
審査にも通っている。
でも、社員たちはこうこぼしていました。
「正直、この仕組みが何のためにあるのか、よく分かっていません」
「書類を作るのが仕事みたいになっていて、現場が置いてけぼりなんです」
社長は悩んでいました。
「こんなはずじゃなかった」と。
私が最初に提案したのは、「マネジメントシステムを“家”ではなく“暮らし”として見直すこと」でした。
──どういうことか。
家を建てたあとに大事なのは、暮らしやすさです。
家具の配置を変えたり、必要な場所に棚を増やしたり。
住んでみて初めて分かる不便さを、日々改善していく。
それが「定着」や「活用」ということです。
この会社では、現場のリーダーや中堅社員たちと一緒に、こう問い続けました。
「この手順書、本当に今も役に立ってる?」
「この記録、誰の判断の助けになってる?」
すると、小さな改善が次々と生まれました。
・形式だけだったチェックリストを、判断ポイントを明確にしたシンプルなフローに
・誰も使っていなかったマニュアルを、写真付きで“現場版”に再編集
・「記録のための記録」をやめて、「見返して使う記録」へと転換
社員たちの表情が変わりはじめたのは、まさにここからでした。
「前より考えて動けるようになった気がします」
「やっと、自分たちの仕組みになった気がする」
社長も言いました。
「ああ、これが“品質マネジメント”なんですね」
ISOというのは、取得することがゴールではありません。
それはあくまで「器」であり、「道具」です。
どう使うか、どう使いこなすか。
“住みこなす”視点があってこそ、初めて本当の価値を生み出します。
本当の目的を取り戻す
私が支援しているある企業では、ISO9001を取得していながらも、「本当に業務に役立つ仕組みとは何か?」を問い続け、徹底的にムダを見直す活動に取り組みました。
そこでは、文書の目的を再定義し、会議のあり方を見直し、仕組みを“人の動き”と結びつけることを重視しました。
その結果、顧客からのクレーム件数は横ばいだったものの、社員の問題意識が明らかに高まりました。
特に印象的だったのは、会議での発言量の増加と、課題に向かう前向きな姿勢の変化です。
「この会議、意味あるね」「この仕組み、ちゃんと現場に生きてる」
そんな言葉が飛び交い始め、結果として、問題解決のスピードが目に見えて上がっていきました。
数字で見える効果だけでなく、社内の“空気”が変わったことが、何よりの成果だと私は感じています。
組織にとって品質とは、「顧客との約束を守る力」であり、「未来の期待に応える力」です。
そのために、社員の知恵と力を引き出し、継続的な改善を進めていく。
仕組みはその“舞台”であり、主役はあくまで“人”です。
マネジメントシステムとは、人と組織の「思考と行動」を磨くためのフレームワーク。
だからこそ、問題解決力と改善力を高めることが、何よりも重要なのです。
──さて、あなたの会社のマネジメントシステムは、“家”として完成したまま止まっていませんか?
“住みこなす”視点、もう一度取り戻してみませんか?
このコラムを書いたプロフェッショナル

坂田 和則
マネジメントコンサルティング2部 部長 改善ファシリテーター・マスタートレーナー
問題/課題解決を現場目線から見つめ、クライアントが気付いている原因はもちろん、その背景にある奥深い原因やメンタルモデルも意識させ、問題/課題改善モチベーションを高めます。
その先の未来には、改善レジリエンスの高い人材が活躍します。

坂田 和則
マネジメントコンサルティング2部 部長 改善ファシリテーター・マスタートレーナー
問題/課題解決を現場目線から見つめ、クライアントが気付いている原因はもちろん、その背景にある奥深い原因やメンタルモデルも意識させ、問題/課題改善モチベーションを高めます。
その先の未来には、改善レジリエンスの高い人材が活躍します。
問題/課題解決を現場目線から見つめ、クライアントが気付いている原因はもちろん、その背景にある奥深い原因やメンタルモデルも意識させ、問題/課題改善モチベーションを高めます。
その先の未来には、改善レジリエンスの高い人材が活躍します。
| 得意分野 | モチベーション・組織活性化、リーダーシップ、コーチング・ファシリテーション、コミュニケーション、ロジカルシンキング・課題解決 |
|---|---|
| 対応エリア | 全国 |
| 所在地 | 港区 |
このプロフェッショナルの関連情報
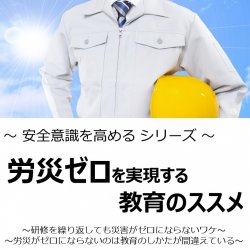
- 無料
- WEBセミナー(オンライン)
- モチベーション・組織活性化
- 安全衛生・メンタルヘルス
- コーチング・ファシリテーション
- ロジカルシンキング・課題解決
- リスクマネジメント・情報管理
【4/14開催】【無料セミナー】~ 安全意識を高める シリーズ ~
労災ゼロを実現する 教育のススメ
開催日:2025/04/14(月) 13:30 ~ 15:30
- 無料
- WEBセミナー(オンライン)
- モチベーション・組織活性化
- キャリア開発
- コーチング・ファシリテーション
- ロジカルシンキング・課題解決
【5/9開催】「なぜを5回繰り返せ」が上手くいかない理由はこれだ!
なぜなぜ分析12カ条 体験セミナー
開催日:2025/05/09(金) 13:30 ~ 14:45
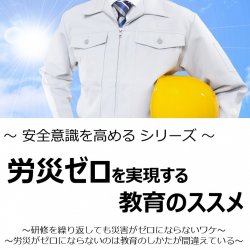
- 無料
- WEBセミナー(オンライン)
- モチベーション・組織活性化
- 安全衛生・メンタルヘルス
- コーチング・ファシリテーション
- ロジカルシンキング・課題解決
- リスクマネジメント・情報管理
【5/12開催】【無料セミナー】~ 安全意識を高める シリーズ ~
労災ゼロを実現する 教育のススメ
開催日:2025/05/12(月) 13:30 ~ 15:30
- 参考になった0
- 共感できる0
- 実践したい0
- 考えさせられる0
- 理解しやすい0
無料会員登録
記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。


 テーマで探す
テーマで探す サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 学び・実務
学び・実務





 イベント
イベント









