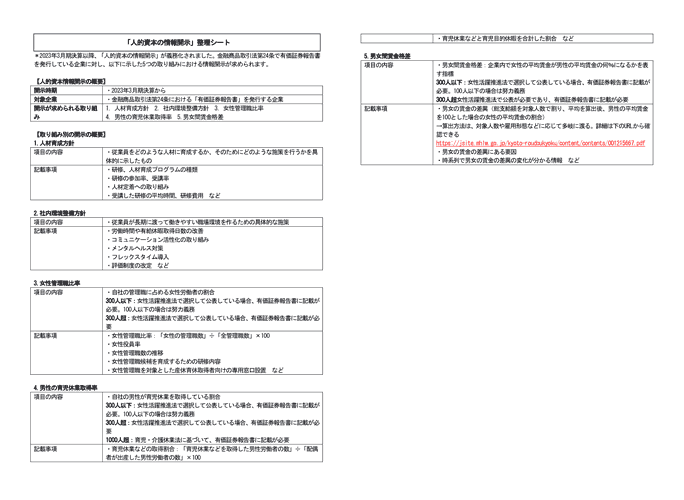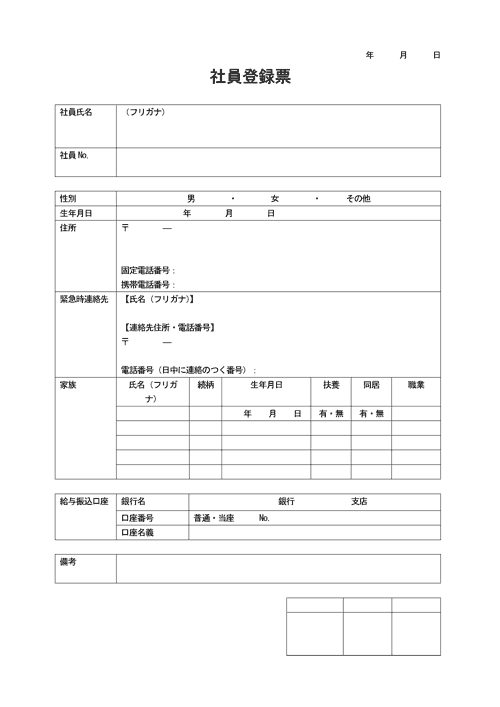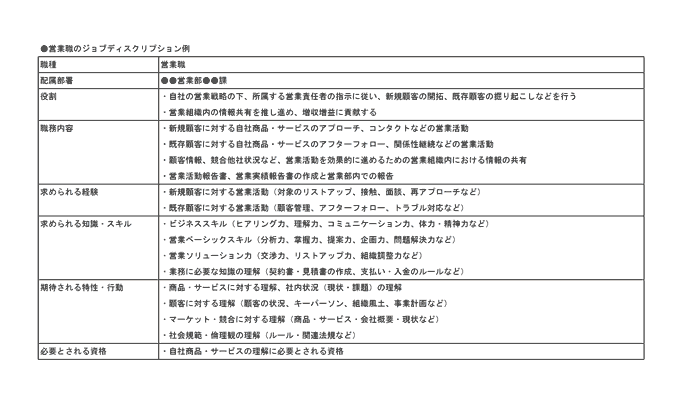ゆでガエル理論
ゆでガエル理論とは?
「ゆでガエル理論」とは、ゆっくりと進行する危機や環境変化に対応することの大切さ、難しさを戒めるたとえ話の一種で、おもに企業経営やビジネスの文脈でよく用いられます。カエルを熱湯の中に入れると驚いて飛び出しますが、常温の水に入れて徐々に熱すると、カエルはその温度変化に慣れていき、生命の危機と気づかないうちにゆであがって死んでしまうという話です。理論といっても、実際は作り話で科学的にも誤りであることがわかっていますが、経営者や経営学者、経営コンサルタントなどによってまことしやかに語られてきたため、すでに一つの教訓として定着しています。
慣れたぬるま湯に浸かりすぎて手遅れに
疑似科学的な虚構でも説得力豊かな寓話
そもそも「ゆでガエル理論」あるいは「ゆでガエル現象」「ゆでガエルの法則」などと呼ばれる話を、寓話として最初に用いたのは、1950~70年代に活躍したアメリカの思想家で文化人類学者、精神医学者のグレゴリー・ベイトソンだといわれています。日本では、経営学者の桑田耕太郎と社会心理学者の田尾雅夫による98年の共著『組織論』が「ベイトソンのゆでガエル寓話」として紹介しています。同書は“組織論のテキスト”といわれる著名な文献だけに、ここから広まっていったのではないかとも推測されています。“失われた10年”に関する議論が盛んだった2003年には、大前研一・田原総一朗の二大論客が『「茹で蛙」国家日本の末路』と題して共著を出し、話題を集めました。
いかにも科学的な実験で確認された現象であるかのように語られていますが、実際には、カエルは熱湯に入れれば飛び出す前に死に至り、水に入れて熱すると、温度が上がるほど活発になり、熱くなる前に飛び出して逃げるそうです。そんな疑似科学的な作り話であるにもかかわらず、ここまで説得力をもって受け入れられているのは、誰にでも思い当たるフシがあるからかもしれません。つまり、急激な変化には危機意識が働くのに対し、変化が緩慢だとそれに慣れ過ぎて、対応するタイミングを逸しやすい。危機を認識したときには致命的なダメージを負っているという「ゆでガエル」の比喩が、人間の思考や行動の本質を鋭く突いているからなのでしょう。
たとえば、業績の悪化が深刻で、抜本的な収益構造の転換や組織改革の必要に迫られている状態であるにもかかわらず、「うちはこのやり方で伸びてきたのだから」と過去の栄光にすがり続ける経営トップ。そしてそのトップの失政に気づきつつも保身に走って指摘しない役員たち。さらには、安易なノルマ達成に満足して問題の本質から目を反らす現場のリーダーなども、慣れたぬるま湯に浸かりすぎたゆでガエルの典型例といえます。
また昨今、女性活躍支援や介護離職への対応が経営課題に浮上し、それに関連して職場全体の働き方改革やワーク・ライフバランス推進の議論も活発化してきましたが、かけ声ばかり大きくて、まだまだ実際の成果には十分に結びついていません。問題の背景にある、少子高齢化や労働人口の減少といった社会の大きなトレンドは高い精度で予測されているものの、誰もが日々実感できるような目に見える変化ではないために、危機を危機として自覚できず、手をこまねいている状態といってもいいでしょう。
個人も組織も、手遅れのゆでガエルになりたくなければ、現状に甘んじることなく、すすんで自らを“カエル=変える”しかないのです。
- 参考になった0
- 共感できる0
- 実践したい0
- 考えさせられる0
- 理解しやすい0

用語の基本的な意味、具体的な業務に関する解説や事例などが豊富に掲載されています。掲載用語数は1,500以上、毎月新しい用語を掲載。基礎知識の習得に、課題解決のヒントに、すべてのビジネスパーソンをサポートする人事辞典です。
会員登録をすると、
最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!
無料会員登録
記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。


 テーマで探す
テーマで探す サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 学び・実務
学び・実務





 イベント
イベント