推薦者の言葉で腹が据わる│若手の覚悟はあなたの一言で決まる
心に火を灯す
「最近の若手は受け身で…」
「自信がないのか、いまいち覚悟が感じられない」
そう感じたことはありませんか?
リーダー候補として期待を込めて推薦したにも関わらず、本人は戸惑った様子で研修に現れ、目をそらしながら「自分なんかでいいんでしょうか…」と呟く。
そんな姿を見ると、「なぜだ?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
組織として、次世代育成に取り組む中で、意欲ある若手に任せていくことは不可欠です。
だからこそ、推薦という行為には「未来を託す」という強い想いが込められているはずです。
しかし、その想いが本人に伝わらないままでは、せっかくのチャンスが“やらされ感”に変わってしまう恐れもあります。
では、何が足りないのでしょうか。
答えはシンプルです。
「推薦の言葉」が、本人の心に届いていないのです。
このコラムでは、リーダー候補の若手に“腹を据えさせる”ために必要な、推薦者としての言葉の力と、その選び方について、掘り下げていきます。
若手の覚悟は、推薦された理由を“自分ごと”として受け止めたときに芽生えます。
そしてその瞬間は、あなたの一言によって訪れるのです。
腹を据わらせる言葉の本質
経営者や管理職の方がリーダー育成に取り組むうえで、ときおり次のような若手の姿に直面することがあるのではないでしょうか。
・推薦されて研修に参加しているにも関わらず、どこか落ち着かず、自分がリーダーにふさわしいのか戸惑っている様子。
・推薦された理由に納得できず、まるで他人事のような表情をしている。
そんな若手が、目の前にいませんでしたか?
その背景には、推薦者からの言葉が十分に伝わっていない、あるいは本人の中で“腹落ち”していないという事情があると感じています。
「推薦した」のに伝わらない理由
リーダー候補に「期待しているよ」と伝えたつもりでも、それが「やらされている」「プレッシャーが強い」と受け取られてしまうことがあります。
これは決して、珍しいことではありません。
心理言語モデルであるLABプロファイルの視点から見ると、人にはそれぞれ言葉の受け取り方に特有のパターンがあります。
たとえば、内発的な動機づけを重視するタイプの若手に「これをやってほしい」と伝えると、「強制された」と感じてしまいます。
逆に、外発的なタイプに「好きなようにやっていい」と言うと、不安になり行動できなくなることもあります。
内発的動機づけの強い人は、自分で判断して決める傾向が強く、外発的動機づけの強い人は、周囲の意見で決めるといった行動のクセがあります。
つまり、どれだけ想いを込めて推薦しても、「相手に合った言葉」でなければ伝わらないのです。
推薦者の覚悟が、言葉ににじみ出る
これまで数多くの若手リーダーと接してきた中で、印象に残っているのは、「推薦者の言葉が心に響いたから挑戦できた」という声です。
たとえば、「君に託したいと思った」「君と一緒にこの組織を変えていきたい」そんな言葉を、真正面から伝えられたときに、若手の表情が変わる瞬間があります。
一方、「成長のために必要だから」「会社として期待している」といった説明的な言葉は、本人の内面にはなかなか届きません。
それは推薦者自身が、“本気で語っていない”と相手に感じさせてしまうからです。
覚悟とは、「選んだ理由を真正面から語る」ことです。
「今の君だからこそ、このタイミングで挑戦してほしい」と具体的に誠実に語ることで、本人の受け止め方はまったく違ったものになります。
推薦の“言葉”が、人生を動かす
私たちが送り出す言葉には、若手の行動を大きく変える力があります。
彼らが「やってみよう」と腹をくくるのは、不安がすべて消えたときではありません。
不安を抱えながらも、「この人の言葉なら信じてみよう」と思えたときです。
推薦者の役割は、単に研修への推薦書を書くことではありません。
本人の心に火を灯す“推薦の言葉”を届けることです。
あなたの言葉が、未来のリーダーの一歩を踏み出す“本気のスイッチ”になることを、心から願っています。
それでは、相手の心に「この人は本気で語っている」と思わせるにはどうすれば良いのでしょうか?
おはなしをさらに進めてみましょう。
「期待している」では伝わらない理由
~言葉がすれ違う心理的メカニズムを読み解く~
管理職が感じる“届かないもどかしさ
「ちゃんと説明したつもりなのに、納得してくれない」
「期待していると何度も伝えたのに、乗り気じゃない」
そんな“もどかしさ”を感じたことはありませんか?
一方で、若手側は「プレッシャーに感じた」「自分に向いていないと思った」と口にします。
推薦者と若手の間で、“言葉のすれ違い”が起きているのです。
ここからは、なぜ「期待している」という言葉が若手に響かないのか、その心理的背景と、受け手の“認知パターン”をLABプロファイルの視点から読み解いていきます。
言葉が刺さらないのは、相手が悪いのではない
まず最初に強調したいのは、「伝わらないのは、相手が悪いからではない」ということです。
多くの管理職の方々は、「あの子は消極的だ」「今どきの若手は腰が重い」と感じ言葉にしますが、それは表面的な反応に過ぎません。
本当の原因は、「伝える側が自分の言葉の“フィルター”で話している」ことにあります。
人は誰しも、自分にとって自然な言葉の選び方・伝え方をしています。
しかし、受け手が同じフィルターを持っていない場合、その言葉はまるで異なる意味に受け取られてしまうのです。
LABプロファイルで見抜く“反応のズレ”
たとえば、あなたが「期待しているから挑戦してほしい」と言ったとします。
これは“外発的動機づけ”の言葉です。
ところが、受け手が「自分で決めたい」=“内発的動機”を重視するタイプであった場合、どう聞こえるでしょうか?
「上司の顔色を伺って動くことになる」
「断れない空気の中で引き受けることになる」
こうして、前向きな気持ちを抱くどころか、むしろストレスや抵抗感を生んでしまうのです。
LABプロファイルは、こうした“言葉と行動のパターン”の違いを見抜く道具です。
内発的か外発的か、選択型か手順型か、人の反応にはタイプがあり、それに応じたアプローチが必要になります。
「自分で決めた感覚」が行動を生む
では、どうすればよいのでしょうか。
カギは、「本人が“自分で選んだ”と感じられるかどうか」にあります。
たとえば、「君ならできるからやってみてほしい」ではなく、
「この機会を君自身がどう捉えるか、一度考えてみてくれないか」と投げかける。
すると、受け手は「やらされている」のではなく、「選ぶ余地がある」と感じ、自分の意志で一歩踏み出す準備が整っていきます。
これは、内発的動機タイプの人に対する“選択を促す”アプローチです。
また、「何から始めたらよいか分からない」と戸惑う若手には、「まずは○○をやってみよう」「次に○○を考えよう」と手順型の言葉で、安心感を与えることが効果的です。
言葉は、相手に合わせて“調合”するもの
伝える側がよく陥りがちなのは、「これが正しい言葉だ」と決めつけてしまうことです。
しかし、効果的な言葉とは、相手の特性に合わせて“調合”されるべきものです。
医師が患者に合わせて処方を変えるように、リーダーが若手の特性に合わせて言葉を選ぶのは当然のことです。
「伝わる」ではなく、「響く」言葉を届ける。
その意識が、若手の腹を決めさせる起点になります。
それでは、さらに具体的な言葉選びの工夫として、「どんな言い回しが若手の心に刺さるのか」「どのタイミングで伝えると効果的なのか」について掘り下げていきます。
若手を動かすのは、あなたの熱意だけではありません。
あなたの“言葉の選び方”が、全てを決めるのです。
「なんだか気持ちが動かないんです」
ある若手社員が研修の冒頭でこぼした一言に、私は思わず耳を傾けました。
話を聞くと、推薦者から「期待してるから」「きっと向いてるよ」と言われただけで、なぜ自分が選ばれたのかがよく分からなかったそうです。
しかし、同じような状況でも、ある若手は別の言葉に心を動かされていました。
「お前の背中を見て、後輩が変わったんだ。だから託したい。」
この違いは何でしょうか?
答えは明確です。
“その人にしか言えない”言葉には、力があります。
この章では、LABプロファイルの視点と、現場の会話事例を交えて、“腹を据えさせる言葉の選び方”をお伝えします。
型にはまった言葉は、届かない
多くの推薦者が口にする定番のフレーズ
「君ならできる」
「期待している」
「チャンスだと思って」
確かに間違ってはいません。
けれど、どれも“誰にでも言える言葉”です。
若手は驚くほど敏感に、「その言葉が本当に自分に向けられたものかどうか」を見抜いています。
言葉に“自分事感”がないと、心には届かないのです。
心に響くのは、「あなただから」の言葉
では、どんな言葉が響くのか。
キーワードは、「あなただから」です。
たとえば、以下のような具体的な言葉が効果的です:
「あのとき、会議で意見が出せなかった新人を、フォローしていたよね」
「君の段取り力が、前回のプロジェクトを円滑にしたんだよ」
「リーダーになってほしいのは、あのときの“らしさ”をみんなが感じているからなんだ」
これらはすべて、観察に基づいたフィードバックであり、相手の行動と結びついています。
相手が「自分の強みに気づく」きっかけにもなり、自己効力感が高まります。
タイプ別:響く言い方の工夫
LABプロファイルでは、人の言葉の受け取り方をパターン化して整理します。
ここでは、代表的な2タイプに対する効果的な表現例をご紹介します。
内発的動機タイプ
→「選択肢がある」「自分で決められる」と感じることが行動のきっかけになります。
NG例:
「この研修は会社として受けるべきだ」
OK例:
「このタイミングで挑戦するかどうかは君が決めていい。けれど、君のこれまでの姿を見て、私は託したいと思っている。」
外発的動機タイプ
→「評価される」「求められている」と感じることが行動の後押しになります。
NG例:
「自分の成長のためにどう動くかは、自由に考えてくれ」
OK例:
「この研修は、将来の昇格候補として、上層部も注目している。君の名前が挙がったのは事実なんだ。」
一言を“磨く”覚悟が、未来を変える
推薦は単なる制度ではありません。
推薦者の“目利き”と“語りかけ”が、若手の人生の分岐点になることもあるのです。
だからこそ、言葉を磨く必要があります。
その若手を観察し、記憶をたどり、「君を推薦する理由」を言葉にできるまで考え抜くこと。
その覚悟が、推薦の質を変え、組織の未来を動かしていきます。
推薦者自身が腹をくくる
それでは続けて、推薦者自身が腹をくくるとは何か?について、掘り下げていきます。
推薦の言葉が空回りするとき、その原因は「自分自身が納得しきれていないこと」にあるかもしれません。
“選ぶ責任”を持つこと。
それは、次世代育成に本気で関わる、というリーダーの覚悟でもあるのです。
推薦の瞬間、問われているのは自分自身
「誰を出せばいいですか?」
そう聞かれて、“条件に当てはまる若手”をリストアップする。
推薦の場面では、こんな光景が日常のように繰り返されています。
けれど本当に必要なのは、「条件に合う人材」ではなく、自分が“託したい”と本気で思える人を見つけることではないでしょうか。
推薦という行為は、選ばれる側だけでなく、選ぶ側の覚悟も問われる瞬間です。
この章では、推薦者としての内省と、リーダー育成における“信頼のバトン”の渡し方を考えていきます。
覚悟なき推薦は、相手の不安を増幅させる
推薦された若手が研修で戸惑う背景には、「選んだ人が本気なのか」が伝わっていないケースがあります。
よくあるのが、こんな推薦理由です:
「将来的に活躍しそうだから」
「そろそろ次の役割を経験させてもよい頃合いだと思って」
「これまでの順番的に、次は彼だと思った」
これらは、“理由”として整っているかもしれません。
しかし、本人にとっては、他人事にしか聞こえません。
なぜなら、その言葉の中に“推薦者の想い”が感じられないからです。
若手は敏感です。
推薦者が本気で選んだのか、それとも「名前を出しただけ」なのか、言葉の端々から感じ取っています。
自分の言葉に、責任を持てているか
私が研修で大切にしている質問があります。
「あなたは、その若手の未来に対して、どれだけの責任を持つつもりで推薦しましたか?」推薦とは、単なるパスではありません。
それは、信頼の証であり、未来への投資です。
もし、その若手が失敗したら?立ち止まってしまったら?それでもなお、「自分が推薦したことに後悔はない」と言えるでしょうか。
推薦者に求められるのは、成功の責任ではなく、“推薦という行為”への責任です。
その責任を自覚していれば、自然と言葉は磨かれ、誠実な対話が生まれます。
リーダー育成とは、「問いを託す」こと
多くの管理職が、推薦の場面で“答え”を与えようとします。
「この研修を受ければ成長できる」「きっと役に立つ」そんな“結果の保証”を言いたくなるのです。
けれど、リーダーシップとは、正解のない問いに向き合う力を育むプロセスです。
だからこそ推薦者は、「問いを託す」姿勢が必要です。
たとえば、こんな言葉が有効です:
「この研修を通じて、君はどんなリーダーになりたいと思うだろうか?」
「今の自分に、何が足りていないと感じている?」
「もし仲間を育てる側に立つなら、どんな関わり方をしていくだろう?」
問いを託された若手は、自ら考え始めます。
腹をくくるとは、外から押し込まれることではなく、内から湧き上がる意志を持つことなのです。
覚悟の推薦が、文化をつくる
推薦の質は、組織の文化を表します。
「とりあえず出しておこう」という推薦が横行すれば、若手も「とりあえず受けておこう」となり、形だけのリーダー研修が量産されます。
しかし、覚悟を持って選ばれた若手は、やがて次の推薦者になります。
そうやって、“本気のバトン”が連鎖していくことで、組織には本物のリーダーシップ文化が育っていくのです。
最後に
あなたが託したい“顔”を思い浮かべてください
このコラムの最初で、「推薦者の言葉で腹は据わる」とお伝えしました。
その言葉の重みは、あなたの本気度と比例します。
だから今、思い出してみてください。
あなたが本当に託したいと思う“あの顔”を。
その人に何と言葉をかけますか?
その人の未来を、あなたはどれだけ信じていますか?
推薦とは、その問いに自分で答えることから始まるのです。
私はリーダー育成をお受けするとき、このようなことまで「膝を突き合わせて」お客様と話しをします。
育てるのは、リーダーですが、リーダーを活かしチームのパフォーマンスを上げるのは、推薦者であるあなたなので。
今年も30名弱の次世代リーダー教育が、始まりました。
8ヶ月に及ぶ、心身ともに成長をねらう人財育成です。
今年もメンバー達は、「自分自身のこと」と覚悟を決めて参加しくれています。
先輩や上司もきっと、腹をくくった証です。

このコラムを書いたプロフェッショナル

坂田 和則
マネジメントコンサルティング2部 部長 改善ファシリテーター・マスタートレーナー
問題/課題解決を現場目線から見つめ、クライアントが気付いている原因はもちろん、その背景にある奥深い原因やメンタルモデルも意識させ、問題/課題改善モチベーションを高めます。
その先の未来には、改善レジリエンスの高い人材が活躍します。

坂田 和則
マネジメントコンサルティング2部 部長 改善ファシリテーター・マスタートレーナー
問題/課題解決を現場目線から見つめ、クライアントが気付いている原因はもちろん、その背景にある奥深い原因やメンタルモデルも意識させ、問題/課題改善モチベーションを高めます。
その先の未来には、改善レジリエンスの高い人材が活躍します。
問題/課題解決を現場目線から見つめ、クライアントが気付いている原因はもちろん、その背景にある奥深い原因やメンタルモデルも意識させ、問題/課題改善モチベーションを高めます。
その先の未来には、改善レジリエンスの高い人材が活躍します。
| 得意分野 | モチベーション・組織活性化、リーダーシップ、コーチング・ファシリテーション、コミュニケーション、ロジカルシンキング・課題解決 |
|---|---|
| 対応エリア | 全国 |
| 所在地 | 港区 |
このプロフェッショナルの関連情報
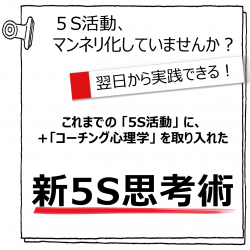
- 無料
- WEBセミナー(オンライン)
- モチベーション・組織活性化
- リーダーシップ
- コーチング・ファシリテーション
- ロジカルシンキング・課題解決
【6/3開催】 5S活動 × その気にさせる心理学 =『 新5S思考術』体験セミナー
~継続できる5S活動とは~
開催日:2025/06/03(火) 13:30 ~ 15:00
- 無料
- WEBセミナー(オンライン)
- モチベーション・組織活性化
- 安全衛生・メンタルヘルス
- コーチング・ファシリテーション
- ロジカルシンキング・課題解決
- リスクマネジメント・情報管理
【6/4~6/17視聴可能】【オンデマンド配信・無料】新時代の労働安全衛生
生産性を高める職場の安全意識とその重要性
開催日:2025/06/04(水) 00:00 ~ 2025/06/18(水) 00:00
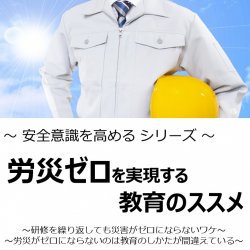
- 無料
- WEBセミナー(オンライン)
- モチベーション・組織活性化
- 安全衛生・メンタルヘルス
- コーチング・ファシリテーション
- ロジカルシンキング・課題解決
- リスクマネジメント・情報管理
【7/1開催】【無料セミナー】~ 安全意識を高める シリーズ ~
労災ゼロを実現する 教育のススメ
開催日:2025/07/01(火) 13:30 ~ 15:30
- 参考になった0
- 共感できる0
- 実践したい0
- 考えさせられる0
- 理解しやすい0
無料会員登録
記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。


 テーマで探す
テーマで探す サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 学び・実務
学び・実務





 イベント
イベント









