「楽しい」には理由がある │ 伝える技術の裏にある科学
「楽しかったです!」
「もう終わり?あっという間でした!」
これは、私が講師として担当する企業内研修のあと、受講者の方からよくいただく言葉です。
年間で延べ3,000人を超える方々と出会う中で、このような感想は本当に励みになります。
ですが、私は心の中でこうつぶやいているのです。
「楽しかった」と言ってもらえるのは、とても嬉しい。
でも、それだけじゃないんです。
「楽しい」と感じてもらうには、仕掛けが必要です。
そしてその仕掛けは、決して偶然ではなく、心理学・教育学・脳科学といった科学的な根拠のうえに組み立てられた“伝える技術”の積み重ねなのです。
私の研修は、一見すると自然体で進行しているように見えるかもしれません。
でもその背景には、細やかな設計と意図があります。
今回は、私が現場で実践している“話し方”や“場のつくり方”の裏にある仕掛けと工夫、そしてなぜ「楽しい」が学びに繋がるのかを、お話しします。
楽しさは“脳”が覚えやすい状態をつくる
「楽しい!」と感じるとき、私たちの脳ではドーパミンが分泌され、報酬系と呼ばれる神経回路が活性化します。
この状態は、記憶の定着や集中力を高めることが分かっています。
つまり、楽しい学びは「よく覚えている」だけでなく、「もっと学びたい」という内発的な動機づけにも繋がっていくのです。
聴いているだけでも嫌になるような伝え方や問い方では、研修効果を高める以前に「その気になっていない」のです。
自己決定理論と“自発的な学び”
教育心理学では、「自己決定理論」という考え方があります。
これは人が何かを学び続けるには、
•自律性(自分で選んでいる)
•有能感(できそうという感覚)
•関係性(他者とのつながり)
この3つが満たされている必要がある、というものです。
私の研修では、問いかけや選択肢を用い、参加者に「自分で考えてもらう」場面を多く設けています。
自分で選んで発言し、自分の考えを他者と共有する。
そのプロセスにこそ、「学ぶ楽しさ」が宿ります。
感情と学びの結びつき
感情は学習の質を大きく左右します。
ポジティブな感情があると、創造性や集中力が高まり、深い学びが生まれる。
逆に、退屈や不安といった感情は、思考を閉ざしてしまいます。
私は、講義の冒頭で必ず「笑い」や「共感」を生むような小話を取り入れています。
それは、感情の場を温める“仕掛け”でもあるのです。
「楽しかった!」の先にあるもの
「楽しい」と感じてもらえる時間を提供すること。
それ自体が目的ではありません。
むしろ、「楽しい」からこそ、次のステップへ進めるのです。
アイスブレイクでは、特に注意を払います。
私が目指しているのは、参加者が帰り道にこう思ってくれること・・・
「なんか元気が出た」
「さっそくあれ、試してみようかな」
こうして行動につながる学びをデザインするために、私は“楽しい”という感情を戦略的に扱っているのです。
それでは、こうした仕掛けをより具体的に、「話し方」という視点からさらに掘り下げてみましょう。
“自然体”に見せる技術 〜話し方の裏にある設計と仕掛け〜
「先生って、いつも自然体で話してますよね」
「何も準備せずに、あれだけ話せるのはすごいです」
そんなふうに言っていただくことがあります。
ありがたい言葉ですが、心の中でこう思います。
《実は、めちゃくちゃ設計してますよ(笑)》
「自然体に見える」というのは、私にとって最高の褒め言葉の一つです。
でも、その裏には明確な意図と技術があります。
私が意識している“話し方”の工夫を、心理学的な背景も交えながらご紹介します。
即時のリアクションが共感を生む
私は、相手の話に対して即座にリアクションを返すように心がけています。
「へぇ、それ面白いですね」
「なるほど、そういう考え方もありますよね」
こうした反応は、相手に「この人はちゃんと聴いてくれている」と感じさせ、場に安心感を生み出します。
これは心理学でいう「アクティブ・リスニング」の技法でもあり、信頼関係を築く土台になるのです。
たとえ話で抽象を具体へと変換する
私は抽象的な概念を話すとき、必ずと言っていいほど「たとえ話」を使います。
「改善は筋トレと一緒です。最初はキツいけど、やれば必ず力になる」
こんな一文を入れるだけで、場の空気が変わります。
相手がストンと理解する瞬間が見えるのです。
これは説得コミュニケーションの基本であり、「記憶への定着」や「納得感の向上」にも効果的です。
自己開示は“場”を溶かすカギ
私は、失敗談をよく話します。
「いや〜、最初は全然ダメでしたよ」
「昔はそれで怒られたこともあります」
この“自分の弱さ”をオープンにすることで、場が和み、受講者の緊張がふっと緩むのを感じます。
これは「自己開示の原則」に基づいた効果であり、講師が本音で語るからこそ、参加者も心を開いてくれるのです。
ところが、かつてこんな指摘をいただいたことがあります。
「失敗談を話すと、講師の威厳が下がるからやめてほしい」
正直、驚きました。
でも、私は迷いませんでした。
むしろ、失敗を“笑い”に変え、そこから“学び”を引き出すことが、講師の役割だと考えているからです。
それに……案外私、レジリエンス高いんですよね(笑)
「間(ま)」が生み出す緊張と笑い
私は話すテンポが比較的速い方ですが、笑いや結論の直前には「間(ま)」を取るようにしています。
たとえば、
「……さて、どうなったと思います?」(間)
この“間”が、聴き手の集中力を高め、期待感を膨らませるのです。
笑いを引き出すときも同じで、“静”から“動”への緩急が笑いの強度を増幅させます。
これは演劇心理学やNLPの技術でもありますが、実はどの職場でも使える、極めて実践的なスキルなのです。
研修生に考えさせる一瞬を絶妙に取り入れているのです。
イジりと肯定の絶妙なバランス
私は研修の中で、あえて受講者に軽くツッコミを入れることがあります。
でも、それは決して相手を否定するためではありません。
「吉田さん、それ正解っぽいけどちょっと違う(笑)…でも、言ってくれたおかげで話が深まりました!」
必ず最後は、“肯定”で結びます。
これが「ユーモアの社会的機能」。
笑いの中に尊重と配慮を込めることで、場は安心し、参加者がのびのびと発言できるようになるのです。
続いては、ここまでの“伝える技術”を支える、もう一段深い「メタ認知」や「場のマネジメント」について掘り下げていきます。
もしあなたが、組織の中で“伝える立場”にあるなら、ぜひ読み進めてください。
場の空気を読み、整える力 〜メタ認知と対話設計の実際〜
「この空気、少し硬いな」
「今、ちょっと集中が切れてきたかも」
私は、研修中にこうした“場の感触”を常に意識しています。
それは、講師としての感覚的なものでもありますが、実は“技術”としても明確に存在するものです。
それが「メタ認知的スキル」です。
メタ認知とは「自分を俯瞰する力」
メタ認知とは、自分自身の思考や行動を客観的に捉え、状況に応じて適切に修正していく力を指します。
私は、話しながら常に、以下のような視点で自分と場を見ています。
•今の言葉は、受講者に届いているか?
•空気が沈んでいないか?笑いが多すぎて本筋がぼやけていないか?
•どのくらい疲労が出ているか?集中力が保たれているか?
このような視点を持ちながら進行することで、受講者に合わせた“その場限りの最適な設計”が可能になるのです。
小さな違和感を見逃さない
場の空気が変わる瞬間、そこには必ず何かしらの“兆し”があります。
たとえば、受講者が一斉にペンを置いた、視線が泳いだ、うなずきが減った・・・
私はこうした変化を「サイン」として捉え、内容を一度止めたり、問いかけを入れたり、全く違うエピソードを差し込んだりします。
これにより、場の緊張を緩め、再び集中と安心を呼び戻すのです。
対話の設計~安心感があるからこそ発言できる~
私の研修では「問いかけ→考える→共有する」という構造を多用します。
このとき重要なのは、「どんな発言も否定されない場」を最初に作っておくことです。
場の空気が整っていれば、参加者は安心して自分の考えを口にできます。
逆に、心理的安全性がないと、誰も手を挙げなくなります。
「誰もが発言できる場」は、偶然できるものではなく、事前に設計された結果なのです。
ワークや演習の進め方も“空気読み”がカギ
たとえば、グループディスカッションが白熱しているとき、私は時間を延ばすことがあります。
逆に、話が弾まないときには問いを変えたり、少し“笑い”を差し込んで緊張を和らげたりします。
この判断もすべて、「空気」を感じながら、その場で組み立てています。
メタ認知力は育てられる
「それって才能ですよね?」と言われることがあります。
でも私は、これは育てられる力だと思っています。
ポイントは、話す前に「話し手の自分」と「受け手の相手」の両方の視点に立つこと。
研修や会議、プレゼンなど、人前で話すあらゆる場面で、この“もう一人の自分”を育てていくことで、場を読めるようになっていきます。
私は、こうした話し方・場づくり・仕掛けづくり、すべてを「私のスタンス」として貫くようにしています。
「話し方」は技術であり、スタンスである 〜講師としての覚悟とこれから〜
「話し方を教えてほしい」
「先生、うちの会社でも同じ研修やってもらえませんか?」
そんな声をいただくことが、ここ数年で本当に増えてきました。
でも私は、ナレッジリーンという企業に所属する一社員であり、個人として“話し方セミナー”を開講しているわけではありません。
しかも、私の話し方は、我が社の公式な研修コンテンツとしては、やや異色の部類に入ります。
それでも・・・
私はこの「話し方」に、自分の信念と情熱を込めています。
「話し方」は、在り方を映す鏡
私が大切にしているのは、上手く話すことではありません。
「伝わる」話し方。
そして、「相手の行動を引き出す」話し方です。
そのために必要なのは、言葉の技術ではなく、相手を尊重する姿勢や、一瞬一瞬を丁寧に感じ取る在り方なのだと、私は思っています。
話し方は、単なるスキルではなく「人間としての在り方」を映す鏡なのです。
楽しく、でも“深く”伝える
「楽しかった!」 それは素敵な感想です。
でも私が本当に目指しているのは、
「楽しかったけど、それだけじゃない。なぜか心に残ってる」
「今でも思い出す言葉がある」
そんな“深さ”のある学びです。
楽しいだけ、で終わらせない。
感情と記憶、思考と行動をつなぐような時間をつくること。
それが、私の講師としての覚悟です。
コラムとして伝えた理由
先に述べたとおり、私は今のところ「話し方セミナー」を個人で開催していません。
けれど、このコラムを通じて、少しでも私の想いや技術、そしてスタンスが伝わればと思い、こうして文章にしてみました。
もしこの文章を読んで、
「この人に一度話してもらいたい」
「うちのチームにも、こんな学びの時間が必要かも」
そう感じていただけたなら、それが何よりの喜びです。
そして、もしかしたら
皆さんの声によって、坂田の“話し方セミナー”が動き出す日も来るかもしれません。
その時は、あなたの「聞いてみたい」が、未来を変える一歩になるのです。

このコラムを書いたプロフェッショナル

坂田 和則
マネジメントコンサルティング2部 部長 改善ファシリテーター・マスタートレーナー
問題/課題解決を現場目線から見つめ、クライアントが気付いている原因はもちろん、その背景にある奥深い原因やメンタルモデルも意識させ、問題/課題改善モチベーションを高めます。
その先の未来には、改善レジリエンスの高い人材が活躍します。

坂田 和則
マネジメントコンサルティング2部 部長 改善ファシリテーター・マスタートレーナー
問題/課題解決を現場目線から見つめ、クライアントが気付いている原因はもちろん、その背景にある奥深い原因やメンタルモデルも意識させ、問題/課題改善モチベーションを高めます。
その先の未来には、改善レジリエンスの高い人材が活躍します。
問題/課題解決を現場目線から見つめ、クライアントが気付いている原因はもちろん、その背景にある奥深い原因やメンタルモデルも意識させ、問題/課題改善モチベーションを高めます。
その先の未来には、改善レジリエンスの高い人材が活躍します。
| 得意分野 | モチベーション・組織活性化、リーダーシップ、コーチング・ファシリテーション、コミュニケーション、ロジカルシンキング・課題解決 |
|---|---|
| 対応エリア | 全国 |
| 所在地 | 港区 |
このプロフェッショナルの関連情報
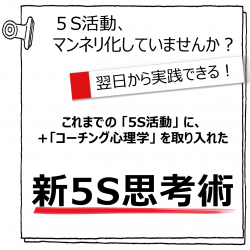
- 無料
- WEBセミナー(オンライン)
- モチベーション・組織活性化
- リーダーシップ
- コーチング・ファシリテーション
- ロジカルシンキング・課題解決
【6/3開催】 5S活動 × その気にさせる心理学 =『 新5S思考術』体験セミナー
~継続できる5S活動とは~
開催日:2025/06/03(火) 13:30 ~ 15:00
- 無料
- WEBセミナー(オンライン)
- モチベーション・組織活性化
- 安全衛生・メンタルヘルス
- コーチング・ファシリテーション
- ロジカルシンキング・課題解決
- リスクマネジメント・情報管理
【6/4~6/17視聴可能】【オンデマンド配信・無料】新時代の労働安全衛生
生産性を高める職場の安全意識とその重要性
開催日:2025/06/04(水) 00:00 ~ 2025/06/18(水) 00:00
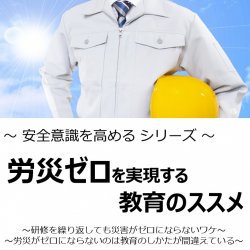
- 無料
- WEBセミナー(オンライン)
- モチベーション・組織活性化
- 安全衛生・メンタルヘルス
- コーチング・ファシリテーション
- ロジカルシンキング・課題解決
- リスクマネジメント・情報管理
【7/1開催】【無料セミナー】~ 安全意識を高める シリーズ ~
労災ゼロを実現する 教育のススメ
開催日:2025/07/01(火) 13:30 ~ 15:30
- 参考になった0
- 共感できる0
- 実践したい0
- 考えさせられる0
- 理解しやすい0
無料会員登録
記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。


 テーマで探す
テーマで探す サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 学び・実務
学び・実務





 イベント
イベント









