若手従業員の業績意識・コスト意識を高めるには

若手従業員の業績意識・コスト意識を高めるには
経営者・経営幹部の方々とお話しする中で、若手人材の育成に関する話題になることがよくあります。若手人材の育成テーマも様々ですが、生産性に着目する先も最近増えてきたためか、「若手従業員の業績意識が低い」「若手従業員のコスト意識が低い」という声を耳にします。
そのような話題でディスカッションを続けていますと、多くの場合ある結論にたどり着きます。それは「若手従業員の財務に関する基礎知識が不足している」という結論です。
もちろん企業様ごとに状況は違いますが、本コラムでは、財務に関する基礎知識の向上が、どうのように若手従業員の業績意識の醸成に繋がるのかを、ご説明させていただきます。
―1.まずは会社が存続・成長するためのメカニズムを知る
財務の基礎知識習得によるメリットは「どのように会社が存続・成長するのか知り、自身に落とし込むことができる」という点です。
若手従業員の方の業績意識・コスト意識を少しでも高めるためには、「自身が属している会社がどのようにすれば存続・成長できるのか」というメカニズムの理解を深めることが重要です。
経営者・経営幹部の方からすれば日々向き合い続ける会社の数字ですが、若手従業員の方からすると与えられた自身の目標範囲内でしか数字は見られていません(または自身の目標を理解していない場合もあります)。
財務の基礎知識習得により、企業経営における売上・コスト・利益・投資の流れが大まかにも見えてきます。細かい部分まで理解を深めるというより、まずは「なぜ全社員で売上・利益目標を目指すのか」・「なぜ売上をあげるだけではダメなのか」などについて理解するということが必要です。
なお、この際の研修で重要なのは、内容が難しすぎることなく、全員が当事者意識を持ち参加させることです。知識のインプットだけでなく、簡単な計算を入れたり、自社の前年度業績数値などを用いて理解を深めることも効果的です。
―2.自部門・自身に与えられている役割を理解する。
自身が属する会社が存続・成長するメカニズムの理解を深めることで、自部門・自身の役割の理解を深めることも可能です。
全社の目指す目標は多くの場合、各事業部にて分解され、各個人目標へ落とし込まれております。しかし、若手従業員の方からすると、財務の基礎知識をインプットする前に、「会社から勝手に自身に振られた目標」ととらえる方も少なくないと感じます。研修を通して会社存続・成長という大きな視点を理解した後は、会社に対する自身の貢献度をより意識しながら業務ができるようになります。そしてその中で、自身の役割が明確になり日常業務の取り組み方を変えていく狙いもあります。
ベテラン社員が若手従業員に財務研修を実施した後に、若手従業員の方が日々自部門の業績状況を社内掲示板に手書き記載している先もありました。その企業の若手従業員の方と話をする機会がありましたが、「研修を受けたことで、入社したこの会社における自身の役割と求めらていることが明確になった」「自身の目標達成で全社へ貢献したい」などの考えを聞くことができました。
少し余談になりますが、その企業においては若手従業員が掲載してくれた業績状況をもとに、目標達成に向けて日々メンバー全員で当日の業務内容を確認しあっているそうです。このような風土も業績意識を高めるポイントなのかもしれません。
また、財務知識習得において視点が変わったことで、コスト意識の醸成にもつながった事例もあります。
ある企業の若手営業パーソンにおいては、これまで売上をあげることだけに専念していたようなのですが、財務研修を受講後に考え方の変化が見られました。聞くと財務研修の中で財務分析のケーススタディを行った際に、製品の利益率を考える項目が合ったそうなのですが、その問題の視点から派生して考えられ、自身の営業費用(交通費・接待など)に対する売上成果は利益面から見て効率が良いのか考え直すようになりました。
このように、財務の基礎知識の向上を行うことで、若手従業員の業績意識・コスト意識が高まった事例は、他にも多くありました。ただし、これらの企業様にお聞きしますと、すぐにこのような良い変化があったわけではなく、考え方の定着・実践までにはある程度の期間がかかり、財務研修は継続的に実施し、研修以外の場でも若手従業員には数字について意識させるようなコミュニケーションも継続的に実施していたと聞きます。
やはり、人材育成には財務研修に関わらず、継続的な実施と、研修以外も含めて意識醸成する関わり方が必要なのだと改めて感じました。
しかし、間違いなく言えるのは「知らないことは意識できない」ということです。理解させる手段は研修か日々の関りかについては各企業様ごとに異なると感じますが、意識を変えて行動を変えていくためにまずは知識の習得を促すということは変わりません。
この度は財務研修という視点をご紹介しましたが、ぜひ貴社の取り組みとしても考えてみてはいかがでしょうか。
タナベコンサルティングの「財務・アカウンティング研修」では、財務会計や管理会計、経営分析の基礎的な知識だけでなく、それらの手法や考え方を体系的に習得できます。さらに、ケーススタディやグループワーク、ビジネスゲームなどの実践的な方法を通じて、実践的なアカウンティング・ファイナンススキルを身に付けることができます。
貴社の課題にカスタマイズしたカリキュラムをご提供しておりますので、ファイナンス思考の人材育成にご興味がございましたら、ぜひ「財務・アカウンティング研修」サービスをご検討ください。
※本コラムは瀧口が、タナベコンサルティングのコーポレートファイナンス・M&Aの情報サイトにて連載している記事を転載したものです。
【コンサルタント紹介】
株式会社タナベコンサルティング
コーポレートファイナンスコンサルティング事業部 ゼネラルマネジャー
瀧口 泰寛
金融機関などのアライアンス先を通じ、全国の経営者の様々な悩みを解決する「アライアンスコンサルティング」に携わる。また、金融機関の抱える会員組織の立ち上げ・活性化支援や、金融機関職員の教育にも多くの実績を持つ。「経営を未来へつなぐ」を信条に、顧客に寄り添ったコンサルティングに定評がある。
主な実績
・地方銀行での2~5年目行員の育成プログラム設計支援コンサルティング
・次世代役員向けの教育プログラム設計支援コンサルティング
・製造業向け営業改善支援コンサルティング
・M&A売り手FA支援コンサルティング
- 経営戦略・経営管理
- 法改正対策・助成金
- リーダーシップ
- ロジカルシンキング・課題解決
- 財務・税務・資産管理
新しい経営技術で企業価値向上を実現する。
コーポレートファイナンス領域において、資本政策・組織再編・M&A・PMIまでワンストップでご支援。
タナベコンサルティングでは、グループ経営、組織再編からコーポレートガバナンス、海外戦略、M&A、DXなど企業価値向上のために必要なコンサルティングサービスを提供し、単純な手段に留まらない、企業の経営強化の支援を行います。
タナベコンサルティング コーポレートファイナンスコンサルティング事業部 コンサルタント(コンサルタント) コンサルタント

| 対応エリア | 全国 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪市淀川区 |
このプロフェッショナルのコラム(テーマ)
このプロフェッショナルの関連情報
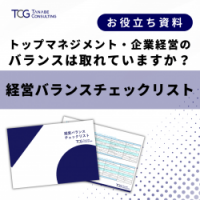
- お役立ちツール
- 経営者・経営幹部研修
- 組織診断・活性化
- ロジカルシンキング・課題解決
【お役立ち資料】トップマネジメント・企業経営のバランスは取れていますか?「経営バランスチェックリスト」
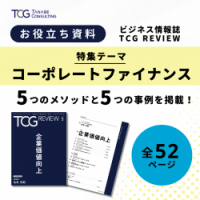
- レポート・調査データ
- 財務・税務・資産管理担当向け
- 経営者・経営幹部研修
- 防災・事業継続計画
【お役立ち資料】企業価値向上(ビジネス情報誌『TCG REVIEW』全52頁)
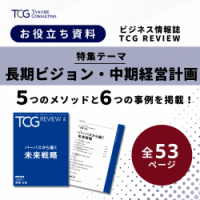
- レポート・調査データ
- 組織開発
- 経営者・経営幹部研修
- 防災・事業継続計画






