- お役立ちツール
- コンプライアンス
- 労使関係
- 法務・知財
障害者雇用の“もしも”に備える─ユニオン・労働局対応に必要な5つの視点合理的配慮・配属・退職…企業はどう動くべきか?
障害者雇用のリスクと対応を「制度+実務」の両面から整理し、トラブルを未然に防ぐための“判断軸と仕組み”をわかりやすく解説しました。
合理的配慮、雇止め、ユニオン対応、記録の整備、初動対応──あらゆる“もしも”に、企業としての判断力を高めたい方におすすめ。チェックリストやNG行動例も掲載しました。
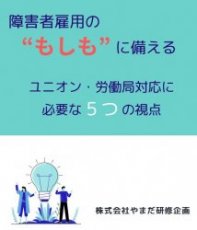
ダウンロード資料詳細
障害者雇用の現場では今、
「よかれと思って対応したのに“差別的だ”と言われた」
「“配慮は不要”と言われたのに、後から“配慮が足りない”と訴えられた」
といった、“すれ違い”が深刻なトラブルへ発展するケースが静かに増えています。
特に、精神障害者や発達障害者の雇用が急増する今、企業には
・「合理的配慮」への正しい理解と対応力
・記録・初動・体制といった“見えるマネジメント”
・ユニオン・労働局・内部通報など“もしも”への備え
が、これまで以上に求められています。
法改正や社会の変化を背景に、精神障害者の雇用は年々増加しています。企業の現場では、「支援の仕方がわからない」「配慮したつもりがトラブルになった」といった声があとを絶ちません。
本資料では、障害者雇用のリスクと対応を「制度+実務」の両面から整理し、トラブルを未然に防ぐための“判断軸と仕組み”をわかりやすく解説しました。
合理的配慮、雇止め、ユニオン対応、記録の整備、初動対応──あらゆる“もしも”に、企業としての判断力を高めたい方におすすめです。現場で「すぐに使える」チェックリストやNG行動例も掲載しました。社内研修や管理職教育にも活用いただけます。
<資料で学べる3つの実践ポイント>
1|トラブルを未然に防ぐ“5つの視点”とは?
・差別・不利益取り扱いに該当しないための基本フレーム
・「説明できる配慮」「一貫した対応」を実現する記録と判断軸
・現場で混同されやすい“支援とマネジメント”の線引き
2|“意図と受け止めのズレ”に潜むトラブルの兆し
・「配慮のつもり」が「差別的対応」ととられたケース
・退職合意が「退職強要」として訴えられた背景
・「配慮不要」と言っていた社員から、後に「配慮がなかった」とクレーム
3|ユニオン・労働局対応に求められる“初動”と“記録”の備え
・初動対応でやってしまいがちなNG行動
・採用〜退職の各フェーズで必要な○○のポイント
・「社内体制チェックリスト」付き
このような方におすすめです
・「配慮したつもりだったのに・・・」と感じたことがある管理職・OJT担当者
・退職やトラブル時に、ユニオンや労働局との対応に不安がある労務担当者
・トラブルを未然に防ぐ“組織としての対応力”を高めたいと考える方
このダウンロード資料に関係するセミナー
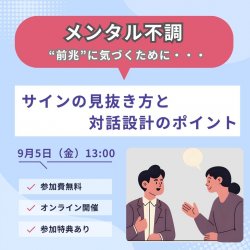
- 無料
- WEBセミナー(オンライン)
- 労務・賃金
- 安全衛生・メンタルヘルス
- コミュニケーション
『メンタル不調の“前兆”に気づく──信頼を育む1on1の技法』
「何も言ってくれなかった」の前にできること。サインの見抜き方と対話設計
この会社のダウンロード資料

- お役立ちツール
- コンプライアンス
- 労使関係
- リスクマネジメント・情報管理


 サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 調査
調査 人事辞典
人事辞典 イベント
イベント



