研修投資のムダをなくす!真の効果を生むキャリア研修とは
すべての研修の土台となる「キャリア開発研修」の考え方
「最近、若手の離職が相次いでいる」「ハラスメントが発生し、管理職研修を急遽実施することに」「セキュリティ事故が起きて全社員向け研修が必要になった」
人事の皆さんなら、このような状況に一度は直面されたことがあるのではないでしょうか。研修の多くは、「問題が起きたから」「トラブル防止のため」という緊急策型・戒め型で企画されがちです。
しかし、この発想では研修が本来持つ価値や可能性を十分に活かしきれません。
受講者の心理的負担は大きく、必要に駆られて「やらされる研修」は、効果が出にくいことが多くのデータで証明されています。会社にとって「守り」だけでなく、「攻め」のツールとして実行される研修を企画したいところ。それを最も力強く後押しするのが キャリア開発研修 です。
社員が自走する組織づくりの第一歩は「キャリア開発研修」
研修には、さまざまな切り口があります。
- 階層別(新人研修/中堅研修/管理職研修/役員研修)
- スキル別(営業力強化/マネジメント力向上/デジタルスキル研修)
- 知識習得(業務知識/業界理解/商品知識/法務・会計基礎)
- 全社共通(理念/コンプライアンス/情報セキュリティ/ハラスメント防止)
これらは本来、社員と組織の持続的な成長を支えるツールです。ですが現場では、
- 問題が起きてから急いで入れる
- 内容が表面的・一方通行
- やりっぱなしで現場実践や定着がない
といった課題が目立ちます。
この背景にあるのは、計画性の欠如と学びの主体が社員にないという2つの要素です。
社員が「学ぶオーナー」になるために——キャリア開発研修の役割
「学ばされる」のではなく、「自分のために学ぶ」。その文化を会社に浸透させるための起点がキャリア開発研修です。
キャリア開発研修は単に自己分析をする場ではありません。
- 自分が何をしたいのか(Will)
- 自分が何を強み・弱みとして持っているか(Can)
- 組織や社会から何を期待されているか(Must)
この3つを棚卸し、言語化し、これからのキャリアを自らのオーナーシップで描いていくための土台です。
キャリア開発研修を通じて、「研修とは自分の成長や目標達成に必要なものだ」と腑に落ちると、後続のスキル研修やOJT/Off-JTに対する社員の向き合い方が劇的に変わります。
研修設計のつの5問い——「何のためにどこまで・誰に・何を・いつ・どうやって」
研修を導入する際は、以下の5つの問いを立てることが重要です。
- 何のためにどこまで(研修の目的を明確に、理想のゴール・状態目標を描く)
- 誰に(どの階層・どのポジション・どのタイプの社員か)
- 何を(知識・スキル・マインドの何を伸ばすのか)
- いつ(どのタイミングで、どのキャリア段階で行うのか)
- どうやって(講師/時間/頻度/講義形式/e-learning/OJTとの連携はどうするか)
とくに最後の「どうやって」は、研修の実践・定着までを詳細に設計することが重要です。
例えば研修後に、
- 上司とのキャリア面談をセットする
- 翌年度の目標設定と紐づける
- 定期的に理解度・実践度・定着度のテスト/アンケートを行う
- 研修で作成したキャリアプランを社内で共有する場を設ける
といった工夫をすることで、単発のイベントで終わらせない設計が可能です。
キャリア開発研修は「一方通行ではない」——対話と実践が鍵
効果的なキャリア開発研修の特徴は以下です。
- 対話・内省の機会がある
- ワークシート、ペア対話、グループ対話などを通じ、自分の価値観・強み・課題を言語化する
- 漠然とした不安や焦りが明確になり、スッキリする
- 似たような境遇の社員と悩みや夢を共有することで刺激や励み、癒しを得る
- 多様な視点を得られる
- 他者の話を聞くことで自分の視野が広がり、気づきが深まる
- 先輩・ロールモデル・他社事例に触れながら、キャリアイメージを持たせる
- 考えもしなかった/知らなかった将来のステップや考え方を知ることができる
- 実践を見据える
- 単なる「良い話」で終わらず、「明日から何を試すか」が具体化される
- 日常の仕事が、理想の将来への一歩になっていると思える
- 自分次第だと思えることで、自分の将来に期待が高まる
- 課せられた目標、日々の挑戦、研修に意欲的になる
キャリア開発研修では、各社・現場ごとの状況を細かくとらえながら、内省を深めていくワークを多く設計しましょう。
理想のキャリア開発研修は、単なるやってきたことの振り返りだけでなく、また従業員のやりたい/やりたくないというわがままを通すものではなく、社員一人ひとりが「課せられた職務や役割」に対して前向きに「自分事化」できるような仕掛けを盛り込むことが大切です。
たとえば、「我々の顧客は誰か」「その人たちは、何に困っているのか」「我々に何を求めているのか」「その人たちへ“最高の仕事“を提供するとしたら、いつまでに・何を・どのくらい行うことか」「この仕事を支えてくれている仲間(社内外)は誰か」「彼らが”最高に喜ぶ“仕事の進め方とは」「同僚・先輩が行った”最高の仕事“とは」「彼らに恩返しをするとしたら」などのワークに全員で向き合い、新しい視点や忘れかけていた情熱を現業に取り戻します。
これだけで、昨日までの同じ仕事が、少し異なる世界に見えてくるので不思議なものです。
学びの効果を最大化する「研修の連携」
研修単体では、効果は限定的です。以下のような連携が、効果を何倍にも引き上げます。
- OJTとの連携
- 研修で気づいた学びを現場で試す/上司が支援する。
- Off-JTとの連携
- 外部講座、e-learning、勉強会など、社外資源を活用する。
- 評価・目標管理との連携
- 学びや挑戦を評価や目標設定に反映する。
- 組織開発との連携
- 個人のキャリア開発と組織の方向性を接続させる。
等々、こうした連携の起点として、キャリア開発研修は最も有効です。
なぜなら、個人の「学ぶ意味」「目指す方向」を明確にしておくことで、あらゆる育成施策が本人にとって意味あるものになるからです。また上司や同僚もそれらを共有することで、その道を応援したり、そこにつながる機会を何かしら提供することが増え、意欲的なキャリア形成が組織活性化につながるからです。本人のやりたいこと・向いていること・できることを活かした、現業での仕事の進め方・役割・貢献の範囲を提供して、共に組織の未来を創ってもらいます。
「将来のキャリアを考えることで、離職が増えるのではないか」という疑念は、むしろ逆であることがお分かりかと思います。
「学ぶ組織」をつくる第一歩としてのキャリア開発研修
多くの会社が、「必要だから」「問題が起きたから」と研修を導入します。
ですが、これからの人事に求められるのは社員の主体的な学びを支援する設計者であり、会社の学び文化をつくるファシリテーターです。
キャリア開発研修はその第一歩です。
社員がキャリアのオーナーシップを持てば、
社員の学びは自走し、
研修の効果は持続し、
組織全体の活力は底上げされます。
単なる「自己分析」や「将来の棚卸し」にとどまらない、未来志向のキャリア開発研修を、ぜひ貴社の育成戦略に組み込んでみませんか。
このコラムを書いたプロフェッショナル

高原 朋美
ガイアモーレ株式会社提携講師(株式会社インフィニティ 代表取締役)
大手人材会社にて転職支援、人事、公共就労支援責任者を経て2010年独立。経営者・人事向けコンサル、プロコーチやOJTトレーナーの育成・SV、採用支援、面接官指導、働く環境整備・人事部門の体制構築、年200件超の各種研修・講演・コンサル実施

高原 朋美
ガイアモーレ株式会社提携講師(株式会社インフィニティ 代表取締役)
大手人材会社にて転職支援、人事、公共就労支援責任者を経て2010年独立。経営者・人事向けコンサル、プロコーチやOJTトレーナーの育成・SV、採用支援、面接官指導、働く環境整備・人事部門の体制構築、年200件超の各種研修・講演・コンサル実施
大手人材会社にて転職支援、人事、公共就労支援責任者を経て2010年独立。経営者・人事向けコンサル、プロコーチやOJTトレーナーの育成・SV、採用支援、面接官指導、働く環境整備・人事部門の体制構築、年200件超の各種研修・講演・コンサル実施
| 得意分野 | モチベーション・組織活性化、人材採用、キャリア開発、コーチング・ファシリテーション、コミュニケーション |
|---|---|
| 対応エリア | 全国 |
| 所在地 | 港区 |
このプロフェッショナルの関連情報
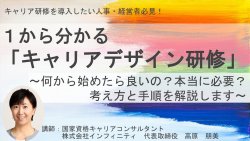
- 無料
- WEBセミナー(オンライン)
- 経営戦略・経営管理
- モチベーション・組織活性化
- 人事考課・目標管理
- キャリア開発
- コミュニケーション
キャリア研修を導入したい人事・経営者の方必見!
1から分かる「キャリアデザイン研修」
何から始めたら良いの?本当に必要?考え方と手順を解説します。
開催日:2025/08/05(火) 10:30 ~ 11:30
- 参考になった0
- 共感できる0
- 実践したい0
- 考えさせられる0
- 理解しやすい0
無料会員登録
記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。


 テーマで探す
テーマで探す サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 学び・実務
学び・実務





 イベント
イベント









