借り上げ社宅|社宅規定の作り方 ─ 契約編 その2 ─
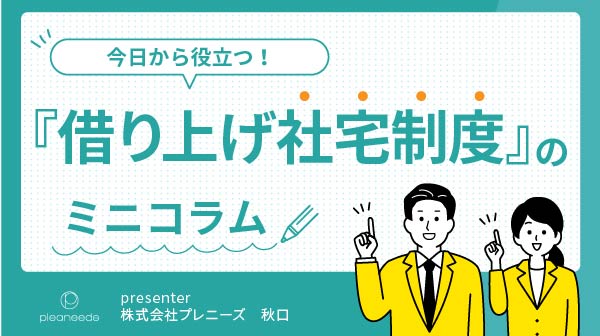
こんにちは、プレニーズ秋口です。
引き続き『社宅規定の作り方シリーズ』契約編として、契約時の取り決めとしてよく掲げられている項目をピックアップ。法人契約するにあたってどのような点に配慮すれば良いのか?なぜその項目を設定する必要があるのか?をご確認ください。
社宅規定の作り方 ~契約編~
※1~4については前回のコラムをご参照ください
──────────────────
(5) 保証会社/連帯保証人
──────────────────
万が一家賃滞納があった際の取り決めをする項目です。保証会社や連帯保証人の設定が有でも契約していいのか、その場合誰が連帯保証人となるのかを定めます。
【 お部屋の契約で大事な“信用” 】
保証会社でも連帯保証人でも、設定する大きな理由は同じで「家賃滞納の可能性がある」からです。法人契約の場合は企業に対しての信用が重要になるため「この企業なら家賃滞納しないだろう」と判断されれば保証会社(連帯保証人)の設定無しとできます。
とはいえ基準は厳しく、<資本金1億円以上>を基本として<上場企業><従業員1000人以上><起業から30年以上>とある程度の規模が必要です。高い法人税を払えるならそれだけ会社に体力があり事業も安定しているだろうと判断されるため、保証会社や連帯保証人を無しにする交渉も通りやすくなります。
ただし最終的には管理会社の判断に委ねられるので、社宅規定では<保証会社/連帯保証人無し>を基本としつつ、もし必要になった場合は誰がなるか?を併記するとよいでしょう。
【 連帯保証人は誰がなるのか 】
基本的にまず会社代表、次に入居者本人が指定されます。
会社代表を設定した場合に注意したいのが後々代表が変わった際の対処です。契約時の会社代表の名前は使用できなくなりますから、全ての契約をチェックし連帯保証人変更の手続きを取らなければいけません。件数が多いと大幅に時間をとられて手間になるためご注意ください。
【 両方用意が必要になることも! 】
管理会社や貸主からすると個人の連帯保証人よりも保証会社が付いてくれた方が安心できます。さらに言えば保証会社からすると連帯保証人がいてくれた方が安心です。
そのためよほど慎重な物件では「保証会社有り+保証会社に対する連帯保証人有り」とどちらも設定が必要になります。この点に関してはそれぞれの立場から見たら好ましい条件が異なるため、交渉して折り合いをつけるしかありません。
──────────────────
(6)海外居住貸主の物件
──────────────────
お部屋の貸主の居住先が海外でも問題ないか否かを決める項目です。近年投資目的で日本の不動産を買い求める海外オーナーが増加しており、お部屋探しで遭遇する確率は上がっています。
「連絡は取りづらそうだけど……どのみち管理会社を挟むから関係ないよね」
「気にしたことなかった、どっちでもいいんじゃない?」
これから社宅導入をご検討の企業様、このようになんとなくOKにしようとしていませんか?ここにも意外と落とし穴が隠れています。
【 海外居住でも日本国内で納税が必要 】
「非居住者や外国法人(以下「非居住者等」といいます。)から日本国内にある不動産を借り受け、日本国内で賃借料を支払う者は、法人はもちろん個人(事業者かどうかは問いません。)であっても、その支払の際20.42%の税率により計算した額の所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。」(国税庁『非居住者等に不動産の賃借料を支払ったとき』より)
日本国内にある物件を賃借したことを理由として非居住者へ賃料を支払うと、それがオーナーの所得になるため“国内源泉所得”とみなされます。このとき借主が“源泉徴収義務者”とされ、源泉徴収をして税金を納付する必要が出てくるのです。
「原則として支払日の翌月10日までに納税すること」など決まりもあり大幅な手間になるため社宅規定では不可にしておくのがオススメです。

──────────────────
(7)入居者入替特約
──────────────────
一定のエリア内で社宅利用希望者が複数いる場合に設定しておくと便利な項目です。
Aさんが住んでいた社宅から引っ越すことになった際、Bさんから「じゃあ代わりに私が住みたいです!」と要望がくることも考えられます。このとき、一度Aさんが解約してすぐにBさんが新規契約‥……というのは、手続きが重なる上に初期費用・退去費用が無駄にかさんで借主も貸主も手間ですよね。
契約内容に「名義はそのまま、入居者だけ変更できる」という特約が入っていると、解約・新規契約の手続きを省くことができます。
【 企業様によっては特にオススメ 】
工場や作業系など短期で勤務している従業員が多い現場や、人材派遣・人材サービスなどの業種は人の入れ替えが多いため、あらかじめ入居者入替特約を付けておくと後々の手続きが楽になります。逆に、入れ替えが考えにくい業種であればこの項目は設定しなくてもよいでしょう。
なお、特約が入っている場合でも実際に入居者を入れ替える際は事前に管理会社への相談が必要なのでご注意ください。
──────────────────
(8)インターネット、水道代等の支払い
──────────────────
この2点はインフラ系の中でも別途請求されることがあります。細かい部分になりますが、これらの支払いに関してもルールを決めましょう。後々のトラブルを防ぐことができます。
【 支払うのは基本的に“入居者” 】
社宅は会社管理なので賃料・敷金などの土台部分は会社負担となりますが、入居者に紐づく費用の多くは入居者負担となります。支払い方法は基本的に以下2パターンです。
- 完全入居者負担。入居者が支払い手続きを行う。
- 入居者負担。ただし法人が一旦立替えて支払い、後で入居者から徴収する。
【 書面に残して“誰が見ても明確”に 】
支払方法が決まったら契約書、及び社宅利用規約に記載しましょう。契約書の中では<水道代(入居者負担):〇〇円>のように誰が支払うのか明確にしておくと安心です。万が一滞納があった際に法人へ支払責任が発生してしまうことを防げますし、社宅担当者や経理担当者の引継ぎがあった際にも状況が把握しやすいです。
また、物件によって記載があったり無かったり、支払いが法人だったり入居者だったり、徴収したりしなかったり……とバラバラになれば当然現場は混乱してしまいます。一部の物件だけ法人立替をしていたら「自分は面倒な手続きをしているのに!」と社員間で不満が出てしまうかもしれません。細かい点になりますが、統一するのがおススメです。
法人契約、取り決めは慎重に!
スムーズな管理を行う事、そしてトラブルを未然に防ぐためには、細かな部分についても設定を行うことが大切です。
会社の名義で契約を行えば、問題が発生した時会社に不利益が生じてしまうことも懸念されます。放置すれば甚大な被害となってしまう可能性も……。
そうならないためには想定しえる不安要素を一つ一つ潰していけば、被害を最小限に抑えることができます。
社宅規定では「どんな部屋なら借りていいのか」「どんな契約なら結んでいいのか」を明確にしましょう。基準があればお部屋探しがしやすく管理もスムーズで、社内の誰にとっても嬉しい福利厚生となってくれます!
このコラムを書いたプロフェッショナル

秋口 朱里
株式会社プレニーズ 法人営業課 社宅コンサルタント
社宅管理のことなら秋口へ!
企業様一社一社の個性に寄り添い、現場の声を大切にしながら実践的なアドバイスをお届けしています。『笑顔』と『経験』を武器に課題解決のお手伝いをさせていただきますので、お気軽にご相談ください!

秋口 朱里
株式会社プレニーズ 法人営業課 社宅コンサルタント
社宅管理のことなら秋口へ!
企業様一社一社の個性に寄り添い、現場の声を大切にしながら実践的なアドバイスをお届けしています。『笑顔』と『経験』を武器に課題解決のお手伝いをさせていただきますので、お気軽にご相談ください!
社宅管理のことなら秋口へ!
企業様一社一社の個性に寄り添い、現場の声を大切にしながら実践的なアドバイスをお届けしています。『笑顔』と『経験』を武器に課題解決のお手伝いをさせていただきますので、お気軽にご相談ください!
| 得意分野 | モチベーション・組織活性化、福利厚生、マネジメント、コミュニケーション、ビジネスマナー・基礎 |
|---|---|
| 対応エリア | 全国 |
| 所在地 | 千代田区神田須田町 |
このプロフェッショナルの関連情報

- 無料
- WEBセミナー(オンライン)
- 福利厚生
- 人材採用
- マネジメント
- その他
【借り上げ社宅】「こんなときどうしたらいい?」社宅管理にまつわる疑問・質問を解決!管理運用のヒントを探しませんか?|個別対応|
開催日:2025/08/01(金) 10:00 ~ 2026/07/31(金) 17:00
- 参考になった0
- 共感できる0
- 実践したい0
- 考えさせられる0
- 理解しやすい0
無料会員登録
記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。


 テーマで探す
テーマで探す サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 学び・実務
学び・実務





 イベント
イベント









