自社ならではの「目指したい状態」を描くには?
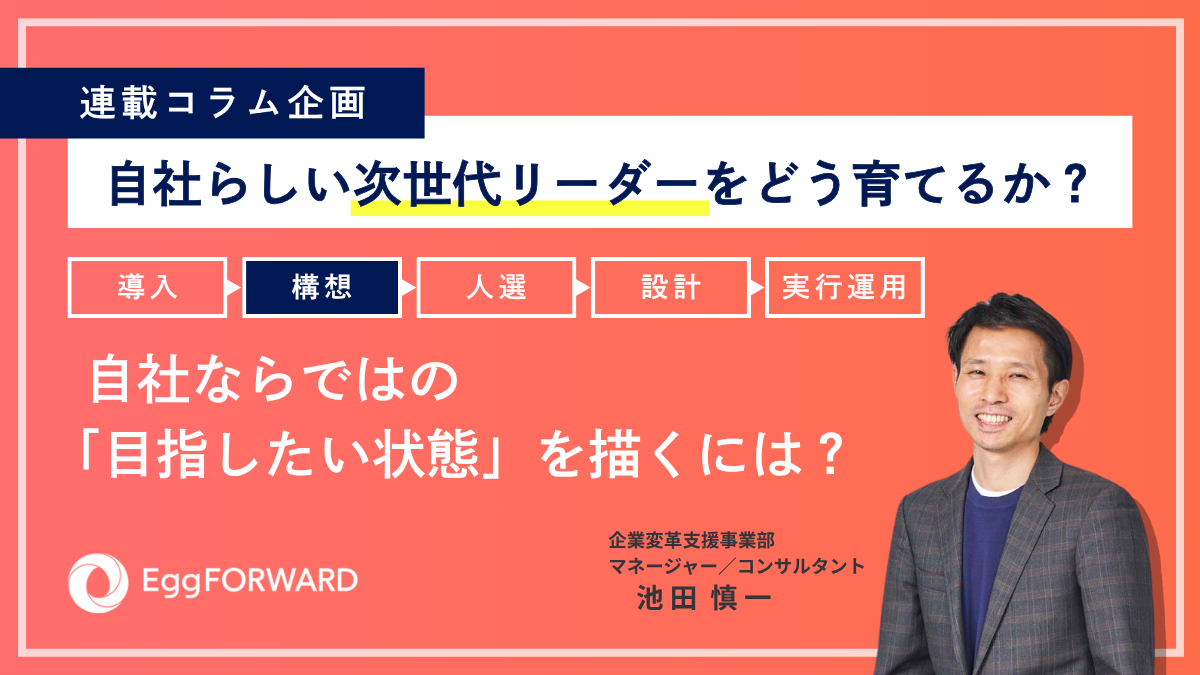
自社らしい次世代リーダーをどう育てるか?
【構想編】自社ならではの「目指したい状態」を描くには?
本シリーズでは、「自社らしさ」を軸にした次世代リーダー育成の在り方を、紐解いていきます。エッグフォワードによる多様な企業との取り組み事例をもとに、育成の構想・設計・実行における実践的な観点を紹介します。
前回の記事では、「会社の未来を担う人材」をどう育てるか、というテーマのもと、 “義務対応”ではなく、“自社らしさ”に根差した探求活動としてのリーダー育成の在り方について考察しました。今回はその第一歩として、自社のビジョンに根差した「目指したい姿」をどのように描き出すのか? そして、それを軸に育成全体像をどのように構想していくのか?という観点から紐解いていきます。
未来を担うリーダー育成の出発点とは
あなたの組織では、「会社・組織の未来を担うリーダーを育てる」取り組みに着手する際、何を起点にされているだろうか。
我々が多くの企業様とご一緒してきた中で感じる「能動的で、一貫性のある取り組み」の共通点は、「自社ならではの強固なストーリー」から出発しているケースが多い、ということだ。
自社固有のストーリーから、「目指す姿」を言語化する
そのストーリーとは例えば、
-
創業から今に至るまでの経緯や関係者の想い、
-
自社を取り巻くビジネス環境の変化や事業特性、
-
経営戦略や守り続けたいこだわり・新たに踏み出したい方向性
といった、自社ならではの過去・現在・未来にまたがる一連の流れである。
これらと真摯に向き合うことで、「目指す組織の状態」や「未来の経営をリードする人物像」などについて、独自の、腹落ちした方針を描けるようになる。
たとえば、
-
「創業からの価値を守りながら、持続的に成長したい」会社と、
-
「これまでにない領域に挑み、新しい価値を生み出したい」会社
では、求める人物像や要員計画の描き方も、大きく変わってくるのである。
経営思想によって変わる「未来の描き方」
未来の描き方も、会社によって様々だ。
王道としては、事業戦略から逆算して要員計画を明確にし、重要ポストやその要件を言語化する進め方がある。
一方で、「中長期戦略は定めず、アジャイルに経営する」企業では、計画よりも「どんな人物を育てたいか」を明確にし、どんな変化にも挑戦できる人材プールを確保するアプローチが有効になる。このような場合には、社内にいるロールモデルの棚卸しやインタビューを通じて、「輩出したい人物像」に迫るのが効果的だ。
「ありたい状態」を描く主導者は誰か?
覚悟ある経営トップの関与がカギを握る
このように、「自社ならではの未来」を真剣に描こうとすると、経営トップや創業時を知る人物、将来を担うステークホルダーなど、多くの関係者の想いが交錯してくることになる。
だからこそ、取り組みの起点においては、誰が「目指す姿」を定めるのか、その主体を明確にすることが重要だ。そして初期段階においては、やはり経営トップの意思と覚悟が不可欠である。
たとえば、人事部門が起点となる場合でも、経営トップと早期に対話し、方針の一致とコミットメントを引き出すプロセスがなければ、施策が形骸化したり、頓挫する可能性もある。
逆に経営トップが主体となるケースでも、社外の声や体裁ばかりを意識すると、「可もなく不可もなく」の一般的な設計に終始してしまい、自社らしさを反映できないリスクもある。
もちろん、創業経緯や多様な関係者の想い、制約事項など、考慮すべき観点は多い。ただ、最終的に未来のあり方を「見定め、決める」ことができるのは、やはり経営者なのだ。
とはいえ、人事部門や育成担当者が、こうした経営トップの関与をどう引き出すか?は、多くの企業でぶつかるリアルな壁でもある。私たちがご一緒してきた中でも、「社内で育成の優先度が伝わらない」「経営者が忙しく巻き込めない」といった声は数多く耳にしてきた。
そのようなときには、まず「なぜこの取り組みが会社の未来に不可欠なのか?」を、経営者の視座に立ってあらためて言語化し、可能な形で小さな対話の場を設けることから始めるとよい。経営者にとっては、自らがコミットする意味や価値が十分に伝わっていないだけの場合も少なくない。だからこそ、最初から完璧な合意形成を目指すのではなく、人事と経営の関係性を少しずつ耕しながら、意志の共有を重ねていく。そうした対話のプロセスそのものを、「育成に向けた取り組みの一部」として捉えておくことが大切だ。
人事・事業・HRBPの連携が構想を形にする
また、将来のリーダー層に求められる人物像は、「会社として大切にしてきた思想や、体現したい価値観・こだわり」といった要素だけでなく、「各事業の成長や変革を推進できる実践力」も織り交ぜる必要がある。
この両輪を踏まえた人物像の設計には、経営者と人材開発部門のコミュニケーションだけでなく、事業部門やHRBPと連携を行うことも重要となる。
実際、多くの企業においては、育成全体像の構築や育成機会の検討にあたり、人事・育成のプロである人材開発部門と、事業視点で現場ニーズを把握する事業部内の育成担当、さらにはHRの視点で橋渡しを担うHRBPが連携する体制が成果を生みやすい。
こうした多面的な視座を統合しながら進めることによって、現実的で骨太な育成の構想が、より実効性のある「育成方針や機会設計」として立ち上がっていくのである。
取り組みの“想い”を象徴する一文としてコンセプトを言語化する
「ありたき状態」を描いた先には、「要員計画」や「人物像」が整理されることになるが、加えて「取り組みコンセプト」という象徴的なキーセンテンスを言語化するケースも多い。
これは、「選定・育成・モニタリングを進めるプロジェクトの、自社にとっての目的を簡潔に示す言葉」として機能する。
例えば「好奇心を起点に問いを立て、組織の未来を切り拓く人材を育む」といった短いフレーズが、全体の意思統一や判断基準として機能するようになる。やや抽象度は高いが、取り組みを進める中で分岐点にったとき、立ち戻る「想いの源泉」があることで、プロジェクトの一貫性が保たれやすくなるのである。
次回は【人選編】として、言語化したコンセプトや構想に基づく、人選の基準づくり・候補者の発掘・抜擢までを紐解いていきます。
このコラムを書いたプロフェッショナル

池田 慎一
エッグフォワード株式会社 企業変革事業部 マネージャー
リーダーや若手の育成、マネジメント強化、理念・カルチャー浸透など、企業の優先課題に応じて幅広く支援を行っています。
お客様固有の歴史や想い、組織文化に根ざした「ありたき姿」の言語化と、その実現に向けた構想・実行の伴走を得意としています。

池田 慎一
エッグフォワード株式会社 企業変革事業部 マネージャー
リーダーや若手の育成、マネジメント強化、理念・カルチャー浸透など、企業の優先課題に応じて幅広く支援を行っています。
お客様固有の歴史や想い、組織文化に根ざした「ありたき姿」の言語化と、その実現に向けた構想・実行の伴走を得意としています。
リーダーや若手の育成、マネジメント強化、理念・カルチャー浸透など、企業の優先課題に応じて幅広く支援を行っています。
お客様固有の歴史や想い、組織文化に根ざした「ありたき姿」の言語化と、その実現に向けた構想・実行の伴走を得意としています。
| 得意分野 | リーダーシップ、マネジメント、コーチング・ファシリテーション、チームビルディング、ロジカルシンキング・課題解決 |
|---|---|
| 対応エリア | 全国 |
| 所在地 | 渋谷区 |
- 参考になった0
- 共感できる0
- 実践したい0
- 考えさせられる0
- 理解しやすい0
無料会員登録
記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。


 テーマで探す
テーマで探す サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 学び・実務
学び・実務




 イベント
イベント









