真の「戦略人事」を実現するため、いま人事パーソンには何が求められるのか
- 髙倉 千春氏(ロート製薬 元取締役(CHRO)、高倉&Company合同会社 共同代表)
- 伊達 洋駆氏(株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役)

長年にわたり「戦略人事」の重要性が叫ばれてきたが、実現できている企業は多くはない。しかし環境が激しく変化する昨今、人事には真の「戦略人事」の実現が求められている。では、なかなかうまく進まない原因はどこにあるのか。人事は、どのような視点や心構えを持って組織や従業員に向き合い、「戦略人事」に取り組んでいけばいいのか。長年にわたり「戦略人事」を実践してきた高倉&Companyの髙倉氏が、持論と事例を紹介。ビジネスリサーチラボの伊達氏が、学術的・データ分析の視点から実現に向けた議論を深めた。

(たかくら ちはる)農林水産省入省後、米国Georgetown大学にてMBA取得。コンサルティング会社を経て、外資系製薬・医療機器企業の人事部長を歴任。味の素グローバル人事部長、ロート製薬取締役・CHROなどを経て現職。将来の経営を見据えた戦略的な人事戦略、人材育成を推進。著書に『人事変革ストーリー』(光文社)がある。

(だて ようく)神戸大学大学院経営学研究科博士前期課程修了。2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。組織・人事領域において調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知を活用した組織サーベイや人事データ分析を提供。近著に『60分でわかる!心理的安全性超入門』(技術評論社)など。
注目すべき「アジャイル型人事」という概念
まず、自律的な組織作りのための人材育成・組織開発を支援しているITプレナーズジャパン・アジアパシフィックの最上千佳子氏から、本セッションのイントロダクションが語られた。
「戦略人事」とは、経営戦略と人事マネジメントを連動させることによって自社の競争優位の実現を目指そうとするものであり、1990年代に提唱された。ただし、『日本の人事部』の「人事白書」によると、「戦略人事は重要だと認識しているが実践できていない」という日本企業が多いのが実状だ。
「戦略人事」が機能していない理由は、大きく三つ挙げられる。「経営陣が、これまでの成功体験に固執してしまう」「人事部門に、経営戦略方針について既存のものが正しいかを議論できる機会や能力、時間がない」「経営陣と人事部門との間で、年度単位でしか対話ができていない」の三つである。
これに対する解決策として注目されているキーワードが、「俊敏であること」 を意味する「アジャイル」だ。海外では経営層レベルで、「アジャイル型人事への移行」が注目されているという。従来のような、成功体験をもとに制度や規則や慣習に従い、経験豊富なメンバーで着実な事業展開と業績向上を目指す、継続性のマネジメント「ウォーターフォール型人事」のやり方だけでは、これからの時代の変化への対応は難しい。そのため、試行錯誤を繰り返して早期に価値を創出する多様な個の力を組織の力へ変える、戦略性のマネジメント「アジャイル型人事」 が求められているのだ。「戦略人事」実現のためぜひ取り入れたい考え方だと、最上氏は強調した。
「四つの地殻変動」への対応が必要
続いて、高倉&Companyの髙倉氏が登壇。長年にわたりさまざまな企業で人事を務めてきた経験から、「戦略人事」への流れを実感しているという。
「『戦略人事』には、新しい“価値を創造”し、競争優位性を高めるために人事戦略をいかに展開するか、という各社のストーリーが必要です。採用、育成、人材マネジメント、組織開発などに関する人事施策メニューを単発で『人事戦略』として行っても、『戦略人事』は実現できません。会社の価値を出して継続的に進化するためにどんなメニューの有機的な展開が必要なのか、という経営視点を人事が持つことが大事です」
「戦略人事」を推進するHRミッションのコアを、髙倉氏は二つ掲げた。
一つは、今後の「船」の航行を先導すること。航行の行き先を見据えて船がきちんと進むようにするには、将来の事業戦略展開に向けた人財戦略が求められる。つまり、将来洞察経営視点、事業ポートフォリオと人財ポートフォリオの連動、ベンチ・ストレングス(多様な人財パイプライン)が必要になる。人財育成には一定の時間かかるため、将来を読んだ戦略を念頭に置かなければならない。
もう一つは、「船の乗組員」のエンゲージメントを高めること。乗組員にやる気がなければ空回りしてしまうため、乗組員の「個」を活かして「全員戦力化」するための組織風土開発が求められる。そのためには、多様な「個」、それぞれの人財への理解、多様性受容(DE&I)、人間行動に対する理解、コミュニケーション力が欠かせない。
「ただし、四つの地殻変動が昨今起こっているため、これらに対応しながら『戦略人事』を展開させていかなければなりません。
一つ目は『多様性、多元性の重要性』。スピードの速い外部環境に対応するために最前線の人財に権限移譲し、多元性を受け入れて新しい価値を作っていく必要があります。トップダウンを待っていては、スピードに対応できません。大きな方向性を共有しながらも各自の特性を踏まえて任せる、本当の権限移譲(エンパワメント)が不可欠です。
二つ目は『遠心力(多様性)と求心力のマネジメントの必要性』。求心力としての経営理念と個人のパーパスとの重なりが内発的動機のエネルギーになることで、個人は柔軟に行動でき、ポテンシャルを開花させて成長できます。また、多様な「個」を活かして、権限移譲(エンパワメント)していくと、この遠心力を回すためにも求心力としての共有すべき大きな方向性となる経営理念の浸透が必要となります。つまり、遠心力と求心力の両方が重要なのです。
三つ目は『個と組織の関係性の変化』。組織はプロとして個人を尊重し、さまざまな挑戦する機会を創出する。そして、個人は“専門性×多様性×信頼関係構築力”によるプロ意識を持ち、自分の成果に責任を持つ必要があります。挑戦した結果から学びとり、よりさらに成長していく、このような双方の関係性の維持が、不確実性の中でも主体的に個人が活躍できる源泉になるのです。
四つ目は『少子化による労働市場の変化』。全員戦力化を目指し、個人がそれぞれの特性と意欲を尊重してチームワークを活かして新しい価値を作っていく、場合によっては、AIなどの先端技術を取り入れながら、タスクに向き合っていく必要があります」
つまり、多様性の進化を見据えたタレント・マネジメントが不可欠になる、ということだ。そこでは、異なる軸の多様性を歓迎し表現する「Diversity」、全ての人の考え・アイデア・視点を大切にする職場環境作りである「Inclusion」だけでなく、全ての人が同じ機会にアクセスでき、公平に扱われるようにする「Equity」、グループの一員として受け入れられ、評価され、会社とつながっていると感じる「Belonging」への配慮も忘れてはならないと、髙倉氏は語った。

戦略をうまく動かす「組織風土」をどう作るか
次に髙倉氏は、前職の味の素、また、ロート製薬時代の事例を紹介した。
「個人の自発的なプロフェッショナリズムが会社に新しい事業を起こす」と捉え、個人は自発的にチャレンジし、会社はそのチャレンジ機会を提供する。双方の間には経営理念が共有されており、自律した関係で共に成長していくことが企業価値創出にもつながる。このような自律的な関係の構築を目指し、施策を打っていったという。
「その一つが動的タレント・マネジメントです。経営戦略、事業戦略に対して、人材要件、従業員のタレントを整理し、どれくらい人材が必要なのかを検討したうえで、適所適材と適時適量を判断していきます。
事業ポートフォリオが変われば人材ポートフォリオも連動させなければなりませんから、多様な個を尊重しつつ外部環境変化に対応できる組織のOSを作ることになります。特に、事業ポートフォリオがなかなか描きにくい変化の激しい時代に入ったため、不確実性の高い外部環境下では、現在のコア事業ですらいつまで維持できるのかが、わかりません。戦略的な事業ポートフォリオを考えると、コア事業のほかに新規事業領域を設けておくのが賢明です」
戦略的な事業ポートフォリオに人材ポートフォリオを連動させていくためには、
新規事業の創出も視野に入れた人財要件、タレント・マネジメントが継続的に求められる。そのためには、多様な人材を組織の中にできるだけ内包させておくという、分厚い人財プールであるペンチ・ストレングスが重要になる。
「では、個を活かす組織の実現に向けた組織開発には、どのように取り組めばいいのでしょうか。今、世界でも重視されているのは、戦略をうまく動かす組織風土づくりです。これを根底に置いた上で、重要なポイントが四つあります。
まずは、長期的視点での育成。失敗を受容して、学びと行動を循環させていくトライ&ラーンの姿勢による育成です。二つ目は、人のネットワークを活用した業務遂行。外部とも公私にわたるネットワークを確立して、多様性・多元性を進めます。
三つ目は、組織への社員の帰属意識の向上。これにはまず、会社の特徴、社風、風土などをしっかりと明文化して伝達していくことから着手すべきです。四つ目は、社員がさまざまな経験を積める環境の整備。キャリアの軸、幅広い視点、個々のプロ意識に応えられるような、オープンな場づくりです」
組織風土づくりにあたって核となる“人の心に火をつける”ための二つのアプローチを、髙倉氏は提示した。
一つは「エンゲージメントサーベイ結果の真剣なフォローアップ」。率直な社員の声を知るだけではなく、その声の本当の原因、特にスコアの良くない項目の真因を分析して、アクションを立てフォローしていく。組織として、それぞれの声に丁寧に向き合って変えていく動きを確実に進めることである。
もう一つは「マネージャ層の上司力向上・リーダーシップの内省」。社員に施策を示し促すだけでは説得力に欠けるため、社長はじめ上層部から、自分自身を見つめ直し内省していく。それによって過去から脱却できるかどうかということは、アジャイル視点からも大きな意味を持ち、戦略人事の原動力になる。
「個人の自律性」と「組織としての結集」の両立法
次に、ビジネスリサーチラボの伊達氏が、本セッションの論点を整理した。
「髙倉さんのお話の中で非常に印象に残ったのは、個人の自律性は大事だけれど、ただ自律するだけでは遠心力が働いてバラバラになってしまうため、そうならないように組織の力に変えていくことの大切さです。
自律した個人の力を結集していくには、さまざまな難しさがあると思います。一つは、自律そのものの難しさ。もう一つは、自律した個人はそれぞれがいろいろな方向に向かおうとするため、バラバラになってしまう、似たもの同士が派閥を組んで衝突してしまう、といった難しさです。
そこで、人事の出番となるわけです。ビジョンやミッションや経営理念などの共通の目的意識を醸成したり、オープンな組織風土を作ったり、ジョブを明確にしてかつジョブを生み出していったり、情報を透明化して一元化していったりするなど、さまざまな工夫や働きかけが行われます。
ところが、自律を結集させるにしても、個々人の自律した力を“どこに向けて”組織の力に変えて結集させればいいのか、定めなければなりません。高倉さんは“価値創造”というキーワードを使われましたが、ここは本当に重要だと思います」

価値創造とは、社内にある資源を組み合わせて変換し、顧客にとって有用なものを生み出していくことを意味する。価値創造を担うのは人だが、自然発生的に価値は創造されない。つまり、人材への働きかけがなければ価値は創造されない、と伊達氏は言う。
「さらに、価値創造に持続性を持たせるためには、サクセッションが必要です。髙倉さんがおっしゃった『ベンチ・ストレングス』、つまり、人材の層の厚さを実現させることは、人事にとって大きなテーマになると考えられます」
続いて、ディスカッションが行われた。
伊達:自律した個人を組織としてまとめていくことは難しいと思いますが、人事部門としてまず、どんなことを考慮すればいいのでしょうか。
髙倉:人が働く理由は、経済的な糧の獲得だけではありません。社会的な価値を創造することも理由だと思います。そこで目を向けたいのが、「自分は何をやりたいのか」というキャリアオーナーシップです。何をやりたいというWill、何ができるというCanを明確にした上での能力開発が大切です。
ただし、WillやCanと会社の価値観、経営理念が同期できなければ、双方にとって望ましくありませんので、採用が鍵になると考えています。採用面接の際、会社の経営理念にどのぐらいの理解度と共感を持っているのかをしっかりと見極める軸は不可欠です。中途採用の際に、応募者から経営の理念やバリューの話が出なければ採用しない、という話を聞いたこともあります。
ただし、同期できる人をバスに乗せるだけでは不十分です。乗った後にも経営理念のワークショップを通じて会社と個人の思いのシンクロを常に探求し、新しい知恵や工夫を出して生産性を上げ、さらに、新規事業を創造したり、OKRについてのミーティングで方向性を確認したり、といった取り組みを意図的、複合的に行っていくべきだと思います。
伊達:経営理念との合致についてですが、学術的には合致というのは二種類に分類できます。「自分とこの会社の考えは似ている」という意味での合致、もう一つは、「自分のニーズを満たしてくれる」「自分の能力を発揮させてくれる」という“補完”の意味での合致です。
後者の“補完”の意味での合致という形が、重要になってきているように感じます。個人にしても人事にしても、補完という関係性を互いに受け容れながら仕事に向き合い、採用し、配置し、育成していく。そんな姿勢も大切にしていくべきですし、必要な形、関係性になると考えています。
次に、参加者からの質問を紹介します。「人材が多様化していくと必ずしも組織の目指すべきバリューと食い違うケースや完全に合致しないケースも出てくると思いますが、どのように対処すればいいでしょうか」。いかがですか。
髙倉:価値観が合致していても、それを実践するにあたっての知恵や考え方は多様なままで、一つにまとまらなくてもいいと思います。今の時代、完全に一致してしまう状況の方が危険ではないでしょうか。いろいろな視点からいろいろな捉え方をすることは、明確な答えのない時代の価値創造を目指すにあたっても大切です。多様な人による議論の交わりが次の方向性を見つけ出すきっかけにもなるはずですから、逆に摩擦を起こした方がいい、というスタンスで構えて欲しいと思います。
伊達:今の延長線上にある質問です。「多様で自律した個人が意見をぶつけ合っていく場は、どのようにつくればいいでしょうか」。
髙倉:まずは信じ合うことです。プロとしてその人の持っているポテンシャルや専門性を尊重してチームを組むわけですから、部下の成長や活躍を望むのであれば、上司は一人のプロとして部下に接するべきです。そして、積極的に経験の場を与え、活躍できる場を作り、たとえ失敗してもその結果から学ぶ場を提供すればいいと思います。
伊達:プロとして尊重していくことは、心理的安全性の実現にもつながりますね。
髙倉:さらに、意見をぶつけ合う場がつくられるわけですから、部下にはそれなりの覚悟を持ってほしいと思います。結果を出すのがプロですし、覚悟がない限り成長は望めません。
伊達:プロには、大きく三つの条件があります。一つ目は体系的な知識、二つ目は社外のコミュニティへの所属、三つ目は倫理観。こういった認識も、自律した個人には持ち備えていただきたいと思います。
最後に、「経営層も学ぶ必要があるとのお話でしたが、人事部門からはどのように経営層に働きかければいいでしょうか」というご質問にお答えください。
髙倉:経験が豊富になって年齢も上がると、自分のやってきたことは正しいと思いたくなる自己肯定感が強く働くものです。しかし、肯定的に自己否定できることこそ変化の時代に重要です。新卒が辞めた理由を理解できなくても、理由を分析して考えていかなければ、変化には対応できません。今まではうまく機能して成長を遂げてきたものでも、これからは通用しないケースが当然起こるわけです。自分を一度捨てて次の新しい自分を作るという自己破壊を経て、学び続けるサイクルが、成長の源泉になります。本当の自己肯定感がないと、この自己破壊ができない、つまり、継続して学び続ける大切さを理解してもらえるように働きかけてみてください。
伊達:経営層だけでなく、人事自身にとっても自己破壊と学びのサイクルは必要です。皆さんもぜひ、学びを止めずに「戦略人事」に取り組んでください。本日はありがとうございました。
現代のビジネス提供価値の最大化に欠かせない「IT利活用スキルの装着」「変化に強いマインドセットの醸成」を軸に、イノベーションを生み出す自律的な組織作りのための人材育成・組織開発を支援します。お客様の状況や課題に合わせ、研修実施、講師内製化支援、コンサルティングなど多角的にサービスを提供いたします。
現代のビジネス提供価値の最大化に欠かせない「IT利活用スキルの装着」「変化に強いマインドセットの醸成」を軸に、イノベーションを生み出す自律的な組織作りのための人材育成・組織開発を支援します。お客様の状況や課題に合わせ、研修実施、講師内製化支援、コンサルティングなど多角的にサービスを提供いたします。

[A]ワコールが取り組む自律型組織・自律革新型人材の育成 ~創業者から受け継ぐ想いと変革の両立~

[B-7]NLP心理学を活かしたDX推進 自律性を高めるDX人材育成と、DXをクライアントビジネスに活かす秘訣

[B]従業員の「心」に寄り添い、戦略人事を実現する「従業員体験」

[C-8]新卒3年以内の離職率50%を0%にした三和建設の取り組み

[D-3]報酬・処遇制度見直しの最前線 - ジョブ型人事制度の更なる進化と「ペイ・エクイティ」の実現に向けて
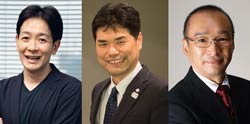
[D]モチベーション高く、いきいきと働き続ける環境をどうつくるのか 先進事例から考える「シニア活躍支援」

[E]書籍『理念経営2.0』著者と、NECのカルチャー変革から学ぶ、これからの組織の在り方

[F]「人的資本経営」推進プロジェクトはどうすれば成功するのか

[G-2]事例で理解するテレワーク時の労務管理と人事考課 テレワークでもパフォーマンスを上げる具体的な手法

[G]「対話」で見違える、個人と組織の成長サイクル ~キャリアオーナーシップ実践編~

[H-5]個々人の“違い”を活かし、超えていくチームの築き方。

[H]ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン先進企業は、過去10年に何をしてきたのか?

[I]今後の人事戦略にAIという観点が不可欠な理由 ~社会構造の変化や働く意義の多様化から考える~

[J]変革創造をリードする経営人材の育成論

[K-7]全社のDX人財育成を推進する 人事が取り組む制度設計と育成体系のポイント

[K]人事評価を変革する~育成とキャリア開発をふまえて~

[L]いま人事パーソンに求められる「スキル」「考え方」とは

[M]社員は何を思い、どう動くのか――“人”と向き合う人事だからこそ知っておきたい「マーケティング思考」

[N-1]【中小・中堅企業さま向け】組織活性化に向けた次世代リーダー(管理職・役員候補者)の育成プログラム

[N]人的資本経営の「実践」をいかに進めるか ~丸紅と三菱UFJの挑戦事例から考える~

[O-1]キャリア自律を促進する越境学習の効果と測定方法~東京ガスの事例とKDDI総研との調査結果から探る~

[O]従業員の成長と挑戦を支援! 大手日本企業が取り組む「人事の大改革」

[P]「意味づけ」と「自己変革」の心理学

[R]人的資本経営とリスキリング~中外製薬に学ぶ、経営戦略と人材施策の繋げ方~

[S-4]「カスタマーサクセス」を実現させる人材育成方法とは? ~顧客の成功に伴走する組織の作り方~

[S]多忙な管理職を支え、マネジメントを変革する人事 ~HRBPによる組織開発実践法~

[T]いま企業が取り組むべき、若手社員の「キャリア自律」支援 次代の変革リーダーをどのように育成するのか

[U-4]ハラスメント無自覚者のリスクをいかに検知し防止するか 360度評価の事例にみる無自覚者の変化プロセス

[U]事業の大変革を乗り越え、持続的成長に挑戦 CCCグループが実践する人事データ活用とタレントマネジメント

[V]日本一風通しが良い会社へ コミュニケーションを軸にしたNECネッツエスアイの組織風土変革

[W]真の「戦略人事」を実現するため、いま人事パーソンには何が求められるのか

[X-5]NTT東日本とNECが挑戦する越境体験を活用したビジネスリーダー育成

[X]事業成長を実現する採用戦略 競争が激化する市場で必要な取り組みとは




