従業員の「心」に寄り添い、戦略人事を実現する「従業員体験」
- 守島 基博氏(学習院大学 経済学部 経営学科 教授/一橋大学 名誉教授)
- 井無田 仲氏(テックタッチ株式会社 代表取締役 CEO)

人的資本経営を進めるにあたって重要な要因として、従業員体験(従業員エクスペリエンス)が注目されている。経営戦略に沿って人的資本を有効に活用し、人材価値と企業価値を結びつける人材マネジメントを有効に行うためにも、従業員体験は重要だ。従業員体験を向上させるためのポイントはどこにあるのだろうか。人材論・人材マネジメント論を専門とする学習院大学教授の守島氏が、従業員体験の重要性・必要性をあらためて解説。社員満足度の高さで評価されているテックタッチの井無田氏が、施策を組み立てる上で必要な観点や推進方法を紹介した。

(もりしま もとひろ)人材論・人材マネジメント論専攻。イリノイ大学でPh.D.を取得後、サイモン・フレーザー大学助教授、慶應義塾大学助教授・教授、一橋大学大学院教授を経て、2017年より現職。2020年より一橋大学名誉教授。著書に『人材マネジメント入門』『全員戦力化 戦略人材不足と組織力開発』『人材投資のジレンマ』などがある。

(いむた なか)慶應義塾大学法学部、コロンビア大学MBA卒。新生銀行、ドイツ証券などで投資銀行業務に従事、上場企業の資金調達/M&A案件を数多く手がける。その後入社したユナイテッド社では、アプリ事業責任者、米国子会社代表としてアプリサービスのグロース/スケールを経験。2018年3月にテックタッチを創業。
今、組織に必要な「従業員体験」
テックタッチは、「多くの人々が使う『システム』を使いこなせる世界をつくることで、社会を良くしたい」という意志のもと、2018年に設立。「すべてのシステム利用者をアシストし、人々の人生、社会を変えること」を使命に掲げるソフトウェア会社である。
開発・提供しているのは、デジタルアダプションプラットフォームである「テックタッチ」。ソフトウェア上にナビゲーションを表示させることができるソフトウェアだ。誤入力や操作ミスの削減、システムの定着や利用の促進など、従業員が使用するシステムのユーザビリティを大幅に向上させ、企業のDX実現をサポートしている。
デジタルアダプションツールは、米国企業の50%超が導入しており、テックタッチは3年連続で国内トップシェアを獲得するなど、日本のデジタルアダプション市場をけん引している。
同社はドクタートラスト社が実施している従業員サーベイによって、従業員100名以下の会社の中で957社中2位の社員満足度を獲得。職場優良法人として評価され、偏差値も91.6という高い数値を獲得している。この結果をもたらした背景には、同社の井無田氏の経験に基づいた「従業員体験」に対する考えがあるという。
「近年、人的資本経営が重要だと叫ばれていますが、人的資本経営とは『人』という無形資産の企業価値創造力に注目した経営のあり方を意味します。人的資本と人的資本投資に関する情報開示も求められるようになりました。企業で人材価値が最大限発揮されているのかを、マーケットも重視するようになってきたのです。
そのため企業には、可能な限り全ての人材の能力や意欲を活用する人材戦略や、従業員一人ひとりの能力やキャリアプランに応じた人材活用が求められています。言い換えると、従業員を丁寧に採用、育成、配置し、パフォーマンス向上を支援し、個の事情に配慮しながら、可能な限り全員に活躍してもらうことを人事は目指すべきであると言えます。そのための重要なレバー要因として注目されているのが、従業員体験なのです」
従業員体験とは、従業員が組織で働くことで獲得するあらゆる経験を指し、従業員と企業の接点全てにおいて発生するものである。特に、意義のある仕事、公平で納得できる評価や処遇、働きやすい仲間、仕事とキャリアの進展・成長が期待できる職場環境、家族との充実した時間などのポジティブな経験が重要とされており、ミレニアル世代やZ世代は、以前の世代よりも従業員体験を重視しているという調査が見られる。
「バブル経済が崩壊して人件費を減らすことを重要視した日本企業では、優秀層や選抜層などのトップ人材を中心に投資をしており、結果として他の層の戦力が削がれている状態がしばらく続きました。現在はそうではなく、全ての層の一人ひとりを大切にマネジメントして、総合的に戦略を達成していく力をより強化していこう、という考え方にシフトしているわけです。それを行うために従業員体験への投資は欠かせません。
従業員体験が従業員のエンゲージメントに相関しているというデータも多く見られています。『いい経験をしている』『いろんな側面で自分が大切にされていると感じる』『尊重されていると感じる』『公平に扱われていると感じる』といった経験を持つ人材は、『企業のために頑張っていきたい』『貢献したい』という感覚が強くなると考えられています」
しかし最近の各種調査によると、むしろ従業員体験が劣化している結果が見られると守島氏は指摘する。その理由は、経営戦略の変化、リスキリングの要請、職場環境の劣化など、企業が大きく変革するなかで従業員の日々の経験が変わっていることや、労働時間の削減、在宅勤務やテレワーク、研修のオンライン化、対面コミュニケーションの減少など、働き方改革やコロナ禍によって働き方が変化し、それに適応しきれていないことが考えられる。
「働く喜びを感じられた人が50%以下」「世界的に見ても日本の従業員のエンゲージメントは低い」といった調査結果も出ており、従業員体験を向上させ、従業員のエンゲージメントを高めていかなければ、日本企業の競争力は落ちてしまうばかりだと、守島氏は危惧する。
「今まさに、従業員体験の向上に対する投資が求められていると感じています。たとえば、従業員が仕事に意味や意義を感じるためには、パーパスの共有、従業員の達成感、仕事の納得感などが必要です。また、働きやすい職場には、ハラスメントの防止や自由に意見を言える心理的安全性のある環境、成長実感を従業員が持てることが欠かせません。働きやすい職場が整っていたり、ワーク・ライフ・バランスが維持されていたりする環境づくりは、経営者の責務だと言えます」
「従業員体験が向上すれば、生産性も上がり、イノベーションも生まれ、リテンションにも効果的だと考えられます」

過去の経験を元にデザインしたテックタッチの施策
続いてテックタッチの井無田氏が、自社の従業員体験について紹介した。同氏が、従業員エクスペリエンスを大切に考えるようになった理由は、起業前の経験にさかのぼる。
「大学を卒業後、複数の金融機関での勤務で勤務したあと、中小IT企業では事業責任者や米国子会社の代表などを歴任してきました。その期間に『評価制度がネガティブ体験の温床になっている』『若手に裁量権が与えられない』『チャレンジが評価されない』『新規事業に成功しても失敗しても待遇が変わらない』という状況に直面しました。20代、30代でこのような経験をするなかで、何かがおかしい、本当は変えたいと、ずっと思い続けてきました。
起業するにあたって、自分のような体験を自分の会社で働く仲間には味わってほしくないという強い思いがありました。それが原動力になって、会社の組織設計や組織開発に興味を持ち、自分の過去の経験の中に、従業員体験を向上するカギが隠されているという思いで施策へと落とし込んでいきました」
しかし、全社の施策や設計で、従業員体験の向上に取り組むのは難しい。そこで、現場部門にも人事施策を担当してもらうことにしたと井無田氏は語る。社長やHR部門は全社のグランドデザインや方向性を定めて、MVV策定、採用ポリシー、評価制度の報酬設計、マネジャーのハンドブック策定などを担い、現場部門は実際の細かな施策を設計して、1on1ポリシー、フィードバックシステム、評価制度の評価部分などに取り組んで具体化を進めた。従業員体験の詳細設計は、現場部門のマネジャークラスに任せたのである。
「現場部門がコンテンツの部分を担当しました。たとえば、1on1の枠組みはボードメンバーやHR部門で決めますが、1on1で掲げる目標や実施頻度、『何を話すのか』という具体的な設計は現場部門に預けたのです。これは、部門によって1on1でフォーカスすべきことが異なるためです。たとえば、開発部門と営業部門では、実際に伸ばすべきスキルセットや、考えるべきキャリアパスも、成果認識が全く異なります。
一方では、セーフティネットとして、従業員サーベイを4週間に1度行って、各部門の従業員体験が損なわれてないかをチェックするようにしました。現場と二人三脚で従業員体験を作っていくというグランドデザインです」
グランドデザインには、井無田氏が起業前の経験を通じて抱いた疑問を元にいくつかのアンチテーゼを立てて、まずは思考ツリーを作成。そこから社内スローガンや事業ミッション、バリューへと落とし込み、従業員体験へと具現化させていった。
打ち立てたスローガンは「仕事を輝くものに」。人生の時間の8〜9割を仕事に費やすことを考えた時、仕事の質が生活の質にもリンクするのは明らか。そうであれば、ワクワクしながら仕事ができる会社をみんなで作り、そのための方策をみんなで考えよう、という想いが込められている。
「従業員体験」を最大化する三要素
スローガンを実現させるために、大事な要素は三つあると井無田氏は掲げる。三つをしっかりそろえていくことが、従業員体験の最大化、また、エンゲージメントの最大化に欠かせないという。
一つ目は「事業ミッション」。「自分の仕事の先に実現できる世界に本当にワクワクできるか」「ミッションクリティカルな事業か」といった事業への共感のためにも、言語化は非常に重要だ。
二つ目は「キャリアにおけるパーソナルなチャレンジ」。メンバーが“夢中になれる”チャレンジを会社がどういう形で提供するのかが、ポイントとなる。
たとえば、「心理的安全性の担保」を考慮して、チャレンジに失敗はつきものであるという考え方の共有のもと、チャレンジを応援するバリューや制度を提供。採用・異動に際しては、「個人のWILLとキャリアプランをヒアリング」してから、会社での役割とマッチさせるチャレンジを提供している。また、優秀なリーダーを採用して「現場へ権限委譲」するという形で、チャレンジできる環境も提供しているという。
報酬面では、「長期成果(企業価値向上)と連動」した普通株とストックオプションを付与し、全社ボーナスには「短期成果(当期売上)と連動」させた計算式を全社へ開示。新規事業を立ち上げるチームは給与を減らして成功報酬を高めに設定する「新規事業ボーナス」を設けている。
三つ目は「一緒に仕事をする仲間」。「苦しい時に手を差し伸べられるか」「チームの垣根なく成功を分かち合えるか」「心理的安全性が高い議論ができるか」という観点から、施策に工夫を加えていく。
たとえば、心理的安全性を保ち、チームプレイを促すために、「立場や年齢・経験にかかわらずアイデアや意見をとにかく出す」「対立構造を作らない」「強い口調で詰めない」をカルチャーとして浸透させている。
採用時には、チームプレイヤーであるかどうかを見極めるため募集部門以外の部署からも大勢の社員が関与している。候補者にとってはミスマッチが予防でき、入社前後のギャップがゼロになるメリットがある。
ダイバーシティについては、性別・人種ではなく、職務経験や能力のダイバーシティを意識しているという。部門によって考え方や会話に使う用語も異なってくるものだが、補完し合える関係づくり、刺激し合える関係づくり、多様な意見交流のためにも望ましい。
「テックタッチのバリューは三つあります。『挑み続けろ、援護があるから』『Deep Thinking』『いつでもごきげん』。従業員体験の向上のためにも、自分と現場の間にギャップがあってはならないと考えて、社員全員で議論した末に作り上げました」

対談:評価制度がカルチャー化に効く
最後に、両氏による対談が行われた。
守島:非常に面白い話でした。井無田さんは、いわゆる大企業、特に金融という、比較的古い文化が残っている業態とITベンチャーでの経験を踏まえて、従業員体験に生かしていらっしゃるわけですが、何が大きな原因となって、企業における従業員体験の低下が起こっていると思いますか。
井無田:私の経験から考えると、おそらく経営者のコミットメントの弱さが原因の一つにあるのではないかと思います。当時の私はまだ若かったので、違和感を抱いても声に出さずにそのまま過ごしていました。従業員体験の低下に対して、言い出しにくい環境であることも一因かもしれません。
私達のようなスタートアップ企業は企業規模も小さいため、大企業と異なりさまざまな施策をゼロから思い切って実行できます。考え方の引き出しが増える体験を過去に得られたのは、本当に大きかったと実感しています。
守島:経営者が目線を高く、広くしておくことは重要だということですね。人事として、そのサポートをすることもできると思います。
井無田:私もそう思います。ただ、経営者の方には従業員体験に高い興味を持つ方もいれば、全く関心のない方もいらっしゃいます。経営の中枢は人だということが、社会的にもっと盛り上がっていってほしいですね。
守島:IT産業の日本経済や人々の生活のなかでの重要性はここ数年で極めて大きくなっています。これまでの製造業のようです。でも、注視してみると、IT企業の人事は、製造業の人事とは全然違います。企業の中で何を大切にするか、つまりカルチャーを重視したIT企業はかなり多いと思われます。逆に言うなら、だからこそIT企業が大きくなって、プレゼンスが出てきたのではないかと思っています。カルチャーに関してはどのようにお考えですか。
井無田:最初にグランドデザインを作っておくことが欠かせないと思います。ただ、「グランドデザインに沿って人事制度を作っていこう」と表層をなぞるだけでは不十分です。カルチャー化に一番効くツールは評価制度です。たとえば、チャレンジを推奨し、チャレンジを評価し、チャレンジに失敗してもよしとするような軸を、評価制度に反映させることから始めていけば、カルチャーが変化するきっかけになると思います。
守島:チャレンジはすごく大切ですが、成熟期にある企業の中でチャレンジしろと言われても、従業員は何をやっていいのかピンとこないと思います。私が知っているある企業では、まず、「こういうものがチャレンジなのですよ」ということを、ミッションやバリューに紐付けて、働く人と経営が対話しながら、チャレンジのカルチャーを作っていきました。チャレンジを促すコツはありますか。
井無田:チャレンジという言葉を理解するのは簡単ですが、体制がなければ、なかなか行動に移せないと思います。ですから、チャレンジを定義付けるだけでなく、補助輪を付けて、少なくともまずは体験を積んでもらうことが大事ではないでしょうか。「これがチャレンジなのだ」という体験を得ると、次のチャレンジが生まれやすくなると思います。当社ではその1歩を踏み出せるような支援を心がけています。
守島:特に規模の大きな企業になると、現場によってチャレンジの内容は異なってくるため、チャレンジの背中を押してあげるマネジャーがカギになります。ただ、そうなるとマネジャーの負担が大きくなってしまいます。ここに関して、何か対応策など講じていますか。
井無田:マネジャーに向けたハンドブックや研修でフォローしたり、従業員サーベイなどを見ながら1on1をしたりして議論しています。マネジャーの存在はとても大事ですから、マネジメントスキルの体系化にもトライしているところです。
守島:今日、井無田さんにお話頂いた施策の全てを、他の企業が取り入れるのは容易ではありませんし、一気にやるべきではないと思います。重要なのは、井無田さんのお話を参考にしつつ、自社の企業のミッション、バリューや価値観に合わせた形で取捨選択をしていくことです。ぜひ、そのようにして、従業員体験を高めていくよう、施策に臨んでほしいと思います。本日はありがとうございました。
デジタルアダプションプラットフォーム「テックタッチ」を提供。国内シェア3年連続No.1※。 ※「ITR MarketView:コミュニケーション/コラボレーション市場2023」デジタル・アダプション・プラットフォーム市場:ベンダー別売上金額推移およびシェア(2021~2023年度予測)
デジタルアダプションプラットフォーム「テックタッチ」を提供。国内シェア3年連続No.1※。 ※「ITR MarketView:コミュニケーション/コラボレーション市場2023」デジタル・アダプション・プラットフォーム市場:ベンダー別売上金額推移およびシェア(2021~2023年度予測)

[A]ワコールが取り組む自律型組織・自律革新型人材の育成 ~創業者から受け継ぐ想いと変革の両立~

[B-7]NLP心理学を活かしたDX推進 自律性を高めるDX人材育成と、DXをクライアントビジネスに活かす秘訣

[B]従業員の「心」に寄り添い、戦略人事を実現する「従業員体験」

[C-8]新卒3年以内の離職率50%を0%にした三和建設の取り組み

[D-3]報酬・処遇制度見直しの最前線 - ジョブ型人事制度の更なる進化と「ペイ・エクイティ」の実現に向けて
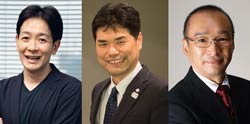
[D]モチベーション高く、いきいきと働き続ける環境をどうつくるのか 先進事例から考える「シニア活躍支援」

[E]書籍『理念経営2.0』著者と、NECのカルチャー変革から学ぶ、これからの組織の在り方

[F]「人的資本経営」推進プロジェクトはどうすれば成功するのか

[G-2]事例で理解するテレワーク時の労務管理と人事考課 テレワークでもパフォーマンスを上げる具体的な手法

[G]「対話」で見違える、個人と組織の成長サイクル ~キャリアオーナーシップ実践編~

[H-5]個々人の“違い”を活かし、超えていくチームの築き方。

[H]ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン先進企業は、過去10年に何をしてきたのか?

[I]今後の人事戦略にAIという観点が不可欠な理由 ~社会構造の変化や働く意義の多様化から考える~

[J]変革創造をリードする経営人材の育成論

[K-7]全社のDX人財育成を推進する 人事が取り組む制度設計と育成体系のポイント

[K]人事評価を変革する~育成とキャリア開発をふまえて~

[L]いま人事パーソンに求められる「スキル」「考え方」とは

[M]社員は何を思い、どう動くのか――“人”と向き合う人事だからこそ知っておきたい「マーケティング思考」

[N-1]【中小・中堅企業さま向け】組織活性化に向けた次世代リーダー(管理職・役員候補者)の育成プログラム

[N]人的資本経営の「実践」をいかに進めるか ~丸紅と三菱UFJの挑戦事例から考える~

[O-1]キャリア自律を促進する越境学習の効果と測定方法~東京ガスの事例とKDDI総研との調査結果から探る~

[O]従業員の成長と挑戦を支援! 大手日本企業が取り組む「人事の大改革」

[P]「意味づけ」と「自己変革」の心理学

[R]人的資本経営とリスキリング~中外製薬に学ぶ、経営戦略と人材施策の繋げ方~

[S-4]「カスタマーサクセス」を実現させる人材育成方法とは? ~顧客の成功に伴走する組織の作り方~

[S]多忙な管理職を支え、マネジメントを変革する人事 ~HRBPによる組織開発実践法~

[T]いま企業が取り組むべき、若手社員の「キャリア自律」支援 次代の変革リーダーをどのように育成するのか

[U-4]ハラスメント無自覚者のリスクをいかに検知し防止するか 360度評価の事例にみる無自覚者の変化プロセス

[U]事業の大変革を乗り越え、持続的成長に挑戦 CCCグループが実践する人事データ活用とタレントマネジメント

[V]日本一風通しが良い会社へ コミュニケーションを軸にしたNECネッツエスアイの組織風土変革

[W]真の「戦略人事」を実現するため、いま人事パーソンには何が求められるのか

[X-5]NTT東日本とNECが挑戦する越境体験を活用したビジネスリーダー育成

[X]事業成長を実現する採用戦略 競争が激化する市場で必要な取り組みとは




