いま人事パーソンに求められる「スキル」「考え方」とは
- 西田 政之氏(株式会社 ブレインパッド 常務執行役員 CHRO)
- 江夏 幾多郎氏(神戸大学 経済経営研究所 准教授)

人的資本経営の推進をはじめとして、人事が向き合うべき課題は高度化し、人事パーソンに求められる役割は複雑化している。変化を続ける時代にあって、人事パーソンは何を学び、どのように成長していくべきなのだろうか。人事パーソンの学び方や働き方に関する持論を発信してきた西田政之氏と、長年にわたり人事実務の在り方を提言してきた江夏幾多郎氏によるディスカッションを通じて、これからの人事パーソンに求められる「スキル」と「考え方」を明らかにした。

(にしだ まさゆき)1987年、金融分野からキャリアをスタート。2004年にマーサーへ転じ、2013年 同社取締役COO。2015年にライフネット生命保険取締役副社長兼CHROに就任。2021年6月に株式会社カインズ執行役員CHRO(最高人事責任者)兼 CAINZアカデミア学長に就任。2023年7月より現職。

(えなつ いくたろう)1979年生まれ。一橋大学商学部卒業。同大学にて博士(商学)取得。名古屋大学を経て2019年より現職。専門は人的資源管理論、雇用システム論。日本労務学会会長。主著に『コロナショックと就労』(ミネルヴァ書房)『人事評価における「曖昧」と「納得」』(NHK出版)など。
人事パーソンは「贈与しあうコミュニティ」を作れているのか
まず江夏氏が本セッションの趣旨を説明。「人事の仕事に携わる当事者や研究者の立場から、このミッションへの向き合い方を考えていきたい」と切り出した。
「情報技術が急激に進化していますが、人も社会もまだまだ追いついていません。私たちは21世紀に生きていますが、変化に流されるそのありようは中世の時代にいるかのうようです。中世には“PDCA”などという概念はなく、全ての神や自然の計らいとして受容してきました。現在になってまた、PDCAが少なくともそれ単体では通用しなくなりました」
そんな時代に頼るべきは自己であり、「楽しみ、遊び、今をしっかりと生きられるパターンを見つけるのが有効」と江夏氏は話す。目先の達成、「意味がある」と主観的に思えることの積み重ねこそが自分らしいキャリアになっていくのだ。
「人事パーソンのキャリアにおいて、今の充実が大切であることは言うまでもありませんが、どういう自己満足が求められるのでしょうか。仕事の中で関わる他者との交換だけでなく、誰かから贈与され、自分も誰かに贈与することを通じて、ある種のコミュニティを作ることが、仕事人としての充実の礎になると考えています。では、そうしたコミュニティを人事パーソンは作れているのでしょうか。そんな問題提起を切り口に、本日のセッションを展開していければと思います」
信頼を勝ち得るために欠かせない「脱中心化」プロセス
鍵を握るのは贈与実感・邂逅経験・修羅場体験
江夏氏の言葉を受けて、西田氏が登壇し、自身の経験をもとに語った。
自然豊かな北海道・十勝の大樹町で生まれ育った西田氏。キャリアの前半は外資系金融機関などを渡り歩き、40歳のときにキャリアチェンジして人事コンサルタントに転身した後、数々の企業でCHROを務めてきた。
プライベートでは、大樹町の隣にある幕別町の森林組合員として植林などの活動も行っている。そうした活動から西田氏は新たなインスパイアを得ているという。
「森林を構成する木々はそれぞれが自立しています。土の中をのぞいてみると、『菌根菌』と呼ばれる菌が張り巡らされて根と根をつなぎ、木々同士が密なコミュニケーションを取って、時には養分などのやり取りをしている。これは企業にも応用できる理想的な組織形態ではないかと考え、『自立連携型組織』と名づけてHR戦略に取り入れてきました。こうしたプライベートの活動もさまざまなインスパイアにつながり、実業に結びつくのです」
そうした活動の広がりを生み出すには何が必要なのか。西田氏は人事に最も求められるスキルは「信頼」だと言う。打算的に人事パーソンが磨くべきスキルを考える前に、自分がどれくらい信頼されているかを内省することが、遠回りのようで重要なのだと。
信頼を勝ち得るためには、当たり前のことを普段からきちんとやり遂げ、内省しなければならない。その内省の鍵となるのが「脱中心化」だという。
「私たちは生まれた瞬間から、自分を中心に世界が回っていると考えて育ちます。そこから徐々に成熟化し、自分一人では生きていけないと悟る。つまり“脱中心化”していくわけです。還暦を迎えた私も、脱中心化の過程にあります。キャリアを振り返ってみると、MBA留学したり外資系企業を点々としたり、経営者養成塾に入ったりする中で、さまざまな人との出会いがあり、脱中心化の助けを得てきました」
西田氏は、脱中心化に必要なファクターとして「贈与の実感」「邂逅(かいこう)の経験」「修羅場の体験」を挙げる。
「贈与の実感とは、目に見える・見えないにかかわらず、さまざまな施しを受けて生かされてきたと自覚することです。私たちは親からの無償の愛に始まり、周囲から与えてもらったさまざまな機会によって成長します。
次に邂逅の経験。私のキャリアの転換点には、必ず素敵な人との出会いがありました。上司や勉強会仲間、ビジネスでのカウンターパートの方々との出会いを通じて、自分を高めることができました。
最後に修羅場の体験。自分の成長や飛躍につながった苦しい経験を指します。私は証券会社時代にどぶ板営業を経験し、アライアンス交渉ではディールブレイクの危機に直面し、異文化ビジネスでは語学の壁にぶつかりました。昨日まで一緒に働いていた仲間が突然亡くなるというつらい別れもありました。これらの修羅場体験が現在の私を形作っています」
これら三つのファクターを生かすドライバーが、リベラルアーツと哲学的思考力だ。歴史や文学は、他社への共感を深めて利他的行動を促進してくれる。文化的・哲学的教養は、異なる価値観の人を受け入れて学ぶ姿勢を提供してくれる。
「つまり、私たちは学び続けなければいけない、ということです。学びを止めた瞬間に、年齢にかかわらず『老害』になってしまう。脱中心化の過程では、自律的に学ぶことが大切です」

次に西田氏は、人事パーソンに求められる考え方を提起した。キーワードは「遊びと仕事のリンク」だ。仕事も遊びの延長線上と捉え、楽しむからこそ極められるのだという。
フランスの社会学者ロジェ・カイヨワは、遊びには四つのカテゴリーがあると述べている。 「競争(アレゴ)」「偶然(アレア)」「模擬(ミミクリ)」「めまい(イリンクス)」だ。
「遊びと仕事はどのようにつながるのでしょうか。『競争』については、仲間と競い高め合う仕組みを人事が作ることが大切でしょう。『偶然』では、思いきった登用や抜てき。『模擬』は学びのプラットフォームを拡大し、『めまい』は新規事業などの新たな挑戦の舞台を用意することで提供できるかもしれません。このようにして遊びと仕事をリンクさせることで、人事は従業員に対してエンターテインメントを提供できるのです」
人事パーソンとしての実践知を深める
「事例」「理論」「歴史」の振り返り
続いて江夏氏が、研究者の視点からプレゼンテーションを行った。
人事の世界では、約30年前から言われ続けてきたことがいよいよ現実になろうとしている。会社が個人を好きなように使える時代は過ぎ去り、個人と企業が対等であることを前提に考えなければならない時代となった。個人と企業は、互いに高い関心を持ちながら関わっていかなければならないのだ。
「そんな時代の人事は『従業員が会社をどう見ているか』という視点から考えるべきです。従業員は常に『この会社は何を目指しているのか』『私にどうあってほしいのか』を考えています。これらが分かり、自分にとって魅力的である場合、事業活動に参加しようという意志が芽生えます。従業員の意志ある仕事が会社を活性化させますが、そのきっかけはあくまで会社側からのメッセージングで、メディアとしての人事の役割は極めて大きい。会社が考える方向性を、人事の仕組み作りや運用を通じて、ストーリーとして伝えていく。そのストーリー形成こそが人事パーソンの専門性になるでしょう。
ストーリーを裏付ける仕組みを作り、従業員の反応を見ながら、また仕組み、ストーリー、両者の関係に磨きをかけていく。これはとても実践的な取り組みであり、合理的な計算だけで成り立つものではありません」
実際の人事の展開の起点には「こうなるだろう」という計算や予測があるべきだが、その通りに動き、それに経営者や従業員がワクワクするとは限らない。計画を修正したり、計画を度外視でやるべきことを見出し、没頭したりといった、即興的な「賭け」も必要。それを可能にする実践知は、人々の身体感覚と直面する「現場」の共振の中で常に生まれ、変化するもので、この律動に耳を傾け、委ねるという即興性が人事パーソンにも求められる。人事パーソンの向こうには経営者や従業員がいて、実際の人事は彼らとの「ジャズセッションのようなかけ合い」の中で成立するという見方をしたほうがいいという。
では、実践知を深めていくにはどうすればいいのか。江夏氏は「社会・会社・自分の由来を振り返ることが大切」だと語る。
「振り返るときのよりどころは『事例』『理論』『歴史』の三つです。事例とは、自分の仕事に関連がありそうな自社や他社などの事象やデータが該当します。理論は人事に関する経済学や社会学や心理学などの知見。そして歴史は、自社の歴史や社会的な人事の変遷などを指します。これらの知識を重ね合わせ、統合するのです。
事例・理論・歴史と紐づけて自身の経験を振り返り、逆に、自分の経験を踏まえて事例・理論・歴史を理解し、それぞれのつながりを見出していくことで、人事パーソンとしての自分ならではの知恵につながっていくはず。いきなり三つは難しいかもしれません。まずは事例・理論・歴史のそれぞれに慣れていってください」
ただし三つの思考法は、単独で理解すべきではない。理論の裏付けのないデータ利用。いつでもどこでも当てはまるわけがないことを忘れた理論理解。具体例の想起を伴わない表層的な時代認識。こうしたことを回避するために、三つの知識の重ね合わせが必要になる。ただしそれらはきれいに調和しない部分もあるという。「この事例を説明する理論はない」「この理論が歴史的に普遍的だとは思いにくい」などと感じれば、辻褄を合わせるために事例を探す、理論を作る、歴史の推移を促す力を想像する、といった思考を重ねるのだ。
「異なる種類の知識をぶつけ合うことで、しい概念を生み出していく。これは西田さんが語った『遊びと仕事のリンク』にもつながるでしょう。人事パーソンを取り巻く環境にはさまざまなヒントが眠っています。誰かから提示されるものよりも、自分自身で気づいていったものの方が、自分を支えてくれるでしょう」

人事パーソンだけでなく、従業員一人ひとりも
「学びに没頭できる」組織へ
セッション終盤では、聴講者からの質問を交えてディスカッションが行われた。
西田:江夏先生のお話で特に響いたのが「ジャズセッション」のくだりでした。私は現職のブレインパッドに転職直後、OBにインタビューして「自走する組織はジャズセッションをやるような組織」と言われたことがあるんです。私も趣味でサックスを吹くのですが、型をちゃんと身につけた後に、オリジナルにあたるアドリブを工夫し、仲間と調和しながら楽しむプロセスは、まさに自走する組織の作り方に通じると感じます。
江夏:ジャズセッションは、各プレイヤーが型や演奏スタイルをしっかりと持っているからこそ、共演相手に合わせた自由なバリエーションが生み出せるんですよね。仕方がない状態で相手に合わそうとしたら、崩れてしまいます。まさに「形無し」です。コード進行などの一定のルールはありますが、それをどう読み解くかによってプレイヤーごとの個性が出る。人事もまた、法律の体系や組織や人の原理を理解しつつ、自社流に応用していくことが求められるのではないでしょうか。大きな組織における規則・施策について考える際は、ジャズよりもクラシックの方がしっくりくるかもしれません。楽譜にいろいろと書かれていますが、あれをどう読み解くのかも、誰と共演しているのか、自分や周りがどういう状態なのかによって変わってきます。「楽譜通り」といっても色々だし、即興が入るのです。
西田:最近では社会環境の変化に対応するため、人的資本経営が注目されています。この動きをどのように捉えていますか。
江夏:人的資本経営は、私は必要だと考えています。株主も含めた多様なステークホルダーに対し、どのように投資してリターンを生み出しているかを伝えることは大切だからです。ただ、組織から人への関わりは、投資では説明しきれません。従業員は人的資本を組織に差し出しますが、同時に人間なんです。組織に属する以外の活動もしているし、同僚との人間関係や組織への愛着もある。これらは経営の有効性には直接関係しないけれども、それを尊重できるかどうかが経営の質にじわじわと効いてくる。人事が向き合うべきは、さまざまな贈与を受けてそこに存在し、また同僚や家族など別の誰かに贈与しながら人生を送っている人間そのものです。
西田:人に向き合うことと投資対象に向き合うことは、しばしば対立するものかもしれませんね。
江夏:そんなときは立ち止まり、現場を見に行ったり、経営層に直談判したりする必要があると思います。人事の頭の中だけで解決しようとするのではなく、みんなでともに悩むことで、環境変化への対応力が高まるのではないでしょうか。時には「急ぎすぎない」ことも大切です。
西田:自分の中に時間的にも精神的にも余裕がないと、俯瞰して捉えることは難しいかもしれません。忙しい時代だからこそ、意識的に余裕を持つことが大事なのでしょう。
江夏:そうですね。本を読む、誰かに会う、といったように、忙しい日々だからこそ違う世界に身を投じるべきだと思います。西田さんもさまざまなキャリアを積み、忙しい日々を送っておられますが、さまざまな書籍や人に触れて邂逅というレベルまで体験の質を高められていますよね。なぜ、どのようにしてそこに至ったのでしょうか。
西田:一つは、「一度始めたらやめたくない」と考えているからだと思います。邂逅を大切にしているのは、仕事でも趣味でも、人との出会いから事象にのめり込んでいく要素を見つけてきたから。人と出会って信頼関係を築き、その信頼関係に基づいて始めたものは簡単にやめることはないし、もっと突き詰めていこうというドライバーがかかるんです。
江夏:そうやって何かにのめり込み、没頭することが大切なのですね。ただ没頭には、自分を活性化させる没頭もあれば、自分をつらくさせる没頭もあると思います。後者にはどう向き合っていますか。
西田:つらくなるような没頭は意識的に避けていますね。私は陶芸をやるのですが、ろくろに向かうと3時間くらい同じ姿勢で没頭してしまいます。それは脳科学的に見れば脳がニュートラルな状態になり、そこから新しい発想が生まれるから。そうした「無意識に没頭できる対象」を選び、やってみてつらいと感じるものとは距離を置いています。
江夏:リベラルアーツや哲学的思考力を習得する上で、役立ったものは何ですか。
西田:リベラルアーツに強く興味をひかれるようになったのは、ライフネット生命時代に「知の巨匠」と呼ばれる出口治明さんと出会ったことがきっかけでした。自分からアクションを起こし、薫陶を得られる人に会いに行くことも大切だと思います。私が自ら塾を運営し、さまざまな領域から塾長を招へいしたのも、新たな薫陶を得られる出会いを求めてのことでした。
江夏:もう一つ、良い学びの習慣を組織に広げていく方法についても考えたいと思います。忙しい業務の中では、個々人が「いかに学ぶか」の柱を持っていないと、どんな施策を打ち出しても絵に描いた餅になりかねません。内省やコミュニケーションを組織に導入していく上で、どのように工夫していますか。
西田:自分の好きなことだったら、忙しくても絶対に時間を作りますよね。学びにおいても、面白いものを提供してあげることが第一ではないでしょうか。おざなりのプログラムではなく、本当に面白いものを提供する。そこに触れた人は、いろいろな工夫をして学ぶようになるはずです。だから私は「人事はエンターテイナーであれ」と言っています。
江夏:人事パーソンは自らが学びに没頭することに加え、従業員一人ひとりが「これだったら没頭できる」という対象を見つけられるように後押しをするべきですね。人事パーソン自身が学びを楽しんでいる組織は、自律的な学びの輪がどんどん広がっていくでしょう。

[A]ワコールが取り組む自律型組織・自律革新型人材の育成 ~創業者から受け継ぐ想いと変革の両立~

[B-7]NLP心理学を活かしたDX推進 自律性を高めるDX人材育成と、DXをクライアントビジネスに活かす秘訣

[B]従業員の「心」に寄り添い、戦略人事を実現する「従業員体験」

[C-8]新卒3年以内の離職率50%を0%にした三和建設の取り組み

[D-3]報酬・処遇制度見直しの最前線 - ジョブ型人事制度の更なる進化と「ペイ・エクイティ」の実現に向けて
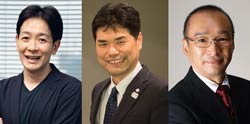
[D]モチベーション高く、いきいきと働き続ける環境をどうつくるのか 先進事例から考える「シニア活躍支援」

[E]書籍『理念経営2.0』著者と、NECのカルチャー変革から学ぶ、これからの組織の在り方

[F]「人的資本経営」推進プロジェクトはどうすれば成功するのか

[G-2]事例で理解するテレワーク時の労務管理と人事考課 テレワークでもパフォーマンスを上げる具体的な手法

[G]「対話」で見違える、個人と組織の成長サイクル ~キャリアオーナーシップ実践編~

[H-5]個々人の“違い”を活かし、超えていくチームの築き方。

[H]ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン先進企業は、過去10年に何をしてきたのか?

[I]今後の人事戦略にAIという観点が不可欠な理由 ~社会構造の変化や働く意義の多様化から考える~

[J]変革創造をリードする経営人材の育成論

[K-7]全社のDX人財育成を推進する 人事が取り組む制度設計と育成体系のポイント

[K]人事評価を変革する~育成とキャリア開発をふまえて~

[L]いま人事パーソンに求められる「スキル」「考え方」とは

[M]社員は何を思い、どう動くのか――“人”と向き合う人事だからこそ知っておきたい「マーケティング思考」

[N-1]【中小・中堅企業さま向け】組織活性化に向けた次世代リーダー(管理職・役員候補者)の育成プログラム

[N]人的資本経営の「実践」をいかに進めるか ~丸紅と三菱UFJの挑戦事例から考える~

[O-1]キャリア自律を促進する越境学習の効果と測定方法~東京ガスの事例とKDDI総研との調査結果から探る~

[O]従業員の成長と挑戦を支援! 大手日本企業が取り組む「人事の大改革」

[P]「意味づけ」と「自己変革」の心理学

[R]人的資本経営とリスキリング~中外製薬に学ぶ、経営戦略と人材施策の繋げ方~

[S-4]「カスタマーサクセス」を実現させる人材育成方法とは? ~顧客の成功に伴走する組織の作り方~

[S]多忙な管理職を支え、マネジメントを変革する人事 ~HRBPによる組織開発実践法~

[T]いま企業が取り組むべき、若手社員の「キャリア自律」支援 次代の変革リーダーをどのように育成するのか

[U-4]ハラスメント無自覚者のリスクをいかに検知し防止するか 360度評価の事例にみる無自覚者の変化プロセス

[U]事業の大変革を乗り越え、持続的成長に挑戦 CCCグループが実践する人事データ活用とタレントマネジメント

[V]日本一風通しが良い会社へ コミュニケーションを軸にしたNECネッツエスアイの組織風土変革

[W]真の「戦略人事」を実現するため、いま人事パーソンには何が求められるのか

[X-5]NTT東日本とNECが挑戦する越境体験を活用したビジネスリーダー育成

[X]事業成長を実現する採用戦略 競争が激化する市場で必要な取り組みとは



