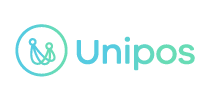「人的資本経営」推進プロジェクトはどうすれば成功するのか
- 今井 のり氏(株式会社レゾナック・ホールディングス 取締役 常務執行役員 最高人事責任者(CHRO))
- 佐藤 誉司氏(株式会社荏原製作所 執行役CHRO 兼 人事統括部長)
- 田中 弦氏(Unipos株式会社 代表取締役社長 CEO)

人的資本開示の義務化以降、人的資本経営が各社で急速に進行しているが、経営・人事・IR・現場管理職などステークホルダーが多く、苦労する企業は少なくない。プロジェクトの管理、KPIの設定、現場の実態把握などのポイントはどこにあるのか。会社統合を経たレゾナック・ホールディングスの今井のり氏、グループ・グローバルに事業を展開する荏原製作所の佐藤誉司氏の両氏が、それぞれが取り組む人的資本経営を紹介。国内外の人的資本経営に詳しく、独自の見解を発信しているUniposの田中弦氏がモデレーターを務めた。

(いまい のり)1995年慶応義塾大学理工学部卒。旧日立化成入社後、経営企画、オープンイノベーション、海外営業(米国駐在)などを経て、2019年執行役に就任。昭和電工との統合では日立化成側の責任者として統合リード。2022年から統合会社のCHROとして、HR改革や企業文化醸成、事業戦略に合致した人材育成に注力。

(さとう ようじ)1987年株式会社荏原製作所に入社後、環境プラント事業に長く携わり、 2012年青島荏原環境設備有限公司総経理、2019年荏原環境プラント株式会社取締役を歴任。2022年より株式会社荏原製作所執行役兼人事統括部長、2023年より現職。最高人事責任者としてグローバル人材戦略やDE&Iの取り組みを推進。

(たなか ゆづる)カルチャー変革を支援するUniposの提供を中心に活動。人的資本経営専門家として「人的資本経営フレームワーク(田中弦モデル)」の公開や約5000の人的資本開示から導き出した見解を発信し注目を集め、メディアへの出演多数。『心理的安全性を高める リーダーの声かけベスト100(ダイヤモンド社)』著者。
●組織遂行能力の提示と、経営学上インクルージョンへの注目
Uniposは、HR領域のソフトウエア「Unipos」の開発・提供および、組織風土改革のコンサルティングを事業の柱としている。「Unipos」は、従業員同士が、日々の行動や仕事の成果に対して「称賛のメッセージ」と共に「少額のインセンティブ」を送り合う、「ピアボーナス」を軸とした全社参加型カルチャープラットフォーム。同社独自の社内制度に由来するサービスである。ピアボーナスには、称賛文化の醸成、心理的安全性の高まり、エンゲージメントの向上、離職率の改善などの効果があるという。アナリティクス機能も備えているため、蓄積されたデータを活用・分析することで、戦略的な優先度に応じた組織課題の解決にもつながる。サービスの利用会社数は370社以上、継続率は99%に及ぶ。同社は「感情報酬を社会基盤に」をコーポレートミッションに掲げ、ピアボーナスのさらなる発展を目指している。
同社を創業した田中氏は、国内外の上場企業5000例以上の人的資本経営に関する研究を進めてきた。

「日本では未曽有の人手不足が目前に迫っています。人的資本へ投資した企業に人材が集中し、投資しない企業は人材が減り続ける“分岐点”に差し掛かっていると考えられます。AIやDXによってカバーできる面もあるとは思いますが、何かしら対処すべき状況にあることは間違いありません。
パーパスや中計を達成するためには三つの組織遂行能力が必須です。一つ目は既存事業を守る/着実に伸ばす能力(オペレーション能力・業務改善能力・DXでのコスト削減能力など)。二つ目は新規領域を伸ばす能力(挑戦量の増加・既存事業からの人員シフト・新たな能力開発・多様性など)。そして三つ目はM&Aや外部調達する能力(カルチャーの融合・多様性・採用)。これらの能力を株主や社員、求職者といったステークホルダーに正しく伝達していかなくてはなりません」
他にも、「課題がちゃんと提示されているか」「独自のKPIが設定されているか」といった、機関投資家の要望に耐えうるコーポレート・コミュニケーションに必要なチェックリストを紹介した上で、住友ゴムグループと安川電機の事例を紹介。住友ゴムグループは「挑戦」と「安住」に課題があると認識し、組織体質の改善に取り組んだ結果、「挑戦しやすい環境がある」というポジティブ回答率が8割以上に上昇。安川電機は、女性管理職の比率が低いという課題を踏まえて意識改革の施策を行い、女性従業員の管理職への意欲の高まりを示すアンケート結果が得られたという。
「“経営学上のインクルージョン”にも注目すべきだと思っています。集団の中で帰属意識が高く、かつ集団の中で自分らしさも高い状態です。日本の企業の場合『集団への帰属意識は高く、集団の中での自分らしさは低い』というケースが多いのではないでしょうか。つまり、同質性が強く、集団の中にいると安心できるけれど、物は言いづらい。この点をどうやって解決するかも重要だと感じます。例えばNIKEは、エンゲージメントスコアとインクルージョンスコアを同時開示して、すべての従業員が自分らしさを表現し、最高の自分になって潜在能力を最大限に発揮できるよう、魅力的で包括的な企業文化の創造に取り組んでいます」
●レゾナック:改革のステップに応じた施策で「共創型人材」を育成
レゾナックは、昭和電工と日立化成が2023年に統合して生まれた会社で、石油化学を中心とする伝統的な総合化学メーカーから、優れた特性や機能をもち付加価値の高い製品を中心とする機能性化学メーカーへとかじを切った。さまざまな化学製品を生産する中、半導体・電子材料の売り上げが3割以上を占め、半導体後工程に使われる材料分野では世界トップの売上高を誇る。
時代が求める機能を先端材料パートナーとして創出し、グローバル社会の持続可能な発展に貢献するためにも、「戦略」「個の能力」「組織文化」の掛け算で企業価値を向上させることが重要になると、同社の今井氏は強調する。
「個の能力」としては、「共創型人材」が必要になるという。社会課題の解決を目指し、会社や部門を超えて、共感・共鳴で自律的につながり、共創を通じて創造的に変革と課題解決をリードできる人材を意味する。トップダウンの戦略を待つのではなく、自発的に多様な技術を組み合わせ、社内外と共創しながらイノベーションを生み出すことが求められている。
「そんな人材が自由活達に動ける文化をつくるために四つのバリューを制定し、バリューが発揮できるように人事制度も改革しました。改革のステップを『経営体制の再構築』『従業員の自発性促進』『企業文化へ定着』といった3段階に分けて、各段階に応じた施策を実施しています。
長期的な取り組みになるため、ポートフォリオ変革や事業構造・成長戦略は事業部長やCFO、CSOが推進し、CEOとCHROは文化醸成や共創型人材の育成に注力する、というように役割分担しながらチームで経営しています」
具体的な施策としては、例えば「AHA!(Awards of Harmony)」という、共創やバリュー発揮を称賛するグローバルの表彰制度を実施。「タウンホール・ラウンドテーブル」では、経営陣と従業員が直接対話する場を設け、共創文化の定着を図っている。バリューに基づく人事制度や研修、実践事例を共有する交流会、共創文化の理解と浸透を図るハンドブック・勉強会なども新設した。

「特に従業員の満足度が高かったのが『モヤモヤ会議』です。悩み事や困り事があってもなかなか言えない状況はイノベーションを阻害してしまいますので、何を言ってもいい場として設けました。若手を20名ぐらい集めて、それぞれが抱えるモヤモヤをポストイットに書いてホワイトボードに貼り、マネジャーも加わってオープンに議論します。最初は自分たちのバリューで解決できないかをグループで考えてもらった後、若手自らが具体的な解決案を提案し、その場で拠点長やCEOの髙橋、私が決断する流れです。迅速な対応を見せることで会社の本気度が伝えられますし、参加者それぞれが課題を自分ごととして捉える機会にもなります。
今年は、一人ひとりがパーパスに向き合えるような『パーパス探求カフェ』を開き、自律を促しています」
変革の成果を確認し見直すために、従業員エンゲージメント調査は欠かせない。調査結果の因果探索によって施策の有効性を統計的に分析している。変革に取り組み始めた当初は「会社がどの方向に向こうとしているのかわからない」という課題が明確になったが、1年後にはパーパス・バリューの実践が16ポイント向上した。現在は「生産性を高める業務プロセスが安定していない」という課題が浮かび上がってきたため、対応を進めているところである。
「事業戦略と連動した人材ポートフォリオ構築も重要だと考えています。事業成長に向け、To Be像を策定し、現状とのギャップを埋める施策の見える化も行いました。『中長期を見据えて育成するのか』『成長領域にリソースシフトするのか』といった分類も、部門ごとに作成していきます。
人材マテリアリティ(重要課題)のKGI、KPIもまとめました。実現のための要素も示しつつ従業員の皆さんに公表することで、一人ひとりがどんどんアップデートし、フィードバックを経て、共創型人材へと育っていくと期待しています。とはいっても、定量的な数値にこだわりすぎずに、『自分らしさは何か』という定性的な部分も含めた対話も大切にしていきます」
●荏原製作所:グループ・グローバル全体で人財育成
続いて、荏原製作所の佐藤氏が、人的資本経営の実践に向けた取り組みを語った。同社は大学発ベンチャーのポンプメーカーとして1912年に創業した。現在は「建築・産業」「エネルギー」「インフラ」「環境」「精密・電子」の五つの事業セグメントで、身近な暮らしに不可欠な社会インフラや世界の産業・生活を支えている。「与えられた仕事をただこなすのではなく、自ら創意工夫する熱意で取り組み、誠心誠意これをやり遂げる心をもって仕事をすること。そして、何事も熱意と誠心をもって人に接すれば相手に通じないことは無い」。創業精神「熱と誠」を大切に、事業を拡大してきた。
「2030年の世界を見据えた長期ビジョン『E-Vision2030』を掲げ、マーケットインの視点で事業を通じた社会課題の解決に取り組んでいます。マテリアリティ(重要課題)を五つ定めていますが、その中の一つが『人材の活躍促進』です。
当社の事業が日本発からグローバルへと大きく変わっていることを念頭に、2024年の方針に『グローバルで戦える多様・多能な人財が活躍できる仕組みを整え、経営計画の実現と共に企業価値の向上に寄与すること』を打ち立てています。『多様な人財の活躍促進とグローバル基盤の確立』『グローバル共通の人財マネジメント基盤構築』『ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン』を骨子としてKPIを設定しました。2030年までにエンゲージメントサーベイスコア86以上、外国籍社員率50%以上、GKP(グローバルキーポジション)の女性比率10%以上を目標に定めて、毎年進捗をチェックしています」
人事体制としては、五つの事業セグメントに分かれてグループ・グローバルに事業を行っていくため、「横軸としてのCxO制」を導入。グループ全体の最適化を考えた視点での施策立案・ガバナンスを実行しているグローバルな人事課題、人財育成に関する活発な議論ができるようになり、グループ・グローバル全体での「人的資本経営」の強化を図る。

「必要なスキルをアルファベットの記号で表し、元素表に見立てて配列した『技術元素表』というものも更新しました。例えば、Prはプランニング アンド プロポーザルという、お客さまに最適な提案をできるスキル。Btはベアリングテクノロジー、Caはケミカルアナリシスといった具合です。これらのスキルをセグメント軸、技術軸、共通技術軸にして並べることで、事業体は違っても『こんなスキルを保有する従業員がいる』と従業員一人ひとりのタレントを広く見える化できるだけでなく、人事戦略、経営戦略の連動に生かすことができます。今後は、ファイナンスやリスクマネジメントなどのスキルも加えていく予定です」
2012年から取り組む「グローバル人財育成プログラム(GCDP: Global Career Development Program)」も、進化させているという。海外での実務経験を積むために2年間海外に派遣する育成プログラムであり、これまでに累計163名を派遣。2023年からは「海外から日本へ」や「海外から海外へ」というオプションも追加し、グループ全体を対象としたプログラムに位置付けている。グループ・グローバルで活躍する楽しさを学んでもらうことをコンセプトに、より大きな舞台に立つ人財育成を目指していく。
「グローバルでのサクセッションプランの展開やジョブポスティングといった仕組みを整備し見える化することで、グローバルに活躍できる具体的な場面を従業員に提示し、キャリアの多様性を推進していきます。人財データプラットフォームの統合、全世界共通タレントマネジメントデータベースの確立、『横軸としてのCxO制』や『技術元素表』も併せて、事業の成長をより強力にサポートしていきたいと考えています」
●対談:人事と現場をつなぐ組織体制、HRBPの重要性
最後に、ディスカッションが行われた。
田中:両社とも技術者が多いと思いますが、HRBP(ビジネスパートナー)を導入、推進するにあたって、現場を直接知らない人事に対する違和感などはなかったのでしょうか。
今井:最初は警戒されました。「人材が戦略の重要な要素、全てである」とトップメッセージを出し、新たな取り組みを次々に開始したところ、リーダーの皆さんは「ピープルマネジメントをどうしたらいいのだろう」と、結構困った状態になりました。そこで、HRBPがリーダーに寄り添い、困り事を拾っていったところ、次第に信頼を得ることができました。一緒に苦労した経験を重ねたことで、今ではHRBPは引っ張りだこです。ミーティングにも呼ばれますし、戦略議論の中にも入っています。
佐藤:当社も同じような形です。HRBPとシェアードサービスの部分を各事業に配置して、現場との距離を縮めるような体制に整えました。小さなPDCAをクイックに回していくことができるため、現場の困り事に関する解決にも迅速に対応ができます。一方、「部分最適なのか・全体最適なのか」という議論も必要ですから、CHROオフィスミーティングやグローバルHRミーティングの場を活用しながら、人事みんなで考えていく文化をつくっていこうとしています。
田中:非常に幅広い動きを取りながら施策を進めていらっしゃいますが、人事の人員は足りていますか。
今井:全然足りません。特に今は統合の過渡期でもあるので、HRBPの皆さんがいろんな問題を拾っている状態です。次のレベルに上げるために、役割と組織構成を改めて見直し、グローバルのHRメンバーを含めて配置をどうしていくか、業務の標準化・システム化でどれだけ効率化して時間を作り戦略人事にもっていけるか、といった点を大きなテーマとして議論しているところです。
佐藤:グループ・グローバルの視点での推進を考えると、足りないと感じています。より高いスキルを持った人財が集まってくれたら、もっと施策も加速できるだろうという肌感覚です。外資企業の経験を持っている人財はいるのですが、日本企業が、日本を起点としてグループ・グローバルに変革していくとなると、そこに関する知見をお持ちの方はまだ非常に少ないです。
田中:視聴者からの質問ですが、「人的資本経営とは何でしょうか」。大きな質問ですが、どのように捉えていますか。
佐藤:当社では世界中で約1万9000人以上の従業員が活躍しています。それぞれの力を最大化してグループ・グローバルに事業を伸ばしていくことが人的資本経営だと考えています。
今井:経営戦略の根幹にあるものであり、私たち一人ひとりのパーパスを、会社という器を使ってどう実現するか、社会に良い影響を与えていくか、ということだと思っています。
田中:私の考えもお話ししますと、機会さえあれば個人のポテンシャルはまだまだ引き出せるはずです。そういった個人の可能性というものをもっと信じることができるのが人的資本経営ではないかと思っています。当社の 「Unipos」は、従業員の方たちの「良い行動」を見つけて、認めて、応援することで個人の可能性を高めるプラットフォームなので、人的資本経営に役立つツールになると強く感じています。
お二方の話から、ヒントが得られたのではないでしょうか。皆さまの人的資本経営の推進に生かしていただければと思います。
Uniposはピアボーナス®を通じてカルチャーを変え、人と組織の力を引き出します。称賛文化を醸成して心理的安全性を高め、エンゲージメントの向上 / 離職率の改善を実現します。
Uniposはピアボーナス®を通じてカルチャーを変え、人と組織の力を引き出します。称賛文化を醸成して心理的安全性を高め、エンゲージメントの向上 / 離職率の改善を実現します。

[A]ワコールが取り組む自律型組織・自律革新型人材の育成 ~創業者から受け継ぐ想いと変革の両立~

[B-7]NLP心理学を活かしたDX推進 自律性を高めるDX人材育成と、DXをクライアントビジネスに活かす秘訣

[B]従業員の「心」に寄り添い、戦略人事を実現する「従業員体験」

[C-8]新卒3年以内の離職率50%を0%にした三和建設の取り組み

[D-3]報酬・処遇制度見直しの最前線 - ジョブ型人事制度の更なる進化と「ペイ・エクイティ」の実現に向けて
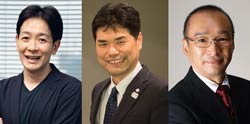
[D]モチベーション高く、いきいきと働き続ける環境をどうつくるのか 先進事例から考える「シニア活躍支援」

[E]書籍『理念経営2.0』著者と、NECのカルチャー変革から学ぶ、これからの組織の在り方

[F]「人的資本経営」推進プロジェクトはどうすれば成功するのか

[G-2]事例で理解するテレワーク時の労務管理と人事考課 テレワークでもパフォーマンスを上げる具体的な手法

[G]「対話」で見違える、個人と組織の成長サイクル ~キャリアオーナーシップ実践編~

[H-5]個々人の“違い”を活かし、超えていくチームの築き方。

[H]ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン先進企業は、過去10年に何をしてきたのか?

[I]今後の人事戦略にAIという観点が不可欠な理由 ~社会構造の変化や働く意義の多様化から考える~

[J]変革創造をリードする経営人材の育成論

[K-7]全社のDX人財育成を推進する 人事が取り組む制度設計と育成体系のポイント

[K]人事評価を変革する~育成とキャリア開発をふまえて~

[L]いま人事パーソンに求められる「スキル」「考え方」とは

[M]社員は何を思い、どう動くのか――“人”と向き合う人事だからこそ知っておきたい「マーケティング思考」

[N-1]【中小・中堅企業さま向け】組織活性化に向けた次世代リーダー(管理職・役員候補者)の育成プログラム

[N]人的資本経営の「実践」をいかに進めるか ~丸紅と三菱UFJの挑戦事例から考える~

[O-1]キャリア自律を促進する越境学習の効果と測定方法~東京ガスの事例とKDDI総研との調査結果から探る~

[O]従業員の成長と挑戦を支援! 大手日本企業が取り組む「人事の大改革」

[P]「意味づけ」と「自己変革」の心理学

[R]人的資本経営とリスキリング~中外製薬に学ぶ、経営戦略と人材施策の繋げ方~

[S-4]「カスタマーサクセス」を実現させる人材育成方法とは? ~顧客の成功に伴走する組織の作り方~

[S]多忙な管理職を支え、マネジメントを変革する人事 ~HRBPによる組織開発実践法~

[T]いま企業が取り組むべき、若手社員の「キャリア自律」支援 次代の変革リーダーをどのように育成するのか

[U-4]ハラスメント無自覚者のリスクをいかに検知し防止するか 360度評価の事例にみる無自覚者の変化プロセス

[U]事業の大変革を乗り越え、持続的成長に挑戦 CCCグループが実践する人事データ活用とタレントマネジメント

[V]日本一風通しが良い会社へ コミュニケーションを軸にしたNECネッツエスアイの組織風土変革

[W]真の「戦略人事」を実現するため、いま人事パーソンには何が求められるのか

[X-5]NTT東日本とNECが挑戦する越境体験を活用したビジネスリーダー育成

[X]事業成長を実現する採用戦略 競争が激化する市場で必要な取り組みとは