HRアワード入賞企業に聞く
企業の成長と人財の成長を結びつける自律型組織に必要な人事制度とは
- 杉山 誠氏(株式会社シグマクシス Vision Forestチーム ディレクター)
- 山本 政史氏(東洋アルミニウム株式会社 人事総務ユニット並びにグループ安全統括チーム担当 常務執行役員)
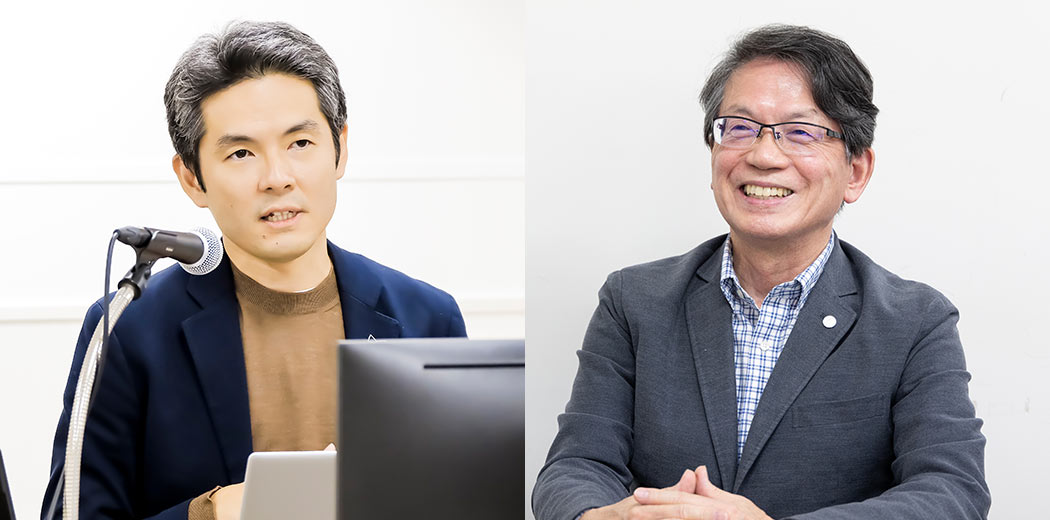
市場競争力の源泉がモノからコトへシフトし、社員一人ひとりのキャリア志向も多様化している中、企業は自律型組織への変革が求められている。企業経営における「社員一人ひとりの個性を活かし、成長を支援できる自律型の組織に変革できるか」という観点は、価値を創造し続ける企業であり続けるために非常に重要だ。本講演では、全社変革を2年間で実現した東洋アルミニウムの取り組みを紹介。東洋アルミニウム人事担当常務の山本政史氏と、同社の人事制度変革を支援するシグマクシスの杉山誠氏が「自律型組織のあり方」や「自律型組織に求められる人事制度」について考察した。

(すぎやま まこと)野村総合研究所に新卒入社、情報通信業界を中心に事業戦略立案・新規事業立上げと幅広いテーマを中心に取り組む。その後スタートアップ企業を経て、2014年シグマクシスに参画。人財組織のテーマを中心に多数の企業変革を支援、ワークショップのファシリテーターやリーダーとの対話に強みを持つ。

(やまもと まさし)大学卒業後、1980年に東洋アルミニウム(株)入社。技術者として主に加工品事業の生産・製造技術並びに新製品開発に従事し、群馬製造所長を経て2018年5月まで加工品事業を率い、その後人事部門に異動して経営プラットフォーム(MX)改革の中で責任者として人事制度改革に携わり現在に至る。
従来の規律型組織の中に自律型組織を取り込んでいく
株式会社シグマクシスは、企業のデジタル・トランスフォーメーション(DX)、サービス・トランスフォーメーション(SX)、マネジメント・トランスフォーメーション(MX)の「3つの変革」を実現するコンサルティング・サービスを提供している。同社が開発した人財・組織変革プログラム「Vision Forest」では、自ら変革し続ける人財・組織作りを支援している。
「Vision Forest」チームがミッションに掲げているのは「自ら変わり続ける個と組織を創る」。時代や環境の変化に対して自ら試行錯誤し、変化を生み出す力を身に着ける新しい人財・組織作りをサポート。人の想いやリアルな課題と向き合い、ありたい姿への実現を促す組織変革プログラムを個社ごとに設計・提供していることが特徴だ。
Vision Forestでチームディレクターを務める杉山誠氏は「『自ら未来を描き、変化と創造を仕掛ける個』が企業の中でいかに活躍できるかが非常に重要です。企業がそうした個人を活かしていくためには、変化と創造を生み続ける組織、まさに自律型組織の構築が必須です」と語る。
杉山氏はまず、自律型組織の定義を説明。自律型組織とは、トップダウンで決められたことを実行するのではなく、パーパスやMission/Vision/Valueを判断基準として、社員が自律的に考え行動し、チームワークでその目的・目標を実現する組織であるとしている。
従来、多くの企業でマネジメントされてきた規律型組織は、生産の効率性を追求して利益を最大化するスタイル。対して自律型組織は、複雑で予測可能な変化に適応し続けるため、多様な価値観を重視する組織だ。
「我々は規律型組織も重要だと思っており、『すべての組織が完全に自律型に切り替えるべき』というわけではありません。規律型でマネージした方がうまくいく組織はこれまで通り運用しながら、自律型組織の方が成功確度を上げられるものがあれば、どのように組織の中に取り込んでいくかを考えていきましょう」
「自律的に考えて行動しなさい」では自律型組織にはなり得ない
では、規律型組織の中でどのように自律型組織の要素を組み込んでいくのか。ポイントは「(1)何のための自律化なのか=事業戦略との整合性」と「(2)どこから自律化を進めていくか=現在のステージと変革のアプローチ」を見極めて一貫性をもって設計する、組織のグランドデザインを描くことだ。
「きちんとした規律でマネージしている組織であればあるほど、自律型組織に変えるのは難しい。フェーズを分けながら、『事業がこう変わっていくなら組織はこう変えていく』という大きなストーリーを描くことも大切です。時間をある程度かけて、目安では約2年かけて自律型に転換していくことが求められます」
一方で、自律型組織を目指しているにもかかわらず「この場合はこういうふうに自律的に動け」という規律的なプロセスで推進していては自律型組織にはなり得ない。
例えば、制度・システム側のアプローチで、組織・人財の要件を細かく正確に定義してしまうと、社員の考える力を奪ってしまう。また、人財側のアプローチとして、マネージャーの意識変革のために研修ばかりを実施しても、概念を理解したところで具体的な行動に落とし込めず、結局変わらなかったり元に戻ってしまったりすることも多い。つまり、変革推進ストーリーを描く中でも、自律的なプロセスが求められるのだ。
「ルールブックが分厚くなればなるほど、人は規律的になっていきます。ルールはいかにシンプルでみんなに腹落ちするものを設計できるかがポイントです。制度・システムは、最終判断は『人』がするという前提に立ち、最低限のルールのみ決めます。判断の余地を残すことで、〇〇トランスフォーメーションといった今後新たな業務やプロジェクトが出てきても、一つひとつ行動要件を定義する必要がありません。また、対話する環境を作ることで自律的に考えることを習慣化することも、運用ルール設計において重要です」

ここで杉山氏は、シグマクシスが考える人事制度変革について解説した。制度や評価基準はシンプルに示し、対話と議論を通して人の評価を考えて決めて運用する。そして、制度の運用を通してマネージャーの「人を見る力(抜擢)・活用する力(配置)・育てる力(育成)」を養う。そうすることで自律型マネジメントスタイルが定着するという。
その自律型マネジメントスタイルを後押しする制度も必要だ。従来型の人事制度では、個人のキャリアの決定権は会社にあり、等級は単一のキャリアモデルで、個人業績・達成度にフォーカスがあたり、報酬も平等性を重視するため複雑な制度になってしまいがちだった。シグマクシスが考える人事制度変革の方向性は、キャリアの決定権は個人にあり、シンプルでわかりやすい制度を全社員が意識的に使いこなせるというものだ。
「等級は多様なキャリアモデルを提示し、個人評価は『いかに自分の能力を高めたか』『会社にとって必要な能力を高めたか』という能力評価。一方業績評価は、チームのコラボレーションがベースとなるため、チームでいかに成果が出せたかで評価されていく。そしてシンプルな報酬テーブルの設計が必要だと考えています」
2年間で自律型組織への変革を行った東洋アルミニウム
続いて、東洋アルミニウムの山本氏が登壇。同社が2020年4月から取り組む人事制度改革について紹介した。2022年で創業91年を迎えた東洋アルミニウムは、2031年に迎える100周年を前に、組織再編や人事制度の改定、Mission/Vision/Valueといった経営理念の再設定などに取り組み、プロジェクトを発足している。
本プロジェクトでは、2年後の姿を「全社員が、顧客にとってベストとは何かを考え、その実現に全力を尽くしている」「全社員が、生産性を向上させることが社員・会社・株主にとって重要であることを理解し、実践している」「全社員が、ミッション・ビジョンを軸に一体となり、高いモチベーションによって、価値創造を成し遂げている」と策定。自律型人財・組織の育成に向け、経営プラットフォーム改革に着手した。
2021年4月の経営理念再設定では、新たに「未来を創る、私が創る、みんなで創る」というスローガンを掲げた。Missionを「社会に新たな常識を」、Visionを「自分にも世界にも誇れる会社」、Valueを「楽しさ想像力」「誠実さ・真摯さ」「顧客とともに」と、設定した。このMission/Vision/Valueを実現する土台作りとして、人事制度改革を実施。改革の主なアジェンダは「新たな職群の創設」「個人業績評価の廃止」「能力評価制度の導入」「OKRによる目標マネジメント」の四つだ。
「一つ目の『新たな職群の創設』では、年功序列・役職に基づく職能資格から『発揮能力』に基づく等級へ変更。これまでの資格職群制度では、非管理職と管理職相当というラインが1本しかありませんでしたが、等級が上がるに従ってマネジメントとして活躍する人財と、プロフェッショナルとしてキャリアアップできる2ラインに改正。役職と等級を完全に分離することで、マネジメント業務に限らず、得意分野での能力発揮によるキャリアアップが可能になりました。
二つ目の『個人業績評価の廃止』では、年功による定期昇給はせず、賞与の個人業績も廃止。報酬は発揮する能力に基づき決定し、賞与は組織業績に基づき配分することで、個人間の競争からチームによる共創を促す仕組みへと変更しました。マネジメント職群、シニアプロフェッショナル職群及びプロフェッショナル職(総合職)以上のメンバーは全てシングルレートで月次給与を決定しています。
三つ目の『能力評価制度の導入』は、今回最も力を入れました。年功序列を中心とした人事制度から脱却し、客観的な評価が得られる仕組みを作り、自分自身が自己申請することで初めて昇格をしていくというスキームへと変更。自分でキャリアを形成して自律的に動けるような能力評価制度へと改革しました。
能力評価基準は、全社統一のシンプルなものを使用。評価項目は日常の業務の遂行に関する能力を最大7項目と、Mission/Vision/Valueをどれだけ体現できているかを問うヒューマン能力も設定しました。また評価プロセスは、上司の評価だけでなく別の組織の上位職、つまり斜め上からのアセッサー評価やパネル評価により複数の目線で評価。正解のない評価に組織的に向き合い、一人ひとりに対するフィードバックの質を向上させています。これだけ社員の評価に時間をかけたのは、東洋アルミの91年の歴史の中ではありません。今後は、形骸化しないように継続性のある運用へとブラッシュアップしていきます。
四つ目は『OKRによる目標マネジメント』。OKRそのものは能力評価には使用せずに、あくまでも目標達成が会社への貢献に繋がることを前提にしています。「『ワクワクする』目標として、簡単には手の届かない達成率6~7割のObjectivesを設定。また、四半期ごとに、経営チームとユニットリーダー・チームリーダー間でOKRの共有会を開催しています。経営チームも参加し、社員の困りごとを聞き取りサポートする場になっています」
以上の人事制度改革の効果に山本氏は「まだ緒に就いたばかり」というが、「未来を創る、私が創る、みんなで創る」というスローガンのもと、具体的な動きもある。例えば、2021年4月の組織変革の抜てき人事で起用した若手の新リーダーによる成果創出が実現した。パネル会議やOKR共有会で各組織の取り組みや悩みを共有することで、部門を超えた新しいコラボも生まれている。自律的キャリア形成の支援策としては、2023年1月からキャリア開発支援制度を導入予定だ。
「制度は作って終わりではありません。ダーウィンの進化論の『唯一生き残ることができるのは変化に対応できるもの』という言葉を肝に銘じて、現状に合わせて毎年ブラッシュアップし、従業員が納得感を持って自律的にキャリアアップできる制度に変えていくことによって、9年先に迎える100周年を笑顔で迎えたいと考えています」と、山本氏は意気込む。

改革における議論では「健全な対立」も重要
続いて、杉山氏と山本氏によるディスカッションが行われた。
杉山:従来の制度も、とりわけ不満が出ているものではなかったと思います。そうした中、これほどの大改革を行ったことで、社内の反発はありませんでしたか。
山本:新しい経営プラットフォームへの改革は、従業員にとっては期待も不安もあったと思います。新制度に変革していくうえで大事なことは、まず経営陣が心を一つにすることです。制度設計にあたってはシグマクシスさんから、分科会、その上の全役員を含んだ推進コアミーティング、その上のステアリングコミッティーという3階層の仕組みをご提案いただきました。分科会や推進コアミーティングで事業本部サイドを巻き込んだことで、全員が自分ごとに捉えることができ、不安を緩和するプロセスで推進できました。
また、「総論賛成、各論反対」もよくあることです。制度の中身を作り込んでいく議論では、時に意見が食い違うこともありました。それは健全な姿だと思っていまして、意見を戦わせることなく制度ができてしまうことこそが最も危険です。反対意見も異論もありながらブラッシュアップしていった制度だからこそ、「自分たちで作り上げた」と自分ごと化が進んだ背景のひとつですね。
杉山:私も伴走する中で、「健全な対立」は重要なプロセスだったと感じています。最後に、山本さんから一言お願いします。
山本:制度改革の信念は、絶対に軸をぶらしてはいけないと思っていますし、私もそれを肝に銘じてやってきましたし、今もその思いは変わりません。一方で、運用面においては、ブラッシュアップしてより良いものにしていくためには柔軟に変える勇気も必要です。組織を成長させていくためには、これからも「変わらぬ信念と、変える勇気」を貫くことが重要だと確信しています。
杉山:本日は貴重なお話をありがとうございました。

[A-2]従業員エンゲージメントは、何のため? ~EX(従業員体験)を基点に考える、当社の取り組み事例~

[A]これからの時代に必要な「人材マネジメント」と「データ活用」とは? ――人事パーソンに求められる役割

[B-4]人的資本の情報開示 その先に待つこと ~取組みの課題と対策のポイント~

[B]日本企業にはなぜぶらさがり社員が多いのか? 〜キャリア自律が進まない理由とその処方箋

[D]人事に求められる「聴く力」 社員の声を引き出し、より良い組織をつくる

[E-2]【産業医・臨床心理士が解説!】コロナ禍で増える休職者を支援し、サステナブルな働き方を実現するポイント

[E]成長企業が実践している、従業員エクスペリエンスを向上させる組織づくりとは

[F-2]優秀なDX人材の雇用に不可欠な『報酬戦略』とは 国内市場報酬トレンドの最前線から紐解く

[F]心理的安全性を高めるリーダーの流儀 ~組織を生まれ変わらせるリーダーの「振る舞い」と「声かけ」~

[G]キャリア形成と学びをめぐる変化の本質とは

[H-4]ワーク・エンゲイジメントの第一人者が語る、職場のポジティブメンタルヘルス対策のポイント

[H]越境学習は組織に何をもたらすのか その効果を最大限に高める方法を考える

[I]カインズ、三井情報が実践! 従業員の「キャリア自律」を実現する「組織風土改革」

[J]学び続ける組織 -個人の学びが組織に広がるサイクル-

[K-5]管理職のマネジメントスタイルをアップデート 360度フィードバックを活用した仕組みづくり

[K]「パーパス」とは何か~その重要性と取り組みについて考える~

[L]仕事に対する“モヤモヤ”を“ワクワク”へ変える 働きがいを高め人的資本経営を実現する「心理的資本」とは

[M]「人的資本経営」推進の鍵~NECの12万人の組織風土変革を紐解く~

[N-3]23,000名以上の適性検査結果傾向から見るパワハラ行為者にありがちな6タイプと上司教育のアプローチ

[N]ミドルシニアが活躍する企業は何が違うのか? NTTコミュニケーションズ、日本マクドナルドのアプローチ

[O]「今どきの若手は……」と言わせない! 自律的成長を促す若手社員育成“虎の巻”
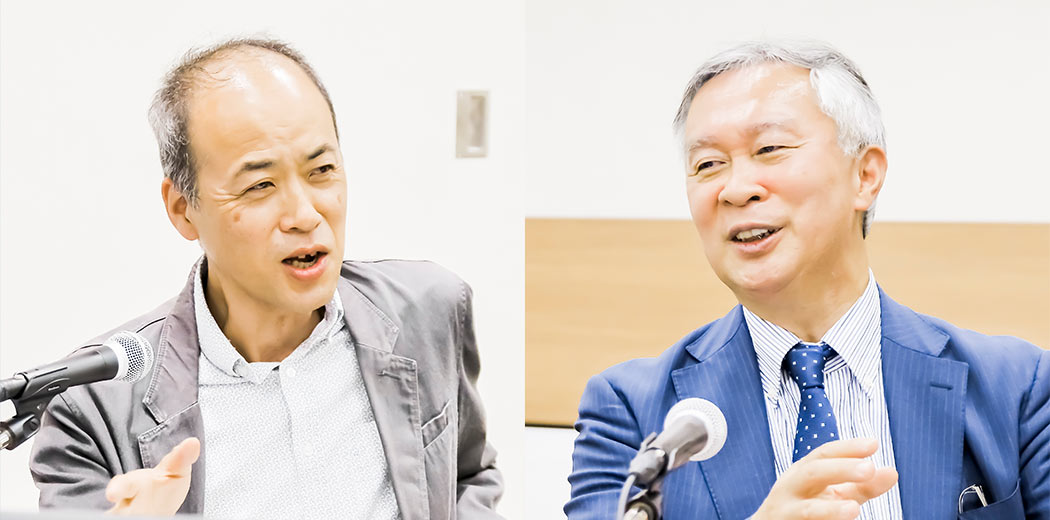
[P]カゴメの事例を基に考える、自社に必要な「タレントマネジメント」

[Q-1]1対1面談を組織に導入・定着させるために人事が行うべき4ステップ

[Q]自社に関わる全ての人を幸せにする経営とは ワーク・エンゲイジメント向上から考える「ウェルビーイング」

[R]今後の組織強化に欠かせない「ピープルエクスペリエンス」は、採用やマネジメントの概念をいかに変えるか

[S-2]サッポロHDが経営戦略で取り組む「越境人財の育成」の必要性と人財活用のビジョンとは

[T]企業戦略の推進に不可欠な「オープンな組織」と「テクノロジー活用」の在り方・進め方とは

[U-8]360度フィードバックはなぜ機能しないのか!? ~バンダイナムコアミューズメント・紀伊産業から学ぶ真の多面観察とは~

[U]Hondaが挑む、変革のカルチャー推進と学びへの文化醸成 ~企業文化の掘り起こしと自律的キャリア形成~

[V-7]「しなやかさ」で考える、これからの人と組織の関係性 人的資本の基盤づくりに必要な4つのポイント

[V]いかに人事がDX推進に関わるか 味の素社のデジタル変革に学ぶ、「ビジネスDX人財」の育て方

[W-6]HRアワード入賞企業に聞く 企業の成長と人財の成長を結びつける自律型組織に必要な人事制度とは

[W]企業が変わり続け、発展し続けるために。 経営戦略と人事戦略を連動させた「人事の大改革」

[X-7]日立ソリューションズの事例に学ぶ、 HRテクノロジーを活用した人事業務の効率化

[X]人事パーソンはどう働き、どんなキャリア戦略を考えているのか? 「シン・人事の大研究」調査結果報告 第2弾



