人事に求められる「聴く力」
社員の声を引き出し、より良い組織をつくる
- 谷本 美穂氏(グーグル合同会社 執行役員 人事本部長)
- 江澤 身和氏(株式会社スープストックトーキョー 取締役副社長 兼 人事本部長)
- 堀田 美保氏(近畿大学 総合社会学部 総合社会学科 教授)

人事に求められる「聴く力」とは、人事が一方的に傾聴することではない。組織をより良くするための「聴く-語る」の継続によるコミュニケーションだ。グーグルの谷本氏、スープストックトーキョーの江澤氏、近畿大学の堀田氏が人事に求められる「聴く力」について議論した。

(たにもと みほ)大学卒業後、2000年GEに入社。戦略人事、組織開発、リーダーシップ開発に携わり、一貫してグローバルリーダー育成とビジネスに寄り添い変革を起こす人事パートナーを志向してきた。2016年よりGEジャパン株式会社 執行役員 人事部長。2018年より現職。イノベーションを起こす組織づくりを推進する。

(えざわ みわ)短大卒業後、フリーターを経て2005年にスープストックトーキョーのパートナー(アルバイト)として入社。社員登用後は店長を歴任し、法人営業グループへ異動。2016年、取締役兼人材開発部長に着任。現在は取締役副社長 兼 人事本部長として新たな採用・育成の仕組みづくりに取り組んでいる。

(ほった みほ)大阪大学大学院前期課程、人間科学研究科を修了後、カナダCarleton大学にてPh.D(Psychology)を取得。現在、近畿大学 総合社会学部 心理系専攻にて、社会心理学などを担当。アサーティブジャパン認定講師、理事。『アサーティブネス: その実践に役立つ心理学」(ナカニシヤ出版)を上梓。
人事に求められる「聴く力」~社員の声を引き出し、より良い組織をつくる
堀田氏ははじめに、聴く力につながるアサーティブコミュニケーションについて解説した。アサーティブ(assertive)とは自己主張する、という意味だ。
「アサーティブコミュニケーションとは、自分の感情や提案や価値観を大事にしながら、相手の状況や相手が大事にすることにも配慮していくコミュニケーションです。自己主張と他者配慮のバランスを取るコミュニケーションといえます」
アサーティブな言い方を身に付けると、人との関係性がよくなると堀田氏は語る。組織の心理的安全性を醸成するうえでも役に立つという。
アサーティブコミュニケーションで大事なことは他者配慮であり、人の声を「聴く・訊く」ことがポイントになる。
企業の中で人の話を聴くことには、どのような効果があるのか。社員個人には「メンタルヘルスが維持・改善される」「労働意欲が高まる」「働きがい・生きがいが生まれる」といった心理的メリットがある。業務的には「仕事の効率が上がる」「強みを活用できる」「活気が生まれる」といったことが期待できる。堀田氏は、今日は「聴く」だけではなく、その一歩先まで行きたいと語る。
「一歩先とは聴くことで、組織を『より良い組織』にしていくことです。社員の話を聴くことにより、その内容を制度・仕組み・商品・サービスに生かしていくことができます。これは組織的なメリットです」
しかし、人には資質・経験・価値観の多様性がある。一人ひとり大事にしていることは異なり、意見も違う。全員の声に応えることは不可能だ。意見が通らなかった人は幻滅感、不公平感、無力感に苛まれることになる。
「単に『全員に話を聴けばいい』というわけではありません。自分の意見が通らなかったときに、ネガティブな感情が生まれてしまえば、次から話すのをやめてしまう可能性があります。つまり、継続的に意見を話してもらうには『話してよかった』『話したことで少し変わった』と思ってもらい、『自分も何かの役に立てている』といった、『語ることの効力感』が必要です。また、こうした語りを続かせるには、よい聴き手の育成も必要です。
今日はお二人に、『組織メンバーの一人ひとりから聴くために』、また、『聴くことで得たことを組織づくりに活かすために』、そして『聴く-語るが継続していくために』、大切にしていることや心構え、具体的な工夫についてお聞きしたいと思います」

本音を話してもらうためには、問いのつくり方や関係性構築が重要
堀田:参加者から事前にいただいた質問への回答から始めたいと思います。一つ目は「人事は傾聴するだけでは足りないのか。どうしたら人事として引き出したい声が引き出せるか」という質問です。谷本さんいかがですか。
谷本:人事の仕事において聴く目的は二つあると思います。一つ目は社員一人ひとりと向き合い、その人の悩みやキャリアで困っていることなど、その人そのものを知るための1対1の対話。二つ目は組織全体を一つのシステムと捉え、「みんなは今、組織に対してどんなことを感じているのか」を知るために、社員の声を集めるヒアリングです。私がこれまで聴く作業を続けてきて、徐々に気づいたことは問いの大切さです。「どんな質問を投げかけるのか」によって、出てくる反応はまったく違ってきます。問いのつくり方が鍵になるのではないでしょうか。
堀田:具体的には、どのような問いのつくり方が必要ですか。
谷本:例えば、フィードバックをもらうときに「この人の強みは何か」ではなく「強みが行動としてどのように表れていますか」とたずねる、弱みを訊くときには「この人がさらによいリーダーになるためにはどんなアドバイスがありますか」といった問いをつくります。
堀田:質問する際はできるだけ具体的なことを聴くこと、改善点を聴くことが大事です。曖昧な問いには、曖昧な答えしか返ってきません。改善点も「この人が何をすればいいか」といった具体的な改善点を導くことが必要です。この点について、江澤さんはいかがですか。
江澤:関係性がとても大事だと思っています。最初は誰でも「この人に本音を話しても大丈夫か」という状態から始まります。きちんと心を開かないと、本音はなかなか話してもらえません。私が営業として働いていたとき、営業の同僚は何でも話してくれていたのですが、私が人事になるとなかなか話をしてくれないことがありました。「人事に話すと、誰にどう話が広がるのかわからない」と考え、本音が言えなくなっていたのだと、私自身が話を聴く立場になってはじめてわかりました。谷本さんも言われていましたが、関係性を築くためにはまず一人ひとりを知るところから始め、そこから段々と話を聴くようにするというステップが大事だと思います。

堀田:一日で人との関係性は作れませんから、一つずつ信頼を築くようにして、焦らないことは大事ですね。次はチャットからの質問です。「年上部下との対話で苦労しているが、どのように聴けばよいか」ということです。
江澤:私にも年上部下はたくさんいます。基本的なスタンスとして、年齢に関係なく相手に敬意を持って接します。皆さんそれぞれに得意なことや強みがとてもあるので、それを理解し敬意を払いつつも、できるだけ対等に話をするようにしています。また、年齢によって接し方を変えると、距離感を感じさせてしまうときがあるようです。年上の方には敬語で話し、年下の方には少しラフな言葉で話していると、それを見た年上の方から「自分たちには壁をつくっている」と思われたりします。そのため、誰に対しても丁寧に話をする、丁寧な言葉を使うことを意識しています。
堀田:私もアサーティブを行ううえでは、誰に対しても同じ態度で接することを意識しています。常に相手に対するリスペクトをもって、相手をまっすぐに見つめる。そのためには、その人のいい部分をきちんと知っておいて、日頃から「本当にこの人はすごいな」とか「頑張っているな」という行動を見ておくことが必要ですね。
江澤:正直、年上の人からすれば、私に対して「この人で大丈夫かな」と心配に思う部分はあると思います。私も決して強がらずに、できないときには助けてもらうなど、弱い部分もさらけ出しながら、互いに助け合える関係性をつくりたいと思っています。
谷本:リスペクトの話で思ったのですが、まさに相手へのリスペクトがグーグルのカルチャーのキーワードです。これが本当にうまく多国籍の人たちをつないでいると感じます。逆にいえば、人へのリスペクトがないと社内では評価されません。リスペクトのない行動は評価に響く、マネジャーはリスペクトを見せなければいけないなど、カルチャーが一人ひとりの行動につながる人事の仕組みができあがっています。それによって皆が「リスペクトのある行動って何だろう」と考えるようになり、日頃の人への接し方、聴き方につながっているように思います。

堀田:リスペクトを評価に組み込む企業はなかなかないですね。次ですが、「一度でも会えれば信頼関係をつくりやすいが、テレワークでの信頼関係の築き方での工夫はあるか」という質問です。
谷本:テレワークを行っていて思うのは、リモートでも関係性はつくれるということです。ただし、雑談の時間をあえてつくったり、会議の合間でお互いのことを知る時間をつくったりする工夫は必要です。そうしたうえで実際に会うと、誰もが笑顔になって会話も盛り上がります。関係性が良くなると、仕事の生産性向上につながり、組織もよりオープンになっていきますね。
堀田:例えば、ミーティングの5分前や10分前に集まって、わいわいと話してからスタートするやり方もいいですよね。
谷本:あえて意図的に対話するメニューをつくる方法もいいと思います。例えばグーグルでは、夏休みシーズンが終わったときに、「夏休みをどのように過ごしたかを1枚のスライドで紹介しよう!」というミーティングを行いました。こうした対話セッションはフレームワークをつくれば誰でも簡単にできるので、たくさん行うといいと思います。そうするとお互いのことを知って、よりオープンになっていきます。それこそ、聴くことが自然にできるようになると思います。
声を挙げてくれた社員たちと、「一緒に解決策を探る」関係性をつくる
堀田:では続いて、「組織全体で傾聴力を上げていくにはどうすればいいか」という質問です。
谷本:私はグーグルに来て学んだことがあります。グーグルのプロダクトが強いのは、「ユーザーの声を聴く」ことを一生懸命やっているから、ということです。その考え方を社員にも当てはめていて、「社員はいろんなヒントやアイデアを教えてくれるから常に聴く」ことが徹底されています。常に、事あるごとに、聞きます。たとえばタウンホールミーティングで、リーダーばかりが話をするのではなく、みんなの声も聞きます。それが終わったら「今日のタウンミーティングはいかがでしたか」と簡単なサーベイを行い、また声を聞く。もう常に聞いています。続けていると、どんどん社員がオープンになっていきます。
オープンになるには、覚悟も必要です。社員から寄せられる質問には「これは答えづらい」「その質問はここでしなくてもいいんじゃないか」「この意見は厳しすぎるのではないか」などと思うものもあります。でも、オープンに質問してもらって、みんなで対話の中で消化するようにしていると、最終的にはポジティブな方向に向かいます。そのため、出てきた意見をジャッジせず、まずは声を上げてくれた人に「勇気を出して言ってくれてありがとう」と伝えるようにしています。
堀田:「意見が反映されなかった方に対して、心がけていることは何か」という質問が複数きています。
江澤:「言ったのに何もしてくれなかった。これは不公平だ」と思ってしまうのは、社員が受け身の姿勢だからだと思います。人事がしっかりしていれば会社が良くなるわけではありません。一人ひとりの社員が、会社のこと、ブランドのことを自分ごととして考えていかないと何も変わりません。私にも変えられること、変えられないことがあるので、今、自分たちにできることについて、社員と一緒にすり合わせています。そこでの基本的なスタンスは「一緒に変えていこう、一緒に考えよう」というものです。ちょっとネガティブな声があったとき、それに気づいた人こそが一番の解決策を持っているように思います。そういう人には詳しく意見を聴くスタンスで接しています。
谷本:江澤さんの話には私も共感します。タウンホールで厳しい意見や要望が出て、それに対してただノーと答えれば、やはり炎上します。でも同じノーでも、「一体なぜノーなのか」「どういうプロセスを経てノーに至っているのか」をシェアすると、みんな安心します。また、強い意見を持つ人には、個別にアプローチして対話するようにしています。本人の言い分を、一度きちんと聴くことは大事です。そこで、まさに江澤さんがおっしゃったように、意見の裏にある「何を解決したいのか」という、根本の「何」を聴ければ、別の解決策が見つかるかもしれません。聴くことも大事ですが、対話を行うこともすごく大事だと思います。
堀田:ある問題があるとき、自分ができること、相手ができることをすり合わせながら、少しずつ解決の方向に向かっていくイメージですね。一方的に「頼る、頼られる関係」にならないことは大事ですね。では、最後にお二人が現場で「聴く」ことを、組織づくりに活かす際のノウハウや実践例があればお聴きしたいと思います。
江澤:私が人事になったとき、最初に行ったのは社員との面談でした。「これからの働き方を考えたいから、話を聴かせてほしい」と依頼し、「ネガティブなことこそ言ってほしい」と伝えて行いました。ただ漠然と聴くのではなく、何のために聴くのかを伝えておくことは、一番深い部分までヒアリングするうえでも大事だと思います。その結果、人事制度を決めるときも、その制度を採用することで喜んでくれる社員が浮かぶものを選べましたし、リリースするときも、「みんなの声を聴いたので、これに決めました」と伝えることができました。
谷本:ここまでお話したように、対話することで出てきたものがアクションとなり、それに対する意見を聴くというサイクルを回しています。それともう一つ、社内でリスニングセッションを行っています。例えば戦争やジェンダー問題など、何か話したいことがある人が話を聴いてもらえるセッションです。毎回、ポツポツと意見が出てきて、最終的には結構心に響くものになります。こうした試みが結果としてウェルビーイングにつながるといいなと思っています。
堀田:アサーティブのテクニックとして、言いづらいときには言いづらい気持ちを正直に言う、というものがあります。そうした姿勢が物事の突破口になることもあります。本日は、それぞれの会社で使えるようなキーワードが聴けました。ぜひ現場で生かしてください。ありがとうございました。

[A-2]従業員エンゲージメントは、何のため? ~EX(従業員体験)を基点に考える、当社の取り組み事例~

[A]これからの時代に必要な「人材マネジメント」と「データ活用」とは? ――人事パーソンに求められる役割

[B-4]人的資本の情報開示 その先に待つこと ~取組みの課題と対策のポイント~

[B]日本企業にはなぜぶらさがり社員が多いのか? 〜キャリア自律が進まない理由とその処方箋

[D]人事に求められる「聴く力」 社員の声を引き出し、より良い組織をつくる

[E-2]【産業医・臨床心理士が解説!】コロナ禍で増える休職者を支援し、サステナブルな働き方を実現するポイント

[E]成長企業が実践している、従業員エクスペリエンスを向上させる組織づくりとは

[F-2]優秀なDX人材の雇用に不可欠な『報酬戦略』とは 国内市場報酬トレンドの最前線から紐解く

[F]心理的安全性を高めるリーダーの流儀 ~組織を生まれ変わらせるリーダーの「振る舞い」と「声かけ」~

[G]キャリア形成と学びをめぐる変化の本質とは

[H-4]ワーク・エンゲイジメントの第一人者が語る、職場のポジティブメンタルヘルス対策のポイント

[H]越境学習は組織に何をもたらすのか その効果を最大限に高める方法を考える

[I]カインズ、三井情報が実践! 従業員の「キャリア自律」を実現する「組織風土改革」

[J]学び続ける組織 -個人の学びが組織に広がるサイクル-

[K-5]管理職のマネジメントスタイルをアップデート 360度フィードバックを活用した仕組みづくり

[K]「パーパス」とは何か~その重要性と取り組みについて考える~

[L]仕事に対する“モヤモヤ”を“ワクワク”へ変える 働きがいを高め人的資本経営を実現する「心理的資本」とは

[M]「人的資本経営」推進の鍵~NECの12万人の組織風土変革を紐解く~

[N-3]23,000名以上の適性検査結果傾向から見るパワハラ行為者にありがちな6タイプと上司教育のアプローチ

[N]ミドルシニアが活躍する企業は何が違うのか? NTTコミュニケーションズ、日本マクドナルドのアプローチ

[O]「今どきの若手は……」と言わせない! 自律的成長を促す若手社員育成“虎の巻”
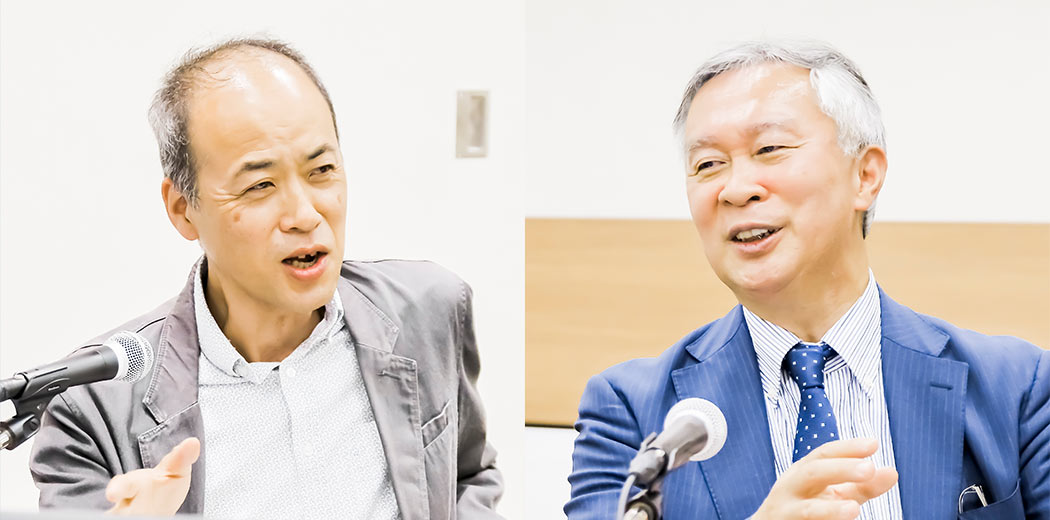
[P]カゴメの事例を基に考える、自社に必要な「タレントマネジメント」

[Q-1]1対1面談を組織に導入・定着させるために人事が行うべき4ステップ

[Q]自社に関わる全ての人を幸せにする経営とは ワーク・エンゲイジメント向上から考える「ウェルビーイング」

[R]今後の組織強化に欠かせない「ピープルエクスペリエンス」は、採用やマネジメントの概念をいかに変えるか

[S-2]サッポロHDが経営戦略で取り組む「越境人財の育成」の必要性と人財活用のビジョンとは

[T]企業戦略の推進に不可欠な「オープンな組織」と「テクノロジー活用」の在り方・進め方とは

[U-8]360度フィードバックはなぜ機能しないのか!? ~バンダイナムコアミューズメント・紀伊産業から学ぶ真の多面観察とは~

[U]Hondaが挑む、変革のカルチャー推進と学びへの文化醸成 ~企業文化の掘り起こしと自律的キャリア形成~

[V-7]「しなやかさ」で考える、これからの人と組織の関係性 人的資本の基盤づくりに必要な4つのポイント

[V]いかに人事がDX推進に関わるか 味の素社のデジタル変革に学ぶ、「ビジネスDX人財」の育て方

[W-6]HRアワード入賞企業に聞く 企業の成長と人財の成長を結びつける自律型組織に必要な人事制度とは

[W]企業が変わり続け、発展し続けるために。 経営戦略と人事戦略を連動させた「人事の大改革」

[X-7]日立ソリューションズの事例に学ぶ、 HRテクノロジーを活用した人事業務の効率化

[X]人事パーソンはどう働き、どんなキャリア戦略を考えているのか? 「シン・人事の大研究」調査結果報告 第2弾


