「人的資本経営」推進の鍵~NECの12万人の組織風土変革を紐解く~
- 佐藤 千佳氏(日本電気株式会社 コーポレート・エグゼクティブ)
- 川内 正直氏(株式会社リンクアンドモチベーション 常務執行役員)

2022年の注目キーワードとなった「人的資本経営」。多様な人材が活躍する文化の醸成や、それを組織の力とする人的資本経営の考え方は、持続的に企業を成長させるために必要不可欠だ。とはいえ、人的資本経営で求められる要素は多岐にわたり、「どこから手を付けていけばいいのか」「どのように推進していくべきなのか」と問題 視する声も少なくない。そこで本セッションでは、従業員数約12万人の規模で組織文化改革を進めるNECの佐藤千佳氏を招き、現在進行形の人的資本経営の実践例を紹介。リンクアンドモチベーションの川内正直氏とともに、事業と組織を強くするための具体的なアクションを考えた。

(さとう ちか)1982年住友電気工業(株)入社。1996年よりGEにて、組織開発、HRBP、企業買収・統合業務やHRリーダーを経験。2011年より日本マイクロソフト(株)執行役人事部長、ノキアにて日本・東アジア地区HRリーダーを経て、2018年日本電気(株)へ入社。カルチャー変革、人事改革、インクルージョン&ダイバーシティをリードする。

(かわうち まさなお)入社後、組織人事領域のコンサルティングに加え、新規拠点立ち上げ、新規事業部門立ち上げを担当。2010年、西日本地域の組織人事コンサルティング部門の執行役員に当時最年少で着任。グループ会社の取締役を経て、2018年、同社の取締役に就任。現在はグループ最大規模である組織変革コンサルティング部門の責任者に着任。
人的資本開示で伝えるべきなのは
How(情報の羅列)ではなくWhy(人事戦略ストーリー)
まず、モデレーターを務める株式会社リンクアンドモチベーション 常務執行役員の川内正直氏が登壇した。
2000年に創業したリンクアンドモチベーションは、社名に「モチベーション」を掲げる通り、人的資本を企業の競争優位の源泉と考え事業展開を進めている。2016年にサービス提供を開始した組織改善クラウドサービス「モチベーションクラウド」は、従業員エンゲージメント市場において5年連続で売上シェアナンバーワン。また、同サービスは 日本の人事部「HRアワード2022」において、組織変革・開発部門で最優秀賞を受賞した。
リンクアンドモチベーション社も東証プライム上場企業として人的資本開示を実践。人的資本に関する情報開示のガイドラインである「ISO 30414」認証を世界で5番目、日本・アジアでは初めて取得している。
従業員数を問わず 幅広い企業の課題解決に携わってきた経験に基づき、川内氏は人的資本経営が注目されている背景として「三つの市場の変化」を挙げた。三つの市場とは、企業を取り巻く「資本市場」と「商品市場」、そして「労働市場」だ。
「資本市場では無形資産である人的資本への注目が高まっており、環境変化に対応できる組織のあり方が求められています。商品市場ではソフト化と短サイクル化が進み、ヒット商品の賞味期限が短くなる中で、企業は次々と新たな基軸を打ち出していく必要性に迫られています。労働市場においては人材の流動化と多様化によって、企業が働く場所として選ばれ続けることの難易度が高まっているのです」
では、人的資本経営を実現するためには何が必要なのか。川内氏は「人事戦略と組織施策をリンクさせることが重要」だという。
「人事に携わる方々は、人的資本開示で求められる各項目に対応して情報を出していくことに戦々恐々としているかもしれません。しかし、大切なのはHow(単なる情報の羅列)ではなく、Why(人事戦略ストーリー)を伝えることです。企業としてどのようなパーパスの実現を目指しているのか、そのためにどんな人事戦略を描いているのかをストーリーで語ることによって、見かけ上の数値の浮き沈みではなく、取り組みへのプロセスや本気度が市場に伝わるはずです」

ここで示された人事戦略ストーリーを社内外に共有し、約12万人を擁する大規模な組織の風土改革に取り組んでいるのがNECだ。
コミュニケーション改革で従業員の本音と向きあう
次に日本電気株式会社(NEC) コーポレート・エグゼクティブの佐藤千佳氏が登壇し、NECにおけるカルチャー変革とダイバーシティの取り組みを説明した。
1899年に設立されたNECは、長い歴史と伝統を持つ「典型的な日本の大企業」だった。そんな同社が2018年の中期経営計画以降、大規模なカルチャー変革に挑んでいる。佐藤氏はその背景について、「収益構造の改革と成長の実現、さらに『実行力の改革』が求められていた」と明かす。かつてのNECは、綿密な戦略やプランを立ててもなかなか成果につなげられないという問題を抱えていたのだ。
「取り組みを推進するため、2018年4月にはカルチャー変革本部が設立されました。カルチャー変革の三本柱として打ち出した人事制度改革、働き方改革、コミュニケーション改革を実行していくには、日常のオペレーションを担う既存の主管部門のほかに、新たな専門部署を置くことが必要だと考えたのです」
コミュニケーション改革の一環として、経営層や人事が従業員の声と徹底的に向きあう取り組みが進められた。2018年以降は社長自身が従業員と向きあう「ダイアログセッション」を全国各地の拠点で開催し、約1万人が参加。しかしここで明らかになったのは、経営陣が予想していたよりもはるかに根深い問題だったという。
「事後に取ったアンケートには、現状に不満や不安を覚えている従業員の切実な声が書かれていました。『無駄な仕事が多い』『人事評価がフェアではない』『NECは大企業病に陥っている』など、従業員からのさまざまな指摘が届きました」
この結果を受けて、カルチャー変革本部は課題を整理し、六つのキードライバーに分類した。経営力の再構築、オープンで分かりやすいコミュニケーション、社員の主体性と創造性を引き出す仕組み、プロセスと仕事のシンプル化、責任の明確化とフェアな評価、そしてNECの行動規範である“Code of Values”の浸透とマインドセットチェンジだ。これらのキードライバーに基づき、さまざまな施策を展開していった。
「”Code of Values”は、約12万人のNEC従業員が体現すべきことを示したグローバル共通の行動規範です。個人の年間評価にも適用されるようになりました。以前は数字ばかりが評価され、プロセスや行動、あるいは将来の種まきなどはあまり評価されていなかったのですが、Code of Valuesに基づいて成果だけでなく行動も評価する制度へと変わりました」

サーベイ参加率急上昇の背景にある「即時対応」
カルチャー変革と合わせて、NECでは2018年よりダイバーシティ推進も進められている。これも中期経営計画に盛り込まれた重要事項だ。
「従前のNECには自前主義があり、外部の知見をあまり取り入れてきませんでした。しかし市場環境の激しい現在、自前主義だけでは限界があります。私たちが必要とする知見を持つ人材をキャリア採用でどんどん取り入れていくとともに、同質性の高い組織から、女性や外国人など多様な人材が活躍できる組織へと改革しているのです」
多様な人材が集まるようになった今、佐藤氏は「NECの既存メンバーと新たなメンバーを融合させ、切磋琢磨しながら成果を出していけるようにするのが次のチャレンジ」だと話す。2021年に打ち出した新たな中期経営計画では、重要KPIとしてエンゲージメントスコアを掲げ、現状の35% から2025年度に50%へ引き上げることを目標としている。
こうしてさまざまな改革を進めるNECでは、発信するメッセージや展開する施策が現場へ根づいているかを測るための取り組みも進めてきた。65問の設問とコメントをグローバルで収集する年1回の「One NECサーベイ」に加え、四半期ごとに20問弱の設問を投げかけるパルスサーベイを実施。各サーベイに対する従業員の反応からも改革の手応えを感じているという。
「分かりやすい変化として表れているのがサーベイの参加率です。2018年に始めたタイミングではわずか26% でしたが、直近の2022年9月は85% まで上昇しました。人事からサーベイへの参加を呼びかけてきたことも要因だと思いますが、それ以上に、従業員からの声に即時対応してきちんと施策に反映してきたことがサーベイの意義につながっているのだと考えています」
組織変革の入り口は「固定観念を溶かす」ことから
続いては、佐藤氏と川内氏によるトークセッションが行われ、参加視聴者からの質問も反映しながら人的資本経営の実践について意見が交わされた。
川内:これまで進めてこられたカルチャー変革やダイバーシティ推進の取り組みの中でも、特に大変だったのはどんなことでしょうか。
佐藤:大変な部分は、取り組みのフェーズによって変わっていったように思います。当初は新しいことを始めるにあたって、言葉で説明してもなかなか従業員に伝わりませんでした。どうしても過去にとらわれがちで、何かをやるにしても「それはNECでは前例がない」「昔やったことがあるけどうまくいかなかった」という言葉でストップしてしまうこともあったんです。
川内:やはり取っかかりの部分が最も苦労するんですね。
佐藤:はい。取り組みやすいところから手を着 けるものの、すぐに変化が見えてくるわけではないので、人事としては疲弊しそうになってしまうかもしれません。また、取り組みを進める中で従業員の共感は得られるようになってきたものの、実例はまだまだ少ないのが現状。組織変革の実感値が広がっていくのはこれからだと思っています。

川内:当社でもいろいろな企業の組織変革をお手伝いしていますが、最初は固定観念を溶かすところからスタートします。頭では分かっていても、どうしてもすぐに結果を求めてしまいがちなんですよね。
佐藤:そんな状況でも、走り続けなければいけないというプレッシャーも感じています。気を緩めてしまうと元に戻ってしまうのではないかと。経営陣とのコミュニケーションも重要ですね。変化には時間がかかるという前提を共有しているものの、エンゲージメントスコアなどの指標になかなか変化が表れないと、経営陣からは不安の声も聞かれます。
川内:その点で言えば、「役員の本気度を引き出すのが難しい」と感じている人事パーソンも多いと思います。組織変革では上から変えていくことがセオリーとはいえ、これはなかなか難しい。佐藤さんはどのように経営陣へ働きかけているのでしょうか。
佐藤:経営戦略とつなげて語るようにしています。カルチャーや人事の話題は「数字のほうが大切だから、ふんわりとした話はいらない」と言われてしまいがちなんですよね。だから私は市場が何を求めているのか、どんなアクションが必要なのかを経営戦略と接続して語るようにしているんです。
川内:先ほどの佐藤さんのプレゼンでは評価に関する話題も上っていました。業績の評価は分かりやすいですが、”Code of Values“に基づいた行動の評価はどのように進めているのでしょうか。
佐藤:行動評価のポイントは、同質性の高い人たちだけでなく、多様性のある集まりで議論していくことだと考えています。評定の際には上司陣や担当HRが集まり、複数の観点を重ね合わせて議論しています。あわせて、周囲からフィードバックを得られるシステムも導入しました。また、取り組みを始めた当初は適正な評価がなされない可能性も考慮して、行動評価が金銭的な報酬にダイレクトに結びつかないようにしましたね。議論が熟して評価者の目が育ってきたタイミングを見計らい、導入3年目ごろから昇給などにつなげていきました。
重要なのは指標クリアではなく、自社の変革ストーリーを追っていくこと
川内:2021年からの新たな中期経営計画では、従業員エンゲージメントを重要指標に掲げています。この背景を教えてください。
佐藤:エンゲージメントを高めるのは大変ですが、これが企業の成長の源泉になることは間違いありません。従業員それぞれの中にある「この会社で何を成し遂げたいのか」「どんなふうに世の中へ貢献していきたいのか」といった思いの力は、とても強い。だからこそNECではエンゲージメントを重要視しています。ただ、会社が本気で取り組んでいることは伝わるようになったものの、スピード感はまだまだ。サーベイを見ると全体的にエンゲージメントは高まっていますが、若手層は最も伸びが鈍いんですよ。これからの時代を担う人たちにとって、現状の変化のスピード感ではまだまだ足りないということなのだと考えています。
川内:NECの場合はシニア層も多いと思いますが、シニア層のエンゲージメント向上についてはどのようなアプローチを取っていますか。
佐藤:役職定年を撤廃しました。以前は55歳あたりで役職定年となり、その後は働きがいを感じられないまま過ごす人が多かったようです。定年まで常に緊張感を持ち、個人と社員が対等な立場で仕事に取り組むためには、役職定年は必要ないと判断しました。自身の役割をポジティブに見出せるシニア層を増やしていきたいと考えています。
川内:私自身は、NECの取り組みを聞いて、従業員からの生々しいネガティブな声をオープンにしていることが素晴らしいと感じています。多くの企業はそうした従業員の本音を隠そうとしがち。しかしNECはマイナスな声もオープンにし、向きあう姿勢を示しています。
佐藤:きれいごとではなく、従業員の声はものすごく貴重なものだと思っています。意識して声を聴き、制度や施策に反映させることで、着実に現場に根づいていくのだと実感しました。
川内:ダイバーシティの取り組みについてもお聞かせください。同質性の高い組織では、無意識的にバイアスが働いてしまうことがあると思います。この問題をどのように乗り越えたのでしょうか。

佐藤:いわゆるアンコンシャスバイアスは、まだ取り除けていません。まさに今、部下を持つピープル・マネジャーに対してアンコンシャスバイアスの研修を行っているところです。従来のNEC管理職は日本人男性を中心とした極めて同質性の高い集団だったので、自分たちとは違う属性への想像力が働かない面があるのも事実。たとえば、女性の部下に対して「この仕事をお願いしたら大変だろう」と配慮しているつもりが、結果的には本人の貴重な経験の場を奪っていることもあります。研修ではそうした実例を伝えながら、意識変革を促しています。
川内:あらためて、佐藤さんは人的資本経営を実践する上で最も大切なポイントは何だと考えますか。
佐藤:自社が今どんな状態にあるのか、何に注力していくべきなのかをストーリーとして示すことだと思います。人的資本経営に向けてはさまざまな指標が示されていますが、フォーカスすべき部分は企業によって異なるはず。指標をどんどんクリアできても、それがゴールではありません。変革に向けた中長期のストーリーを実現できているか。そんな視点で職場の変化を見つめ、進捗を把握しながら社内外へ共有していくことが大切だと考えています。
川内:本日は素晴らしいお話をありがとうございました。
2000年4月に創業した世界初の「モチベーション」にフォーカスした経営コンサルティング会社です。当社の基幹技術「モチベーションエンジニアリング」は、経営学・社会システム論・行動経済学・心理学などの学術的成果を取り入れ、実行性と再現性を強みに、創業以来多くのお客様の企業変革をサポートしております。
2000年4月に創業した世界初の「モチベーション」にフォーカスした経営コンサルティング会社です。当社の基幹技術「モチベーションエンジニアリング」は、経営学・社会システム論・行動経済学・心理学などの学術的成果を取り入れ、実行性と再現性を強みに、創業以来多くのお客様の企業変革をサポートしております。

[A-2]従業員エンゲージメントは、何のため? ~EX(従業員体験)を基点に考える、当社の取り組み事例~

[A]これからの時代に必要な「人材マネジメント」と「データ活用」とは? ――人事パーソンに求められる役割

[B-4]人的資本の情報開示 その先に待つこと ~取組みの課題と対策のポイント~

[B]日本企業にはなぜぶらさがり社員が多いのか? 〜キャリア自律が進まない理由とその処方箋

[D]人事に求められる「聴く力」 社員の声を引き出し、より良い組織をつくる

[E-2]【産業医・臨床心理士が解説!】コロナ禍で増える休職者を支援し、サステナブルな働き方を実現するポイント

[E]成長企業が実践している、従業員エクスペリエンスを向上させる組織づくりとは

[F-2]優秀なDX人材の雇用に不可欠な『報酬戦略』とは 国内市場報酬トレンドの最前線から紐解く

[F]心理的安全性を高めるリーダーの流儀 ~組織を生まれ変わらせるリーダーの「振る舞い」と「声かけ」~

[G]キャリア形成と学びをめぐる変化の本質とは

[H-4]ワーク・エンゲイジメントの第一人者が語る、職場のポジティブメンタルヘルス対策のポイント

[H]越境学習は組織に何をもたらすのか その効果を最大限に高める方法を考える

[I]カインズ、三井情報が実践! 従業員の「キャリア自律」を実現する「組織風土改革」

[J]学び続ける組織 -個人の学びが組織に広がるサイクル-

[K-5]管理職のマネジメントスタイルをアップデート 360度フィードバックを活用した仕組みづくり

[K]「パーパス」とは何か~その重要性と取り組みについて考える~

[L]仕事に対する“モヤモヤ”を“ワクワク”へ変える 働きがいを高め人的資本経営を実現する「心理的資本」とは

[M]「人的資本経営」推進の鍵~NECの12万人の組織風土変革を紐解く~

[N-3]23,000名以上の適性検査結果傾向から見るパワハラ行為者にありがちな6タイプと上司教育のアプローチ

[N]ミドルシニアが活躍する企業は何が違うのか? NTTコミュニケーションズ、日本マクドナルドのアプローチ

[O]「今どきの若手は……」と言わせない! 自律的成長を促す若手社員育成“虎の巻”
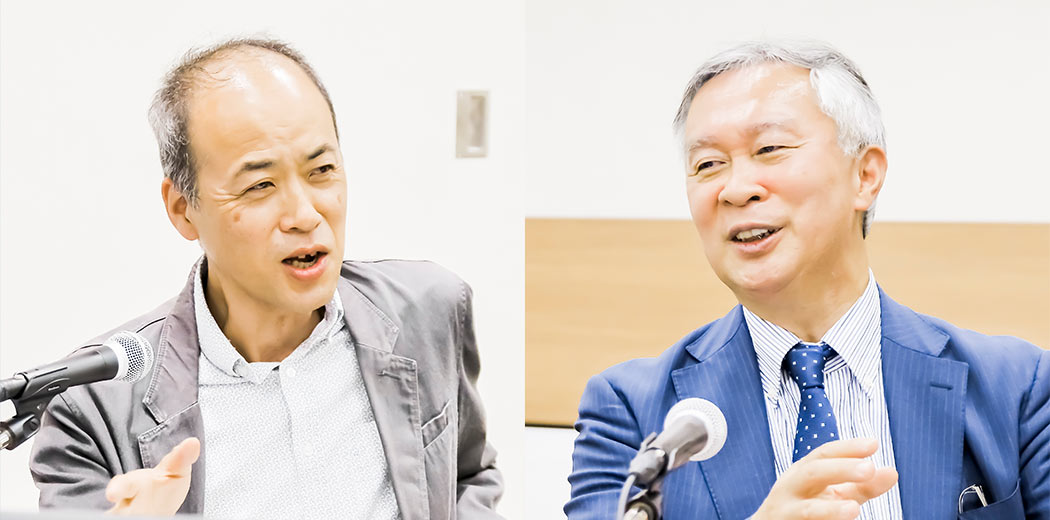
[P]カゴメの事例を基に考える、自社に必要な「タレントマネジメント」

[Q-1]1対1面談を組織に導入・定着させるために人事が行うべき4ステップ

[Q]自社に関わる全ての人を幸せにする経営とは ワーク・エンゲイジメント向上から考える「ウェルビーイング」

[R]今後の組織強化に欠かせない「ピープルエクスペリエンス」は、採用やマネジメントの概念をいかに変えるか

[S-2]サッポロHDが経営戦略で取り組む「越境人財の育成」の必要性と人財活用のビジョンとは

[T]企業戦略の推進に不可欠な「オープンな組織」と「テクノロジー活用」の在り方・進め方とは

[U-8]360度フィードバックはなぜ機能しないのか!? ~バンダイナムコアミューズメント・紀伊産業から学ぶ真の多面観察とは~

[U]Hondaが挑む、変革のカルチャー推進と学びへの文化醸成 ~企業文化の掘り起こしと自律的キャリア形成~

[V-7]「しなやかさ」で考える、これからの人と組織の関係性 人的資本の基盤づくりに必要な4つのポイント

[V]いかに人事がDX推進に関わるか 味の素社のデジタル変革に学ぶ、「ビジネスDX人財」の育て方

[W-6]HRアワード入賞企業に聞く 企業の成長と人財の成長を結びつける自律型組織に必要な人事制度とは

[W]企業が変わり続け、発展し続けるために。 経営戦略と人事戦略を連動させた「人事の大改革」

[X-7]日立ソリューションズの事例に学ぶ、 HRテクノロジーを活用した人事業務の効率化

[X]人事パーソンはどう働き、どんなキャリア戦略を考えているのか? 「シン・人事の大研究」調査結果報告 第2弾



