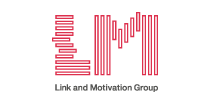100年企業カゴメの人事改革から紐解く、「人的資本経営」推進のポイント
- 有沢 正人氏(カゴメ株式会社 常務執行役員 CHO(最高人事責任者))
- 川内 正直氏(株式会社リンクアンドモチベーション 常務執行役員)

変革の時代において、持続的に企業を成長させていくために注目されているのが「人的資本」を軸にした経営だ。2022年5月13日に経済産業省「人的資本経営の実現に向けた検討会」が発表した“人材版伊藤レポート2.0”においても人的資本経営に向けた提言が盛り込まれ、話題となった。一方で人的資本経営の推進には、人事制度の抜本的な改革や従業員エンゲージメントの向上が求められ、その取り組みは容易ではないのも事実。顧客と従業員、そして投資家をはじめとしたステークホルダーから選ばれる企業となるためには何が必要なのか。人的資本経営の取り組みを進めるカゴメ株式会社 常務執行役員 CHO(最高人事責任者)の有沢正人氏を招き、実践へのヒントを探った。

(ありさわ まさと)1984年に協和銀行(現りそな銀行)に入行。 銀行派遣により米国でMBAを取得後、主に人事、経営企画に携わる。その後、HOYA株式会社やAIU保険会社にて、職務等級制度やグローバル人事制度構築の多くを主導する。2012年1月にカゴメ株式会社に入社。2012年10月より現職となり、国内だけでなく全世界のカゴメの人事最高責任者となる。

(かわうち まさなお)入社後、組織人事領域のコンサルティングに加え、新規拠点立ち上げ、新規事業部門立ち上げを担当。2010年、西日本地域の組織人事コンサルティング部門の執行役員に当時最年少で着任。グループ会社の取締役を経て、2018年、同社の取締役に就任。現在はグループ最大規模である組織変革コンサルティング部門の責任者に着任。
企業を取り巻く「三つの市場」から注視される人的資本経営

冒頭ではモデレーターを務める株式会社リンクアンドモチベーション 常務執行役員の川内正直氏が登壇し、本セッションのテーマである「人的資本経営」について解説した。
2000年に創業したリンクアンドモチベーションは、経営の肝を「人」「組織」「モチベーション」と位置づけて顧客企業への支援を行っている。2016年にサービスを開始した組織改善クラウドサービス「モチベーションクラウド」は、エンゲージメント市場において5 年連続でナンバーワン(※1)となり、多くの企業に導入されている。
※1 ITR「ITR Market View:人材管理市場2022 」 従業員エンゲージメント市場:ベンダー別売上金額およびシェア (2017〜2021 年度予測)
川内氏は、こうした事業を通じて「良い会社の定義を変えることを目指している」と語る。
「良い会社とは、規模や売上高だけで決まるものではないと考えています。今後の社会ではサステナブルに事業を継続できる企業こそが『良い会社』だと見なされるはず。私たちはそのために組織診断と変革、そして世の中へ公表していくというサイクルを回し、良い会社の定義を変えたいと思っています。自社も良い会社となるべく、日本・アジア初、世界でも5番目に、人的資本に関する情報開示のガイドラインである『ISO 30414』(※2)の認証を取得しました」
※2 社内外のステークホルダーに対して人的資本に関する情報開示を行うためのガイドライン。ISO(国際標準化機構)が2018年12月に発表した。
なぜ今、人的資本経営の考え方が注目されているのか。川内氏は「企業を取り巻く三つの市場、つまり商品市場・労働市場・資本市場のそれぞれから求められているのが人的資本経営である」と説明する。
「商品市場ではソフト化と短サイクル化が起きており、次々と新しい価値を提供していくために人的資本が重要になっていることは言うまでもありません。
労働市場という面では、応募者から選ばれ続ける企業であることが重要です。人材の流動化と多様化が進む中、応募者から選ばれ続けることの難易度は高まり続けており、自社らしさをいかに追求して発揮するかが課題になっています。
さらに資本市場においても人的資本開示というキーワードが注目を集めています。報道でも大きく取り上げられるようになり、今後は人的資本をいかに開示していくかが、投資家から選ばれる際の大きな要素となるでしょう」
顧客からも従業員からも、そして投資家からも選ばれる会社を作っていく。そのために注目される人的資本経営だが、非常に難易度の高い取り組みであることも事実だ。本セッションでは人的資本経営を推進するためのヒントを探るべく、人的資本経営を実践するカゴメ株式会社 常務執行役員 CHO(最高人事責任者)の有沢正人氏を迎えた。
経営の最重要ミッションは人的資本の価値を高めること

有沢氏は、「カゴメは約8年前から人的資本経営に取り組んでいる」と紹介した。
「背景には、カゴメの企業風土を変えなければならないという思いがありました。それまでの当社は、年功序列の職能資格制度を継続していました。私は年功序列や職能資格制度を単純に悪だと断じるつもりはありません。しかし従来の評価制度の中では、上司によって評価が変わってしまうという問題が起きていました」
そこで有沢氏は経営トップに直談判。「今、変わらなければカゴメは潰れるかもしれない」と強く訴えたという。
提言したのは評価基準を明確にし、それを公開すること。その前提として中期経営計画では「人材戦略こそが経営戦略の中で最も重要である」と位置づけ、経営の最重要ミッションとして人的資本の価値を高めることを共有した。
こうした流れの中で同社はジョブ型人事制度を導入していった。有沢氏は「ジョブ型人事制度はあくまでもツールに過ぎず、導入自体が目的ではない。ジョブ型を導入することでさまざまな変革を進めやすくなった」と振り返る。
「変革の入り口で行ったのは、ジョブグレードや評価基準を統一して目盛りを明確にすることでした。次にコア人材のサクセッション・プランを策定し、加えてグローバル教育体制を強化していったのです。当社では、職務等級制度などのジョブ型システムは役員から導入しました。まずは社長や役員の報酬制度と評価制度を変え、そこから従業員へも展開していきました」
一般的にジョブ型人事制度ではジョブ・ディスクリプション(職務記述書)の運用が重要だとされているが、カゴメではジョブ・ディスクリプションを作ったことがないという。その代わりに運用されているのが「人材要件定義書」だ。職種ごとに求められる人材要件を言語化し、共有することで、従業員のジョブが頻繁に変わっても柔軟に対応できるようにしている。
「ジョブ型人事制度を導入したことによって、職能資格制度の時代よりも人事戦略を進めやすくなりました。どのポジションにどんなミッションがあり、何をやれば評価されるのかが明確になり、統一された基準のもとでぶれのない評価ができるようになりました」
「適所適材」でキー・ポジションの後継人材を育成
同時にカゴメは、10年先を見据えた次世代経営者づくりにも注力している。ジョブ型人事制度の考え方に則り、40以上のキー・ポジションを設定。それぞれにどのような人材が望ましいのかを明確化し、後継人材の育成状況を可視化しているのだという。
「キー・ポジションに関しては、社長と二人の専務、そして私の四人からなる『人材開発委員会』が意思決定しています。担当者レベルの一般層は原則人ベースのマネジメントを行っていますが、管理職以上になるとポジションベースのマネジメント。たとえば『東京支社・営業第一部の部長には誰が適任なのか』など、個別具体的に人材選定を進めていきます」
こうした手法について、有沢氏は「適材適所ではなく『適所適材』の考え方に基づいている」と説明する。
人材開発委員会では、経営の肝となるキー・ポジションの現任者に後継人材育成の状況をヒアリング。後継人材候補の指名には、現任者が管掌する本部からの輩出を半数以下に抑え、半数は別部門から選ぶようにも求めている。部門利益ではなく全体利益を代表し、顧客へ価値を届けられる人材を育てるためだ。
「執行役員候補には現在の部長から相当数を選び、部長候補には現在の課長から数十人を選ぶ。こうして後継人材育成のサイクルを回しています。明確な人材育成計画のもと、それぞれが目指すポジションで求められる要件を満たせるよう、高いレベルの研修プログラムを実施していきます」
目標設定と評価が正しく機能していない「ファクト」を突きつけた
続いて、セッション視聴者から寄せられた質問を踏まえ、川内氏と有沢氏がQ&A形式でカゴメの取り組みをさらに深掘りした。
川内:有沢さんのプレゼンテーションから、人的資本経営を行う上では経営戦略と人材戦略がイコールであり、リンクしていることが重要なのだと感じました。中期経営計画などで描かれる経営戦略は、基本的に時間軸が長いもの。人材についても、その場の対応ではなく長期的な視点で描かれるべきではないでしょうか。そうした観点から、カゴメの取り組みがどのようなストーリーでつながっているのかを聞いていきたいと思います。
まず、有沢さんは人的資本経営を進めるにあたってトップに直談判したということでしたが、多くの企業では「総論賛成、各論反対」といった状況に陥りがちです。どんなふうにトップの共感を得ていったのでしょうか。
有沢:私がどのような課題意識をトップにぶつけたのか、その背景をご説明します。
私は2012年にカゴメへ入社し、その年にオーストラリアの子会社を視察しました。その子会社のCEOに「営業部長の評価シートを見せてほしい」と言ったところ、最初は出し渋られたのです。何とかシートを見せてもらうと、営業部長の期初の第一目標として“Meet many people”、つまり「多くの人に会うこと」と書かれており、結果として「多くの人に会えた」ことが評価されていました。これが営業部長の第一目標として本当に適切なのか、疑問を禁じ得ませんでしたね。当時は国内拠点でも、同じような状況があちらこちらで見られました。目標設定と評価が正しく機能していなかったのです。
それまでの職能資格制度は「SABCD」の5段階評価。A評価で5ポイント、Bで4ポイント、Cで2ポイントが与えられるといった建て付けで、16ポイントを取れば上の職位へ上がれるようになっており、これを4年間で取るというのが慣例となっていました。つまり4年間B評価を継続すればいいわけです。結果的には当たり障りのない目標設定と評価が行われるようになり、Sを取る人などほとんどいない、Dについてはカゴメの120年の歴史の中で一人もいないという状況でした。これは現場が悪いのではなく、こんな制度を作った経営の責任だと感じました。
しかし当の経営側は、組織がこうした現状に陥っていることを知らなかったのです。そこで私は50ページにおよぶレポートを社長に出し、現実を伝えた上で、どのように変革していくべきなのかの処方箋を9つ提示しました。その中で第一に経営戦略において人材戦略が最重要であることを内外に示す。第二に職能資格と決別してジョブ型へ移行する。第三に報酬評価制度を変える。そして第四に、それまでなかった役員の評価制度を入れるといった内容です。
つまりトップとのコミュニケーションで言えば、「なぜ今のままではいけないのか」というファクトを突きつけ、その上でどうすればよいのかまで提言することが大事だということです。
全部署の業務内容、全従業員のKPIを共有
川内:続いての質問では「下位職級における人材要件の粒度に悩んでいる」という悩みが寄せられています。下位職級では業務内容が多岐にわたるため人材要件が曖昧になりがちだが、これでは職能資格制度と変わらないのではないか、という悩みです。

有沢:下位職級の人材要件は非常に難しいところですよね。種明かしをすると、カゴメは担当者レベルの一般層にはジョブ型制度を導入していません。対象は管理職だけです。
たしかに、担当者レベルでは例えばプロジェクトのようなさまざまな仕事が振られる現実があります。ジョブ・ディスクリプションが設定されていると柔軟に対応できなくなり、従業員の成長を阻害してしまいかねない。だからカゴメでは管理職だけを対象としました。
川内:一般職内のジョブローテーションは実施していますか。
有沢:かなり頻繁に行っています。カゴメのタレントマネジメントシステムでは、異動希望を第1希望から第5希望まで出してもらうのです。たとえば「東京支社の第一営業部のどのポジションのどの仕事をやりたい」といったことまで細かく希望を出してもらい、HRBPがその理由をヒアリングしていきます。結果的に、5〜6割は希望が通るようになっていますね。「やりたい人がやりたい仕事をやればいい」という考え方で運用しています。
川内:そもそもジョブ・ディスクリプションを作っていないという話は衝撃でした。職務内容の理解が人によってぶれてしまうことはないのでしょうか。
有沢:カゴメの場合は、イントラネット上で各本部・各部署が課単位・グループ単位まで業務内容を明確にしています。一方で個人はKPIシートを作り、五つの大項目と25の小項目を設定し、全従業員に公開。新入社員でも私のKPIシートを見ることができます。それぞれが何をいつまでに、どこまでやるかが共有されているので、職務内容への理解や評価がぶれません。こうやって定量化することが大切であり、透明性と公開性は、人的資本の取り組みやジョブ型への移行において大きな意味を持っていると感じています。
川内:社内にどんなポジションがあるのか、誰がどのポジションを担い、どのような目標を掲げているのか。それらがすべて明確に共有されているのですね。
有沢:はい。役員同士でも、誰がどんなミッションを担うのかを膝詰めで話し合って決定しています。その内容が経営戦略や人材戦略につながっていることを人材開発委員会で確認し、一斉にイントラネットで公開。かつ、各本部長には掲げた内容についてプレゼンしてもらい、全社の視点が統一されるようにしています。
川内:期中で事業環境が変わったときは、目標設定を変更するのでしょうか。期初にすべてを決めるのは難しい時代でもありますよね。
有沢:期中の目標変更はもちろんあり得ます。そして変更した際には、変更した理由も私のところへ届くようになっています。たとえば昨今の原材料価格高騰は、昨年には予測できなかった部分もある。期初に立てた目標がすべてではありません。そうやって柔軟に対応しなければ、エンゲージメントが下がってしまいますよね。
「降格・降職」も含めた大変革を進めるために意識したこと
川内:後継者育成についても教えてください。数千人の従業員がいる中で、一人ひとりの能力をどのように測っているのでしょうか。

有沢:カゴメではキー・ポジションとして、執行役員や本部長、さらにジョブグレードが一定以上の部長職など、40以上のポジションを設定しています。こうしたポジションを担当している人の成果が人材要件に届かなかった場合は、降格や降職もあり得ます。あくまでも「このポジションには誰についてもらうべきか」を考え、結果に応じて、さらに上のポジションを担ってもらったり、残念ながら降格してもらったりといった判断をしています。
川内:日本企業の場合は、降格への抵抗感を持っている組織が非常に多いと思います。これをスムーズに進めるために必要なことは何でしょうか。
有沢:最初にジョブ型へ移行した際は、相当数の方が降格となりました。当然反発の声も多かったですよ。私は全員と面談し、なぜジョブ型へ移行しなければならないのか、どんな理由で降格となったのかを丁寧に説明しました。全員に納得してもらえるかどうかは別としても、説明責任は私たちにあります。その責任を尽くしていくしかありません。
ちなみに、最初に降格したのは役員でした。従業員はそれを見て「ポジションにかかわらず降格・降職があり得るのだ」と認識するようになったのです。こうした過程も、キャリア自律への変化のために必要だったと考えています。同時に大切なのはバランスです。売上や収益が厳しいときには営業が叩かれがちですが、業績悪化の原因は商品開発やマーケティングにもあるかもしれない。悪いときはみんなで負担を分け合うし、良いときにはみんなで喜びを分かち合う。そうした全体バランスを意識していますね。
川内:変革期にはさまざまな混乱や反対が付きものだと思いますが、離職率に影響しなかったのでしょうか。
有沢:離職率は一時的に少し上がりました。ただ、もともとカゴメの離職率は1%台と非常に低いのです。自社が大好きな人が本当に多い。一時は2%台になりましたが、今はまた1%台となっています。一方で、異能・異彩の人材が入社してくれるようになったというメリットを強く感じていますね。
私が信じているのは、一人ひとりの考え方や行動の変容が会社を変える、ということ。それは人事も同じです。人事にとっては、トップの考え方をいきなり変えるのは難しいかもしれない。それなら、トップの一つ下でも、そのまた一つ下でもいいから、変えられる対象にアプローチしてみると良いと思います。現在の自社の体制は、本当に従業員を幸せにできているのか。顧客やステークホルダーに価値を提供できているのか。それを常に振り返り、アクションを起こしていくことが大切なのではないでしょうか。
川内:有沢さんのお話からも分かる通り「人的資本経営推進」のポイントは、事業戦略とリンクさせること、自社独自のストーリーを描き、その会社ならではの変革を進めることです。私達リンクアンドモチベーションもそのお手伝いを通じて、良い会社を日本全国に増やしていきたいと思います。本日はありがとうございました。
当社は2000年4月に創業した世界初の「モチベーション」にフォーカスした経営コンサルティング会社です。当社の基幹技術「モチベーションエンジニアリング」は、経営学・社会システム論・行動経済学・心理学などの学術的成果を取り入れ、実行性と再現性を強みに、創業以来多くのお客様の企業変革をサポートさせて頂いております。
当社は2000年4月に創業した世界初の「モチベーション」にフォーカスした経営コンサルティング会社です。当社の基幹技術「モチベーションエンジニアリング」は、経営学・社会システム論・行動経済学・心理学などの学術的成果を取り入れ、実行性と再現性を強みに、創業以来多くのお客様の企業変革をサポートさせて頂いております。

[A-4]「成長し続けるミドルマネジャーを創る人事」~リーダー育成先進企業の共通点とは~

[A]「心理的安全性」の高い組織をつくる

[B]大手企業が実施する人材採用の「新潮流」 データ起点の採用ブランディング・マーケティングの現在と未来

[C]これからの戦略人事は、人の「ココロ」を中心に

[D-2]新ドコモグループの挑戦:社員の自律的キャリアを支援する人材開発のあり方

[D-7]GMOペパボの人事部門が行った、試行錯誤から学ぶ「OKR」とは

[D]人事部門は、さまざまな課題に直面するマネジャーをどう支援すればいいのか

[F]企業に新たな価値をもたらす「デジタル人材」 人材不足を乗り越え、採用・育成に成功するポイントとは

[G-5]人的資本を最大限に活かす組織になるために ~EVP経営のすすめ~

[G]「感情」との向き合い方が組織を強くする 誰もがいきいきと働くための職場コミュニケーションと人材マネジメント

[H-6]これからの人事制度と組織づくりの勝ち筋 ~ジョブ型はどのように定着していくのか~

[H]「やらされ感」を「やりがい」に変える! 従業員が主体的に仕事に取り組むための「ジョブ・クラフティング」

[I]日立製作所の人財マネジメント変革~経営戦略・事業戦略と連動した人財戦略の実行~

[J-2]「大退職時代」におけるサステナブルな給与戦略とは -専門人材の獲得とリテンションに必要な具体的施策

[J-6]発達障害者人材の活用・戦力化によるDX推進 ~当事者に聞き、企業に学ぶ~

[J]違いを価値に変えるダイバーシティ&インクルージョン 先進企業に学ぶイノベーションを起こす組織づくり

[K]脳科学で考える、生産性の高い組織を実現するための「リーダーシップ」と「職場コミュニケーション」

[L]人事パーソンは何を学び、どんなキャリアを描いているのか? 「シン・人事の大研究」調査結果報告 第一弾

[M]パーパス・ドリブンな組織のつくり方 〜発見・共鳴・実装で企業を変革する〜

[N-8]コロナショックを経たZ世代の育成方法 対人基礎力と主体的行動の低下を補う3つのポイントとは

[N]メルカリの事例を通じて考える、これからの「組織開発」

[O-5]何から始める? デジタル時代の人材開発改革! ~グローバルトレンドと日本でとるべきアプローチ~

[O]100年企業カゴメの人事改革から紐解く、「人的資本経営」推進のポイント

[P]キャリア形成の不安解消によるエンゲージメント強化の取り組み ~学びに向かう文化の醸成について考える~

[R-3]次世代選抜リーダーの修羅場経験による部門変革のすゝめ

[R]変化に適応し矛盾を両立するこれからの経営とリーダーのあり方 リーダー育成事例と最新の経営理論で紐解く

[S]従業員エンゲージメント向上の次に考える、組織的課題とは ~ネットワーク組織による未来の組織の可能性~

[T-8]「人的資本の最大化と情報開示」を実現 人事データの戦略的蓄積と活用方法とは?

[T]ビジネスパーソンの学び方改革 主体性と普遍性の高い学びとは

[U-2]ハラスメント無自覚者のリスクをいかに検知し予防するか ~360度評価とAIを活用した本質的な対策~
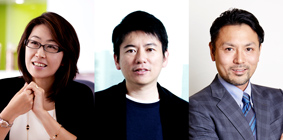
[V]エンゲージメントを高める組織づくり ~組織を変えていく人事のあり方~

[W]データに基づいた戦略が企業の未来を変える 組織と人材の成長を促す「データドリブン経営」

[X-6]どの企業にもやってくる、“節目(周年記念)”を活用したエンゲージメント向上への取組み

[X]組織と従業員をつなぐ新たな価値観 これからの人事の軸になるEmployee Experience