脳科学で考える、生産性の高い組織を実現するための「リーダーシップ」と「職場コミュニケーション」
- 枝川 義邦氏(早稲田大学理工学術院 教授/早稲田大学ビジネススクール 兼担講師)

生産性の高い組織には、一人ひとりのパフォーマンスを高める要因がある。DX、リーダーシップ、人材育成など、生産性を高めるアプローチは数多くあるが、脳科学の観点から生産性を捉えるとどうなるだろうか。組織の生産性につながるリーダーシップや職場コミュニケーションの要素について、脳の仕組みや働きの観点から早稲田大学 理工学術院 教授の枝川義邦氏が語った。

(えだがわ よしくに)東京大学大学院博士課程修了(博士(薬学))、早稲田大学ビジネススクール修了(MBA)。早稲田大学研究戦略センター教授などを経て現職。脳科学の視点を取入れた人材育成、組織開発、マーケティングなどが研究対象。2015年に早稲田大学ティーチングアワード総長賞、2017年にユーキャン新語・流行語大賞を「睡眠負債」にて授賞。
脳科学と組織開発の現在地点
働き方改革が進むにつれ、企業では「生産性」が重視されるようになった。また健康経営やウェルビーイングの考え方が浸透し、健康上の問題で生産性が低下している状態を表す「プレゼンティーイズム」という言葉が根付き始めている。さらにはエンゲージメントやCSVなど、現代はいろいろな面に目を向けて経営を行わなければならない。
枝川氏ははじめに、参加者に対して「あなたの勤務先ではどのような要素が人事評価につながっていますか」という質問を投げかけた。選択肢は次の五つだ。(1)アウトプットの多さ、(2)アウトプットの質、(3)アウトプットの効率性、(4)アウトプットの速さ、(5)アウトプットの正確性。投票機能を用いた結果、最も多かった回答は「(2)アウトプットの質」で、「(4)アウトプットの多さ」が次点だった。
職場の評価が「アウトプットの多さ」だった場合、少し状態が悪くても休まず仕事を続けてしまうことにつながりやすいという。その日一日なら乗り切れるかもしれないからだ。しかし、中長期的にその働き方を続けられるかというと、そうではないだろう。これからの働き方に求められるのは、中長期的な視点や、自分の働き方をマネジメントするという考え方だ。
さて、脳科学を組織開発に活かすとはどういうことか。人にはそれぞれ脳の仕組みや使い方にクセがあり、それを起点に行動が決定づけられている。脳でのクセを調べることでブラックボックスを解き明かしていくことが、脳科学を活用するという考え方の軸だ。脳の中には、五感(視覚、聴覚、触覚、嗅覚、味覚)を通して「情報」が入ってくる。脳の中では、電気情報と化学物質の伝達で情報を処理し、「こころ」を経て「行動」へとつながっていく。
次に枝川氏は「汎用性」と「個体性」というキーワードを挙げた。汎用性とは、人類誰もが持っている脳の仕組みや働きのこと。文化的背景や遺伝的背景をもとにした、日本人に特徴的な脳の仕組みや働きもある。そのため「マス」に訴求する場合は汎用性を意識するとよい。一方、人はそれぞれの経験をもとに脳が現在の状態に至ったといえる。そのため個体差にも留意しなければ、メッセージは届きづらい。
昨今は職場に心理学の考え方を取り入れる企業も増えてきていることをふまえ、枝川氏は心理学と脳科学の関係にも触れた。
「時代が変わると、二律背反的に『心理学の時代』から『脳科学の時代』に変わるのではないかという意見もありますが、私はそのように考えていません。心理学は、刺激というインプットと反応・行動というアウトプットに着目することで、脳や心の働きを解明していくアプローチです。一方の脳科学は、脳の働きそのものを解き明かしていく学問です。心理学と脳科学は相補的で、両輪で考えていくことによって一気通貫で理解が進むのではないかと考えています」
脳科学には四つの領域がある。「脳を知る」「脳を守る」「脳を創る」「脳を育む」という4分野だ。この中で特に人材育成に関連するのは「脳を育む」という考え方。いくつになっても学ぶことができるという人材育成の考え方は、「脳を育む」という脳科学領域によって支えられている。
ここから先は、脳科学のエンジニアリングが進んでいく時代だと枝川氏は言う。これまでに4領域でわかってきたことをもとに、社会実装をしていくのが脳科学のエンジニアリング。脳科学の考え方や研究成果の展開を期待できる経営関連の領域は、マーケティング、感情マネジメント、人材採用・育成、意思決定、健康経営・労務管理、クリエイティビティ、商品開発、CXなど。広範な活用ができそうとの見立てだ。
HR業界でも脳科学を起点にDXを進める潮流があり、リーダーシップ、共感、心理的安全性、自己効力感、ストレスマネジメントなどは人事領域で脳科学を活用できそうな一例だという。
生産性の高い組織の特徴とは
コロナ禍を経て、リモートワークが世の中に広く浸透した。リモートワークを実施した結果、対面コミュニケーションの良さを再確認するなど、働き方においても企業の姿勢が反映される時代となっている。
枝川氏から二つ目の質問は「働きやすい職場の要素は何ですか」というもので、選択肢は、(1)DX化されたオフィス、(2)密なコミュニケーション、(3)素早いフィードバック、(4)上司に相談しやすい仕組み、(5)雑談のしやすさ。参加者が投票した結果、最も多かった回答は「(5)雑談のしやすさ」だった。
「ちょっとした雑談や息抜きで、ストレス管理だけでなく生産性にも影響があることがわかっています。新しい仕事のアイデアも雑談の中から生まれます。今般の状況のように半ば強制的に施行されたリモートワークの中で、多くの方が雑談の重要性を感じていることがわかります」

次の議題は、生産性が高い組織にはどのような特徴がみられるのか。枝川氏はGoogleのプロジェクト・アリストテレスを引用し、生産性の高いチームの共通点に「均等な発言の機会」と「社会的感受性の高さ」を挙げる。前者はフェアな組織風土、後者は組織のメンテナンスが行き届いていることを意味する。そして、最終的なインパクトにつながる起点は、ハーバード大学のC・エドモンドソン教授が提唱する「心理的安全性」。チームの心理的安全性が高まると、結果としてチームのパフォーマンスが上がるという考え方だ。
チームのパフォーマンスが上がる一歩手前には「チームの学習行動」というフェーズがある。学習は、一人ひとりがするものだが、仕事はチームでするもの。知見を共有することでチーム全体や組織全体の学習につながっていく。個人の学習をいかにチームの学習に転用できるかが重要だと枝川氏はいう。
「こんなふうに成功しましたというポジティブな共有もいいのですが、失敗の共有のほうが実は重要です。変化を恐れずに新しいところへと飛び込んでいくためには、成功も失敗も両方かみ砕きながら進めるようなメンタリティが必要です。組織の中でいかにそのような文化を醸成するか。ここで出てくるのが心理的安全性という概念です」
チームのパフォーマンスを高めるには、心理的安全性の他にもう一つ必要なものがある。それは「内発的動機付け」。内側から湧き出るような意欲がない限りは、いくら心理的安全性があってもパフォーマンス向上にはつながらない。従業員の満足度だけではなく、エンゲージメントを高めるということだ。心理的安全性と内発的動機付けがそろって初めて、学習行動が可能になる。
では、モチベーションを高めるために必要なものは何だろう。金銭的報酬、人からの賞賛、人とのつながり、自己実現など、モチベーションの源泉になりうるものは人それぞれで、場面によっても異なる。だが、脳科学的には共通点がある。報酬系の神経ネットワークの活動性が高まるかどうかが、やる気スイッチが入ったかどうかの分岐点になっている。
「神経ネットワークの働きには、いろいろな化学物質が関わっています。ワクワクして楽しいからという内発的動機付けに関わる物質はドパミン。『明日までにこのプロジェクトを完成させなきゃ』などといった、締切前の焦りなどからお尻に火が付いたように頑張れるのはノルアドレナリンが強く作用しています。人とのつながりや環境などから得られる落ち着きや癒やしがモチベーションになるときは、セロトニン。最近は接触によって生じやすい愛情や信頼に関係したホルモン、オキシトシンも注目されています」
心理的安全性とパフォーマンスを高めるリーダーシップ
枝川氏からの三つ目の質問は、「組織の生産性を高めるために取りたい(取ってもらいたい)リーダーシップや、組織の状態とは」。(1)変革型リーダーシップ、(2)サーバント型リーダーシップ、(3)放任型リーダーシップ、(4)オーセンティック・リーダーシップ、(5)シェアード・リーダーシップの選択肢のうち最も多かったのは「(4)オーセンティック・リーダーシップ」で、「(2)サーバント型リーダーシップ」が続いた。
ここまで生産性、心理的安全性、内発的動機付けといったテーマを扱ってきたが、ここにリーダーシップが絡むとどうなるか。リーダーシップの定義に「リーダーシップとは、共通の目標を達成するために、個人がグループへ影響を及ぼすプロセスである」というものがある。キーワードは「共通の目標」と「周囲への影響力」。ここでいう影響力とは、人にもともと備わった能力ではなく、プロセスのことを指す。
リーダーの要素というと、調整力、積極性、独創性、公正、自信、感情のバランスといった言葉が挙げられるが、脳科学的に言うとどうだろう。枝川氏は「意思決定」と「コミュニケーション」という枠組みで考えることができると話す。
「リーダーシップ研究の歴史を見ると、初期は集積化とコントロールに焦点を当てていましたが、現代に近づくにつれ、一人ひとりのこころに寄り添ったマネジメントが重要であると、人のほうに焦点が向いていきます。シェアード・リーダーシップのように仕組みに着目した理論もあるため、現代は仕組みと個人の双方を重視したリーダーシップが推奨されていると言えるでしょう」
さまざまなリーダーシップ理論がある中で、チームのパフォーマンスにつながりやすいリーダーシップには二つのタイプがある。一つは、変革型リーダーシップ。リーダーの認知的信頼が、チームの能力を向上させる。いわば「頭で考える」タイプのリーダーシップだ。もう一つは「こころで考える」リーダーシップで、感情的な信頼を得るサーバント型リーダーシップ。心理的安全性というアプローチからパフォーマンスの向上を目指すならば、サーバント型リーダーシップが好ましいことが最近の研究からわかっている。
では、サーバント型リーダーシップとは何か。求められる10の特性を挙げると、傾聴、共感、癒やし、気づき、説得、概念化、先見性、執事役、人々の成長への関与、コミュニティ作りという要素が挙がる。まとめると、こころへの関心、意思決定の仕組み、コミュニケーションという三つが重要な特性ということになる。
ここで枝川氏は、日本発の「PM理論」というリーダーシップ理論を紹介した。PM理論とは、リーダーが取るべき行動に着目した行動理論のことで、「P:目標達成機能」(Performance)を重視するか、「M:集団維持機能」(Maintenance)を重視するか、「P」と「M」の2軸で定義する。PとM、それぞれの強さを大文字と小文字で表し、「PM型」「Pm型」「pM型」「pm型」という4パターンのリーダーシップ像に分けられる。
「理想的なリーダーといえば、成果を上げる力も集団をまとめる力もあるPM型ですが、そのような力がない場合でも、仕組みで解決しようという考え方もできます。例えば、フランチャイズの店長の場合は、マニュアル通りに運営できることを大切だとした場合、pm型のほうが好ましいとされています」
枝川氏はPM理論を脳科学の観点からも分析した。
「先ほど、報酬系というモチベーションに関係した脳の仕組みを話しましたが、報酬系が大きいほどP機能が高くなります。もう一つは感情的な部分なのですが、危険察知能力のような脳の仕組みも関わってきます。例えば、ギャンブルをしていて負けそうなとき、考えるより体が先に反応するような脳の働きがあります。それを情動・嫌悪系といいますが、その働きが大きいほどM機能は高くなります」
理想的なリーダーシップはPM型、あまり好ましくないリーダーシップはpm型というのは多くの人の知るところだ。では、Pm型とpM型ではどちらがよいのか。何を優先するかによって順位づけも変わるが、部下の意欲・満足度、職場のコミュニケーション、事故の発生率低下という観点から見ると、PM型>pM型>Pm型>pm型という順になる。また、集団の生産性という観点から見ると、短期的には PM型>Pm型>pM型>pm型だが、長期的には、やはりPM型>pM型>Pm型>pm型という順になるという。ここからわかるのは、部下の意欲や満足度、職場のコミュニケーションが良好な状態が、長期的な生産性を高めるということだ。
生産性を高めるため、リーダーが取るべき行動とは
枝川氏は、サーバント型リーダーシップがなぜ生産性に有効なのかを脳科学の視点から説明する。サーバント型リーダーシップは、メンバーの心を支え、支えられるというメンタルの架け橋ができている状態。
「リーダーを決めずに、3人に自由にディスカッションしてもらうという実験を行い、自然発生的にリーダーが決まっていくプロセスにおいて、脳の中では何が起きているかを分析した研究があります。ディスカッション後に結果を発表してもらうことを伝えており、これを別室から審査員が観察し、リーダーらしき人を選定します。この場合、発表役に回る人がリーダー的存在ということになりますが、この発表者は外部から見ている審査員が選んでいた人物と同一だったという結果に。自然発生的にリーダーになる人は、外から見ても『それらしい』振る舞いをしているということです」
そのときの脳の活動を見ると、リーダーが発言している、まさにそのとき、フォロワー(その他のメンバー)もリーダーと同じ脳の場所が活性化していた。フォロワーからリーダーに話しかけるときはその同期性がさほど強まらず、フォロワー同士の会話では同期現象は見られなかったという。また、言語コミュニケーションでは同期が見られ、非言語コミュニケーションでは見られなかった。リーダーが話した頻度は影響せず、たとえ話す回数が少ない場合でも、コミュニケーションの質が高いほど同期性は高まることがわかった。

では、チームの生産性を高めるため、リーダーに求められるものとは何だろうか。枝川氏は四つの項目を挙げた。まずは、リーダーには言葉が必要であること。非言語コミュニケーションより、言語コミュニケーションが重要だ。二つ目は、会話の量より質が重要であること。言葉が重要とはいえ、多くを語る必要はないのだ。三つ目は、リーダーはフォロワーとの対話を始める際にはまず相手への共感を示すようにすること。リーダーシップと共に、最近はフォロワーシップも大切だと言われている。心理的なつながりによって、脳活動の同期につながる。四つ目は、リーダーは権力を示すことより脳活動の同期性を意識することが重要であるということ。
「共感」がリーダーに必要だと最近よく言われるが、共感とは、他者の感情・状態を共有する脳やこころの働きのこと。三つの種類があり、頭で考える「認知的共感」と、こころで感じる「情動的共感」「共感的関心」に分けられる。
「リーダーに必要な要素として感情のマネジメントが挙げられるのは、理性を働かせるためには感情をマネジメントする必要があるからです。人を人たらしめているのは認知的な理屈部分だけではなく、感情のふれあいやこころのつながり。PM理論において、メンテナンスが軸の一つになっているのも、メンバーのやる気スイッチを入れるためには感情的なものが重要だからです。こころのつながりを持つことが、組織の学習行動を促し、結果的に生産性を高めるのです」
生産性の高い組織の特徴には、高い心理的安全性、学習やパフォーマンス向上への動機付け、適したリーダーシップのスタイルがあり、これらを裏付ける脳の状態が次第に解明され始めている。脳科学はサイエンスからエンジニアリングへ。枝川氏は社会実装への期待を語って、講演を締めくくった。

[A-4]「成長し続けるミドルマネジャーを創る人事」~リーダー育成先進企業の共通点とは~

[A]「心理的安全性」の高い組織をつくる

[B]大手企業が実施する人材採用の「新潮流」 データ起点の採用ブランディング・マーケティングの現在と未来

[C]これからの戦略人事は、人の「ココロ」を中心に

[D-2]新ドコモグループの挑戦:社員の自律的キャリアを支援する人材開発のあり方

[D-7]GMOペパボの人事部門が行った、試行錯誤から学ぶ「OKR」とは

[D]人事部門は、さまざまな課題に直面するマネジャーをどう支援すればいいのか

[F]企業に新たな価値をもたらす「デジタル人材」 人材不足を乗り越え、採用・育成に成功するポイントとは

[G-5]人的資本を最大限に活かす組織になるために ~EVP経営のすすめ~

[G]「感情」との向き合い方が組織を強くする 誰もがいきいきと働くための職場コミュニケーションと人材マネジメント

[H-6]これからの人事制度と組織づくりの勝ち筋 ~ジョブ型はどのように定着していくのか~

[H]「やらされ感」を「やりがい」に変える! 従業員が主体的に仕事に取り組むための「ジョブ・クラフティング」

[I]日立製作所の人財マネジメント変革~経営戦略・事業戦略と連動した人財戦略の実行~

[J-2]「大退職時代」におけるサステナブルな給与戦略とは -専門人材の獲得とリテンションに必要な具体的施策

[J-6]発達障害者人材の活用・戦力化によるDX推進 ~当事者に聞き、企業に学ぶ~

[J]違いを価値に変えるダイバーシティ&インクルージョン 先進企業に学ぶイノベーションを起こす組織づくり

[K]脳科学で考える、生産性の高い組織を実現するための「リーダーシップ」と「職場コミュニケーション」

[L]人事パーソンは何を学び、どんなキャリアを描いているのか? 「シン・人事の大研究」調査結果報告 第一弾

[M]パーパス・ドリブンな組織のつくり方 〜発見・共鳴・実装で企業を変革する〜

[N-8]コロナショックを経たZ世代の育成方法 対人基礎力と主体的行動の低下を補う3つのポイントとは

[N]メルカリの事例を通じて考える、これからの「組織開発」

[O-5]何から始める? デジタル時代の人材開発改革! ~グローバルトレンドと日本でとるべきアプローチ~

[O]100年企業カゴメの人事改革から紐解く、「人的資本経営」推進のポイント

[P]キャリア形成の不安解消によるエンゲージメント強化の取り組み ~学びに向かう文化の醸成について考える~

[R-3]次世代選抜リーダーの修羅場経験による部門変革のすゝめ

[R]変化に適応し矛盾を両立するこれからの経営とリーダーのあり方 リーダー育成事例と最新の経営理論で紐解く

[S]従業員エンゲージメント向上の次に考える、組織的課題とは ~ネットワーク組織による未来の組織の可能性~

[T-8]「人的資本の最大化と情報開示」を実現 人事データの戦略的蓄積と活用方法とは?

[T]ビジネスパーソンの学び方改革 主体性と普遍性の高い学びとは

[U-2]ハラスメント無自覚者のリスクをいかに検知し予防するか ~360度評価とAIを活用した本質的な対策~
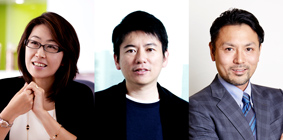
[V]エンゲージメントを高める組織づくり ~組織を変えていく人事のあり方~

[W]データに基づいた戦略が企業の未来を変える 組織と人材の成長を促す「データドリブン経営」

[X-6]どの企業にもやってくる、“節目(周年記念)”を活用したエンゲージメント向上への取組み

[X]組織と従業員をつなぐ新たな価値観 これからの人事の軸になるEmployee Experience


