【ヨミ】ディーエックスジンザイ DX人材
「DX人材」とは、デジタルトランスフォーメーション(DX、Digital Transformation)の推進・実行に必要なスキル・マインドを有する人材のことをいいます。DXは単なるデジタル化ではなく、企業の競争優位を生むためのビジネス変革を伴う取り組みと位置付けられます。そのため、DX人材には変革をリードする役割が求められています。
「DX人材」とは、デジタルトランスフォーメーション(DX、Digital Transformation)の推進・実行に必要なスキル・マインドを有する人材のことをいいます。DXは単なるデジタル化ではなく、企業の競争優位を生むためのビジネス変革を伴う取り組みと位置付けられます。そのため、DX人材には変革をリードする役割が求められています。
DX人材とは、DXを推進・実行していく人材のことを指します。統一された定義はありませんが、経済産業省の「DXレポート2」では、以下のように説明しています。
つまり、デジタル技術やデータ活用における知見だけでなく、自社の事業と市場を理解し、ビジネスや組織の変革を進めていくための力が求められているといえます。
DXには様々な定義がありますが、日本におけるDXの定義は、経済産業省が公表している「デジタルガバナンス・コード2.0(旧DX推進ガイドライン)」が参考になります。同ガイドラインでは、「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」と定義しています。DXでは、小手先のデジタル化だけではなく、企業全体が変化することが求められています。

DX人材の職種と役割は多岐にわたります。独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)は「DX推進に向けた企業とIT人材の実態調査」の中で、以下の七つの職種に分類しています。
プロダクトマネジャーは、DXやデジタルビジネスの実現を主導するリーダーとして組織をけん引する存在です。具体的な役割は、ビジネス戦略の策定、プログラムの再構築、デジタル活用、予算管理など多岐にわたり、誰よりも現状の組織課題の解決に対するコミットメントが求められます。
ビジネスデザイナーは、プロデューサーが描く方向性や戦略を、具体的な企画・計画に落とし込み、計画達成に向けた推進役を担います。プロデューサーと現場で実際に動くエンジニアとの間に入り、さまざまな調整業務も行います。プロジェクトの進行中に問題が生じた場合には、ミーティングのファシリテーション役を担うこともあります。
テックリードは、DXやデジタルビジネスに関するシステムを設計する役割を担います。プロデューサーやビジネスデザイナーによって具体化されたDX戦略を、自社のビジネスに合うように実現可能なものに設計していくことがミッションとなります。そのため、専門外の人たちにも理解してもらえるよう、わかりやすい言葉で説明するといったコミュニケーション力も求められます。
データサイエンティストは、社内外から集められた膨大なデータの分析・解析をする役割を担います。膨大なデータの中から何が課題として導きだされるか、データをビジネスにどのように生かしていくのかといったことを構想する力も求められます。
先端技術エンジニアは、機械学習やブロックチェーンなどの先進的な技術を用いて開発を行う役割を担います。最新技術は流行り廃りが早いため、常に最新の情報をキャッチアップし、自らのスキルも高められることが求められます。
UI/UXデザイナーは、DXやデジタルビジネスに関するシステムのユーザー向けデザイン制作を担います。サービスの利用率や満足度を高めるには、ユーザー体験の向上が欠かせません。例えば、操作が初めてでもわかりやすいか、デザインは見やすく使い勝手が良いかなど、ユーザーを基点に画面設計を行うためのスキル習得などが求められます。
エンジニア/プログラマは、デジタルシステムの実装や、インフラ構築などを担います。DXプロダクトを実現するサービス開発に向けて、データベースの設計から必要な機能の実装までを行います。コーディングスキルだけではなく、プロジェクトの管理能力や外部との関係構築など幅広い対応も求められます。
DX人材には、デジタル技術だけではなく、プロジェクトを推進する上での事業に対する正しい理解や、他者を巻き込む力といったさまざまなスキルが求められます。
IPAでは、DX人材に求められるスキルすなわち「適性因子」には、六つの種類があると解説しています。
| 職種 | 特に重要な因子(スキル) |
| 1. プロダクトマネージャー | 不確実な未来への創造力、社外や異種の巻き込み力、モチベーション/意味づけする力 |
| 2. ビジネスデザイナー | 不確実な未来への創造力、社外や異種の巻き込み力 |
| 3. テックリード | 失敗した時の姿勢/思考、いざという時の突破力 |
| 4. データサイエンティスト | 失敗した時の姿勢/思考、いざという時の突破力 |
| 5. 先端技術エンジニア | 不確実な未来への創造力、失敗した時の姿勢/思考 |
| 6. UI/UXデザイナー | 臨機黄変・柔軟な対応力 |
| 7. エンジニア/プログラマ | 失敗した時の姿勢/思考、いざという時の突破力 |
六つの因子のなかで、人材タイプを問わず重要なのが「臨機応変/柔軟な対応力」です。DX人材は、デジタルビジネスの推進を担うことから、どの職種も前例のないプロジェクトに取り組む傾向があります。プロジェクトマネージャーやデータサイエンティスト、テックリードなど、立場が異なっていても、柔軟な発想や状況に合わせた対応力が必要とされます。
そのほかの因子については、人材タイプ(職種別)に重要度がわかれます。たとえば、「不確実な未来への創造力」は、DXの企画・立案・推進を担うビジネスデザイナーで重視されます。一方、システムの実装やインフラ構築・保守を担うエンジニア/プログラマではさほど重視されません。
「社外や異種の巻き込み力」は、プロダクトマネージャー、ビジネスデザイナーで強く求められます。「いざというときの自身の突破力」は、エンジニア/プログラマで最も重視されます。重要とされる適性因子から、それぞれの職種に期待される役割が明確になります。
DX人材育成・確保に悩む企業が多い中、すでにDX化が進んでいる企業の取り組みを知ることは、新たな活路を見出すきっかけになります。
(※取り組み内容、経歴は取材当時のものです)
住友生命では、健康増進型保険商品「Vitality」のサービス開発が転機となり、DX人材の開発に力を入れるようになりました。
同社ではもともと、ビジネス部門とシステム部門が完全に切り分けてシステム開発を行っていました。しかしDX型の開発では、エンジニア自身がビジネス起点でものごとを捉え、顧客視点でサービスやシステムの設計を考える役割を担うことが重要であると考え、社内エンジニアの育成に着手しました。
内部育成を図るにあたり、3種類のテストを用いてDX人材の適性を見極めています。
| テスト種別 | 診断・検定内容 |
|---|---|
| イノベーティブ人財診断 | 新しいものごとへの関心や好奇心の旺盛さなどのイノベーティブ資質 |
| 人間力診断 | 実行力や推進力をはじめとしたプロジェクトマネジメント力 |
| DX検定 | DXに対する関心度合いなど |
DXの適性を見込まれた人材は、「Vitality DX塾」と呼ばれる、主に意識改革を目的とした「価値創造型人財教育プログラム」に参加し、インターネットリサーチ・情報統合・アイデア創発・アウトプットという一連のフローを体験します。
こうしたリサーチとアウトプットを繰り返し行うことで、頭の使い方の切り替えができるようになります。「こんなことができそう」「これとこれを組み合わせたら、こんな風になるのではないか」といったように気づきの感度を上げていくことが、DXでは特に肝要であるといいます。
住友生命の場合は、「Vitality」の導入という「やらなければならない事業」が先にあったため、実務を通じてDX化が進みました。
社内のDX化を踏まえ、同社理事でデジタルオフィサーの岸 和良さんは「DX人材を育てたいという会社は多いと思いますが、目的もなしに育成するのは違うと思います。まず先にDXビジネスがあって、求める人材像が定まり、育成の方針や施策が決まるはずです」と述べています。
少子高齢化の影響に伴い国内の労働人口が年々減少する中、DX人材の確保を社外に求めるだけでは立ち行かなくなることもあります。
住友生命のように社内で専門チームを発足し、既存社員の中からDX人材として配置転換するのも一つの方法です。何をDXのテーマとするかは、企業によって異なります。そのため、まずは自社の課題を洗い出し、デジタルの力で改善できないかを考えることがスタートです。
DXの真の目的は、デジタル技術を活用することで、新たな価値の創出や競争優位を生み出すイノベーションを起こすことです。難易度が高く、容易には成功しない可能性が高い取り組みですが、リスクを恐れて何もしないままでは、状況が好転することもありません。
情報処理推進機構(IPA)では、DX成功に向けた原則には二つあると解説しています。
まずは勇気を持ってチャレンジすることが大切です。
上場企業に義務付けられた人的資本の情報開示について、開示までのステップや、有価証券報告書に記載すべき内容を、具体例を交えて解説します。
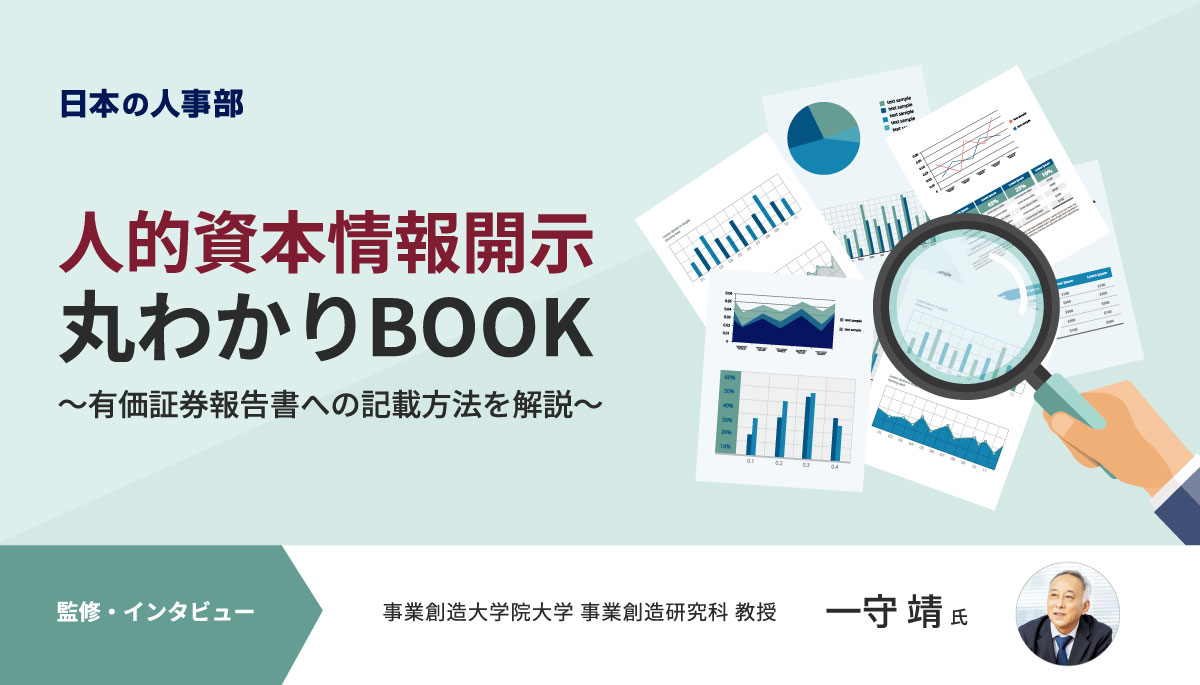
人的資本情報開示~有価証券報告書への記載方法を解説~│無料ダウンロード - 『日本の人事部』