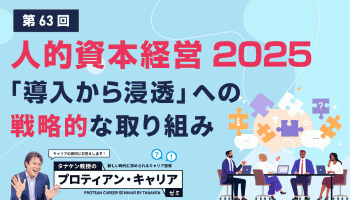「人的資本経営」推進において不可欠な「従業員エンゲージメント」の高め方
従業員エンゲージメント、人的資本経営、従業員満足度、サーベイ

人的資本経営における重要な指標の一つとして、「従業員エンゲージメント」が挙げられます。その重要性を多くの企業が認識している一方、日本は欧米諸国などと比べて、低い水準にあることが指摘されています。どうすれば従業員エンゲージメントを向上させ、企業価値の向上へとつなげていくことができるのでしょうか。「人的資本経営」推進において不可欠な「従業員エンゲージメント」について解説します。
従業員エンゲージメントが重要な理由
従業員エンゲージメントとは
従業員エンゲージメントとは、「企業が目指す姿や方向性を、従業員が理解・共感し、その達成に向けて自発的に貢献しようという意識を持っていること」を指します。もともと「エンゲージメント(engagement)」は日本語で「約束」「契約」「婚約」などの意味がある言葉ですが、仕事の領域では1990年、ボストン大学のカーン教授がはじめてエンゲージメントの概念を提唱しました。また同年代には、アメリカの調査会社ギャラップ社がエンゲージメントの用語を使用し、コンサルタント業界で用いられるようになりました。
その後、さまざまな研究者がエンゲージメントについての研究を進めました。とりわけ2002年にユトレヒト大学のシャウフェリ教授が提唱した「ワーク・エンゲージメント」は、いまも広く活用されています。国際的に認知が進んできた従業員エンゲージメントですが、グローバルで比較すると、日本企業の従業員エンゲージメントは低い水準にあることが指摘されています。
なお「従業員満足度」は従業員エンゲージメントと混同されがちですが、異なる概念です。従業員エンゲージメントは従業員が会社の理念や目指す方向性に共感したうえで、「どれだけ主体的に貢献したいと考えているのか」を表すものですが、従業員満足度は単に従業員個人の尺度で、給与や労働条件、人間関係といった観点から「どれくらい会社に満足しているか」を表すものです。
従業員エンゲージメントが重要視されるようになった背景
海外での普及
2007年、世界最大級の人材育成カンファレンスであるASTD(現ATD:The Association for Talent Development )でエンゲージメントに関するレポートが発表され、欧米で従業員エンゲージメントが注目されるようになりました。またさまざまな研究結果から、従業員エンゲージメントは企業業績とも相関があることが示されています。もともと日本企業は従業員満足度を向上させることで優秀な人材を確保してきましたが、従業員満足度が企業業績や従業員の主体性につながらないという悩みを抱えていました。そこで日本においても、従業員満足度より従業員エンゲージメントを重視する傾向が強まってきています。
ギャラップ社のエンゲージメント調査
ギャラップ社が2017年に発表した世界各国における従業員エンゲージメント調査では、日本の「熱意あふれる社員(Engaged)」の割合は6%にとどまり、調査対象の139ヵ国中132位と非常に低い水準にあることが示されました。また「やる気のない社員(Not Engaged)」が70%を占めていました。この調査結果が広く報じられたことで従業員エンゲージメントに注目が集まり、国や経済団体が従業員エンゲージメント向上の重要性を訴えるようになったのです。
人的資本経営とのかかわり
人的資本経営の観点からも、従業員エンゲージメントを取り入れる動きが加速しています。少子高齢化の進行による働き手の減少や転職の一般化、生産性の低さなど、多くの日本企業が課題を抱えています。そんな中で従業員エンゲージメントのスコアが高い会社は、従業員にとって高いモチベーションで働ける環境が整っているといえます。
2020年9月に発表され、日本における人的資本経営ブームの火付け役ともなった「持続的な企業価値の向上と人的資本に関する研究会報告書~人材版伊藤レポート~」でも、従業員エンゲージメントの重要性について言及しています。従業員のエンゲージメントを向上させることは、優秀な人材の確保や離職防止、生産性の向上など、企業価値の向上につながると、多くの企業が認識し始めています。
従業員エンゲージメントと人的資本経営
人材版レポートにおける「5つの共通要素」
人材版伊藤レポートでは、持続的な価値向上に向けた人材戦略に求められる「3つの視点・5つの共通要素」が整理されています。その中で、どのような企業でも共通して戦略に組み込むべき「5つの共通要素」の1つとして挙げられているのが、従業員エンゲージメントです。
レポートでは、「現在の経営戦略の実現、新たなビジネスモデルへの対応に必要な人材が自身の能力・スキルを発揮してもらうためにも、従業員がやりがいや働きがいを感じ、主体的に業務に取り組むことができる環境を創りあげることが必要」と言及。具体的なエンゲージメント向上施策として、エンゲージメントレベルに応じたストレッチアサインメントや副業・兼業といった多様な働き方の推進などを推奨しています。
人的資本可視化指針における価値向上プロセス
2022年に内閣官房が公表した「人的資本可視化指針」では、人的投資が企業価値の向上につながるまでのプロセスを明示しています。具体的には、従業員エンゲージメントに関する取り組みに向けた投資を行うことで、従業員エンゲージメントが向上し、従業員一人ひとりのチャレンジ姿勢や発想力が向上。それにより売上高・販売管理費双方が増加して利益率が上がって、投下資本利益率(ROIC)・自己資本利益率(ROE)の向上につながり、結果として株価収益率(PER)の向上がもたらされるとしています。
また人的資本経営を進めるうえでは、「どのような状態であれば人的資本経営が達成できているといえるのか」を可視化するための具体的な指標の設定および開示も重要です。人的資本可視化指針では、企業独自の人的資本開示例の一つとして、従業員エンゲージメントに関連する事項を挙げています。実際に従業員エンゲージメントに関連する指標を開示している企業も、大企業を中心に増加傾向にあります。
従業員エンゲージメントの測定方法
従業員エンゲージメントの指標
従業員エンゲージメントを測る指標や方法を見ていきます。
エンゲージメント総合指標
エンゲージメント総合指標とは、従業員の会社に対する評価を数値化した指標です。
例
eNPS(employee Net Promoter Score)
「自分が勤める会社を勤務先として友人や知人に勧められる度合い」を表したもの。やり方としては、まず自分が勤務する職場の推奨度を0~10の11段階で尋ね、9~10点を「推奨者」、7~8点を「中立者」、0~6点を「批判者」と分類します。そして「推奨者」の割合から「批判者」の割合を引いた数値がeNPSのスコアとなります。eNPSが高いほど、従業員エンゲージメントが高いといえます。
継続勤務意向
「現在勤めている会社で今後も働き続けたいか」を聞くもの。
ワーク・エンゲージメント指標
ワーク・エンゲージメント指標とは、業務に対する活力や没頭度合いを数値化した指標です。
例
ユトレヒト・ワーク・エンゲージ尺度(UWES)
全17項目の質問で、「活力」「熱意」「没頭」のスコアを計測するもの。「活力」では「仕事をしていると、活力がみなぎるように感じる」、「没頭」では「仕事をしていると、時間が経つのが速い」、「熱意」では「自分の仕事に、意義や価値を大いに感じる」といった質問項目が設定されています。
新職業性ストレス簡易調査(New BJSQ)
57~141項目の質問から、エンゲージメントの状態やハラスメント発生リスクを数値化し、可視化するもの。常時50人以上の労働者を有する事業場で義務付けられるストレスチェックにおいて使用することが望ましい調査とされており、中でも80項目版が多く使用されています。
エンゲージメントドライバー指標
エンゲージメントドライバー指標とは、今後従業員エンゲージメントを高めると想定される要因を表す指標です。 エンゲージメントドライバー指標を構成するのは「組織ドライバー」「職務ドライバー」「個人ドライバー」の3つとされています。
組織ドライバー
人間関係や働きやすさなど、企業と従業員の関係を表す指標
職務ドライバー
人間関係や働きやすさなど、企業と従業員の関係を表す指標
個人ドライバー
従業員自身の資質が業務に及ぼす影響を計る指標
エンゲージメントの測定方法
センサスサーベイ
センサスサーベイとは、半年〜1年に1回程度の頻度で行われるサーベイです。ボリュームのある質問項目になっていることが一般的です。長期的に調査することで、組織の状況がどう変化してきたのかを可視化し、組織の理想の姿と現状とのギャップに対する打ち手を考えることができます。さまざまな角度から組織の現状を可視化できる一方、質問項目が多いため、回答者の負担は大きくなります。
パルスサーベイ
パルスサーベイとは、週1回~月1回といった短いスパンで実施するサーベイです。「パルス」とは日本語の脈拍を指します。高頻度で行うため、従業員の負荷とならないように質問項目は数問程度に設定されていることが一般的です。従業員の意識の変化を、よりリアルタイムで測ることが可能です。
従業員エンゲージメントの測定・開示状況
従業員エンゲージメントの測定状況
ギャラップ社が2023年に発表した調査結果によると、日本の従業員エンゲージメントは2017年時点よりも減少し、「熱意あふれる社員」の割合は5%と、4 年連続で過去最低を記録しました。なおグローバル平均の「熱意あふれる社員」の割合は23%となっています。「やる気のない社員」は72%にのぼり、日本ではまだまだ従業員エンゲージメントが低い水準にあることがわかります。ギャラップ社は、日本の従業員エンゲージメントが低いことにより、91.7兆円の経済的損失が生まれていると試算しています。
従業員エンゲージメントの開示状況
パーソル総合研究所が、TOPIX(東証株価指数)の上位500銘柄で構成される時価総額加重平均指数であるTOPIX500企業のうち、2023年3月期決算の380社の有価証券報告書(有報)を調べた結果によると、有報において何らかの形で従業員エンゲージメントに言及している企業は64.2%に上ります。一方で、従業員エンゲージメントの実績値を開示していたのは27.9%にとどまっていました。多くの企業が従業員エンゲージメントへの関心を持ちながらも、測定を行っていなかったり、行ったけれどもその結果が悪かったりしている背景から、まだ開示までには至っていない状態にあることがわかります。
従業員エンゲージメントを向上させるには
従業員エンゲージメントの実態把握
まずは現時点での従業員エンゲージメントの実態を把握することが出発点です。センサスサーベイやパルスサーベイを実施して定量的に計測するとともに、「なぜそのスコアになったのか」を理解するため、ヒアリングや1on1といった定性的なアプローチを行うことも重要です。それらの結果を基に、組織の強みや弱み、理想の姿とのギャップを洗い出し、改善していくべき事項を検討します。
ビジョン、価値観の共有
従業員エンゲージメントには必ず、従業員の「企業に貢献したい」との思いが含まれています。つまり従業員エンゲージメントを向上させるためには、企業のビジョンやミッション、パーパスや価値観を従業員に積極的に発信し、共感してもらうことが不可欠です。せっかく具体的な施策を展開しても、従業員の自社への共感が根底になければ、その効果は大きく損なわれます。企業の思いや方針は一度の発信では定着しないため、経営陣やマネジャーが繰り返し発信するとともに、組織の情報を可能な限りオープンにしていく取り組みも有効です。
社内コミュニケーションの活性化
従業員エンゲージメントが高い企業では、従業員が主体性を持ち、活発に議論が行われている姿が見られます。従業員一人ひとりが「何を言っても大丈夫」と思える心理的安全性が確保されていることが、従業員エンゲージメントを向上させる土台となります。従業員が積極的に発言できる組織風土をつくりあげていくほか、普段あまりかかわりのない従業員が交流できる機会をつくるなど、さまざまな仕掛けを講じていくことが重要です。
体制の整備・施策の展開
テレワークや時短勤務を含む多様で柔軟な働き方や兼業・副業の解禁、リスキリングなど、従業員エンゲージメントを向上させるための施策はさまざまです。ただし、何を優先事項とするかは、自社の従業員エンゲージメントの実態や目指す姿によって異なります。他社のまねをするのではなく、自社に必要な施策を展開していくことが求められます。なお海外では、従業員エンゲージメントを始めとする非財務指標を経営陣の報酬に反映する動きが活発化しており、日本でも少しずつその動きが見られるようになってきました。このように、施策の結果を目に見える形で反映させていくことも有効です。
企業事例
ソニー
ソニーはグループ共通の人材理念「Special You, Diverse Sony」に基づき、「個を求む」「個を伸ばす」「個を活かす」との人事戦略のフレームワークを定義しています。そのうちの「個を活かす」において、「社員の成長を支援するさまざまな人事施策は、最終的には社員エンゲージメントにその結果が集約される」との考えから、エンゲージメント向上に向けたさまざまな施策に取り組んでいます。
具体的には、フレックスタイム制や裁量労働制、高度プロフェッショナル制度の導入により、柔軟な勤務を可能にしました。そのほかにも復帰後のキャリア展開を豊かにすることを目的とした最長5年の休職制度や、育児・介護・治療の3つを軸にしたサポートを行う「Symphony Plan」の推進など、ワークライフバランスの充実を強く意識しています。
同社では、社員一人ひとりのエンゲージメントを高め、組織の活性化を図る起点として、グローバル共通で社員エンゲージメント調査を実施しています。2022年度のエンゲージメント指標は89%と、高い水準を示しました。さらにこの調査結果に基づいて組織ごとに詳細を分析し、シニアマネジメントを中心に改善に向けた行動について議論。社員エンゲージメント調査を通じて現状を把握し、その結果を各組織における対話とアクションの実行にいち早くつなげることを重視しています。
- 【参考】
- ソニー:サステナビリティレポート2023
旭化成
旭化成では、グループの価値創造に資する人財を育成するため、人財戦略に基づいて「終身成長」と「共創力」の2つを高める施策を展開しています。また「終身成長」を構成する「成長の実現と個とチームの力を引き出すマネジメント力向上」にひもづく、独自のエンゲージメント向上施策「KSA」にて、各職場の活力や成長行動を可視化しています。
KSAとは「活力と成長アセスメント」の頭文字を取ったもので、個人と組織の状態を可視化することで、従業員のワーク・エンゲージメントや挑戦・成長につながる行動を促し、PDCAを効果的に回す取り組みを指します。具体的には、毎年1回、ストレスチェックの実施時に合わせて「上司部下関係・職場環境(組織の資源)」「活力(エンゲージメント)」「成長行動指標」の3つの指標を測定しています。
結果は組織ごとの各ラインマネジャーにフィードバックし、 各組織の課題解決に向けて当事者意識の醸成に注力。各ラインはそれぞれにKSAを活用しており、「自分たちの組織に対する理解がより深まり、いまの良い職場風土を維持しようという部門の団結につながった」などの意見が寄せられています。3つの指標のうちではとりわけ「成長行動指標」をKPIとして重視しており、取り組みを開始した2020年度は1~5段階評価で3.65、2022年度には3.71と少しずつ向上しています。
- 【参考】
- 旭化成レポート2023
大東建設
大東建設では、従業員一人ひとりの成長を支援する人材育成、従業員エンゲージメントを起点とした働きがいのある組織づくりを推進しています。2021年度から「従業員エンゲージメント調査」を実施。その結果を基に、課題として浮かび上がってきた「組織の風通し」「柔軟性や多様性に富む働き方」を改善するための施策に取り組んできました。
2024年1月の調査結果では、従業員エンゲージメントを偏差値化した結果が全11段階のうち3番目、エンゲージメント調査の結果も過去最高となりました。また、従業員エンゲージメント調査と売上高や営業利益などの財務指標の相関をみたところ、両者の間には相関・連動があることが確認できました。同社は「従業員の働きがいや成長支援が経済的な成果と結びつき、持続的な成長に貢献すると考えている」と表明しています。
また、2023年度の役員報酬より、業績連動報酬の係数に非財務指標を導入することを決めており、2025年3月までの事業年度の対象期間においては、そのKPIの一つに「従業員エンゲージメントスコア」を挙げています。対象期間終了後は再度見直しを行い、そのときどきにふさわしい非財務指標を採用することで、事業活動の発展と持続可能な社会の実現を両立する報酬体系を実現するとしています。