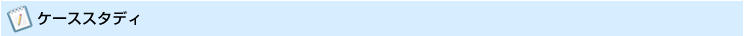【ヨミ】フォーモ
FOMO
「FOMO(フォーモ)」とは、「Fear of Missing Out」の略で、「取り残されることへの恐れ」を意味する心理状態です。特にSNSなどで誰かが楽しそうに活動している投稿を見て、「自分だけが楽しい経験を逃しているのではないか」と不安になる状態を指します。今やSNSに限らず、FOMOは職場にも広がっています。重要な情報や会議、キャリアアップの機会から取り残されることへの不安は、従業員のストレスや焦燥感を増大させます。生産性の低下やエンゲージメントの悪化につながるため、人事部門にはFOMOの発生メカニズムを理解し、対策を講じることが求められます。
「自分だけが知らない」という不安
職場におけるFOMOの実態と人事の処方箋
FOMOがビジネスシーンで注目される背景には、働き方の大きな変化があります。特にリモートワークの普及はFOMOを加速させる一因となりました。オフィスでの偶発的な会話や何気ない情報交換が減少し、チャットツールやオンライン会議がコミュニケーションの主軸になったことで、「自分だけが重要な情報にアクセスできていないのではないか」「特定のチャネルでの議論から疎外されているのではないか」といった不安を従業員が抱きやすくなっています。
職場で見られるFOMOの兆候は多様です。例えば、常にチャットやメールの通知を気にしてしまい、本来の業務に集中できない状態。自分に直接関係のない会議でも「どんな情報も逃したくない」という一心で、無理に参加しようとするのも典型例です。同僚の昇進や新しいプロジェクトへの抜てきといったニュースに過剰に反応し、「自分だけがキャリアで遅れを取っている」と強い焦りを感じるケースもあります。こうした状態が続くと、心身ともに休まらない状況に陥りかねません。
FOMOに悩む従業員が増えると、組織に深刻な影響を与えます。例えば、従業員の注意が散漫になることによる、生産性の低下。「この機会を逃したら損だ」という焦りから、不要なタスクを引き受けたり、不十分な検討のまま判断を下したりする危険性もあります。
継続的なストレスや不安は、メンタルヘルス不調や燃え尽き症候群(バーンアウト)のリスクを高めます。「自分は重要な存在として扱われていない」という疎外感を抱くことで、会社への信頼や帰属意識を損ね、エンゲージメントの低下につながる可能性もあります。
人事部門に求められるのは、FOMOを生み出す組織構造への対策です。まず、組織の重要な情報や決定事項が特定の人物に偏らず、必要なメンバー全員に公平に伝わる仕組み作りが不可欠。そのためには、議事録作成の徹底や周知ルールの明確化などが必要です。
次に求められるのが、心理的安全性の醸成。知らないことを非難したり、情報を得られないのは本人の努力不足だと責めたりせず、「聞けば教えてもらえる」「情報共有を歓迎する」という風土を作ることが重要です。
評価・登用プロセスの透明化も求められます。不透明な評価は臆測と不安を生むため、キャリアパスや昇進・昇格の基準を明確にし、プロセスが公正であることを示します。1on1ミーティングなどを通じてキャリア観を丁寧に聞く場を設けるなど、疎外感を和らげる積極的なコミュニケーションも有効です。
FOMOは個人の心理問題であると同時に、組織の情報共有や文化、制度設計に起因する組織課題でもあります。従業員が情報格差への不安から解放され、目の前の業務に安心して集中できる環境を整えることが、組織全体のパフォーマンス向上につながります。