講演者インタビュー
競争から協走へ! 管理職の「罰ゲーム化」を防ぐ、昇進前後の伴走の仕組みづくり

株式会社リアセック HR事業グループ マネージャー/昭和女子大学 現代ビジネス研究所 研究員
灘 成昭氏
近年「管理職の罰ゲーム化」というバズワードが示すように、昇進意欲の低下が深刻化しています。その背景には、昇進前後の自己理解不足と伴走不在があります。本講演では、アセスメントツールを活用した自己理解の整理を起点に、昇進前の意欲形成から直後のトランジション支援、定期的な対話までを一貫させる実践を紹介。人事が取り組むべき、罰ゲーム化を防ぎ、成長を実感できる管理職育成の在り方・仕組みを考えます。
―― 今回の貴社講演はどのような課題をお持ちの方向けの内容でしょうか?
本講演は、管理職候補者の昇進への意欲低下や、昇進後の伴走不足に課題を感じている企業の人事担当者向けの内容です。近年、従業員のキャリア志向が多様化し、年齢関係なく売り手市場な環境があります。起業・副業の選択肢も活発化する中、従来の昇進制度や支援施策だけでは不十分となり、昇進意欲の低下や離職、成長実感の欠如といった課題が顕在化しています。こうした背景を踏まえ、アセスメントツールを活用した自己理解の整理を起点に、昇進前の意欲形成、昇進直後のトランジション支援、定期的な対話やフィードバックまでを一貫して行う伴走型育成の具体的手法をご紹介します。企業に大きな影響を与える管理職の意欲醸成や成長を支える施策を検討したい企業に向けた内容です。管理職育成に関する課題を整理し、実務に役立つ具体的な設計のヒントを得られます。
―― 今回の講演の聞きどころ・注目すべきポイントをお聞かせください。
管理職育成における「伴走型支援」の考え方と具体的手法にフォーカスし、管理職候補者が納得感を持ち、成長実感を得られる仕組みをどう設計するかについて、人事担当者の方が実務で活かせるポイントを整理して紹介します。
「伴走型育成の設計ポイント」として、昇進前の意欲形成から昇進直後のトランジション支援、定期的な対話やフィードバックまで、一貫して支援するための考え方を学べます。「自己理解を軸にした具体例」を提示し、アセスメントツールを活用した自己理解の整理や、実際の導入事例を通じて、現場ですぐに使えるヒントを確認できます。
「人事が考える仕組みづくり」として、単なる研修や制度提供にとどまらず、管理職候補者が納得感を持って役割を選び、意欲的に成長できる環境を整えるポイントを解説します。
本講演を通じて、管理職育成に関する課題を整理し、実務に役立つ設計のヒントを持ち帰ることができます。また伴走型支援の考え方や具体策を学ぶことで、人事としての施策立案にすぐに活かせるだけでなく、昇進候補者一人ひとりの強みや課題に応じた支援を考え、組織全体の管理職育成戦略にも反映できるポイントを得られます。
―― 講演に向けての抱負や、参加される皆さまへのメッセージをお願いします。
管理職は人的資本経営における「事業戦略に基づいた人事戦略」の重要なキーパーソンで、組織に大きな影響力を持つ重要な存在です。ただ、不確実な時代に、働き方・キャリア観の多様化により管理職育成の難易度が上がっていると言われています。人事としても、キャリア自律が当たり前の時代における管理職育成は悩ましいテーマなのではないでしょうか。
皆さんと一緒に、管理職が納得感を持ち、組織全体に良い影響を与えられる育成のあり方を考える場にしたいと思っています。私の講演が、自社の管理職育成の再確認やディスカッションの材料として活用いただければ幸いです。
- 灘 成昭氏(なだ なるあき)
- 株式会社リアセック HR事業グループ マネージャー/昭和女子大学 現代ビジネス研究所 研究員
- リアセック入社後、大学の教学改革支援、教職員の能力開発、PBL教材開発、就職支援事業のPM、新規事業開発を担当。24年に社会人向けのグループを立ち上げ、アセスメントを軸とした人材育成・キャリア自律の施策支援などで主に大手企業を担当。GCDFキャリアカウンセラー、ワークショップデザイナー(青学33期)。
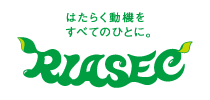
「日本の人事部」「HRカンファレンス」「HRアワード」は、すべて株式会社HRビジョンの登録商標です。
当社はプライバシーマーク取得事業者です。類似のサービスやイベントとの混同にご注意ください。